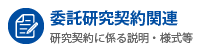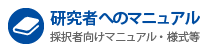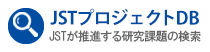開催概要
- 日時
- 2025年9月3日(水) 10:00~12:30
- 会場
- 幕張メッセ 国際会議場201会議室
- 主催
- JST未来社会創造事業「共通基盤」領域 本格研究
MEEP 「マテリアル探索空間拡張プラットフォームの構築」
- イベントURL
- 「MEEP公開シンポジウム」
> 「共通基盤」領域
> 探索加速型 本格研究
報告
本格研究「マテリアル探索空間拡張プラットフォームの構築(長藤課題)」(研究開発代表者:長藤圭介(東京大学))の最終シンポジウムが2025年9月3日に幕張メッセ・国際会議場(JASIS2025)において開催されました。
冒頭では、長我部信行運営統括による開会あいさつに続いて、研究開発代表者の長藤圭介教授からプロジェクトの成果概要の紹介がありました。その後、岡島博司テーママネージャーからマテリアル産業の現状と課題についてお話いただき、続いてそれぞれの研究グループリーダーである清水亮太教授(自然科学研究機構)より自律実験システムについて、小野寛太教授(大阪大学)より計測データからハイスループット知識化について、長田貴弘グループリーダー(物質・材料研究機構)からマテリアルデータベース構築について、牛久祥孝氏(OMRON SINIC X/NexaScience)から機械学習についての研究成果と取り組みの紹介がありました。
長藤圭介教授の司会によるパネルディスカッションでは、「日本のマテリアル研究現場のあり方」と「日本の計測機器の役割」の2テーマについて6名の登壇者による議論が交わされました。「日本のマテリアル研究現場のあり方」では、日本独自の強みとして挙げられる勘・コツ・経験に内在する物性発現の因果条件や操作手法の意図的な活用が、マテリアル研究の発展に重要である点が論じられました。さらに、大量のデータ相関および実験自動化のためにロボット指示する実験操作の指定が因果関係の解明に寄与する点や、これらの解明が生産のスケールアップを行うためにも重要であることが議論されました。また「日本の計測機器の役割」では、研究用途と生産現場用途の計測分析装置のデータや取り組みを繋ぐこと、ロボットの導入による自動化を含めたワークフローの設計を、ユーザーとメーカーが協力して行う重要性について議論されました。
その後の質疑応答では、データ共有のインセンティブや自動自律実験の導入コストへ関心が寄せられ、登壇者と聴講者の間で議論が交わされました。
最後に各グループリーダーから一言ずつ、今後の展開についてメッセージを発信した後、岡島博司テーママネージャーよる今後の活動に対する激励を含む挨拶で閉会しました。

長我部信行運営統括による開会の挨拶

パネルディスカッション
以上