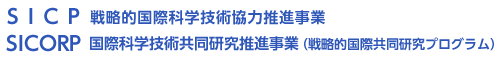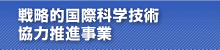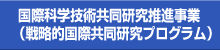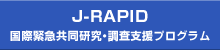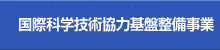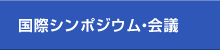[本文]
平成23年11月30日
独立行政法人科学技術振興機構
国際科学技術部
独立行政法人科学技術振興機構
国際科学技術部
1.趣旨
戦略的国際科学技術協力推進事業 日仏(CNRS)研究交流における平成22年度終了課題の事後評価の結果を別紙1〜5のとおり報告する。
2.事後評価の目的
研究交流の実施状況、研究成果、波及効果等を明らかにし、今後の研究成果の展開及び事業運営の改善に資することを目的とする。
3.対象となる研究課題
日仏(CNRS)における平成22年度終了の以下の課題を対象とする。
「コンピュータサイエンスを含む情報通信技術」(5課題)
 実環境のオンライン情報構造化を用いたロボットの運動計画および実行に関する研究
実環境のオンライン情報構造化を用いたロボットの運動計画および実行に関する研究
(研究交流実施期間:平成20年2月1日〜平成23年3月31日)
 暗号と理論:計算機によって検証された安全性証明
暗号と理論:計算機によって検証された安全性証明
(研究交流実施期間:平成20年2月1日〜平成23年3月31日)
 量子コンピュータ:理論と実現性
量子コンピュータ:理論と実現性
(研究交流実施期間:20年2月1日〜平成23年3月31日)
 ハイスループットスクリーニングのためのタンパク質チップのロボット化に関する研究
ハイスループットスクリーニングのためのタンパク質チップのロボット化に関する研究
(研究交流実施期間:平成20年2月1日〜平成23年3月31日)
 超臨場VR 体験環境
超臨場VR 体験環境
(研究交流実施期間:20年2月1日〜平成23年3月31日)
「コンピュータサイエンスを含む情報通信技術」(5課題)
 実環境のオンライン情報構造化を用いたロボットの運動計画および実行に関する研究
実環境のオンライン情報構造化を用いたロボットの運動計画および実行に関する研究(研究交流実施期間:平成20年2月1日〜平成23年3月31日)
 暗号と理論:計算機によって検証された安全性証明
暗号と理論:計算機によって検証された安全性証明(研究交流実施期間:平成20年2月1日〜平成23年3月31日)
 量子コンピュータ:理論と実現性
量子コンピュータ:理論と実現性(研究交流実施期間:20年2月1日〜平成23年3月31日)
 ハイスループットスクリーニングのためのタンパク質チップのロボット化に関する研究
ハイスループットスクリーニングのためのタンパク質チップのロボット化に関する研究(研究交流実施期間:平成20年2月1日〜平成23年3月31日)
 超臨場VR 体験環境
超臨場VR 体験環境(研究交流実施期間:20年2月1日〜平成23年3月31日)
4.評価項目及び基準
(1)評価項目
 研究成果の評価
研究成果の評価
・新しい知の創造/画期的な科学技術の進展/新分野の開拓
・相手国との協力による研究への相乗効果
・当該研究の今後の展開見込、社会への波及効果
 交流成果の評価
交流成果の評価
・相手国との研究交流につながる人材育成
・当該事業を端緒とした相手国との研究交流の増加/持続的発展の可能性(終了後の交流計画を含む)
 研究成果の評価
研究成果の評価・新しい知の創造/画期的な科学技術の進展/新分野の開拓
・相手国との協力による研究への相乗効果
・当該研究の今後の展開見込、社会への波及効果
 交流成果の評価
交流成果の評価・相手国との研究交流につながる人材育成
・当該事業を端緒とした相手国との研究交流の増加/持続的発展の可能性(終了後の交流計画を含む)
(2)評価基準
秀、優、良、可、不可、の5段階にて達成度を評価。達成度の評価基準は以下の通り。
「秀」90%以上、「優」80%以上、「良」65%以上、「可」50%以上、「不可」50%未満。
秀、優、良、可、不可、の5段階にて達成度を評価。達成度の評価基準は以下の通り。
「秀」90%以上、「優」80%以上、「良」65%以上、「可」50%以上、「不可」50%未満。
5.事後評価の進め方
採択時の「申請書」等と研究終了報告書をもとに事後評価委員が事後評価を行った。
なお、事後評価の進め方については下記の通りである。
なお、事後評価の進め方については下記の通りである。
1)研究終了報告書(公開資料として作成を依頼したもの)を研究代表者が作成
2)研究終了報告書及び申請書等を事後評価委員に送付し、査読による評価
3)事後評価委員「主査」による事後評価報告書の作成
 事後評価委員の評価結果とりまとめ
事後評価委員の評価結果とりまとめ
 事後評価報告書(案)の作成
事後評価報告書(案)の作成
 事後評価報告書(案)を研究代表者に提示し、事実誤認の確認
事後評価報告書(案)を研究代表者に提示し、事実誤認の確認
 事後評価委員の評価結果とりまとめ
事後評価委員の評価結果とりまとめ 事後評価報告書(案)の作成
事後評価報告書(案)の作成 事後評価報告書(案)を研究代表者に提示し、事実誤認の確認
事後評価報告書(案)を研究代表者に提示し、事実誤認の確認4)業運・理事会への報告後、研究終了報告書および事後評価報告書を一般に公開
6.評価委員
主査
南谷 崇 キヤノン株式会社 顧問
委員
岡田 謙一 慶應義塾大学 教授
岡本 栄司 筑波大学 教授
北川 勝浩 大阪大学 教授
坪内 孝司 筑波大学 教授
南谷 崇 キヤノン株式会社 顧問
委員
岡田 謙一 慶應義塾大学 教授
岡本 栄司 筑波大学 教授
北川 勝浩 大阪大学 教授
坪内 孝司 筑波大学 教授