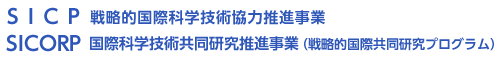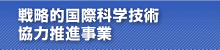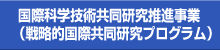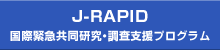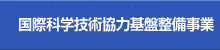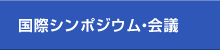[本文]
平成21年1月27日
独立行政法人科学技術振興機構
国際部
独立行政法人科学技術振興機構
国際部
国際部では、この度、戦略的国際科学技術協力推進事業 日本—中国−韓国 研究交流における平成19年度終了課題の事後評価を実施した。
1.事後評価の趣旨
本事業は、政府間合意等に基づき文部科学省が特に重要なものとして設定した国・地域・分野において、共同研究、研究集会、シンポジウム、セミナー等の国際科学技術協力を推進するものである。
事後評価は、研究交流の実施状況、研究成果、波及効果等を明らかにし、研究成果の今後の展開に向けた施策及び事業運営の改善に資することを目的として、実施したものである。
事後評価は、研究交流の実施状況、研究成果、波及効果等を明らかにし、研究成果の今後の展開に向けた施策及び事業運営の改善に資することを目的として、実施したものである。
2.評価対象研究課題
日本—中国−韓国 研究交流における平成19年度終了の以下の4課題を対象とする。
 東アジアにおけるGPSを用いた地殻変動の研究
東アジアにおけるGPSを用いた地殻変動の研究
 砂漠化を抑制する乾燥耐性植物の開発
砂漠化を抑制する乾燥耐性植物の開発
 日韓中の極短パルス高強度レーザー研究協力のための連携体構築
日韓中の極短パルス高強度レーザー研究協力のための連携体構築
 アジア地域における標準物質開発ネットワークの構築
アジア地域における標準物質開発ネットワークの構築
 東アジアにおけるGPSを用いた地殻変動の研究
東アジアにおけるGPSを用いた地殻変動の研究 砂漠化を抑制する乾燥耐性植物の開発
砂漠化を抑制する乾燥耐性植物の開発 日韓中の極短パルス高強度レーザー研究協力のための連携体構築
日韓中の極短パルス高強度レーザー研究協力のための連携体構築 アジア地域における標準物質開発ネットワークの構築
アジア地域における標準物質開発ネットワークの構築3.研究交流実施期間
平成17年1月〜平成20年3月31日まで
4.事後評価の進め方
採択時の「申請書」等と研究実施終了報告書をもとに事後評価委員が事後評価を行った。なお、事後評価の進め方については下記の通りである。
1)研究実施終了報告書を研究代表者が作成。
2)事後評価委員へ研究実施終了報告書及び申請書(研究交流計画書)等を送付し、査読評価を実施。
3)評価委員による最終事後評価結果報告書の作成。
 各評価者の結果を纏めた総合事後評価報告書(案)を国際部が作成。
各評価者の結果を纏めた総合事後評価報告書(案)を国際部が作成。
 総合事後評価報告書(案)を各評価委員に提示し、内容の確認。
総合事後評価報告書(案)を各評価委員に提示し、内容の確認。
 最終事後評価報告書(案)を研究代表者に提示し、事実関係の確認。
最終事後評価報告書(案)を研究代表者に提示し、事実関係の確認。
 上記の
上記の 及び
及び を経て、主査に最終確認し各課題の事後評価報告書を完成。
を経て、主査に最終確認し各課題の事後評価報告書を完成。
 各評価者の結果を纏めた総合事後評価報告書(案)を国際部が作成。
各評価者の結果を纏めた総合事後評価報告書(案)を国際部が作成。 総合事後評価報告書(案)を各評価委員に提示し、内容の確認。
総合事後評価報告書(案)を各評価委員に提示し、内容の確認。 最終事後評価報告書(案)を研究代表者に提示し、事実関係の確認。
最終事後評価報告書(案)を研究代表者に提示し、事実関係の確認。 上記の
上記の 及び
及び を経て、主査に最終確認し各課題の事後評価報告書を完成。
を経て、主査に最終確認し各課題の事後評価報告書を完成。(被評価者から意見書が提出された場合は、 〜
〜 を再実施)
を再実施)
 〜
〜 を再実施)
を再実施)4)JSTの業務運営会議・理事会に報告後、一般に公開。(JSTホームページに掲載)
5.評価基準
本事業は諸外国との協力分野における研究交流の推進を主旨としており、研究成果の評価だけでなく、研究交流の評価を重視した。
(1)評価基準
 研究交流の評価
研究交流の評価
・研究交流の実施状況
・課題の実施を端緒とした協力対象国・地域との研究交流の持続的発展への貢献
・交流体制の強化などの波及効果
 研究成果の評価
研究成果の評価
・外部発表(論文、口頭発表等)、特許、研究交流を通じての新たな知見の取得等の研究成果の状況
・得られた研究成果の科学技術への貢献
 研究交流の評価
研究交流の評価・研究交流の実施状況
・課題の実施を端緒とした協力対象国・地域との研究交流の持続的発展への貢献
・交流体制の強化などの波及効果
 研究成果の評価
研究成果の評価・外部発表(論文、口頭発表等)、特許、研究交流を通じての新たな知見の取得等の研究成果の状況
・得られた研究成果の科学技術への貢献
(2)基準
秀、優、良、可、不可、の5段階にて、評価を実施。
秀、優、良、可、不可、の5段階にて、評価を実施。
6.評価委員
| 事後評価課題名 | 氏名 | 所属・役職 |
|---|---|---|
| 東アジアにおけるGPSを用いた地殻変動の研究 | 鷺谷 威 | 名古屋大学大学院 環境学研究科 教授 |
| 橋本 学 | 京都大学防災研究所 教授 | |
| 内藤 勲夫 | 元 国立天文台 教授 | |
| 砂漠化を抑制する乾燥耐性植物の開発 | 一前 宣正 | 元 宇都宮大学 雑草科学研究センター長 |
| 篠崎 和子 | 東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授 | |
| 西澤 直子 | 東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授 | |
| 日韓中の極短パルス高強度レーザー研究協力のための連携体構築 | 大橋 裕二 | 元 東京工業大学大学院 教授 |
| 小原 實 | 慶應義塾大学 理工学部 電子工学科 教授 | |
| 増原 宏 | 奈良先端科学技術大学院大学 客員教授 | |
| アジア地域における標準物質開発ネットワークの構築 | 角田 欣一 | 群馬大学工学部 応用化学科 教授 |
| 保母 敏行 | 東京都立大学 名誉教授 | |
| 吉田 尚弘 | 東京工業大学大学院 総合理工学研究科 教授 |