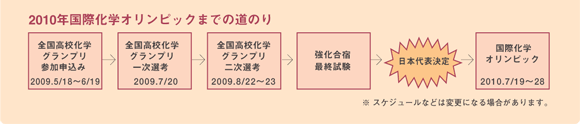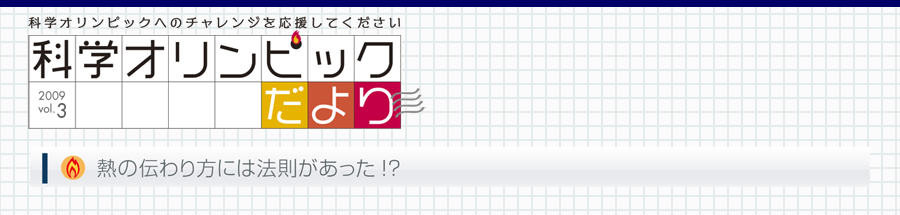Vol3では、物理チャレンジ2008の第1チャレンジで出題された「熱量保存」についての問題を紹介します。
熱量保存とは、熱は必ず熱いほうから冷たいほうへ移動し、熱いほうが失った熱の量と、冷たいほうが得た熱の量は 同じになるということ。
私たちの身近にも、その法則を使ったものがあります。
それでは、問題とその一例を見てみましょう。
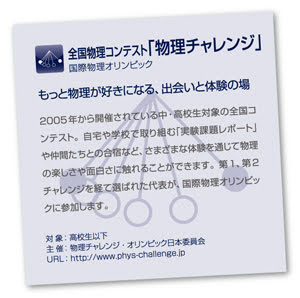
火を使わずに温度が上がる熱伝導マジック
第4回全国物理コンテスト 物理チャレンジ2008 第1チャレンジ
理論問題コンテストより出題(一部改変)
次の文を読んで,問題に答えなさい。
断熱性のよい容器A,Bと熱伝導性の高い容器C,Dがある。
容器A,Bにはそれぞれ,80℃のお茶(ただし,比熱は水と等しいとする)1,000gと,20℃の水1,000gが入っている。
A,Bは容器C,Dを中に入れられる大きさで,中の液体がこぼれることはない。これらの容器は,次のような使い方ができる。
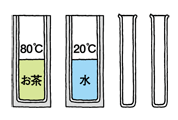
1)容器Bに入っている水をすべて容器Cに移し,容器Cを容器Aの中に入れる。
2)熱伝導によって,しばらくすると,容器Aのお茶と,容器Cの水の温度は等しくなる。
このとき,(移動する熱量)=(物質の質量)×(比熱)×(温度変化)とすると,
(容器Aの中のお茶が放出した熱量)=(容器Cの中の水が吸収した熱量)という関係が
成り立つと考えられる。ただし,ここでは,容器の温度変化のために
吸収する熱量は考えないものとし,周囲の環境への熱の放出もないものとしている。
問題
容器A~Dを利用した熱伝導の過程だけを用いて,お茶と水を混ぜるこ となく, 最終的な水全体の温度を,最終的なお茶全体の温度より高くする ことはできるだろうか。できるとすればその方法の1例を,またできないとすればその理由を述べなさい。
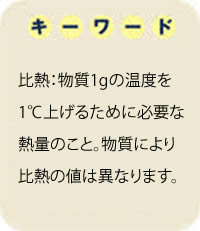
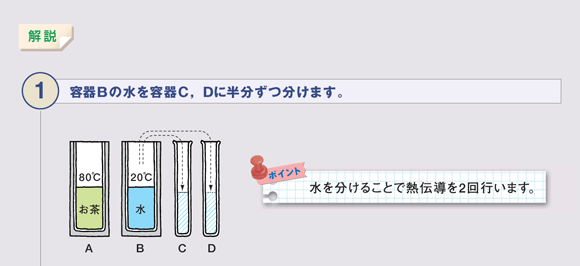
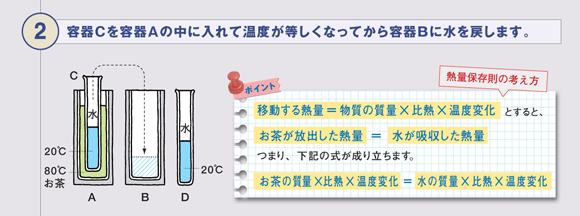
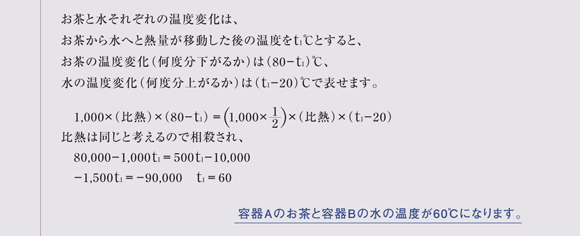
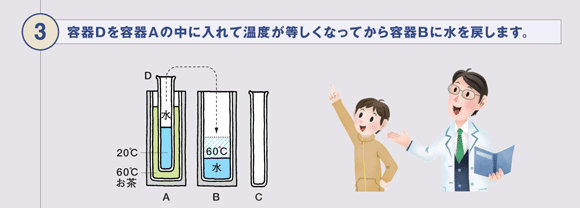
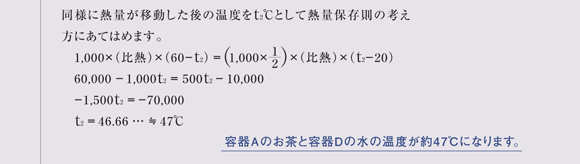
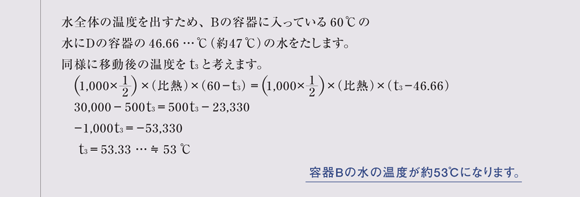
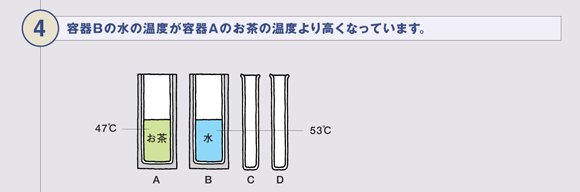
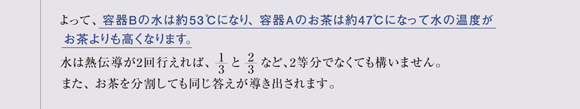
回答
できる。一例として,次の手順で行えばよい。
(1)容器Bの水を容器C,Dに半分ずつ分ける。
(2)容器Cを容器Aの中に入れると,60℃になるので,水を容器Bに戻す。
(3)容器Dを容器Aの中に入れると,約47℃になるので,水を容器Bに戻す。
(4)容器Bの水は約53℃になり,容器Aのお茶は約47℃になっている。
条件として示した,容器による熱の吸収や周囲への熱放出はないとした容器A~Dを用いた熱伝導だけで, 左記のようなことが可能である。始めに分割するのがお茶でもよい。また,2等分でなくてもよい。 熱交換器の原理である。
![]()
INTERVIEW
飲み物の温度を保つ厚さ1mmの“宇宙空間”

宇宙空間のような真空状態を人工的に作り出すことで、飲み物の温度を長時間保てる容器。それが魔法瓶です。保温・保冷の仕組みについて、象印マホービン商品企画部の鎌田明博さんにお話を伺いました。
象印マホービン株式会社
商品企画部サブマネージャー
鎌田 明博氏
「保温や保冷は、熱の伝わりをさえぎることで初めて可能になります。熱の伝わり方には、伝導・対流・放射の3つがあり、魔法瓶にはこれらすべてをさえぎる仕組みが備わっています」。伝導とは、物質と物質が接することで、温度の高いほうから低いほうへと熱が移動すること。対流とは、気体や液体の中で温度差ができたとき、熱の移動が起こること。そして放射とは、熱が電磁波として物質を介することなしに移動すること。太陽の熱が真空の宇宙を通って地球まで届くのも、放射の働きがあってこそなのです。「魔法瓶は、内瓶と外瓶の2重構造にして間に真空層を作ることで、熱の伝導・対流を防いでいます。さらに、真空層内部に金属箔を封入したり、メッキを施したりすることで電磁波としての熱を反射し、放射によって熱が逃げることも防げるのです」と鎌田さん。
ただ、魔法瓶は構造上、どうしても注ぎ口の部分で内瓶と外瓶が接するため、そこから少しずつ熱が逃げてしまいます。そのため、ふたの部分に断熱材を入れたり、空気の層を挟んだ2重構造にしたりすることで熱が逃げるのを最小限に抑えているそうです。
「目指すは、真空層1mm以下!」と鎌田さんは意気込みます。真空層の幅が広くても狭くても、真空状態であれば断熱効果に差が出ることはないとのこと。しかし、幅が狭くなるほどわずかな衝撃で内瓶と外瓶が接する可能性も高くなり、そこから熱が逃げてしまいます。「薄さと軽さとコンパクトさ。そして強度の両立が魔法瓶を作るうえで変わらないテーマですね」。さらに鎌田さんは次のように続けました。「魔法瓶の真空断熱技術を応用して、壁面などに使われる平面状の真空パネルの開発・製品化に成功しました。今後はサイズと形のバリエーションを増やしてさまざまな分野で展開していく予定です。また、真空層を作る排気の工程で低温化を進め、より省エネで効率よく生産できる技術を開発していきたいと思います」
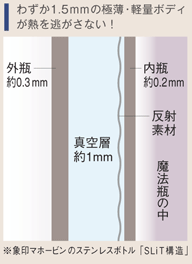
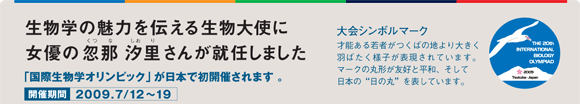
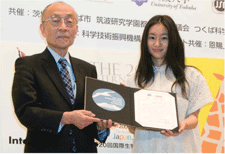
国際生物学オリンピック2009組織委員会の井村裕夫委員長から生物大使任命状を受け取る忽那汐里さん。
今年の夏に日本で初めて開催される「第20回国際生物学オリンピック」を盛り上げ、より多くの人に知ってもらおうと、参加者と同年代である女優の忽那汐里さんが生物大使に任命されました。「カモノハシが大好き」という忽那さんは、オーストラリアの広大な自然の中で生まれ育ち、さまざまな生物と触れあってきたそうです。就任の意気込みを次のように語りました。
みなさんにいま以上に興味を持ってもらえるよう、生物学の魅力を伝えていきたいです。いろいろな国からたくさんの生徒が集まる貴重な機会だと思いますので、日本代表の方にも生物学のおもしろさや一般に知られていないことなどを伝えてもらえればと思います」。国際生物学オリンピック2009組織委員会の井村裕夫委員長は「ダーウィンの生誕200年となる本年に日本で開催できるのは非常にうれしいことです。
この機会に、若い人々には生物学を一層深く愛するようになってほしい」と語りました。
国際生物学オリンピックとは、世界各国の主に高校生を対象とした国際的な科学コンテストです。20回の節目となる今大会は、茨城県つくば市で7月12日~19日の8日間にわたって開催され、約60ヵ国から240名が参加する予定です。
成績の上位10%の優秀者に金メダル、次の20%に銀メダル、次の30%に銅メダルが贈られます。日本代表には2,482名の応募者の中から3回の選考試験をへて4名の生徒が選ばれました。日本代表はこれまでに数回にわたる強化合宿をこなしており、まだ獲得したことのない金メダルを目指します。
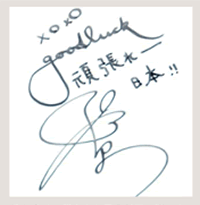
任命式で忽那さんが日本代表に贈った応援メッセージ。
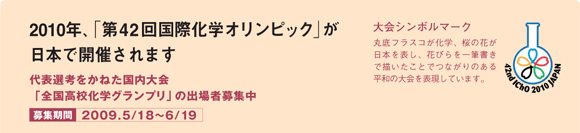
2010年の夏、「第42回国際化学オリンピック」がここ日本で開催されます。世界約70ヵ国から280名の高校生が集まり、筆記、実験問題(各5時間)に取り組んで化学の実力を競います。会期は7月19日~28日の10日間にわたり、東京で開催されます。
国際化学オリンピックへの挑戦は、国内大会である「全国高校化学グランプリ」に参加することから始まります。この国内大会は“化学の甲子園”とも呼ばれ、毎年2,000人を超える参加者が熱い戦いを繰り広げます。一次選考の筆記試験では、学校で習う基礎的な内容は押さえつつも、教科書では扱われない化学の一面に触れられるような問題が出題されます。
二次選考で実施される合宿形式の実験試験では、参加者が実験手順を自分で考えて答えを導き出します。生徒の化学への興味を呼び起こし、意欲や能力を高める絶好の機会です。参加申込みが2009年の5月18日~619日までとなっていますので、ぜひ多くの生徒に参加を呼びかけてください。
大会への参加は、ホンモノの化学を身につける自己訓練にもなります!
化学オリンピック日本委員会 実行委員会委員長
東京大学 渡辺 正 先生
化学と化学技術は暮らしや産業を支えてきたし、それは今後も変わりません。化学オリンピックは、将来の化学のリーダーとなるヒーロー・ヒロインを発掘するとともに、世界の仲間との交流を通じて精鋭たちが国際理解を深めるための一大イベントです。また、もう国内予選の段階から、ホンモノの化学を身につける自己訓練の場でもあります。多くの生徒が挑戦して世界に通じる化学を知り、貴重な体験を今後の人生にぜひ活かしてもらいたいと思います。世界も日本も、生徒のチャレンジを待っています。