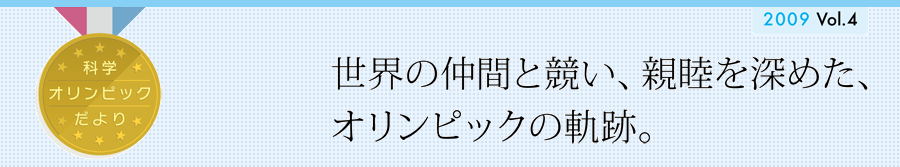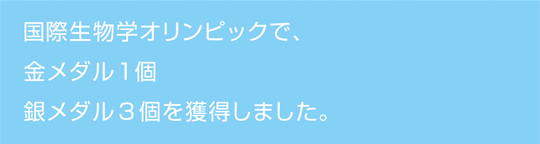
第20回国際生物学オリンピックが、2009年7月12日から19日まで茨城県のつくば市で開催され、日本代表の4選手は全員がメダルを獲得しました。世界の舞台で活躍した生徒たちや、大変な盛り上がりをみせた大会の模様をお伝えします。
国際生物学オリンピックは、生物学の才能に恵まれた生徒を見いだし、国際交流を深めることを目的に毎年行われています。
進化論を提唱したチャールズ・ダーウィンの生誕200年となる記念すべき年に、初めて日本で開催され、過去最多となる56の国と地域から221名の生徒が参加。
世界中の仲間と知力を競い合い、友情をはぐくみ、生徒たちにとって一生の思い出となる貴重な体験となりました。
実験試験・理論試験
今年の生物学オリンピックの試験は、6時間の実験試験と4時間半の理論試験で行われ、高校教育の標準を超えるハイレベルな問題が出題されました。
実験試験は、ショウジョウバエの遺伝メカニズムを計算する問題や、りんごを使った植物の発生過程の推測など合計4題あり、観察・計測・レポートなどの一連の実験スキルが試されました。
筆記試験は、生物学の体系的な理解力を問うものから豊かな発想力を必要とするものまでさまざまな問題が出題され、生徒たちからは「難しいけど楽しかった」という声も聞かれました。


交流イベント『つくばナイト』
すべての試験が終了したその夜、日本の夏祭りをイメージした交流イベント「つくばナイト」が開催されました。
筑波大学の学生たちによる「和太鼓演奏」や、威勢のいい掛け声を上げて躍動的に踊る「よさこいソーラン」など、生徒も先生方もいっしょになって試験の疲れを吹き飛ばすように盛り上がりました。
日本代表の生徒たちは、夏祭りにふさわしい鮮やかな浴衣や、ハッピにねじりハチマキ姿で登場し、外国の生徒たちから記念撮影を求められていました。



表彰式
大会のフィナーレを飾る、表彰式。生徒たちは伝統的な民族衣装を身にまとったり、国旗のフェイスペインティングを施したりと思い思いの姿で参列し、会場は華やかな雰囲気に包まれていました。今大会の軌跡をふりかえるVTRや、国際生物学オリンピックのプーンピポップ・カセムサップ会長のユーモア溢れるスピーチの後、いよいよメダル受賞者の発表です。メダルは成績の上位10%に金メダル、次の20%に銀メダル、次の30%に銅メダルが授与されます。名前を呼び上げられた生徒たちは本当にうれしそうな表情を浮かべ、自国の先生や生徒だけでなく、親睦を深めた他国の生徒たちからも祝福を受けていました。
日本チームは全員がメダルを獲得し、金メダル1個・銀メダル3個という過去最高の結果を残しました。なかでも金メダリストの大月亮太さんは全体で6位という好成績を挙げました。国・地域別の成績を見ると、シンガポール、アメリカ、オーストラリア、中国、台湾などが上位に連なり、金メダルも複数個獲得しています。 最後に、IBOトロフィーが日本の井村裕夫委員長から来年の開催国である韓国のリー・キング・チェー委員長に手渡され、第20回国際生物学オリンピックは、たくさんの思い出を残して閉幕しました。

![]()

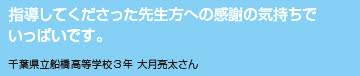
金メダルを取ることができ、びっくりしたのと同時にすごくうれしいです。これまで指導してくださった先生方のおかげだと思いますし、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
僕は英語があまり得意ではないのですが、外国の高校生たちと身振り手振りを交えて一生懸命意思を伝え合ううちに、友達になることができ、とてもいい経験ができました。
試験ですばらしい成績を残せたことや世界中の生物好きの仲間との交流を通じて、生物って本当に楽しいなと再確認できました。
僕は子どものころから生物の学者になりたいと思っていたのですが、やっぱりこの道を進んでいきたいと確信しました。

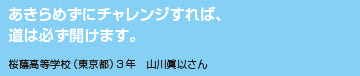
銀メダルとりました! 感無量です。生物学オリンピックは2回目の挑戦で、前回は国内の最終予選で落ちてしまい日本代表になれなかったこともあって、本当にうれしいです。
この2年間をふりかえると、まるで息をするように、ごく自然に生物の勉強をしてきました。それに貴重な体験もさせていただき、自分の知識や考え方を成長させることができたと思っています。お世話になった先生方には心からお礼を言いたいです。
生物学オリンピックは普通の高校生にはできない特別な経験ができる機会だと感じました。生物が好きな人にはぜひチャレンジしてもらいたいです。あきらめずにやれば、道は必ず開けますから。

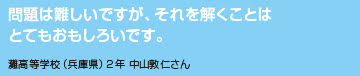
生物学オリンピックに出題された問題は、実験試験も理論試験もとても難しいのですが、その内容は興味深く、解くことがおもしろいと感じられるものばかりでした。
大会期間中はイギリスの生徒と相部屋だったこともあり、海外の方と交流する機会がたくさんありました。試験の合間には日本のアニメの話題で意気投合したり、「つくばナイト」では日本の祭りや踊りをいっしょに楽しんだりもしました。
驚くほど生物の知識がある人とも知り合え、彼らが将来どんな研究をしていくのか楽しみですし、自分も生物の研究者をめざしてがんばっていきたいと思っています。

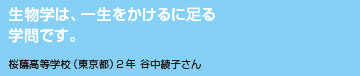
メダル受賞者発表のとき、じつはメダルがとれるか不安でドキドキしていました。いざ銀メダリストに自分の名前が呼ばれたときはとてもうれしかったのですが、それだけでなく金メダルを逃した「あ~」という悔しさもこみ上げてきました。
この結果は私にとって大きな自信になりました。また、世界中の生物好きな仲間と将来のことを話し合ううちに、生物学とは一生をかけるに足る学問だと感じました。
将来は、環境変化の影響で白化現象が起きている、サンゴ礁の研究をしたいと思っています。その前に、来年の生物学オリンピックにもぜひ挑戦したいです。今度は、金メダルをめざして。
![]()
生徒を導くには、本人のやる気と同様に、教師の強い意志が大切です。
石井規雄先生(千葉県立船橋高等学校)
国際生物学オリンピックで日本人初の金メダルを獲得した大月亮太さん。 彼を2年間にわたって指導してきた石井規雄先生に、独自の指導方法や、 ともに挑戦する教師にとって何が大切かをお話ししていただきました。

私が指導を始めたころの大月くんはバスケットボール部に所属していたこともあり、生物学オリンピックへの出場を本気で考えてはいませんでした。ところが国内予選の『生物チャレンジ』で高い評価を得て、頑張れば自分も日本代表になれるかもしれないという思いが、彼の背中を押したのです。
われわれ教師は「全国レベルで自分の力を試せる機会」として生徒の参加を促すと良いと思います。じつは多くの参加国では代表選手の成績によって特典があるのですが、日本にはそうした制度はなく、生徒自身が挑戦する意義を見つけることがとても重要となるからです。
ただ、教師にとって指導の時間を作るのは大変ですし、 時間を上手に使う必要があると思います。私の場合、学期 中は週2~3回の特別授業を組み、夏休みには教室を開放し生徒をサポートするような指導をしています。生徒の挑戦を支えたいと思ったら、教師はまず、生徒に何を伝えたいのか自問自答すると良いでしょう。私はやはり教えることが好きで、生物の本質的な面白さを伝えたいという思いがあります。自然への理解を深め、自然全体のつながりを発見し、物事の見方が変化していくとき、生徒たちの目は輝いています。
生物学オリンピックに挑戦するには生徒自身の努力は重要ですが、教師として何をしたいのか強い意志を持ち、それを実践することも同じように大切だと思います。
さまざまな経験や仲間との交流を通じて、人として成長できるすばらしい機会です。
奥田宏志先生
(日本代表チームリーダー 芝浦工業大学柏中学高等学校)
代表選手の選考や強化トレーニングなど、準備段階から長期にわたって 日本チームを支えてきた奥田宏志先生に、生徒たちが 国際生物学オリンピックに挑戦する意義ついて語っていただきました。

生物学オリンピックに出場するまでの間に、生徒たちはいろいろな先生方のお世話になり、普段の高校生活では学べないことを吸収し、人として大きく成長していきます。
いざ国際大会の舞台に立つときには、日本の代表として恥ずかしくないようにという強い気持ちがみなぎっていて、スタッフとして胸を張って送り出してきました。彼ら、彼女らの成長の過程に関われることは、とても大きな喜びです。
また大会を通じて、かけがえのない友人たちと出会うこともできます。生物が好きな生徒は学校では何百人の うち数人かもしれませんが、世界中からここに集結する生徒たちはみんな生物が大好きです。しかも今年は過去の国際大会に出場した日本代表の先輩たちが応援に駆けつけ、世代を超えた仲間同士の絆も生まれました。
生物学オリンピックには生物学の知識や思考力を競う試験があるので、学力偏重のイメージを持たれがちです。しかし実際には、生徒の人間的な成長やいろいろな人との交流こそが大きな財産になると思います。10年後には、今の代表の生徒たちが大会の運営や引率をしているかもしれません。今後のさらなる成長が楽しみです。
![]()
生物学の体系的な知識や実験技術を試し、知的好奇心を刺激する問題です。
齋藤淳一先生
(日本代表チームリーダー 東京学芸大学附属国際中等教育学校)
試験を受けた生徒たちから「問題を解くことが楽しい」という声が上がるほど、創意と工夫に満ちている国際生物学オリンピックの問題。
その特徴と日本代表の対策について、日本が国際大会に参加して以来、代表の生徒たちを指導している齋藤淳一先生に教えていただきました。

国際生物学オリンピック(以下IBO)は、世界中から集まる高校生たちの能力を発掘・伸張し、将来の科学者を育てることを目的として行われています。問題づくりには特に力を入れていて、生物学の体系的な知識や実験技術を試すだけでなく、知的好奇心を刺激するような内容が出題されます。
試験は90分を4回(合計6時間)行う「実験試験」と、4時間半*におよぶ「理論試験」で行われ、知力のみならず体力や精神力も必要です。(*試験時間は大会によって異なります。)
実験試験では課題分野があらかじめIBOのウェブサイトに公開されますが、十分な訓練なくては対処できないほど高い実験スキルが要求されます。日本チームは、基本的な実験用具や機器の操作は目をつぶってでもできるほどトレーニングを繰り返しました。

理論試験では知識のみを問うような設問は少なく、生物学の多岐にわたる体系的な知識と理解力が求められます。問題はIBOの標準教科書『キャンベル生物学』から出題されますが、1,500ページもの厚さがあるため、講義や実習を通じて生徒たちが楽しく読むためのガイドをして、自主的に学習できるような配慮をしました。
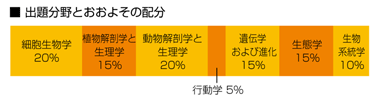
2010年夏、東京で国際化学オリンピックが開催されます。
生物学オリンピック閉会式終了後、生物学オリンピックの井村裕夫委員長から化学オリンピックの本間敬之委員へ、国際科学オリンピックの引継ぎ式が行われました。井村委員長は「若者の情熱に火をつけ、日本の科学教育がいっそう進むことを期待しています」とエールを送り、本間委員は「生物学オリンピックの成功を見習い、生かしていきたい」と抱負を語りました。
第42回国際化学オリンピックは、東京で2010年7月19日から28日まで開催されます。日本代表候補の選出は大詰めを迎え、筆記試験の一次選考と合宿形式の二次選考を経て、3,078名の受験者から約20名が次のステージへと進む予定です。今後さらに強化合宿や最終試験を行い日本代表の4名を決定し、世界へと挑みます。

国際オリンピックにチャレンジしよう!
国際科学オリンピックに出場するためには科目ごとに行われる国内予選にチャレンジし、好成績を挙げることが必要です。 科学に興味のある生徒たちの挑戦を、ぜひ応援してください。
| 教科・科目 | 応募期間 | 応募方法 | 参加賞 | 試験日 | 会場 | 選抜方法 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本数学オリンピック 国際数学オリンピック(IMO) |
2009年 5月1日~ 10月31日 |
郵便振替 | 5,000円 (学校一括申込 割引制度あり) |
2010年 1月10日 |
全国約60カ所 | 単答式筆記試験にて本選に進む約100名を選抜 | ホーム ページ |
| 全国高校化学グランプリ 国際化学オリンピック(IChO) |
2010年 5月~ 6月(予定) |
郵送 | 無料 | 2010年 7月19日(予定) |
全国約50カ所 | 二次選考に進む約80名を選抜 | ホーム ページ |
| 日本生物学オリンピック 「生物チャレンジ」 国際生物学オリンピック(IBO) |
2010年 4月~ 5月(予定) |
郵送 | 無料 | 2010年 7月(予定) |
全国約70カ所 | 筆記試験(マークシート)にて第二次試験に進む約80名を選抜 | ホーム ページ |
| 全国物理コンテスト 「物理チャレンジ」 国際物理オリンピック(IPhO) |
2010年 4月(予定) |
郵送 | 無料 | 2010年6月(予定) |
全国約70カ所 | 理論問題(筆記試験)と実験課題レポートにより第2チャレンジに進む約100名を選抜 | ホーム ページ |
| 日本情報オリンピック 国際情報オリンピック(IOI) |
2009年 9月1日~ 12月11日 |
ウェブサイト | 無料 | 2009年 12月13日 |
ウェブ上にて オンラインで実施 |
PCを使った実技試験で本選に進む約50名を選抜 | ホーム ページ |
※数学では中学3年以下を対象とした「日本ジュニア数学オリンピック」も開催しています。
日本地学オリンピックの参加者を募集しています。
第2回日本地学オリンピックに参加する、高校生と中学3年生を募集します。この大会は2010年9月にインドネシアで開催予定の、第4回国際地学オリンピックの日本代表選手の選考を兼ねており、予選と本選の2回の試験を実施します。
日本中の地学が好きな仲間と真剣に知力を競い合うとともに、親睦を深めることもできる絶好の機会です。地学に情熱を注ぐ生徒の挑戦をお待ちしております。

募集期間:2009年10月1日~11月30日
予選(一次選抜):2009年12月20日(高校3年生も参加可能)
本選(二次選抜):2010年3月24日~26日(茨城県つくば市にて実施)
※地学オリンピックの詳しい情報はホームページhttp://www.chigakun.sakura.ne.jpでご確認ください。
![]()
日本が出場した科学オリンピックの全教科で全選手がメダルを獲得!
国際科学オリンピックはスポーツのオリンピックと異なり、成績優秀者の上位10%に金メダル、次の20%に銀メダル、次の30%に銅メダルが授与されます(教科により異なる場合があります)。
2009年の国際科学オリンピックでは、日本で開催された生物学オリンピックで幸先よく日本代表の全選手がメダルを獲得しました。続く物理・数学・化学・情報のすべてのオリンピックでも全員がメダルを手にし、さらに全教科で金メダリストを輩出するという快挙を達成。
なかでも数学オリンピックは6人中5人が金メダルを獲得し、国・地域別順位で2位という輝かしい成績を収めました。
理数教育への期待が高まっている昨今、年々国内予選の参加者数を増やし、指導やサポートにも力を注いでいる日本の科学オリンピックへの取り組みは、将来への大きな希望となるでしょう。