授業・科学部活動への導入法を探る
国際科学オリンピックの過去問題などを題材にした高校理科教員向けの研修が、8月17日に茨城県立土浦第一高校で行われました。世界水準の理科教育に触れることで指導力アップを図ってもらおうと、国立研究開発法人科学技術振興機構が各地の教育委員会などと連携して、2011年から実施している研修です。
当日は、茨城県高等学校教育研究会理化部に所属する約60人の教員が参加。化学と物理の2教科に分かれて実験問題などに取り組み、授業や科学系部活動に応用するポイントを探りました。
化学の研修課題は、ランベール・ベールの法則を活用した水溶液中の鉄イオンの濃度分析です。参加者は、中村朝夫・芝浦工業大学教授と米澤宣行・東京農工大学教授の指導を受けながら、溶液濃度を目視で調べる手法と、分光光度計による計測を体験。両者を比較検討することで、結果に至るプロセスや濃度測定の原理への理解を深めました。
まとめでは、国際化学オリンピックのシラバスを参考に、世界と日本の化学教育の現状を話し合いました。中村教授は、今年7月の米国大会で、日本代表生徒が実験課題で世界トップの成績を収めたことを報告。「日本の生徒は実験が苦手とされるが、準備学習や高校での指導で力をつけることができる」と話し、高校の実験授業の重要性を強調しました。

科学オリンピックへの親近感もアップ
物理の研修では、国内大会で実際に使用された器具を用いて、剛体の回転運動や剛体振子など複数の実験課題にチャレンジ。講師を務めた北原和夫・東京理科大学教授と近藤泰洋・元東北大学教授は、こうした実験を授業や部活指導に生かすポイントをアドバイスしていました。
化学の研修に参加した茨城県立下館第一高校の四家明彦教諭は、「大学で学んだことを教師の視点で再確認し、改めて気づいたことが多い。授業のネタを仕入れることができました」と感想を語ります。また、自ら実験課題に取り組むことで化学オリンピックへの親近感も高まったとし、「本校から化学オリンピックに挑戦する生徒が出てきたとき、自分にもある程度の指導ができそう」と話していました。
女子中高生を対象にした国際科学オリンピック ワークショップ
~環境に優しい有機化学反応~
世界中の化学好きが集う「国際化学オリンピック」。そこでは学校の授業とは違う化学の世界が展開されています。名古屋市のトヨタテクノミュージアムの一角で開催された実験ワークショップでは,国際化学オリンピックイギリス大会で出題された「アルドール縮合」を課題に,22名の女子中高生が有機合成化学実験に取り組みました。
今回は,化学オリンピック国際大会の参加経験者である大学生4人が講師となって,実験手順や器具の扱い方の詳しい説明をするなど,参加者との交流を図りながらの指導を心がけ,参加した【リケジョ】達も,積極的に講師に質問を重ねながら,全員が実験を完了しました。終了後は,「難しかったけれど,説明もわかり易く楽しく実験ができた」との声が多く聞かれました。

*【リケジョ】理系女子のこと。今回の参加者は,研究者,化学者,薬剤師,臨床医,管理栄養士など,理系を志す人が多数でした。
実験操作の内容
今回行ったのは,1-インダノンと3,4-ジメトキシベンズアルデヒドという2つの物質のアルドール反応です。反応には溶媒を用いないという特徴がある実験です。この2つの物質を混ぜて,液体になったところに,水酸化ナトリウムを加えると,ここでアルドール反応が起こって,炭素と炭素の新しい結合ができますが,違った物質に変わったことで,液体ではなく固体になってしまいます。この固体を塩酸で洗い,その後濾過し,固体から液体成分を吸い取る,という実験です。溶媒を使わないことで,実験者が目の前の物質の変化をしっかりと把握して適切な対応をすることが求められるタフな実験です。
今回は,濾過操作を大胆に簡略化しました。これは,実験者が操作の正確さに神経を使いきって,物質の変化を追いかけられなくなるようなことがないようにと考えてのことです。
実験の背景~有機合成化学
宇宙はいろいろな物質からなりたっています。私たちのすぐ近く,日常生活に限って考えると,自身の体自体も含め有機物質が大きな部分を占めます。それ以外の物質は無機物質です。私たちの周囲の物質は大体いろいろなものの混じりあった状態にありますが,それを人為的に選り分けて,大体純粋な状態にして有機物の性質や,別の物質に変わることを学ぶのが有機化学という化学の一分野です。その中で大きな割合を占めるのが「有機合成」とよばれる,欲しい有機物質を作る化学です。
有機合成化学,私たちの生活に密接に関わっているのですが,高校の化学ではほとんど勉強しません。有機物質を使う実験そのものも非常に少ないのです。これはなぜでしょうか? いろいろ理由はあると思いますが,物質が変わるときには一緒にいろいろなものができるのでそれを分けたり,純品と呼ばれるきれいな状態にするのが大変ということもあるでしょう。特に大きいのが実験廃棄物の処理でしょう。
通常有機反応は溶液中で行います。きれいな溶剤に溶かして,反応を行うということはそこにいろいろ雑多なものを混ぜることを意味します。こういう状態が汚れた状態です。溶剤の中には蒸発して空気に混じるものもあります。
ここで出てくる考えが,「有機溶剤を使わないで反応させたらよいだろう」ということ。有機溶剤の代わりに水を使う,などという試みもあります。究極には溶媒を使わないで,必要なものだけを混ぜあわせて,欲しい物だけできてくればよいわけです。言うのは簡単ですが,実際はどうでしょうか?(次ページへ続く)
さて,国際化学オリンピック第41回イギリス大会の実験問題として出されたこの問題(一部省略してありますが)は,反応時に有機溶剤を使わない,有機合成反応です。反応の種類としては,「炭素-炭素結合生成反応」,反応の名前は「アルドール反応」ですが,その中の「交差型」の属するもので,結構複雑な反応です。また,溶剤を使わないということで,実は溶媒和とか,「物質が物質に溶ける」ということについてもよく知らなければなりません。さらに、この反応がうまく行っても,異性体といって,分子を構成する原子の種類も数も同じだけど,よくみると構造に違いがあるものが複数できてもおかしくなく,どれが(主に)できているかを確かめる必要もあります。
ということですが,今回は,とにかく有機合成をやってみよう,そのとき,簡略化できる操作は簡略化して進めようという試みです。化学実験はいろいろな操作が必要です。それを正確に,間違いのないように終わらせよう,ということばかり考えるあまりに,肝心の物質の変化を観察することがおろそかになってしまったら元も子もありません。
さて,実験の最初,1-インダノンと3,4-ジメトキシベンズアルデヒドは固体状態ですり混ぜると,粘度の高い液体になります。ここまでは確かに溶剤を使わなくてすみました。
次にこの液体に,やはり固体の水酸化ナトリウムを加えます。この段階で「アルドール反応」が進行します。(ここでは本文の最後の注釈に示した反応がおきます。)
反応が進行すると今度は固体になります。ここが大事で,一生懸命かき混ぜなければいけません。この労力で,どのくらいたくさんきれいなものがとれたか,という有機合成化学の評価に差が出ることになります。元々粘っこい液体が固体に変わるということは,中の分子たちは非常に動きにくくなります。反応で生じた熱がある部分にこもって過熱状態になることもあります。ある部分では未反応の分子が足止めを食らったり,ある部分では高温でさらにいろいろな反応が起きたり,ムラが生じることになります。それと比べると,溶液中の反応は分子と熱の移動(拡散)が容易という利点があるのです。
カチカチになった固体は,2つの原料物質と水酸化ナトリウムからできたいろいろなものの混合物です。通常の有機合成の操作では,溶液に溶けているものであれば,それと混じらない溶剤で振って洗い,固体が出てくれば濾過で液体部分と分けることを行います。ここでは,固体に塩酸を混ぜてかき混ぜ,混ざり物の中から塩基性成分を塩酸に溶かしだします。固体を細かくすりつぶして丹念に洗ってあげると,残った固体の主な成分が目的物ということになります。これをお茶漉しの不織布で濾して固体を集めます。後は,それを紙で挟んで塩酸とそこに溶けている物質を固体から取り出します。
ここで得られたものはまだ純度が不十分な粗い物質,粗生成物と呼びます。これは,化学オリンピックの実験試験のように再結晶をすることで,十分に純度の高いものになっているはずです。今回のイベントでは再結晶は行わず,薄層クロマトグラフィーでどの程度の混じり物になっているか,余計なものが検出できない程度にきれいになっているか確認しました。
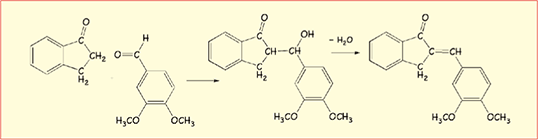
酢酸、アセトンなどの簡単な構造の,小さな有機化合物から炭素数の多い複雑な有機化合物を作るには,炭素-炭素結合を新たに作る必要があります。アルドール反応は炭素-炭素結合を作ることができるので,大きな有機化合物を生成する基本的な反応の一つです。
ここ10数年,「グリーンケミストリー」,「環境に優しい化学」などということば,化学の手法を変革しようという動きが盛んです。
通常アルドール反応を行うのには適切な有機溶媒を用いますが,使用する溶媒の量を極力減らし環境に配慮しようという点が,今回の実験のポイントです。国際大会で実験結果の順番付けは,有機合成化学の実験における通常の評価点,目的の物質だけ(=純度)を,たくさん合成すること(=収量)ができたか,の2点が審査されました。

