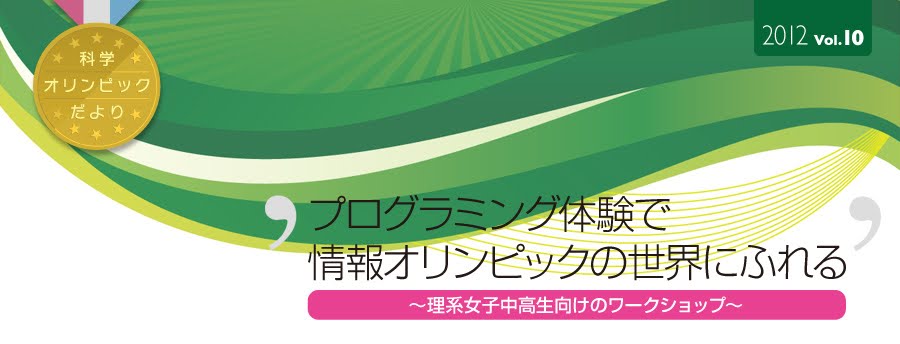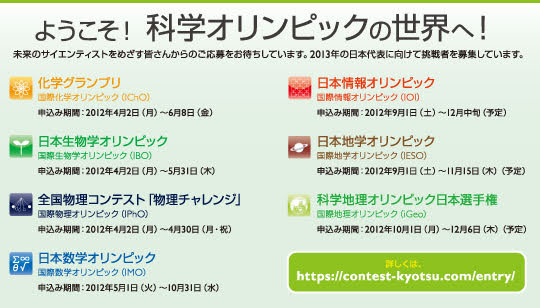身体を動かして遊ぶゲーム作りに挑戦

デジタル作品づくりでプログラミングの楽しさを体験するイベント「スクラッチで体験するプログラミング・ワークショップ ~のぞいてみよう!情報オリンピックの世界~」(主催・特定非営利活動法人 情報オリンピック日本委員会、国立研究開発法人科学技術振興機構)が、2月4日に都内で開かれました。
参加したのは、“リケジョ”として最近話題の理系女子中高生たち。阿部和広・サイバー大学客員教授の指導で、プログラミングソフト「スクラッチ」と人体の動きを感知するモーションセンサーを使ったゲームづくりに挑戦しました。

参加者たちはまず、ソフトを操作し、センサーの前で手足を動かしてプログラミングの基本的な働きを理解。その後は2人1組で作品づくりに取り組みました。四方から飛んでくるボールを両手でキャッチするゲームや、飛び回るドラゴンを避けて帽子と蝶ネクタイを身に着けるゲームなどユニークな作品が完成し、全員でゲームを体験して相互評価を行いました。
情報オリンピックから将来の活躍の場へ
まとめでは、国際情報オリンピック・2006年大会日本代表の秋葉拓哉さん(東京大学大学院)が、ワークショップの内容とコンピュータ科学や情報オリンピックとの関連を紹介しました。国内では男性中心とされるプログラミングの分野も、世界では第一線で活躍する女性が多く、「日本でも今後はみなさんの感性が必要とされる」と強調。「コンピュータ科学に興味を持ったら、まずは情報オリンピックに挑戦を」と呼びかけました。
参加した小原海莉さん(世田谷区立富士中学校・3年)は、「身体の動きを加えると、単純なプログラムでも楽しい作品がつくれることがわかりました」とうれしそう。原愛美さん(都内私立高校・2年)は、「表現したいものを自分の手でつくれるのがプログラミングの魅力。家でもじっくり学んでみたい」と感想を語りました。
講師の阿部氏は、「プログラミングは楽しいものであり、自分のアイデアを表現できる手段であることを、作品づくりを通じて知ってもらえたのでは」とワークショップを総括していました。
科学オリンピックの魅力を授業づくりに生かす
~埼玉県が教員向け研修を実施~
国際科学オリンピックの課題を活用した学習指導を検討する教員研修が、2月25日に埼玉県立総合教育センターで開かれました(主催:埼玉県教育委員会、国立研究開発法人科学技術振興機構)。県内から高等学校教員44人が参加し、生物学、化学、情報の3つの講座で講義と実習に取り組みました。
生物学の講座は、町田龍一郎・筑波大学大学院教授の指導で、動物学系統分類の講義に続きカイコの解剖を体験。化学は、溶液の濃度分析実験を題材に、中村朝夫・芝浦工業大学教授らが授業づくりについてアドバイスしました。谷聖一・日本大学教授らが担当した情報の講座では、アルゴリズムの設計と実装について実際にプログラミングを行いながら学びました。
参加者は、「カイコのように生活と関連付けられる題材は好奇心を醸成しやすい。ぜひ授業に取り入れていきたい」(県立桶川高校 教諭)、「教員にとっても非常に勉強になる内容。今日学んだことを生徒に還元したい」(県立浦和第一女子高校 教諭)と感想を話していました。