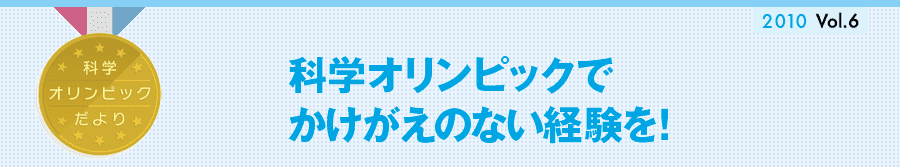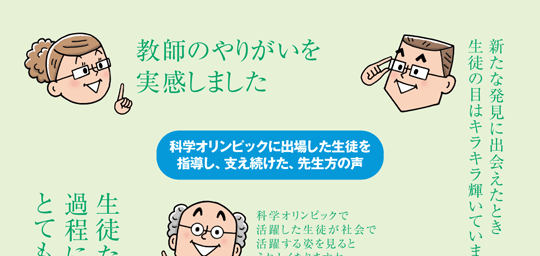
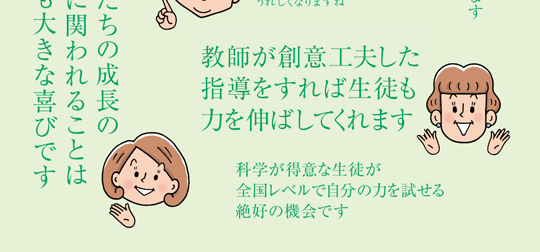
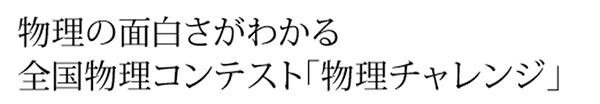
全国の物理好きの高校生や中学生が挑戦する物理チャレンジ。参加者は年々増え続け、2009年は896名が応募しました。問題は暗記した知識を問うようなものは少なく、論理的な思考力や発想の転換が求められ、物理の本質的な力が試されます。
以下に、2009年の物理チャレンジ(第1チャレンジ)に出題された問題をご紹介します。
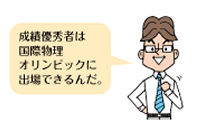
問題無重量状態で起こる不思議現象
2009年物理チャレンジ(第1チャレンジ)の試験問題(一部改変)

ドッキング前のスペースシャトル「エンデバー号」

宇宙ステーション「きぼう」内で無重量状態の3人の宇宙飛行士
左上:野口聡一 右上:スティーブン・ロビンソン 下:テリー・バーツ
問1
宇宙ステーションやスペースシャトルの中では無重量状態となっている。なぜ、そのような状態になるのか。最も適当に説明している文を、次の①~⑤の中から1つ選びなさい。
- ①地表からはるか遠いところにあるため。
- ②まわりに空気がないため。
- ③遠心力の方が重力より大きいため。
- ④重力にしたがって加速度運動しているため。
- ⑤ロケットエンジンで推進力を得ているため。
問2
- 宇宙ステーションの中で、宇宙飛行士は健康管理のため、毎日自分の体重を測定している。どのような方法で自分の体重を測定するのだろうか。最も適当な文を、次の①~⑤の中から1つ選びなさい。
- ①地上にあるものと同じ体重計を用いる。
- ②大きな天秤を用いる。
- ③ばね定数が既知のばねの一端に体を固定し、振動させて周期を測る。
- ④丈夫なひもの一端に体を固定し、振り子にして周期を測る。
- ⑤体を回転運動させて、その周期を測る。
「無重量状態」ってなに?
無重量状態とは、重力が何らかの影響で打ち消され、物体の重さ(重量)がなくなった状隠のことを言います。宇宙ステーションやスペースシャトルが周回している高度300~400kmは、地球の重力の影響を受けていますが、周回運動の影響で重力が打ち消され、重さ(重量)がない状態になっています。このとき、「無重力状態」という言葉を使うと地球の重力がないという意味に誤解される恐れがあるため、近年、「無重量状態」という表現を使うようになってきました。

問1解法「落下」が無重量状態を作り出す
宇宙ステーションやスペースシャトルは、地球の上空をグルグルと周回していますが、その仕組みは、地球上で投げた物体が落下するときと同じ原理を利用しています。
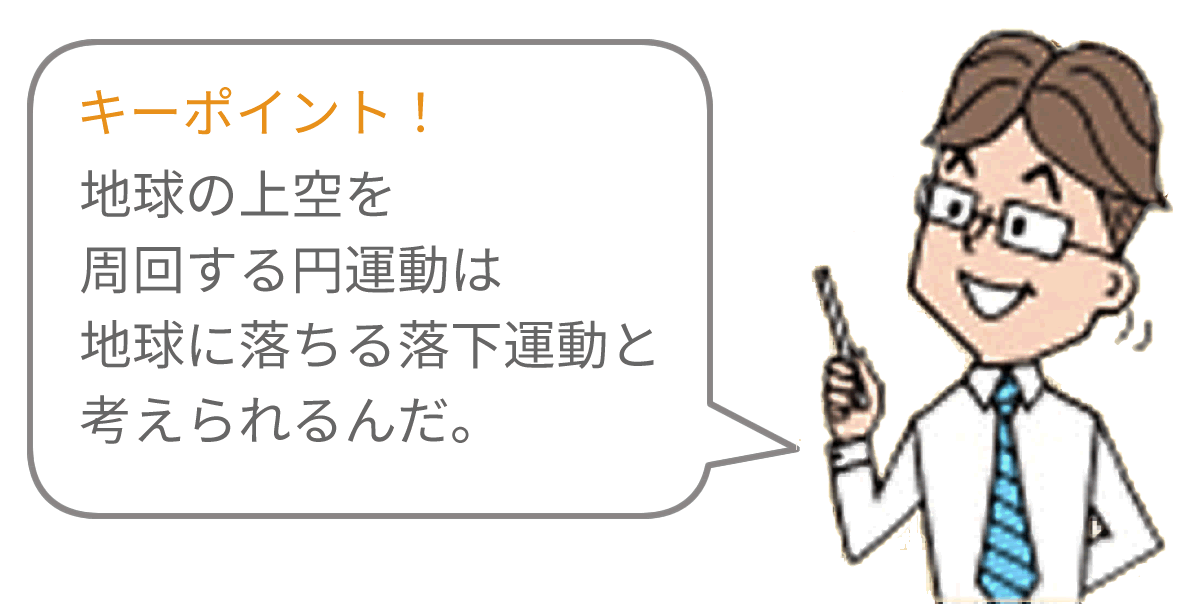
問1の解法
地球に「落ち続ける」から「回り続ける」
水平に投げ出された物体は、スピードが遅いときは手前に、速いときは遠くに落ちます。スピードをとても速くすると、落ちるときの放物線(カーブ)が地球の形状(丸み)と一致して、地球を回り続けることができます(空気抵抗を無視できる場合)。もし地球に重力がなければ、物体はレーザー光線のようにまっすぐ進み、円運動にはなりません。
投げるスピードをどんどん速くすると、やがて地球の形状に沿って落ち続ける。
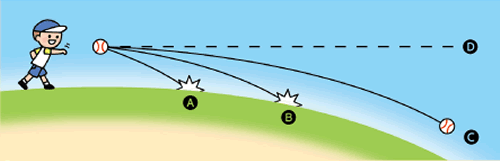
- Aスピードが運いときは 前に落ちる
- Bスピードが運いときは遠くに落ちる
- Cスピードがとても速いとさは地球の丸みに沿つていつまでも落ち続ける
- D重力がないときはレーザー光線のようにまっすぐ進む
自由落下によって無重量状態に
宇宙ステーションやスペースシャトルは、地球の重力圏内を周回しています。つまり地球に向かって落下しているのですが、充分な速さがあるため地球の形状(丸み)に沿って落ち続けています。このとき、宇宙飛行士・荷物・空気など、すべての物体が落下するため、船内は重さのない状態(無重量状態)となります。
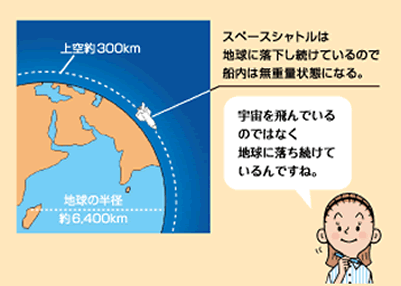
問1解答④重力に従って加速度運動しているため。
解答の解説
物体が重力にしたがって落下(自由落下)すると、無重量状態となります。宇宙飛行士の訓練のひとつに、自由落下する飛行機の中で約25秒間の無重量状態を体感するものがあります。
この解答は観測者が地球にいるという前提で考えていますが、仮に宇宙ステーションやスペースシャトルにいた場合は、「重力と遠心力が等しい大きさになり無重量になる」という答えも成立します。ただし、③は遠心力の方が重力より大きいとあるので不正解です。
月は落ちている
ニュートンは「リンゴが木から落ちるのを見て引力の存在に気づいた」と言われていますが、そこから「なぜ月は落ちないのだろうか」とも考えたそうです。ニュートンは万有引力の法則で、「落ちる」の意味を「上から下に運動する」ではなく「引力を受けて運動する」という意味に転換し、「月は落ちている」という結論を導き出しました。地球の上空を回る人工衛星や、太陽の周囲を回る惑星も、この問題と同じ原理で落下による円運動をし続けています。
問2解法質量の性質に注目して考える
私たちが普段使っている体重計は、重量が下向きに働く性質を利用しています。無重量状態のスペースシャトルの中で体重を量るには、『質量の性質』を利用する必要があります。
問2の解法
重量と質量の違い
「重量」とは、重力によって生じる下向きの「力」のことです。月面では地球のおよそ1/6になり、無重量状態ではゼロになります。一方、「質量」は物質の「量」を表す単位で、宇宙のどんな場所でも一定です。地球上では重量と質量の値は同じですが無重量状態では異なり、重量と質量の性質の違いがはっきりと表れます。
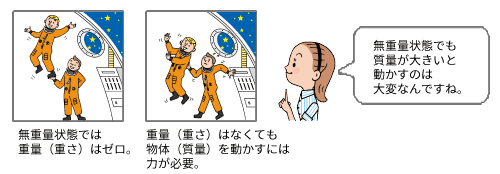
質量を計る工夫
質量の大きさは「運動の変わりにくさ」と言うこともできます。重さのない無重量状態では、質量が小さい物体は簡単に動かせますが、大きい物体を動かすには大きな力が必要です。また、動いている物体も同様で、質量が小さければ簡単に止められますが、大きいものだと大変です。この点に注意して問題を整理してみます。
■重量の性質「下向きに働く力」を利用した装置
- ①体重計…重量で下向きに押し込まれたばねの変化を測る
- ②天 秤…互いに下向きに働く重量を比較して測る
- ④振り子…重量で往来する振り子の振動周期を測る
■質量の性質「運動の変わりにくさ」を利用した装置
- ③ばねの振動…ばねの反動で振動する周期を測る
- ⑤回転の周期…外力で体を回転させてその周期を測る
問2解答ばね定数が既知のばねの一端に身体を固定し、振動させて周期を測る
解答の解説
ばねは、変形させた距離に比例して復元力が生じます。無重量状態でばねと体を接続して決まった長さだけ引っ張ると、ばねを引っ張った力と同じ大きさの復元力で振動し始めます。このとき、体の質量(加速しにくさ)が大きいほどばねが振動する周期は長くなり、そこから質量を計算することができます。
なお⑤の回転運動は、毎回同じ姿勢で同じ力を加えることができれば、理論的には質量の測定は可能です。しかし緻密な制御を必要とするため、現実的ではありません。
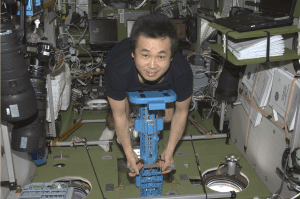
ばねの振動を使って体重計測をしている若田光一宇宙飛行士
ココが面白い!物理チャレンジの問題
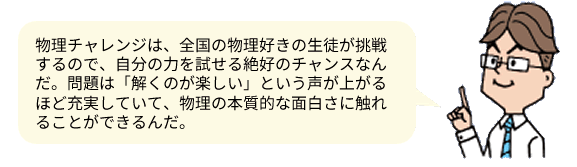
身近な物理に関心を向け、考える力を伸ばす問題
物理は、日常生活のさまざまな場面に存在しています。物理チャレンジでは、身の回りにある物理現象をテーマにした問題を数多く出題し、生徒の物理への興味・関心を高める工夫をしています。
また、物理チャレンジは国際物理オリンピックの代表生徒を選ぶだけでなく、参加した生徒の力を伸ばすことも目的に開催されています。問題を解く過程で思考力が鍛えられ、新たな知識を身に付けることができるよう、問題づくりはとても入念に行われています。
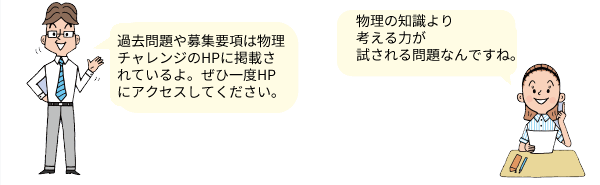
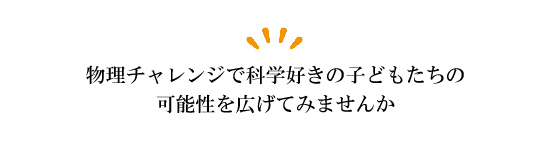
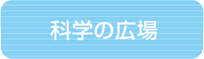
科学教育への提言
考える力のある生徒が、楽しんで伸びる
洗足学園中学高等学校(神奈川県川崎市) 神谷史穂先生
近年、科学オリンピックに挑戦する生徒が増えている私立洗足学園。生徒たちの背中を押し、参加の手助けをしている理科の神谷史穂先生に、子どもたちが科学オリンピックにチャレンジする意義について伺いました。

以前に教えた生徒で、海外の学校にいて理科を習わないまま、中学2 年に編入してきた帰国生がいました。はじめは授業についていけず悩んでいたようですが「どんな本を読んだらいいですか?」と聞きに来たり、わからないことはすぐに質問したりするような生徒で、理解が深まるにつれ理科が好きになり、力もどんどんと伸びていきました。高校生になると学校外での実験イベントや天文学実習、さらに全国高校化学グランプリや物理チャレンジにも参加するようになりました。知識よりも思考力を試される科学オリンピックの難しい問題も、楽しみながら解いていたようです。日本代表には選出されませんでしたが、今も大学で化学を学んでいます。
最初から理科が得意でなくても、自ら考え、探求することが好きなすべての子どもたちにとって、科学オリンピックは楽しみながら力を伸ばすことができる素晴らしい機会になると思います。
世界標準の科学に触れて
スタートラインは、みんな同じです
東京大学理科一類2年生 松元叡一さん
国際情報オリンピックでは2年連続で銅メダルを獲得し、
物理オリンピックでも銀メダルを獲得した松元叡一さん。
世界の舞台でどんなことを経験し、何を感じたのか、詳しくお聞きしました。

国際科学オリンピックに出場したことで、自分より優秀な人たちや、自分がすごいと思っていた人をさらに上回るような人たちとたくさん出会いました。世界の広さを感じたと同時に、彼らと直接に出会えたことでその人柄がわかって、確かにみんなすごいけれど、やはり自分と同じ人間なんだと実感することができたんです。
国際科学オリンピックに参加することは、けっして特別なことではありません。僕は、物理も情報もほぼゼロに近い知識レベルから挑戦し、予選、本選と各試験に向けて勉強するなかで段階的に力を伸ばしていきました。スタートラインは、みんな同じです。自分には無理だと決めつけず、少しでも興味があればまず受けてみてください。そこでしか出会えない仲間がきっと見つかると思います。
| 教科・科目 | 応募期間 | 応募方法 | 1次試験日 | 1次試験会場 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本数学オリンピック 国際数学オリンピック(IMO) |
2011年 5月1日(日)~ 10月31日(月) |
郵便振替 | 2012年 1月9日(月・祝) |
全国約60カ所 | ホーム ページ |
| 全国高校化学グランプリ 国際化学オリンピック(IChO) |
2011年 4月1日(金)~ 6月10日(金) |
郵送・ウェブサイト | 2011年 7月18日(月・祝) |
全国約50カ所 | ホーム ページ |
| 日本生物学オリンピック2011 国際生物学オリンピック(IBO) |
2011年 4月1日(金)~ 5月31日(火) |
郵送・ウェブサイト | 2011年 7月17日(日) |
全国約80カ所 | ホーム ページ |
| 全国物理コンテスト 「物理チャレンジ」 国際物理オリンピック(IPhO) |
2011年 4月1日(金)~ 4月30日(土) |
郵送・ウェブサイト | 2011年 6月6日(月),19日(日) |
全国約70カ所 | ホーム ページ |
| 日本情報オリンピック 国際情報オリンピック(IOI) |
2011年 9月1日(木)~ 12月中旬(予定) |
ウェブサイト | 2011年 12月中旬(予定) |
ウェブ上にて オンラインで実施 |
ホーム ページ |
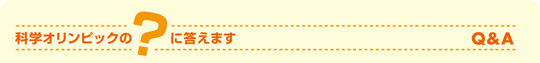
- Q.どうしたら国際大会に出場できますか?
- A.教科ごとに行われる国内予選で好成績を挙げると、日本の代表として出場することができます。スケジュールや募集要項は上記のHPでご確認ください。
- Q.どんな問題が出るのですか?
- A.科学の知識よりも、思考力や柔軟な発想が求められる問題が多く出題されます。そのため、生徒から「解くのが面白かった」という声も上がっています。
- Q.これまで日本で開催したことは?
- A.2003年に東京で国際数学オリンピック、2009年に茨城県つくば市で国際生物学オリンピックが開催されました。2010年は東京で国際化学オリンピックが行われます。
![]()
目指せ金メダル!オリンピックゆかりの地で競い、
友情を深めた日本情報オリンピック本選
2010年の夏にカナダで開催される第22回国際情報オリンピック。531名が参加したオンラインの予選から60名が選ばれ、2月に東京の国立オリンピック記念青少年総合センターで1泊2日の本選が行われました。試験後は、カーナビの渋滞予測システムに関する講演や、参加者の懇親会が催され、学校ではなかなか出会えない仲間と交流する機会となりました。本選で好成績を挙げた16名は3月に国際レベルのトレーニングと試験を受け、その結果をもとに4名の日本代表を選抜。年々、実力アップしてきた日本の選手たち、今年の国際大会での活躍に期待が掛かります。