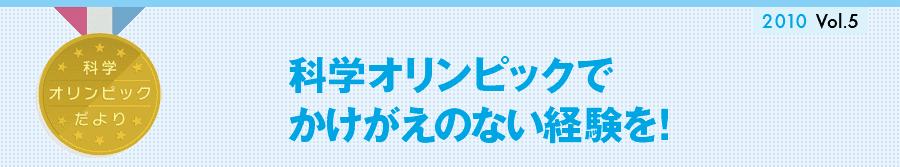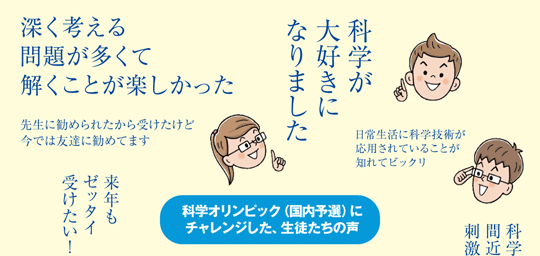
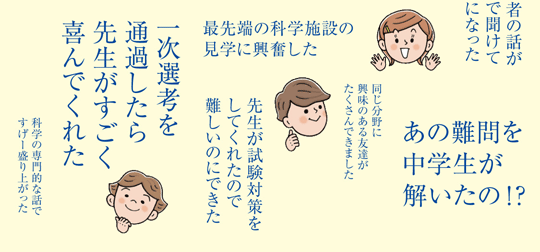
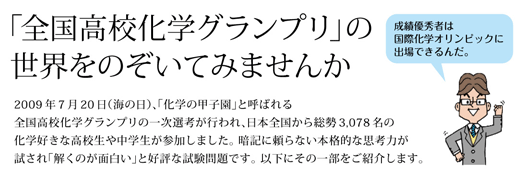
問題日本人が発見した、未来を灯すテクノロジー!光触媒
2009年全国高校化学グランプリの一次選考問題(一部改変)
光のエネルギーによって汚れや臭いの原因となる物質を分解する光触媒は、本多健一博士と藤嶋昭博士の発見が基礎になって生まれた日本発の機能材料である。光触媒としては、主に二酸化チタン(TiO2 )が用いられる。二酸化チタンは、可視光より波長の短い紫外光を吸収する。二酸化チタンが紫外光の光子(光の粒子)を吸収すると、O2-の持つ電子一つが、エネルギー状態の高いTi4+に移る。 この電子を励起(れいき)電子と呼び、電子が抜け+に帯電した“孔”を正孔(せいこう)と呼ぶ。電子は、よりエネルギーの低い状態を好むので、励起電子は近くにある分子やイオンに渡る(還元する)場合がある。これによりニ酸化チタンに正孔ができ、近くにある汚れや臭いの原因となる物質から電子を奪い(酸化し)、それらを分解すると考えられている。
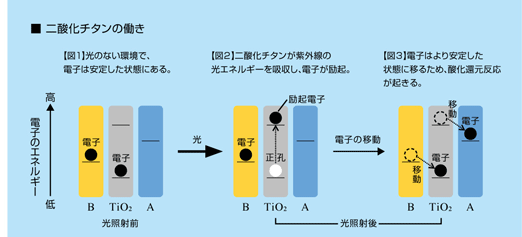
問1
光触媒を用いて励起電子により水を還元して水素を生成し(反応1)、正孔によって水を酸化して酸素を生成することができれば(反応2) 、その水素を燃料電池に利用したり、燃焼したりできるため、光エネルギーを化学エネルギーに変換したことになる。
反応1と反応2をそれぞれ、電子(e-)を含む反応式で表しなさい。
(電子を含む反応式の例: A + e- → A-)
酸化…物質が電子e-を放出する変化
還元…物質が電子e-を受け取る変化
問2
植物の光合成の反応には、光触媒の反応と似ている部分がある。光合成では、光を吸収して電子のエネルギーが高くなり、 ①そのエネルギーによって二酸化炭素を還元し、ブドウ糖(C6H12O6)などを得る。②同時に、水から電子を奪い、酸素へと酸化する。 そして、 ③動物の多くは、植物からブドウ糖などを得て、それが酸素に電子を渡す際に放出されるエネルギーを利用して、生命活動を行っている。 このことから、光が当たらない条件において、以下のどの組み合わせが酸化還元反応を起こしやすいか選びなさい。
ア)二酸化炭素と水 イ)二酸化炭素と酸素 ウ)ブドウ糖と酸素
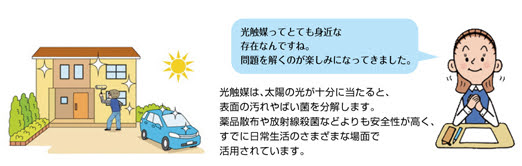
問1解法光触媒の仕組み
光触媒は、反応の前後で自身は変化することなく、光のエネルギーを受け取って接触面で化学反応を促進させる物質です。
二酸化チタンに紫外光が吸収されると、そのエネルギーによって酸化還元反応が起こります。
問1の解法
<反応1>
水が励起電子(e-)を受け取り、水素分子が生成される様子は次のように表せます。
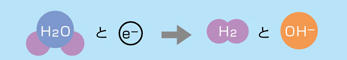
それぞれの原子と電荷の数が合うような係数を求めます。
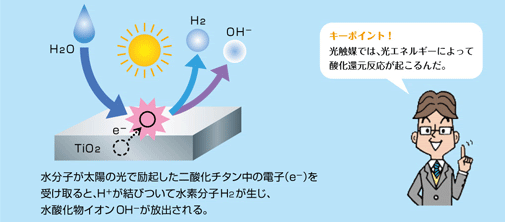
<反応2>
正孔(+)で水から電子が放出され、酸素分子が生成される様子は次のように表せます。
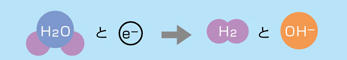
それぞれの原子と電荷の数が合うような係数を求めます。
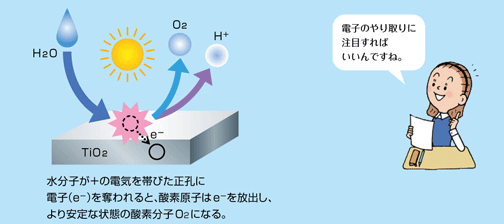
問1解答<反応1>
2H2O+2e- → H2+2OH-
<反応2>
2H2O → O2+4H+4e-
解答の解説
化学反応式にして表すと、水の電気分解と同じ分解反応であることがわかります。 電気分解の場合は2つの電極間に電源からの電圧をかけますが、光触媒では電気エネルギーの代わりに光のエネルギーを利用します。 この現象は日本人の本多博士と藤嶋博士が発見したため、本多-藤嶋効果と呼ばれています。
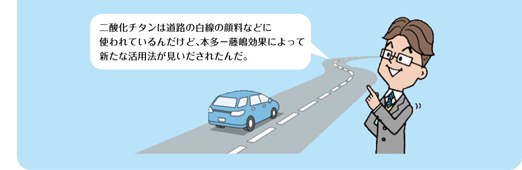
問2解法生命と光触媒の意外な関係
光合成の反応はとても複雑ですが、
光触媒の反応とよく似ている部分もあります。ここではエネルギーの出入りに着目し、
物質の酸化還元反応と合わせて考えていきます。
問2の解法
問2の問題文を整理すると、下図のような3つの化学変化にまとめられます。 光エネルギーがない状況では、どの反応が起こりやすいかを予想します。
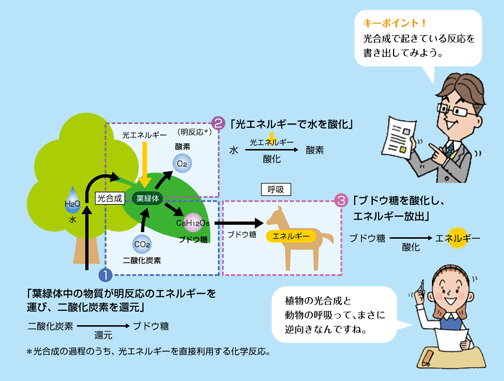
酸素を使ってエネルギーを取り出し、二酸化炭素を排出することを「呼吸」と呼びます。「光合成」は、光エネルギーを有機物質の化学エネルギーに変換します。 植物自身および動物は、呼吸によって有機物からエネルギーを取り出して生命活動を維持しています。
光合成6CO2+6H2O+光エネルギー → C6H12O6+6O2
呼吸 C6H12O6+6O2→6CO2+6H2O+エネルギー
問2解答問2 ウ) ブドウ糖と酸素
解答の解説
ブドウ糖から酸素へ電子が渡るとき、エネルギーが放出されています。 ①と②の反応はエネルギーを必要とする反応なので、光が当たらない条件では③「ブドウ糖と酸素の酸化還元反応(呼吸)」が最も起こりやすくなります。
「できたら楽しい」の心が生んだ光触媒
本多-藤嶋効果を発見した藤嶋博士は、大学院の学生だった当時「光合成の仕組みを人工的にまねできたら楽しい」という一心で研究していました。 純粋な探究心から生まれた二酸化チタンの光触媒は今、環境負荷の少ないエネルギー源として注目される燃料電池への応用や、汚れを分解する建材、水質改善など、幅広い分野で実用化が進められています。
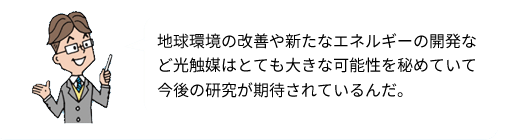
ココが面白い!全国高校化学グランプリの問題
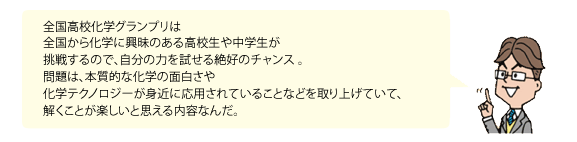
実践的な力を育てる問題
全国高校化学グランプリの問題は、基礎的な化学の原理が社会で応用されていく過程や、最先端の研究を意識して作題されています。また、試験後すぐに解答・解説が配付されるので、参加者は化学への理解をより一層深めることができます。
理解と考察力を試す内容
国際化学オリンピックでは、化学の原理・原則の理解を試す問題が出題されます。全国高校化学グランプリの問題も同様に、与えられた情報を正確に理解し、考える力を試されるように作られています。
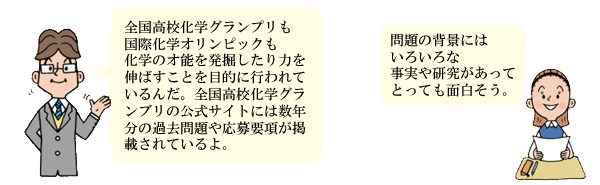
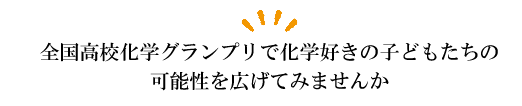
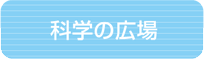
科学教育への提言
子どもたちが、もっと科学を好きになるために
品川区立小中一貫校 日野学園 山口晃弘副校長
小中学生を対象にした科学オリンピック・フェアでジュニア科学オリンピック * の実験問題を紹介してくださった山口晃弘先生に、子どもたちがもっと科学を好きになるためにどんな教育が必要か語っていただきました。

今、子どもたちの理科離れが危惧されていますが、学校の教育現場や科学イベントを見る限り、理科が好きな小中学生はたくさんいます。これからの課題は、そのような子どもたちの好奇心を広げ、探究心を深める機会を増やしていくことです。そのために、学校の授業で自然や科学と関わる場面を設けて、自然の性質やはたらき、規則性などを生活者視点で見直させたり、授業以外でも博物館や科学館などに行かせるのもいいでしょう。また、スポーツが得意な子どもたちが全国大会を目指すように、科学が得意な子どもたちが科学オリンピックを目指すような環境づくりもいいと思います。学校の中でも外でも、もっと子どもたちが自然や科学に触れる機会を増やし、夢中になって取り組んでもらえるようにしたいですね。
※ジュニア科学オリンピックは中学生以下を対象にした世界の科学コンテストです。日本は参加していません。
世界標準の科学に触れて
挑戦しないことは、もったいない
東京大学理科一類 1年生 村下湧音さん
国際物理オリンピックに日本代表として3年連続で出場し、 金メダルを2度受賞した村下湧音さん。 物理が好きになったきっかけや、 物理オリンピックにチャレンジする意義についてお話ししていただきました。

僕は3年続けて物理オリンピックに出場したのですが、特に物理が好きでも得意だったわけでもなく、応募したきっかけというのも母親の勧めでした。 ところが物理オリンピック国内予選の物理チャレンジの問題が、試験とは思えないほど面白く奥深くて、気づいたら5時間もの試験時間中、自分でも驚くほど集中して楽しんでいたんです。 この日を境に、 物理に興味を持つようになりました。
それだけでなく、物理オリンピックでのさまざまな経験や出会いによって、自分の可能性を大きく広げることができ、好きなことについて真剣に話せる仲間もできました。だから、もし受けようか悩んでいる人がいたら、絶対に受けてほしいと思います。挑戦しないことは、もったいないですから。
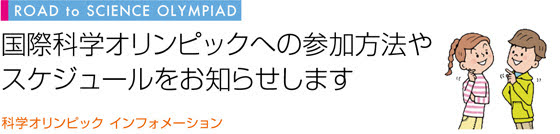
| 教科・科目 | 応募期間 | 応募方法 | 参加賞 | 試験日 | 会場 | 選抜方法 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本数学オリンピック 国際数学オリンピック(IMO) |
2010年 5月1日~ 10月31日 |
郵便振替 | 5,000円 (学校一括申込 割引制度あり) |
2010年 1月10日 |
全国約60カ所 | 単答式筆記試験にて本選に進む約100名を選抜 | ホーム ページ |
| 全国高校化学グランプリ 国際化学オリンピック(IChO) |
2010年 4月1日~ 6月4日 |
郵送 | 無料 | 2010年 7月19日 |
全国約50カ所 | 二次選考に進む約80名を選抜 | ホーム ページ |
| 日本生物学オリンピック 「生物チャレンジ」 国際生物学オリンピック(IBO) |
2010年 4月1日~ 5月31日 |
郵送 | 無料 | 2010年 7月18日 |
全国約70カ所 | 筆記試験(マークシート)にて第二次試験に進む約80名を選抜 | ホーム ページ |
| 全国物理コンテスト 「物理チャレンジ」 国際物理オリンピック(IPhO) |
2010年 4月1日~ 4月30日 |
郵送 | 無料 | 2010年5月31日 (実験課題レポート締切日) 2010年6月20日 |
全国約70カ所 | 理論問題(筆記試験)と実験課題レポートにより70名を選抜 | ホーム ページ |
| 日本情報オリンピック 国際情報オリンピック(IOI) |
2010年 9月1日~ 12月中旬(予定) |
ウェブサイト | 無料 | 2009年 12月中旬(予定) |
ウェブ上にて オンラインで実施 |
PCを使った実技試験で本選に進む約50名を選抜 | ホーム ページ |
※数学では中学3年以下を対象とした「日本ジュニア数学オリンピック」も開催しています。

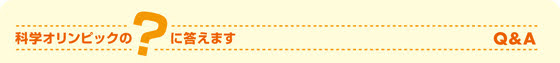
- Q.科学オリンピックに向けてどんな勉強をすればいいですか?
- A.科学の知識よりも、読解力や柔軟な発想が求められる問題が多く出題されます。 過去問題集や公式ガイドブックなどを活用すれば、考える力を養うことができます。
- Q.中学生でも応募することはできますか?
- A.すべての教科に応募できます。年々中学生の参加者は増えていて、国内予選で好成績を挙げ国際科学オリンピックに出場した中学生もいます。
- Q.成績優秀者に特典はありますか?
- A. AO入試や特別選抜入試などの、大学入試の特典があります。 詳しくは国際科学技術コンテストのウェブサイト(下記)かパンフレットでご確認ください。 また、教科によっては副賞や記念品などが贈呈されます。
![]()
知力を競い合い、親睦を深めあった全国物理コンテスト「物理チャレンジ」
国際物理オリンピックの選手選考を兼ねた「物理チャレンジ」の第2チャレンジ(2次試験)が、茨城県つくば市で開催されました。 9日間の日程で行われる本番の国際大会を意識して、試験は3泊4日の合宿形式で実施。 参加者はそれぞれ5時間に及ぶ理論試験と実験試験に取り組み、実験では学校で教わらないような「ばねの振動周期」の考察に挑戦しました。 その他、最先端の研究施設の見学やグループミーティングなどを通じて、参加者同士の親睦を深め合っていました。 「物理チャレンジ」と同様に、「全国高校化学グランプリ」や「生物チャレンジ」にも多くの生徒が参加しており、科学への関心の高さがうかがえます。