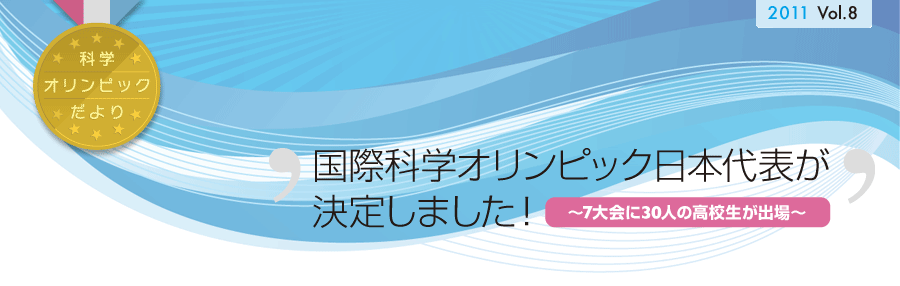一次選考の参加者は1万人近くに

生物学オリンピック本大会に向けて特別訓練に臨む
この夏開催される7教科の国際科学オリンピックに出場する日本代表30人が決定し、6月13日に記者説明会が行われました。
今年の国際科学オリンピックは、7月4日開幕の地理から始まり、化学、生物学、物理、数学、情報の各大会が7月中に、地学が9月に予定されています。それぞれの舞台で、世界中の高校生たちが「科学の力」を競い、交流を深めます。
日本代表の30人(うち1人は数学、情報の2大会に出場)は、各教科の国内一次選考に参加した約1万人から、数回の選考を経て選ばれました。その後、合宿形式の特別訓練などで実力アップを図り、本大会に臨みます。
日本のいまを世界の高校生に伝えたい

笠浦一海さん(開成高等学校2年)

副島智大さん(立教池袋高等学校2年)
各教科とも、例年は春休み中に代表を決定しますが、今年は東日本大震災の影響で選考が遅れました。実施時期や場所を変更した教科のほか、余震が続くなかで試験を行ったケースもあります。被災地から最終選考に参加し、代表に選ばれた生徒もいます。
国際物理オリンピック代表の笠浦一海さん(開成高等学校2年)と国際化学オリンピック代表の副島智大さん(立教池袋高等学校2年)は記者説明会で、「目標は高く金メダル。外国の生徒たちとも積極的に交流して、自分が成長する場にしたい」(笠浦さん)、「代表4人で唯一の2年生なので、3年生に引けを取らないようにがんばって、金メダルを目指したい」(副島さん)と意気込みを語りました。
その一方でふたりは、「震災後の日本の現状を誤解している海外の生徒もいると思う。正確な情報を直接伝えたい」(笠浦さん)、「地震や原発事故について、知る限りのことを教えてあげたい」(副島さん)と話し、日本の代表として、世界の高校生に情報発信したいという思いも抱いている様子でした。
国際大会を目指す生徒たちの熱意と、それを支える家族や関係者の尽力で実現した今回の代表派遣。いつもの年とは違う道のりを歩んできた、特別な30人の挑戦が始まっています。
困難を乗り越えてつかんだ国際大会へのチケット
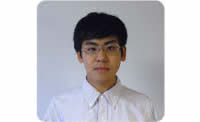
佐藤遼太郎さん(宮城県・秀光中等教育学校6年)
日本代表のなかに、今回の震災を身近に経験した高校生がいます。国際物理オリンピック代表の佐藤遼太郎さん(宮城県・秀光中等教育学校6年)です。多賀城市にある学校が地震の被害を受け、自宅近くにまで津波が押し寄せました。
3月の時点で代表候補11人に残っていた佐藤さん。移動や通信連絡が困難な状況のなか、「最終選考にはぜひ行かせたい」との両親の意向を受け、岡山大学での最終選考を兼ねた合宿に参加し代表の座を勝ち取りました。「答案の書き方がしっかりしていて、迫力があった。彼の芯の強さを感じました」と並木雅俊・物理オリンピック日本委員会副理事長は振り返ります。
佐藤さんはタイでの国際大会に向けて、「無事に参加できることに感謝し、チームメイトや他国の選手と交流を深め、大会を有意義なものにしたい」とコメントを寄せています。
ISFE出場の木村麻里さん(折り紙の研究)
ISEFで見せた未来に向けての力強い決意
5月8日~13日、米国カリフォルニア州で開催された、第62回国際学生科学フェア「Intel ISEF(International Science and Engineering Fair)」に、世界65カ国から1,500人以上の高校生たちが集い、研究成果を披露しました。
日本からの参加者の一人、木村麻里さん(選考当時2010年12月、立命館高等学校3年)は、「小さい頃から折り紙好き」だったこともあり、今回『折り紙を用いた多面体の切断・分割と空間の充填』と題したプロジェクトに取り組みました。
大会期間中、木村さんの研究はメディアからの取材を受けたり、他国の学生たちからも質問を受けたりと、注目度の大変高いものでしたが、残念なことに受賞には至りませんでした。「発表の仕方や練習もがんばってきたけれど、他のプロジェクトを見て、元々の勉強が足りていなかったと感じました。日本代表として、自分がこの会場にいてもよいのかとさえ思いました」と、授賞式直後には肩を落としていました。しかし、しばらくすると「ここでやめたら中途半端なまま。今後も数学の勉強を続けて行こうと思います」と、いつもの笑顔で未来へ向けての力強いコメントを語ってくれました。