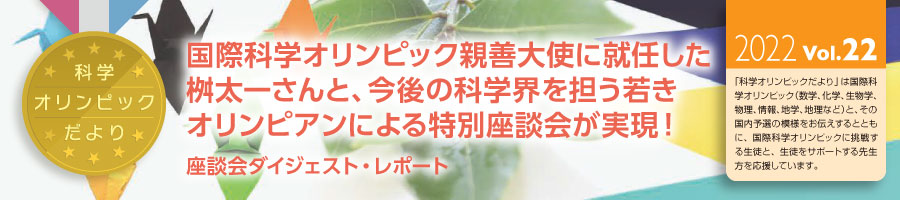2022年8月18日、今年5月に国際科学オリンピック親善大使に就任した同志社大学ハリス理化学研究所専任研究所員・助教の桝太一さんと、国際科学オリンピックに出場したオリンピアン3人との座談会が京都大学小林・益川記念室で行われました。オリンピアンを代表して参加したのは、2010年国際化学オリンピック金メダリストの齊藤颯さん、2019年国際化学オリンピック・2020年国際生物学オリンピックの金メダリスト末松万宙さん、そして、2020年国際化学オリンピック銀メダリストの林璃菜子さん。国際科学オリンピックに出場した経験とともに、科学との関わりや桝さんが現在研究テーマとして取り組む「サイエンスコミュニケーション」の重要性について活発に意見を交わしました。

桝太一さんとオリンピアンの3人がサイエンスコミュニケーションについて語り合う様子
まだまだ足りない?!
科学オリンピックの認知とオリンピアンに対する評価
桝さんがまず尋ねたのは、科学オリンピックを知った経緯と出場後の反応について。「校内に掲示されたポスターで知りました。僕の高校では、ほぼ毎年国際科学オリンピックの日本代表に選出される生徒がいたこともあり、出場自体が校内で大きな話題になることはあまりなかったです」と答えたのは齊藤さん。齊藤さんは現在京都大学大学院で助教として活躍する傍ら、国際化学オリンピック日本代表生徒の指導や国内大会の運営等にも携わっているといいます。一方、東京大学2年生の末松さんは、「僕が通っていた高校は数年に1人日本代表がいるかどうかという状況でした。しかし、所属していた理科系の部活動では国内予選に皆で参加する慣習があったので、僕が国際大会でメダルを獲得したときは先輩や先生が『すごいんだよ』と後輩たちによく話してくれていましたね」。SNSがきっかけだという林さんは、先輩や国内大会で出会った学校外の友人を通じて、情報を除く6つの国内大会に参加したそうです。その後、国際化学オリンピック出場経験を活かして京都大学医学部に飛び級進学しましたが、「飛び級進学で数多くのメディアから取材を受けました。ただ私自身は、国際科学オリンピックに向けて一生懸命取り組んだ学習の成果としてメダルを獲得できたことはとても嬉しかったけれど、その後の通過点としての飛び級進学ばかり注目されたことは正直複雑な思いがありました」と振り返りました。
3人の話を聞いた桝さんは、「これまでの地道な活動によって国内大会の参加者は2万人を超えたけれど、まだまだすべての生徒に認知されているとはいえないわけですね」と述べ、その背景の一つとして、国際科学オリンピック出場が甲子園やインターハイといったスポーツ同様の認知が周りから得られていないからではと投げかけました。林さんのように国際科学オリンピックや国内大会出場経験を大学受験の際に評価する事例などは増えつつありますが、齊藤さんは「確かに、僕が帰国後にテレビ取材を受けたときも、科学オリンピックの仕組みや競技内容について詳しく聞かれることは少なかったです。でも、たとえ説明したとしても、メディアの方々を含め、なかなか一般の視聴者には伝わりにくかったのかな」と応えました。
コロナ禍を機にあらためて実感した
科学と社会をつなぐ「サイエンスコミュニケーション」の重要性

科学オリンピックの認知を広めていくことの大切さについて話す桝太一さん
そうした科学と一般社会との分断が顕著になったのが新型コロナウイルス感染症の世界的流行だったと桝さん。未知の病気に対する不安やワクチンに関する不確実な情報が社会全体を覆い、テレビ局アナウンサーだった桝さん自身も「非常に難しい問題だった」と吐露しました。大学で合成生物学に関するサークル活動に参加している末松さんも、「遺伝子を変えて新しい生物をつくるといった研究は、誤った方向に進んでしまうと非常に危険です。遺伝子組み換え食品がその典型で、社会に対するインパクトが大きい分、誤解を招かないよう科学リテラシーを高めることは科学者の使命だと感じています」と共感。林さんは「『RNA』『DNA』という用語は高校の生物の授業でも扱うのに、どうしても『科学=勉強』のイメージが先行して感覚的に拒否してしまう、または大学受験後に忘れてしまって日常生活との関連性に気づかない人が多いのかなと思います」と指摘しました。
ただ、「僕たちは、突然何かが生まれるのではなく徐々に洗練されていく科学の過程を見て理解することができる立場だけれど、これだけ科学そのものが高度で複雑化してくると、『わからない』と言ってパニックになる人がいるのも仕方がないのかもしれない。でも、これで良いはずがないとも思います」と齊藤さん。そこで、科学と社会をつなぐ役割に話題が及ぶと、桝さんは「まさにそれこそが私の研究テーマです。単に話がうまいだけではなく、伝える相手に合わせて内容を調整し話せることが特にサイエンスコミュニケーターには求められると思います」として、科学者やメディアが社会に歩み寄りながら発信し続けていくことの重要性を説きました。続けて齊藤さんは、社会全般の科学リテラシーを向上させるためには、科学者やアカデミア、メディアだけでなく、製品を世に出していく企業もその責務をともに担って欲しいと提案しました。
科学好きの原点は子ども時代の体験
科学を通じて得た力がその後の人生を豊かに
4人が共通して感じているのは、科学は日常生活で身近にあふれているけれども、あくまでそれは生活のごく一部であり、大人が気軽に科学を楽しむ「文化」までは成熟していないこと。しかし一方で、彼らの科学好きの原点は子どもの頃に出合った図鑑や伝記で読んだ科学者などにあり、その意味で、現代の子どもたちを取り巻く科学教材は昔より数的にも質的にもはるかに充実していることを挙げ、状況変化への明るい兆しに期待を寄せました。
「国際科学オリンピック出場は、大学進学後の学びや自分が研究者として生きていく上での道標になりました」と齊藤さん。オリンピックを通じて出会った同年代の仲間や教員との関係が自分の研究者としての幅を広げてくれたと実感していて、それを後輩や学生の指導でも心がけていると言います。さらに桝さんが、科学を通じて得られるものの一つとして「ロジカルシンキング(論理的思考力)」を挙げると、「どの教科の科学オリンピックでも、国内大会の出題は科学的知識だけでなく論理的に文脈を読み取ることが求められていたように思います。今も私は本を読む際など常に論理的に考えることを意識しています」と林さん。末松さんも「『論理』という道具を持つことによって世界の見方が変わると考えています。世界にあるいろいろなものをつなぐのが論理で、論理によって混沌とした世界を切り取れることは非常に大きな魅力」と述べました。3人の熱い思いを聞いた桝さんは、豊かな人生を送る上で科学を学ぶことの意義を実感できる社会づくりのためにも、「子どもたちのロールモデルとして、ぜひ充実した人生を歩んでいってほしい。皆さんに続く人が増えていくことで、きっと科学も『文化』として根付いていくでしょう」と激励し、座談会を締めくくりました。
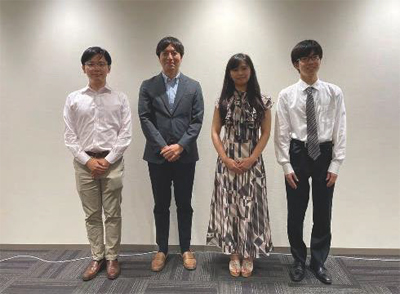
出席者の皆さま、ありがとうございました!
出席者:(所属、肩書き等は2022年8月18日当時)
-
桝 太一さん(同志社大学ハリス理化学研究所専任研究所員・助教)
齊藤 颯さん(京都大学大学院 理学研究科化学専攻 有機化学研究室 助教、2010年国際化学オリンピック金メダリスト、2011年国際化学オリンピック銀メダリスト)
林璃菜子さん(京都大学医学部医学科2年、2020年国際化学オリンピック銀メダリスト)
末松万宙さん(東京大学教養学部理科二類2年、2019年国際化学オリンピック金メダリスト、2020年国際生物学オリンピック金メダリスト)