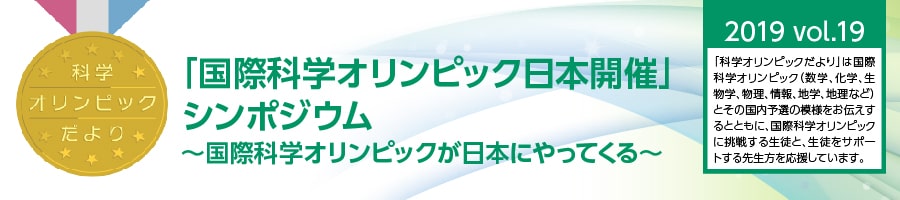2019年8月22日、東京大学伊藤謝恩ホールを会場に「国際科学オリンピック日本開催」シンポジウム ~池上彰さんと考える日本の科学ときみの末来~ が開催されました。 国際科学オリンピックヘの支援事業は2004年に始まりました。2017年には国内選考に挑戦する生徒が2万人を超え、現在では7教科の国際科学オリンピックに延べ31人の代表生徒が毎年参加しています。 国際大会の日本開催も地理、地学、情報と順次終了し、2020年には生物学、2021年化学、2022年物理、2023年数学と続きます。 社会的認知や産業界の支援がより一層重要なこの時期に開催された同シンポジウムは、トップ研究者、グローバル企業の経営者、若手オリンピアンが登壇し、会場は熱気に包まれました。

日本で再び ~2020年国際生物学オリンピック長崎大会開催

シンポジウムは、2020年7月に開催される「第31回国際生物学オリンピック2020長崎大会(1B02020)」の概要紹介から始まりました。 1B02020組織委員会の浅島誠委員長は、「2009年国際生物学オリンピックつくば大会から10年を経て、長崎大会を実施できることは日本の生物教育向上の好機です」、と開催意義を語り、 大会コンセプトに"平和"を加えるなど、長崎らしい大会をめざして、世界80カ国の代表生徒と引率者を迎える準備が進んでいることを伝えました。
山中伸弥教授講演 ~必要は発明の母、偶然は発明の父
2012年にノーベル医学生理学賞を受賞した京都大学iPS細胞研究所所長/教授の山中伸弥氏は、「iPS細胞がひらく新しい医学」と題した講演で、今後の研究の見通しに加え、自身がどのようなきっかけで研究者の道に踏み出し現在に至っているかを紹介しました。
臨床医になった当時、有効な治療法のなかったC型肝炎ウイルスで父親がなくなったことで、将来多くの患者を救う可能を求めて研究医を目指したと話し始めた山中氏は、幾つかの偶然が重なってNATl(Novel APOBECl Targetl)という遺伝子を見つけたこと、 その遺伝子はES細胞にも影響を及ぼすことを突き止めたこと、などを言吾りました。発明を成し遂げるに言われる「必要は発明の母」に重ねて、「浅島先生が発見したアクチビンは、ES細胞からいろいろな細胞ができるときに重要なもので、この発見がなければ今の研究はなかったでしょう」という説明と共に、自身の経験も含め、 「研究は思いがけないことの連続」であるとして「偶然は発明の父」という言葉で講演を締めくくりました。

研究者としての道のりを紹介する山中氏
パネルディスカッション 科学の意義や可能性、国際科学オリンピックが果たす役割について考える
シンポジウムで最も時間をかけたパネルディスカッションには、山中氏、アマゾンジャパン社長のジャスパー・チャン氏、国際生物学オリンピックに日本が初めて参加した第16回大会で銅メダルを獲得し、現在東京大学大学院農学生命科学研究科助教の岩閻亮(リョウ)さん、2019年7月に開催されたばかりの第51回国際化学オリンピックで金メダリストとなった高校2年生末松万宙(マヒロ)さんが登壇しました。
冒頭挨拶で、チャン氏は、「世界中で拡充を続けるアマゾンのイノベーションの源泉は、社員一人ひとりがリーダーシップを発揮できるよう設定した『リーダーの行動理念』にある」と述べ「お客様に徹底してこだわることから、アマゾンのイノベーションは始まり、の終わりは無い。毎日が始まりの日"Day 1"という考え方を大切にしている」とグローバル企業としての姿勢を紹介し、「誰のためのイノベーションかを考え続けて欲しい」と聴衆に呼びかけました。

パネリスト(右から)山中伸弥氏/京都大学iPS細胞研究所所長・教授
ジャスパー・チャン氏/アマゾンジャパン社長
岩間亮さん/東京大学大学院助教(2005年第76回国際生物学オリンピック北京大会銅メダリスト)
末松万宙さん/栄光学園高校2年生(2019年第57回国際化学オリンピックフランス大会金メダリスト)
モデレーター/池上彰氏(左端)

アマゾンのイノベーションについて話すチャン氏

意見を交わすパネリストたち
平成30年を振り返り 令和時代、科学はますます重要に
昨年に続きパネルディスカッションのモデレーターを務めた池上彰氏は、「今日は、令和という新しい時代に日本の科学技術の進む方向を皆さんと話したい」と口火を切り、山中氏に「平成が日本の科学技術にとってどのような時代だったのか」と質問を投げかけ60分間にわたる意見交換を始めました。 平成元年に研究医になることをめざして、大学院に入った山中氏にとって、平成の30年間は正に研究者としての道のりそのものでした。それを踏まえ、「克服できると思ったがんで未だにたくさんの方が亡くなっています。一方でヒトゲノムの解析は一晩もあればできるようになりました。 30年のうちにはいろいろ革新的なことが起こりましたが、それは予想できませんでした。この令和の時代に何が起こるか楽しみでもあり、怖くもあります」と率直に応えました。 「科学の進歩ととともに、科学者の責任はますます重くなっていますね」という池上氏の投げかけに、「資本主義社会を支えているのはイノベーションであり、その原動力として科学は欠かせません」と、科学の責任が重くなったからといってその進歩が止められるものではないと語りました。
イノベーションに話が及んだところで、チャン氏から、「イノベーションというのは皆さんの生活の不便なところを解決し、豊かにするもの」と説明があり、「その中で、日本の開発者はまだ世界をリードする立場にはないのではないでしょうか」とグローバル企業の社長という視点から、日本のイノベーションに対する厳しい指摘がありました。 これに対して岩間さんは、「国際生物学オリンピックに参加した際に、ほかの国の生徒が物おじせすに発言するのをすこいと思いました。また、自分の専門の生物学は、今や化学や物理、情報なくしては研究できない時代になっており、イノベーションには分野融合が必要だと感じているし、 今後は高校教育でも教科をまたいだ授業を実施して欲しい」と意見を述べ、末松さんも、国際化学オリンピックフランス大会での優秀な生徒達と出会ったことや、ご当地問題としてフランス産のワインの成分を分析する実験問題に取り組んだことなどの体験を紹介しながら、 「海外を見ると日本が見えてくる」とし、2人共に国際科学オリンピックヘの参加を適して、日本と世界の違いを体感できたことの意義を伝えました。
日本政府が掲げる統合イノベーション2019について考える
続いて池上氏は、「世界の科学技術の動向」とその中での「日本の立ち位置」に関する資料を提示し、「日本は一部の世界競争力ランキングで上昇しているものの、起業のしやすさでは190カ国中106位と低迷しており、"新しい産業が興りにくい国"だ」と解説しました。 また、「こうした状況の中、日本政府はSociety5.0の実装をめざしているが、それがどのような社会なのか想像してみましょう」と提案。狩猟社会のSociety1.0、農耕社会の2.0、産業革命後の工業社会の3.0、現在は情報社会の4.0と進んできた、 と小学生も混じる聴衆の理解を整備し、Society5.0への意見をパネリストたちに尋ねました。山中氏は、「人間は本当に幸せになったのでしょうか」と疑問を呈し、 「Society5.0の超スマート社会は誰もが幸せである社会にしなくてはならない。例えば医療では、一人ひとりに 最適な個別医療が提供されるようになるべき」と指標を掲げました。

池上さんと話す末松さん
一方、チャン氏は、「この30年のインターネットの発展によって、世の中の変化や競争は激化しています。それでも、アマゾンの『人の生活をよくしたい』という姿勢に何ら変わりはありません。 それは、Society5.0になっても基本的に人間中心の社会だということに変わりはないということです」と、AIなどの技術はあくまでも人のためであることを強調しました。
岩間さんは、Society 5.0がどのような社会なのか、正直よくわからないとしながら、「そうなっても、人との関係を大切にすることは変わらない世界であって欲しい。 スピードが問われる時代ではあるけれど、ゆっくり考えることで面白い発想が生まれることもあるので、じっくり考えることを支えてくれる社会であって欲しい」と願いを語りました。

「AIに仕事を取られると恐れるのではなく、AIに任せる仕事と、人間がやる仕事の見極めが大事ですね」という池上さんの発言をメモしていた末松さんは、 Society 5.0については、「子供の頃に、両親に理科や算数の問題を出してもらい、それを解くことが好きになり、科学が大好きになりました。好きなことがいくらでもできる、好きな分野に専念できる社会になったらいいと思います」と、素直な気持ちを伝えていました。

会場へメッセージ~「科学する心を育てよう」
「第1次世界大戦の後、日本では科学技術をおろそかにしてはいけないということで、『科学する心』が大切と言われるようになりました。 来年はスポーツのオリンピックがありますが、科学の世界でも生物学オリンピックなどが毎年開催されます。『科学する心』を大事にしているパネリストの皆さんからのメッセージを頂きましょう。」と 池上さんの発言を受け、「子供の頃、『科学と学習』という雑誌がありました。付録の実験セットが楽しみで、いつしか”科学する心が芽生えました。子供たちに、どうやって科学の魅力を伝えるかがこれから大事になるでしょう」と山中氏。

チャン氏は「これから20年、30年…どう変化していくかとても楽しみです。この変化の主人公は皆さんです。日本の技術者は知識も技術も優れています。あとは世界的な視野をもつことです。 自分の成功は日本だけでなく世界のためにもなるのだという意識を持って下さい。英語力も大事ですよ」とエールを送りました。
岩間さんからは「当たり前のことを、疑ってみることが一番の科学だと思います。そして、他人と違うことを恐れないこと。それが研究には求められます」。 末松さんは「自分がここで貴重な体験ができるのも、大好きな化学を追究してきたからであって、みなさんにも自分の好きなことを納得のいくまで徹底的にやってほしい」と語りました。
最後は、池上さんの、「好きだから、人と違ってもいいじゃないかとやってきたことが、結果的に日本のため世界のためになる可能性があるというのは、科学の素晴らしさです。 ぜひ、若い方たちには、ここにいるパネリストを始めとした『科学する人たち』に続いてほしいと思います」という言葉で締めくくられました。
パネルディスカッションの後には、生物学、化学、物理の3教科にわかれて各教科の国際大会参加者によるワークショップが行われました。 定員を大きく超える200名近い受講希望の中高生たちは、生物学では葉緑体、化学ではアミノ酸、物理では光をテーマにそれぞれの課題に取り組み、各教科の面白さと難しさを体験し、“科学する心”を刺激されたようでした。

生物学のワークショップ講師も務める岩間さん