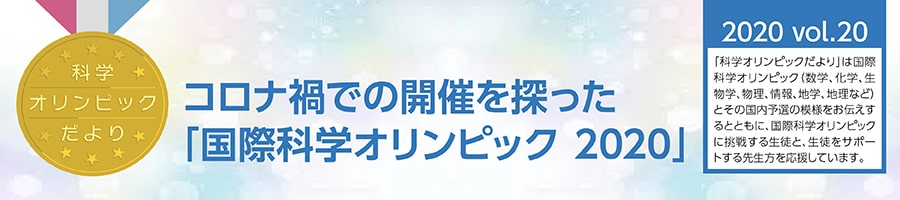2020年8月25日、「国際科学オリンピック2020」の開催状況と日本代表生徒の成績を報告する記者会見がオンラインで行われました。
毎年、夏に行われる国際科学オリンピック7大会(数学、化学、生物学、物理、情報、地学、地理)では、世界中の代表生徒が教科ごとに主催国に集まり、その知識を競い合い、国際交流の機会をもちます。JSTは「未来をつくる人材育成」の一環として、2004年から国際科学オリンピックの支援を行っています。
2020年夏の国際大会に向けても、7教科合計で2万人を超える生徒が参加しての国内予選が行われ、31名が日本代表として世界に挑戦する予定でした。
ところが、新型コロナウイルス感染拡大によって通常開催が難しい状況となり、物理、地学、地理の3大会は中止に、他の4大会についてはリモートに切り替えての開催となりました。
日本で2度目の開催となるはずだった「第31回国際生物学オリンピック長崎大会(IBO2020)」は、「IBO Challenge2020」と名称を変え、8月11日12日にリモートで開催されました。
主催者の思いを託したリモート大会「IBO Challenge2020」
IBO2020組織委員会の浅島誠委員長は、「IBO2020は、3月東京オリンピック2020の中止決定を受けて、中止の判断をせざるを得ませんでしたが『世界の同世代が競い合う機会を奪ってはならないという関係者の強い思いから、リモート大会の可能性』を検討しました。 国によるウェブ環境の違いや時差を考えると試験の公平性は保てるかという懸念はありましたが、実施して良かった。新しい教育のスタイルを提案することにもなりました。 一方で、集まって実施する意義は何なのかを改めて考えなくてはならないと思っています」と、大会を振り返りました。
このような状況で、日本代表生徒たちは健闘し、金メダル1つ、銀メダル3つと全員がメダルを獲得しました。
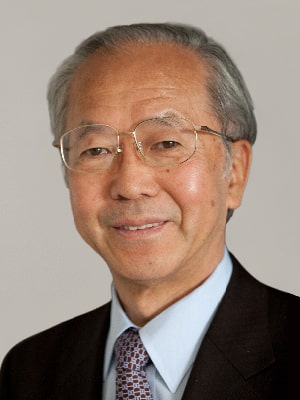
第31回国際生物学オリンピック
2020 長崎大会組織委員会
浅島 誠 委員長
リモート大会ならではの取り組み「国際グループプロジェクト」
国際科学オリンピックで試験と同様に重要なのが、主催国の文化に触れ、他国の生徒たちと交流する機会です。
IBOチャレンジ2020では直接交流に代えて、「国際グループプロジェクト」を企画しました。国籍の異なる4名の代表生徒に、大会OB・OG1名がファシリテーターとして加わり、「進化、多様性と海洋、ゲノム編集、感染症」の4テーマから1つを選び2ヶ月間リモートで議論した後、ポスター発表をします。
「若くて優秀な生徒たちが、その柔軟な頭で何を考え、どのようなアイデアを出してくれるのか非常に楽しみです」と浅島委員長。
続いて、栄光学園高等学校3年の末松万宙(すえまつまひろ)さんが、リモート大会と現地大会の両方に参加した代表生徒として、その貴重な体験を語りました。 末松さんは「IBO Challenge2020」で金メダル獲得し、昨年の国際化学オリンピック・パリ大会にも参加し同じく金メダルを手にしています。 「IBO Challenge2020」に参加したこと自体が貴重な体験でしたし、そこに至るまでの学習期間にも多くを学びました。特にバイオインフォマティクスは、ふだん学校では勉強しない内容だったので新鮮でした。 一方で、昨年参加したパリでの化学オリンピックに比べると、実際に器具を使う実験試験がなかったことや、そのための研修がなくなってしまったことが残念でした。 また、観光やほかの生徒との交流はできませんでしたが、代わりに「国際グループプロジェクト」は他国の生徒と議論できる機会が設けられたので、取組みをとても楽しみにしています。

IBO2020日本代表の4人(左端が末松さん)
国際化学オリンピックに向けた、オンラインでの教育訓練
新型コロナウイルス感染の影響で変わったのは、大会の開催方法だけではありません。日本化学会化学グランプリ・オリンピック小委員会/オリンピック支援委員会の米澤宜行東京農工大学教授は、オンラインで実施した代表生徒の教育訓練について紹介しました。 「2020年の国際化学オリンピックに向けた教育訓練は、代表候補生徒が選ばれた2019年9月から始めました。2020年3月に代表生徒が決定し、実験指導や知識・情報の整理の仕方など合宿形式の本格的な教育訓練を始める予定でした。長年指導を続け改訂を重ねてきたこの流れが功を奏したか、 この数年日本代表は、従来苦手だった実験試験でも成果を出せるようになってきたのですが、今年の訓練は、全てオンラインに変更せざるを得ませんでした。 この試練を通して、例年代表生徒たちは高い水準の洞察力や文書伝達力を身に着け大きく成長しますが、オンラインでも可能なのか心配でした」。7月20日に行われた試験の結果は、全員が銀メダルを獲得。米澤教授によれば、「この成績の裏には、オンラインを利用して問題を出し合い議論するといった、 代表生徒たちの自主的な努力があった」とのことです。

化学グランプリ・オリンピック
小委員会/オリンピック支援委員会 委員
米澤宣行教授
南山高等・中学校女子部の林璃菜子さん
この指導を受け、第52回国際化学オリンピックトルコ大会に参加した4人のうちの1人、南山高等・中学校女子部の林璃菜子さんは、「小学生の頃に炎色反応や有色イオンのきれいな写真を見て、化学に興味をもつようになりました。皆と集まって一緒に化学を学べるのを楽しみにしていたのに、 一人で勉強することになってしまい残念でしたが、ウェブ会議システムを使ってOB・OGの方や、大学の先生などたくさんの方のサポートを受けられたので、不安は感じませんでした。 試験当日は、4人全員が東京で一緒に受けることができてよかったです。閉会式はYouTubeでしたが、銀メダル受賞者に自分の名前を見つけたときには、自分の成長を実感し、支えてくださった皆さんへの感謝の気持ちで一杯になりました。 これからも化学の世界につながっていたいと思います。」と振り返りました。

支援の継続を約束
最後に、文部科学省 科学技術・学術政策局人材政策課の奥野 真人材政策課長から、「新型コロナウイルスの影響が続いていますが、 来年度以降も代表生徒の皆さんが活躍できるよう支援を継続していく予定です」との発言があり、記者会見は終了しました。