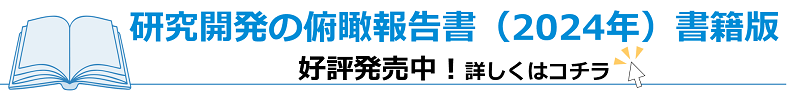- バイオ・ライフ・ヘルスケア
研究開発の俯瞰報告書 ライフサイエンス・臨床医学分野(2024年)
エグゼクティブサマリー
ライフサイエンス・臨床医学分野は、あまねく生命現象の根本原理を見出し、そこに介入する技術の創出と社会実装を通じて、ヒトおよび地球規模の健康、そして持続可能な社会の構築に寄与する研究開発分野である。
本報告書では、ライフサイエンス・臨床医学分野における、グローバルな社会的課題、経済的課題を整理し、主要国の科学技術政策動向や社会との関係、そして最先端の研究開発潮流を俯瞰した。その結果、あらゆる場面において、さまざまな社会的課題および経済的課題を解決しうる先端技術開発や研究開発〜社会実装の仕組み構築への高いニーズとともに、それらが持続可能性の確保を同時に達成することも強く求められていることが明らかになった。
本報告書では、ヒトの健康に関わる研究開発領域を「健康・医療区分」、持続可能な生物生産に関わる領域を「農業・生物生産区分」、この両者に共通し、新規のエマージング技術を含む領域を「基礎基盤区分」として取り扱う。CRDSライフサイエンス・臨床医学ユニットでは、社会・経済的インパクト、エマージング性、基幹性の観点から30の研究開発領域を抽出し、トレンド、トピックス、国際ベンチマークをまとめた。また2024年3月に発行した「論文・特許データからみる研究開発動向(2024年)」の結果を一部盛り込むことで定量的な情報の強化も行っている。
全体を俯瞰して、ここ2〜3年の大きな技術・研究のトレンド(変化、進展)としては、基礎・基盤技術の観点からは“オミクス技術”、“ゲノム工学(編集、合成等)”、“タンパク等構造予測・設計”、健康・医療の観点からは“ 遺伝子治療、ゲノム編集治療”、“ 低・中分子/ 核酸医薬”、“デジタル医療(医療機器、医療データ基盤)”、食料・バイオ生産の観点からは“環境負荷低減農業”、“発酵技術”、“育種技術”の9つが挙げられる。
本報告書の2章で整理した30の研究開発領域の全体に共通する傾向として、米国が全ての領域にわたって基礎から応用まで圧倒的に強く、欧州がそれに次ぐ位置にあり、中国が存在感を急速に増し欧米を凌ぐ勢いも見られた。日本は欧米中と比較してほぼ全ての研究開発領域で存在感が低下しているが、わが国において研究開発が活溌な領域(政府研究開発投資が活発、或いは大型プロジェクトが複数進行中、或いはアカデミア等に多くの研究者が存在、或いは関連する世界的な企業が国内に存在、など)としては、「低・中分子創薬」「幹細胞治療(再生医療)」「遺伝子治療(in vivo /ex vivo )」「ゲノム医療」「がん」「脳・神経」「免疫・炎症」「生体時計・睡眠」「臓器連関」「微生物ものづくり」「植物ものづくり」「農業エンジニアリング」「構造解析(生体高分子・代謝産物)」「光学イメージング」が挙げられる。
以上を踏まえ、わが国において重要と考えられる7つの方向性は次の通りである。
- ① 個別予見的な医療・ヘルスケアの実現へ
- ② 多様な創薬モダリティの開拓・洗練・創出
- ③ 農業・食料・バイオ生産の持続性向上
- ④ 先端計測技術/次世代バイオテクノロジーの開発
- ⑤ 生命現象の統合的理解、メカニズム解明
- ⑥ 研究開発DX基盤の構築 [AI、データ]
- ⑦ 研究開発エコシステムの構築
※本文記載のURLは2025年1月時点のものです(特記ある場合を除く)。
目次
研究開発の俯瞰報告書 ライフサイエンス・臨床医学分野(2024年)
1.俯瞰対象分野の全体像
- 緒言 生命科学・臨床医学のこれから:基礎研究と医療研究
- 1.1 俯瞰の範囲と構造
- 1.1.1 社会の要請、ビジョン
1.1.2 科学技術の潮流・変遷
1.1.3 俯瞰の考え方(俯瞰図)
- 1.1.1 社会の要請、ビジョン
- 1.2 世界の潮流と日本の位置づけ
- 1.2.1 社会・経済の動向
1.2.2 研究開発の動向
1.2.3 社会との関係における問題
1.2.4 主要国の科学技術・研究開発政策の動向
1.2.5 研究開発投資や論文、コミュニティなどの動向
- 1.2.1 社会・経済の動向
- 1.3 今後の展望・方向性
- 1.3.1 今後重要となる研究の展望・方向性
1.3.2 日本の研究開発の現状と課題
1.3.3 わが国で重要と考えられる研究開発の方向性
- 1.3.1 今後重要となる研究の展望・方向性
- 結言 新たな学問の基礎構築とそこから生まれる応用・開発研究に向けて
2. 俯瞰区分と研究開発領域
- 2.1 健康・医療
- 2.2 農業・生物生産
- 2.3 基礎基盤