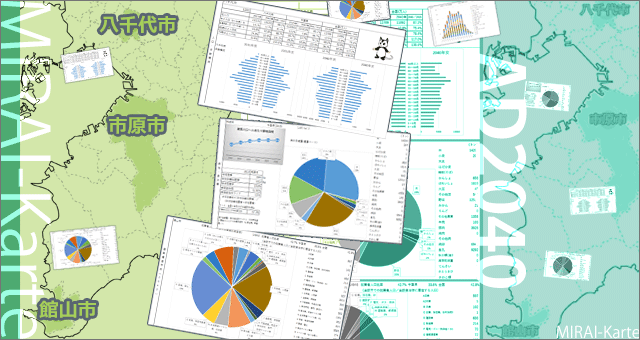
「未来ワークショップ」で中高校生が政策提言。十代の発想力が、このまちの未来を変える!
「未来カルテ」&「未来ワークショップ」研究開発協力3自治体インタビュー (1ページ目)
取材日:2017年(平成29年)11月4日
場所:千葉大西千葉キャンパス
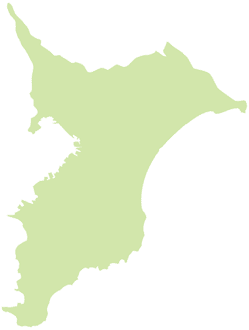 【左から】
【左から】
倉阪 秀史
千葉大学大学院社会科学研究院 教授
RISTEX多世代領域「多世代参加型ストックマネジメント手法の普及を通じた
地方自治体での持続可能性の確保」プロジェクト研究代表者。
市原市 小橋 清司
市原市企画部総合計画推進課 主任
環境省委託平成26年度「環境経済の政策研究」の協力自治体。
日本を代表する工業地帯と農村部を抱える。
八千代市 竹内 誠
八千代市総務企画部総合企画課 主査
地域のつながりを測定する「リソースジェネレータ」の本調査にも協力。
日本の大規模住宅団地の発祥の地。ベッドタウンとして人口を維持してきているが、
老朽化した集合住宅の問題などを抱える。
館山市 長谷川 恵
館山市総合政策部企画課 政策係長
千葉大学COEスタートアッププログラム「人口減少・環境制約下のコミュニティ形成」
プロジェクト(2010~2012)の協力自治体。1980年代から人口減少が進んでいる。
シンポジウム前のお時間に、実際に「未来カルテ」を使い「未来ワークショップ」を行った際の、体験談を伺いました。
1.「未来ワークショップ」で中高校生が政策提言。
十代の発想力が、このまちの未来を変える!
――「未来カルテ」を使って、それぞれの市で中高校生を対象に「未来ワークショップ」を開催されたわけですが、実際に市政に反映できるほどの意見が出てくるものなのでしょうか。記録を拝見すると、明らかにウケ狙いの発言もあるようですが......『カツラの日を設ける』とか(笑)。
倉阪 ワークショップでは白髪のカツラと白衣を着用して「未来博士」役をやっているのですが、「なんでも訊いていいよ」と言ったら、最初の質問が、「どこで買ったヅラですか」でした(笑)。
しかし、「そうした質問にもちゃんと答えてくれる」ということでやる気が出たと、ワークショップ終了後に話してくれました。そのヅラ質問をした生徒が、のちに実現する、流しそうめんイベントの発案をしてくれたんですよ。
――中学生ですか?
倉阪 中二女子です。
――中二女子おそるべし......。市原市では、大人向けのワークショップも開催されたのですよね? 比べてみていかがでしたか?
小橋 市原市ではもともと、総合計画策定の中で「10年後の未来の姿」というビジョン的なものを作成するために、「いちはら未来会議」を開催し、16歳から94歳までの市民約100名と今回のワークショップで40名の中高生の意見を伺いました。
大人の方々からも前向きな御意見を多くいただきましたが、思考に偏りはあるかなとは感じました。子どもたちは非常に発想が柔軟で、「流しそうめん、やりたい!」と言って、本当に実現させました(笑)。
竹内 八千代市の「未来ワークショップ」では、「休耕田を学校などに貸して、学校農園に使えないか」という意見がありました。大人ですと、「次の担い手は?」「後継者は?」と、事業継続の方向で考えがちになるのですが、そうではない選択肢もあると気づかせていただきました。すぐにはできないにせよ、有効利用の一つの手法として検討する価値はありますし、選択肢は多いほうがいいのは当然ですから。
長谷川 「意外な発想」というのではないんですけれども......ほかの自治体さんに比べて館山市は人口減少も高齢化もどんどん進んでいて、喫緊の課題なんです。大人がこういうデータを目の当たりにすると、わかってることがさらに数値化されて、まあ大げさにいえば悲壮感のようなものが漂ってしまうのですが(笑)。子どもたちはそうした数字をぽんと出しても、わりと前向きにいろんなこと考えてくれるんですよ。
一方で子どもたちにとっても、漠然とこうした状況を感じてはいたけれども、ワークショップがひとつの意識づけになったのではないかと思います。事後アンケートで、この市を自分たちが担っていくんだという感覚が芽生えた、という感想もありました。
――教育面での効果も見込めますね。
小橋 はい、教育面での効果もあると思います。選挙権年齢が18歳以上に引き下げになって、教育の現場で、主権者教育が重要となっています。そこで「未来カルテ」を使うと、「自分のすんでいる地域を未来の状況から考えてみよう」と地元の課題や社会参画に関心を持つきっかけになると思います。
――八千代市さんでも館山市さんでも、7割以上が「参加したことで、地元の未来に関心を持つようになった」というアンケートの回答がありました。
小橋 この二日だけでも、地元の課題や未来に触れて考えてくれるというのは、中高校生にとっては、大きな気付きにつながると考えています。ここから本当に、2040年の未来市長が出てきてくれたらいいですね。
長谷川 館山市では 特別支援学校の生徒さんも一緒に参加 していただきました。適用範囲の広さを実感しています。
竹内 大人も「未来カルテ」を見たらもちろんいろいろ考えますけど、何よりも若い世代に考えてもらう材料を提示できたのではないでしょうか。あくまでも「今の状態が続いたら」という前提ですが、ある程度図式を単純化していて、若い人たちに今後の自分たちのまちを考えてもらうためには、とても良い材料になっていると思います。
あとは、ワークショップの事例を積み重ねていく中で、ある程度やりかたが統一されていくとやりやすいのかなと......。
倉阪 はい。そのあたりは経験を積ませていただいたので、ファシリテータマニュアルを2018年の1月までに作って、2月9日金曜日に研修会を行います。
先日、松戸市で新たに「未来ワークショップ」をやらせていただいたのですが、無料配布している未来カルテ「だけ」でやってみるという試みを行いました。みなさんのところでは、「未来カルテ」の情報をまとめ直して、ワークショップ用にわかりやすい資料を作成して使いましたが。「未来カルテ」だけでは若干わかりづらいという意見もありましたので、そこは改善を図っていきます。



「いちはら未来ワークショップ」2015年8月19・20日開催
市原市のワークショップでは、2日間かけて地域の現場も見て回った。参加者は中一から高三までという幅広い年齢層だが、「現場を見ながら質問する」という方式は、理解を深めやすかったようだ。最終日に中学生から出された、「里山保全のために切り出した竹を利用し、内田未来楽校において流しそうめんをすることで、地域資源の活用や地域のつながりの醸成に寄与する。」といった趣旨の提案が、翌年に「流しそうめんの夏~いちはら未来ワークショップリユニオン2016」として実現。当日は、参加者自ら竹でコップと箸をつくり、薪で焚いたわき水でそうめんをゆで、流しそうめんを楽しんだ。
「やちよ未来ワークショップ」2016年11月23日開催
八千代市のワークショップにおいては、参加者に対して参加前後の意識変化に関するアンケート調査を実施した。その結果、参加することによって、 地元市に貢献したい、地元市の課題をもっと知りたいと思うようになったとの回答が多く得られた。
「たてやま未来ワークショップ」2017年8月7日開催
館山市でのワークショップ。「未来カルテ」の空家率を加工して地図に落とし込んだものは、「こんなに減っちゃうんだ!」というインパクトがあり、参加者も運営側も衝撃を受けたという。写真は、「未来市長」から金丸市長へ提言する様子。
2ページ目ヘ 「2040年の うちのまち」の姿。課題とともに見えてきたものは?
関連リンク
- 『持続可能な多世代共創社会のデザイン』研究開発領域 (RISTEX)
- 「多世代参加型ストックマネジメント手法の普及を通じた地方自治体での持続可能性の確保」(平成26年度採択)
研究代表者:倉阪 秀史(千葉大学大学院社会科学研究院 教授)
- 未来のストックが見える「OPoSSuM オポッサム」
( 「未来ワークショップ」の資料や「未来カルテ」 は、こちらのサイトからダウンロードできます ) - NPO法人地域持続研究所



