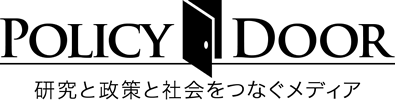千葉大学予防医学センターの近藤克則特任教授は、日本の「老年学」研究の第一人者である。老年学とは、医学だけではなく心理や社会的側面も含む学際的な高齢者研究だ。RISTEXのプロジェクトでは、介護予防研究で築いてきた知見と経験をもとにスポーツ政策の領域に挑んだ。自治体やスポーツ庁との連携を通じ、研究と政策が相互に進化していく「共進化」をキーワードに、近藤教授は本プロジェクトに取り組んでいる。
※「政策のための科学」プログラムでは、行政組織内部において「政策課題」として認識されている具体的な課題群の解決に向けた研究開発を推進する枠組みとして、「共進化枠」を設けている。「通常枠」のプロジェクトでも行政との連携を行っているが、「共進化枠」のプロジェクトでは特に研究と行政の連携・協働に重点を置いている。

「する論」の研究者として政策と現場に寄り添う ―研究哲学とJAGES誕生の背景
近藤教授は、研究者の関心やスタンスを「ある論/べき論/する論」の3類型で捉えている。自然や社会の有り様を解明する「ある論」と、どうすべきかという規範を論ずる「べき論」に対して、近藤教授の関心の出口は「する論」、つまり「ある論/べき論」を踏まえて「ではどうするか?」に向けられてきた。
研究や政策にはもともと関心を持っていたが、「医師として、まずは第一線医療の現場で何が起きているか知ろう」という思いから14年の臨床経験を積んだ。その後、研究者に転身し、日本福祉大学で政策や現場に役立つ研究へと舵を切った。当時、日本が世界に先駆けて高齢化が進む国であるにもかかわらず、老年学における学際的なコホート研究は少ない状況だった。「ならば、老年学のしっかりしたコホートをつくってみたい」と考え、大学のある愛知県の2自治体と連携して、AGES(愛知老年学的評価研究Aichi Gerontological Evaluation Study)を1999年に立ち上げた。
目指したのは、実際に政策形成に資する実証研究である。「研究成果を自治体が使ってくれるような、あるいは厚生労働省が政策判断を行う際に必要とされるような「する」ための研究、ナレッジ・トランスレーション(研究知見の政策や事業への活用)をしたい」という思いで自治体と関わり始めた。
研究を進めると、「健康格差」の存在に気がついた。所得(分配の不平等)・雇用形態・居住地域の環境などの「自己責任とは言えない社会的な要因」が健康状態に影響し、集団・地域間で不公正な格差があることが、見えてきたのだ。
そこで「健康格差を放置すべきではない」という主張の本を2005年に出版した。出版社から「先生、エビデンスが貧弱な段階で本を出すと、批判されて研究者生命を奪われる可能性がありますよ。それでもこのタイミングで出しますか?」と念を押されたという。しかし、WHOが2009年に健康格差是正の総会決議を採択し、厚生労働省も「健康格差の縮小」を「健康日本21(第2次、2013〜)」に掲げたことで、少しずつ主張が実際の政策の流れにのっていく実感を持つようになっていった。
こうした実績を積み重ねる中で、2010年には調査対象地域を全国12道県の30市町村へと拡大し、AGESをJAGES(日本老年学的評価研究 Japan Gerontological Evaluation Study)へと全国展開した(論文1)。2025年調査には70を超える市町村が参加している。
質の高いコホート研究には、偏りのない対象者数の確保と高い追跡率が必要である。近藤教授は、行政機関のデータ追跡率がほぼ100%であることに注目した。また大学の研究者が調査票を送ると回答率は3割程度のことが多いが、行政が送る調査票の高齢者の回答率は6〜7割と高い。「これはすごい」と気づき、良質なデータベースを構築するためにも行政と組まない手はないと思った」と語る。近藤教授にとって、多くの自治体との共同研究が研究基盤となった。
自治体がある取り組み(たとえば後述するスタジアムの建設や、スポーツイベントの実施など)をした前後で追跡調査を行う。さらに、複数の自治体で同じ調査を行うことで、ある取り組みをした自治体を介入群、その取り組みをしなかった自治体を比較対照群とすることができるようになる。それによって「比較対照群を置いて、両群の介入前後のデータを取って効果を評価する」政策評価、プログラム評価研究ができるのだ。
研究成果を行政へ還元する姿勢も徹底していた。「先生、データは提供しますが、行政に役立つ情報をちゃんと返してくれるんですよね?」と行政側から釘を刺された経験を振り返る。「地域マネジメント支援システムJAGES HEART」も開発し、データを「見える化」し、自治体職員が一目でわかりやすいようにして、さらに結果の見方や解釈、実践的助言も惜しまずに重ねてきた。
こうして、近藤教授は「する論」の研究者として、行政との共同研究を深め、延べ200市町村の延べ100万人の高齢者のデータベースが構築されてきた。

スポーツ政策への展開と「共進化」の試み
介護予防においてJAGESの成果を、自治体や国の介護予防政策に役立てる実績を積み重ねてきた近藤教授は、研究のスコープをスポーツ政策へと展開させた。背景には、JAGESの研究を通して得られたスポーツ参加の効果に関する知見があったからだ。「公園のそばに暮らしている人たちは運動頻度が多く、歩行時間が多い。スポーツの会に参加する人が多い町では、転ぶ人、認知症や要介護リスク者が少ない。そのようなデータがたくさん出てきました。スポーツに参加する人を増やすことが、有効な介護予防政策であることを確信したのです」と近藤教授は話す。またスポーツの会への参加が身体の健康だけでなく、社会的なつながりや幸福感にも関連することが明らかになる中で、これまでの研究手法をスポーツ振興政策に応用するという構想が生まれた。
こうした研究成果を発表しているうちに、スポーツ審議会の健康スポーツ部会の委員就任の声がかかった。
「スポーツ庁がスポーツ基本計画でスポーツ振興を進めていることを知り、私がこれまで介護予防分野で取り組んできた考え方や自治体との協働などは、スポーツ振興の領域でも応用できそうだと考えるようになりました。そこにRISTEXの『共進化枠』の公募が出ました」と話す。
「それまでの研究とは異なり、『共進化枠』では私たち研究者側からではなく、スポーツ庁のほうから提案が出された。これは、チャンスだと思いました」研究者と行政官のどちらかが一方的に『これをやってください』と相手にお願いしてもなかなかうまくいかない。「双方が課題意識を共有し同じ思いでテーブルに着いて対話や情報交換していくのは共進化の前提条件です。ただし、同じ思いでテーブルについても、うまくいくのは10回の試みのうち、2〜3回という世界だと思います。2〜3割は低く見えますが、プロ野球の通算打率が3割を超えている人は、わずか20人前後だそうです」。
RISTEXにおける近藤教授らのプロジェクトは、①公園やスタジアムなどの環境整備の効果検証、②市町村単位でのスポーツ振興関連要因のデータの見える化、③アプリなどデジタル技術を活用した個人レベルの行動変容促進の3層構造で構成されている。国・都道府県・市町村・個人のいずれのレベルでも、スポーツをする人を増やす重層的な施策を促す意図がある。
①の「公園やスタジアムなどの環境整備の効果検証」については、公園やスタジアムが周辺の人々の運動実施に与える影響が報告されはじめている。「ある自治体で後期高齢者の6割が、月に1回以上スポーツの会に参加している地区がありました。市の担当職員に話を聞くと、運動公園が近くにあることや、50種類もあるスポーツ大会に向けて練習が行われている地域だとのこと。現場の声からも、『スポーツをやりやすい環境』が大事なことがうかがえました」。このような「建造環境(built environment、人工的につくられた環境)」の視点は、国土交通省の「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりなどの政策に導入されている。現在、新たにスタジアムを建設しているある市をフィールドに、スタジアム建設前の周辺住民に調査を行ったという。建設後まで周辺住民の健康状態や医療・介護費の変化を追跡し、スポーツ関連施設への公共投資の意義を多面的に可視化しようとしている。「たとえば、スタジアムができたことで住民のみなさんが健康になり、医療費が10億円浮くならば、6億円を使ってスタジアムを維持しても十分に費用対効果がある、といったエビデンスをつくりたい」と近藤教授は構想を述べる。
「②市町村単位でのスポーツ振興関連要因のデータの見える化」では、図1の市町村間比較(左側)や関連要因の探索(右側)ができるという。市町村間比較できれば、自分のまちが、他の市町村に比べ、スポーツ実施率が高いか低いかが一目でわかる。都道府県やスポーツ庁が使えば、Good Practiceあるいは支援を必要としている市町村を客観的に把握できる。右側のような公園や歩道の整備の重要性が「見える化」されれば、都市計画部門などとの連携した取り組みも進みやすくなるだろう。
このようなスポーツ振興政策担当者が参考にできるようなエビデンスは必ずしも多くなかった。「運動生理学やスポーツ社会学の研究ではエビデンスの蓄積がありますが、『どのような政策を打てばスポーツ実施率が高まるか』といった政策研究の課題に対する答えやエビデンスは十分に蓄積されていない。これまでに政策研究ができるデータがきちんと集められておらず、研究や活用が遅れているのです。」と話すように、政策立案に使えるエビデンスの不足が政策形成の障壁となっている。
「行政官にピンポイントで1つの研究を示したぐらいでは、政策は変わらないと痛感しています。エビデンスは1つや2つではなく、100、200のエビデンスをかたまりにして提供する。そのためには、データベースを構築して、そこから生み出すエビデンスに厚みを持たせなければなりません」。
しかし、こうした障壁を乗り越えるためのエビデンスも少しずつ生まれ始めている。「みる」スポーツ(観戦)と健康の関連性については、現地もしくはテレビでスポーツ観戦をしている人たちには鬱が少ない(論文2)。さらに高齢者1.1万人に「全体として、あなたはどの程度幸せですか」と尋ね、0点(非常に不幸)から10点(非常に幸福)で回答してもらい、3年間追跡して分析した。すると、現地で観戦をした人たちは、しなかった人達よりも3年後の幸福度が向上していた(論文3)。こうした結果について情報提供をしたところ、令和6年度「スポーツの実施状況等に関する世論調査」に幸福感を問う質問が追加された。それを用いた分析結果として、「みる・する・支えるスポーツ」の単独実施より、3つとも実施者で幸福感が高いことなどが公表された(https://www.mext.go.jp/sports/content/250313-spt_kensport01-000040805_01.pdf p5)。
スポーツ庁が実施する年次調査に、近藤教授らが提案したウェルビーイング評価指標が盛り込まれた。データ蓄積に向け、アカデミック(近藤教授)と行政(スポーツ庁)の「共進化」が生まれた一例である。
「③アプリなどデジタル技術を活用した個人レベルの行動変容促進」では、すでに横浜市のウォーキングポイント参加者で、非参加者に比べ3年後の歩行量が増加し運動機能低下が抑制され、医療費も12.6億円ほど抑制されたと試算されました(論文4)さらに4年間追跡すると「歩数のアップロードあり参加群」では「非参加群」と比較し、要支援・要介護認定および死亡の確率(リスク比)は0.77倍(95%信頼区間:0.59-0.99)と抑制されていた(論文5)。『共進化枠』での研究では、アプリによる社会参加促進を試み、無作為化比較対照研究によってアプリ利用者で3割ほど社会参加が増えたという結果も得られている(論文6)。一方で、アプリの利用者は以前から健康やスポーツに関心をもっていた層に偏っている傾向がある。「スポーツに関心がない人にも使ってもらうかことが次の研究課題だ」とも語る。

10年単位での時間軸
このような好事例は増えてきているものの、こうした取り組みはすぐに全国の自治体へ広がるものではない。「たとえば、ある自治体で医療費・介護費用の抑制効果が出れば、それを見える化する基礎資料をつくることができます。前例が1つできれば、スポーツによる健康増進等の取り組みをどのように始めたらいいかわからなかった自治体も、重い腰を上げるようになるでしょう。そうして新たに取り組み始める自治体が10年ぐらいかけて徐々に増えていき、20年後ぐらいにようやくそれが一つのトレンドやソリューションとして定着していくと予想しています」と長期的な構想を語る。これには、近藤教授の「社会における研究成果の定着や制度化は、短期ではなく10年単位で進むものだ」という認識が根底にある。
さいたま市とは、データを提供してもらい、近藤教授らが定量的な評価の結果を返すという協働ができた。「データの見える化を起点に、自治体職員が抱える課題意識を聞いて、それに対して分析でわかったことをまた返す。そんな“循環”が自治体との間でも回り始めています。これはまだモデル事業で、今は多くの努力を投入している割には伸びが小さいつらいフェーズですが、これをあと10年ほど続けていると、他の自治体の参加も増えてくるのでは」と展望する。「AGESの2自治体での取り組みが30自治体に広がりJAGESとなるのに10年、健康格差を報告した論文から国の政策にのるのにも10年以上かかりましたから」と。「今後10年で社会はこちらに向かうだろうと予測して、求められるようになるであろうエビデンスを準備しておくのが研究者の1つの役割だ」という認識は、短期評価に終始しがちな研究開発支援制度への示唆にも富む。
最近、厚生労働省からJAGESへの協力要請があったという。「省の担当者が替わっていく中でも、我々の取り組みが認知されて、向こうから声をかけてくれました。ここまで来るのに、辛抱強く25年以上かけて、厚みのあるエビデンスを蓄積することが必要でした」と近藤教授はうれしそうに話した。
「する論」の研究者としての国や自治体の行政官との密接なやりとりから研究課題を設定し、着実な10年単位でのデータ蓄積やその「見える化」、そして厚みのあるエビデンスを生み出す研究の積み重ねが、行政との「共進化」を生み出しつつある。
(取材・文 黒河昭雄、小熊みどり、編集・森田由子)
2025年6月24日インタビュー