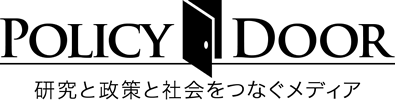感染症の流行時に、科学の知見はどのように政策に生かされるのか。新型コロナウイルス感染症対策の最前線で、数理モデルを用いて政府の対策助言に関わった西浦博教授が科学と政策の関係を振り返る。感染拡大前の数理モデルの導入、ダイヤモンド・プリンセス号での対応、メディアとの協力、そして科学的エビデンスが政策にどのように活用され、どのような壁に直面したのかを探る。科学的助言者としての責任や葛藤を通じて、危機対応における科学の役割を考える。
新型コロナの発生まで
―― 西浦先生の1回目のプロジェクト(2014〜2017年)では、風疹の予防接種指針の改定や新型インフルエンザの被害予想など、先生がこれまでに創られた様々な科学的知見の政策実装に取り組まれました。そして、シミュレーションベースの政策決定が少しずつ浸透しはじめたタイミングで新型コロナに直面されました。1回目のプロジェクト終了から新型コロナ発生までの間、先生はどのような取り組みをされたのでしょうか。
西浦教授:2013年に日本に帰国するまで、数理モデルに関する第一線の研究経験のために海外で10年以上を過ごし、それは自身のトレーニング期間に位置づけてきました。
2014年からRISTEXで取り組んだのは、政策現場で数理モデルの結果や知見を参照してもらう体制を作ることでした。プロジェクトの途中には、代々木公園のデング熱の流行がありました。
2016年に北海道大学で教授になったタイミングで、国際的にジカ熱の流行が起こるなど、その頃はほぼ毎年のように新興感染症の流行が発生しました。それに対応した研究をしてリリースを出し続け、理論モデルに基づく望ましい対策の明示や数理モデル研究者の育成を充実させていく日々でした。
科研費で感染症の流行発生時のリアルタイムの疫学パラメータの推定をしたり、JSPSの「頭脳循環プログラム」にも採用いただき、海外の若手研究者を受け入れました。JSTではCRESTのプロジェクトでビッグデータを利用した予測にも取り組みました。環境省の気候変動のプロジェクトにも採択いただいて、今後の気温上昇で予測されるデング熱流行のリスク評価にも取り組みました。また、HIV感染症の疫学モデル研究では厚生労働科研費のプロジェクトに複数入れていただいて続きましたし、さらには食品安全委員会でもリスク評価のための統計モデルに関する研究プロジェクトに参画させていただいて、毒性評価にモデルを役立てるという取り組みにも参加しました。
こうして数理モデルを活用する機会が増え、だんだん自分一人では回らなくなり、チームの形成に至りつつありました。
―― 統計数理研究所の数理モデル夏期短期コースで育成した人材が、新型コロナ対応で先生を支えるチームとして機能したのでしょうか?
西浦教授:はい。数として全く十分ではありませんでしたが、今までコースだけでなく研究室内で一緒に研究活動を行なったメンバーを再招集させていただきました。ただし、これまでのメンバーの多くは第一波の後に自身の判断で研究室へ戻った人がほとんどです。他方、ありがたかったのと同時に申し訳なかったんですが、現行の研究室の若手の研究者や大学院生たちが、流行対策が緩和まで自分の普段の研究を投げ打って協力してくれる体制はぎりぎり作れました。ただ、人材の数は少なかったですし、皆の経験が十分ではないので、私以外に研究代表者として責任を持って研究知見を述べる立場の人が日本にいなかった点では苦労が多かったです。若手に申し訳なかったのは、パンデミックは研究を拡大するチャンスである一方で、毎週厚生労働省でアドバイザリーボードが開かれて、流行中のデータ分析の結果をみんなが見ていて、間違いはないか、みんなで研究者生命を懸けて真剣にエラーを探すような作業が生じました。そうした中で、各自の研究にかける時間は削られ、あまり十分にとることができませんでした。厚労省でのアドバイザリーボードでのデータ分析や対策の助言に繋がる分析のようなもの、特に間違い探しのような取組みは、個人の研究成果にはなりません。チームができたのはよかったけれど、特にずっと帯同してくれたメンバーに申し訳なかったという思いをボスとして今でも持っています。
―― リアルタイムの分析に追われ、論文作成の時間を確保できない状況になってしまったと。
西浦教授:そうなんです。英国などは人数がいるので、国にフィードバックしながらもNature誌に論文を書ける。早く論文を出せば、高いインパクトのところに若手を連れて行ってあげられて、それは若手研究者として次につながる研究実績になります。そういうチャンスがいっぱいあったのに、厚労省のスライド資料を作ってもらうばかりで情けない気持ちでいます。もちろん、対策成功へ導く土台としてのデータ分析にエフォートを割けるのは国民の命を守る上で尊いものですが、若手研究者は論文業績を挙げて次の未来へつながるポジションを確保しないといけません。でも、第一波の頃から明らかでしたが、人命が最優先で、論文化をする余裕なんてほぼなかったのです。論文化ルールもうまく作れなかったし、分析内容と政策がかけ離れているものは無駄な研究とさえ見られてしまう。現に、論文業績を優先するOBメンバーは手のひらを返して、すぐにクラスター対策班からいなくなりました。
振返っていて実感しているのは、危機管理に取り組むことと並行して研究を進めるのは余りにも難しかったということです。今回の新型コロナの流行では、普段は行政や立法に関わらない専門家が国民の命を背負わないといけない場面が何度もありました。新発見は率先して国際的な学術誌に報告したいのに、自分の研究を進めるよりも命が優先になっていく、という葛藤がかなりありました。研究だけやれていたらどれだけ幸せだったでしょう。

メディアとのコミュニケーション
―― 前回のプロジェクトが終わってすぐに数理モデルに基づいて政策決定ができるようになったわけではないと思いますが、実際には研究成果をどのようにアウトリーチされてきたのでしょうか。
西浦教授:研究成果のアウトリーチはかなり一生懸命やりました。なぜなら、この数理モデルを行政や国民のみなさんに知ってもらう必要があったからです。まず、どんなサイエンスであるのか理解を深めてもらうことが必要です。「数理モデル」というとコンピュータの中で現実をシミュレートするわけですが、ブラックボックスのまま物事が進むので懐疑的に思われてしまいます。「中のメカニズムはこうなっていて、こういう結果が出ているんですよ」というところに丁寧に触れながら物事を前に進めたい。
なので、デング熱などの新興感染症の流行が繰り返し起こっていた頃には、研究成果が出るたびにかなり積極的にプレスリリースを出しました。研究論文が出るたびに科学部の記者の方と直接コミュニケーションを取るようになりました。これは東京大学の有力な先生がやられていた手法ですが、自分に対応する専属の記者さんを大手新聞社に実質的にお一人ずつ作らせていただき、定期的な勉強会まで開催しました。すると、数理モデルならこの方に聞けという人が各社の科学部に必ず1人はいらっしゃる状態になって、こちらとしても結果を伝達しやすい状態を作ることができました。勉強会では、これから論文が受理されてプレスリリースをするだろう研究にさえ事前に言及できて、その詳細や重要性も前倒しでお伝えできました。
―― 情報の信憑性も保つことができていたということですね。
西浦教授:地道に研究の重要性が伝達されやすい環境を構築することで、重要な研究が出たときにプレスリリースをしますけど、その際に中身がより伝わりやすくなります。科学部の記者さんがそれを平易に書いたらどうなるかということであったり、あるいは科学部の方々って他の社会部とか政治とか経済がある中で科学の紙面を取ることにはものすごく頑張られてますよね。この日付はこういう政治的あるいは社会的なニュースがありますとか、この頃は何が話題になるから科学ニュースのリリース日時に向いてないということさえ、記者さんたちから助け舟のようなインプットを受けながら、中身は難しいけどジカ熱がどれだけ危ないのか、そのコミュニケーションのあり方に関してはああしよう、こうしようと細かなことまで向こうからも提案がもらえるようになって、記者さんと科学コミュニケーションやリスクコミュニケーションの発信土台を構築するような理想的なプラットフォームがある程度できました。
―― 一方通行ではなく、記者側からの意見収集もできるような関係性ができ、コロナ禍における報道の仕方も変わりましたか?
西浦教授:厚労省に新型コロナウイルスクラスター対策班が設置されて、臨時に召集された研究者たちがどんなことをやっていて何をフィードバックしているのかというのが毎週NHKで放送されてきましたけど、そのバックグラウンドにはやはりNHKの科学文化部の方々との元々のお付き合いがありました。東北大学の押谷仁先生はそこのディレクターと懇意にされていましたし、やはり新型コロナについてそのサイエンスをどう考えているかを最もスムーズに伝えることができる。特に、あの時は日本独自のやり方をせざるを得ない状況でしたし、検査のキャパシティが少ない中でクラスター対策をしようという発想でやっていたので、その説明をするためにはメディアなどの媒体に密着してもらっても構わないという考えでした。
一方で、いろいろな議論があったのも事実です。重要なインプットを行う役割をしている研究者の顔を生で出してしまう必要は本来はない訳ですので、個々の研究者を守らないといけないという思いは透明性と真反対の考えになります。でも、結局のところ日本にはそういう余裕はありませんでした。もうこんなに必死にやらざるを得ない状態だからやるしかないということで、国民に何を伝えるかという部分で協力してもらおうと決断していました。
実は、あの時はメディアの科学部記者の方々にだいぶ助けられました。国の機関の中に置かれると、私たちは外に向けて正式な発信する手段をほぼ失いました。また、ご存知の通りで、政治と科学の問題が発生する端緒になる機会にも接し始めます。内部にいることで生じる様々な制約や悩みさえ共有できましたので。そういう点ではよかったですけど、ただ、若手の顔がテレビに映ることに関しては、心配しながらやっていたというのがあります。大学院生に至っては1人ひとりを親御さんから預かる立場にありましたから。

ダイヤモンド・プリンセス号
―― その上で新型コロナの場面に移っていくと、ダイヤモンド・プリンセス号の事件が起きた時、先生はどのような経緯で関与されていったのでしょうか。
西浦教授:2019年12月30日の時点で「パンデミックが始まったかもしれない」と海外研究者から直接的に聞きました。31日からは臨戦体制に近くて、研究室外から遠隔で初期リスク評価に要する情報を収集しはじめていました。妻の実家がある福岡で、紅白歌合戦をテレビで流しながら新型コロナの論文と言いますか、これが本当にパンデミックか否かを数値的にジャッジメントする研究をスタートしていました。初動は早くて、うちの研究室から論文が1月に15編ほど出ました。このレベルは英国と自分たちとあと数カ所だけで、世界でも互角に渡り合えるぐらいに新型コロナの新しい知見や今の状態がある程度分かる研究をどんどん進めていった状態でした。結果として、1月はほぼ研究室にいました。
1月後半に国立国際医療研究センター病院に行きました。同病院の大曲貴夫先生、現在は大阪大教授の忽那賢志先生、感染研から脇田隆字先生と鈴木基先生ら、都立駒込病院の今村顕史先生などを1カ所に呼ばせてもらい、The first few hundred studies(FF100)※をしようとしていました。最初の数百例の感染者について、しらみつぶしに疫学的情報を集中的に調べて、新型コロナがどういう形で伝播するか、どれくらい重症か、伝播する特徴、どんな人で重症化しやすいなどを明らかにする計画の立ち上げの会をやっていたんです。その帰りに脇田先生から、「加藤勝信厚労大臣に明日会えますか?」という話をされたのが関与の始まりです。そろそろこの流行を丸腰で受けると、どれくらいのベッドが必要なのかというシミュレーションをしないといけなくて、日本でそれができるのはあなただと聞いている、と。それで実際に厚労大臣室に行ってご挨拶しました。
厚労省への挨拶回り(数理モデルや数値計算の詳細相談)を数回やっている間に2月初旬になり、「ダイヤモンド・プリンセス号が入港します」と2月2日に聞きました。その日は関連する官僚の人たちは全員帰ってなかったです。みんな「これから大変なことになる」ということだけ理解して、どういうことをしなければならないのかと対策本部で皆が走りまわり始めていました。入港後しばらくしてからの日、厚労大臣室からの帰り際に、医務技監から「実は、ダイヤモンド・プリンセス号のデータを管理する部屋を作りはじめている。無線で伝えられる患者さんの情報を集めている」と聞いたのがデータ分析やリスク評価のきっかけです。
なので、2月初旬は非公式に必要となる病床数のシミュレーション分析を担当していましたが、そのなかで一番大変だったこととして船上での感染状況の分析にすぐにシフトしていきました。乗員名簿をもとに、どなたがいつ発病して、どなたがどんな検査を受けて、という情報を一つひとつ分析していました。面倒だったのは、国会での質疑の話題にもなっていて、答弁に要する分析を数十分で出すことさえ求められたりしていました。
そんな状況に至る前の話ですが、2月3日に外国人特派員協会で出版された新型コロナの研究紹介に関する会見をしました。当時の映像を今見ても、あまり間違った評価はしていなかったなと思います。会見では「これからパンデミックになります。結構な伝播性があり、対策を打たなければスペイン風邪より少し悪いぐらい死者が出るかもしれない」という話をしました。
※The first few hundred studies(FF100):感染症による公衆衛生危機発生時に、症例定義に合致した数百症例程度から知見を迅速に収集するための臨床・疫学調査のこと。
―― 研究者として、いち早く新型コロナに関する研究成果を学術的に発表するのは、先生がずっと強調なさっていました。まずは権威のあるところできちんと知見を共有しないと、どれだけ言っても説得力がない。それが結果的に、研究者コミュニティで西浦先生に力を借りたいというような機運につながり、その流れに行政が乗ってくる。大きくいうとそのような流れになったということでしょうか?
西浦教授:感染症のデータをしっかり分析したり、数理モデルで流行動態を定量化する専門家がもともと少なく、頼っていただける限りはもう頑張るしかないという状態でした。
―― 制度上は“座長が出席を求める関係者”という非公式な立場で先生は厚労省で開催された専門家会議に参加されていたということですね。公式に参画するのであればともかく、非公式な立場となると対応の難しさもあったのかと想像します。
西浦教授:本来は審議会などのメンバーになると、大臣名で兼業依頼が大学に来るんです。そうすると問題なく行けるんですけど、当時からずっと“座長が出席を求める関係者”という臨時の状態が続きました。会議に出て難しい発言をして、どこで仕入れたのかわかりませんが、その議場で起こった話がメディアで報道されたりします。そうすると大学に苦情の電話が来ることがあり、大学の事務部の方から「国の会議に参加すると聞いていませんでしたが、何をしてるんですか」と怒られたりしました。だから兼業を求めたこともあったのですが、結局数年やってもその立場は変えてもらえませんでした。不安定な立場であったがゆえに苦労は絶えなかったです。
―― でも、実際にはそこで一番、馬力がかかっていたわけですよね。「非公式の立場であってもやるんだ」と決断された先生のモチベーションや情熱はどこからくるものなのでしょうか。
西浦教授:国民の皆さんは直接垣間見る機会はありませんが、官僚の方々が私たちよりよほど苦しんでいました。彼らは外に向けて声を持たないので代弁しますが、ずっと帰れなくてボロボロになっても仕事をしていました。私たちよりも何倍も政治と科学の間で苦労をしていて、仕事の中身によっては精神を病んで辞めてしまう若手も多数いました。でも、国民に資する政策に志を持って入省した方たちな訳ですから、その志を堅持して奮闘する方も多かったんです。そんな姿を見せられると、若い専門家1人の公式だとか非公式だとかいうことは言っていられない状態でした。より劣悪な環境下で彼らは働いていましたし、責任も、私たちには生じにくくても国には必ず生じるのです。どうあがいても、すぐに国会での政治問題になっていくのが見える課題がゴロゴロ出てくる中で、どうすれば下手を打つことなく制御できるのかといった問題に直面するわけです。データ分析とリスク評価をして理詰めでやれるのであれば、もうやるしかない。それをちょうどお手伝いできる立場にあったので立場に関わらず関与をするという決断をしました。
その際には、厚労省のピラミッドの中で中間管理職の層にあたる課長クラスの方々が自分と同年代になりはじめたこともあり、特に密なコミュニケーションをしていましたが、ピラミッドのさらに上にいる人たちともきちんとお話をさせていただいて、信頼関係を築く必要がありました。上層部のみなさんも「何とかしたいね」ってそっと夜中に言うんです。そうした思いに同意しながら一つ一つ進めていく関係が自然と出来上がっていったのは、とても健康的だったと思います。

エビデンスと政策
―― ここからは科学的なエビデンスを政策に結びつける難しさについてお尋ねします。今回のパンデミック対策では、改めて「エビデンスがあれば政策が決まるわけではない」ことに気付かされましたし、この点は実際に先生が一番ご苦労なさったところでもあると思います。研究者の良心やミッションとして、今ある情報の中で得られる知見を論文にして世に出していく。あるいは、論文にならないまでも、リアルタイムの情報を分析して結果を報告していく。そこに自信も自負もあっただろうと思いますが、一方でそれがそのまま政策につながらないことを、どのように受け止められたのでしょうか。
西浦教授:流行初期には、感染症対策の専門家が集まるたびに、危機感が政策決定者にきちんと伝わらなくてフラストレーションを感じているという危惧について互いに相談していました。尾身茂先生が2月に国を介さずにNHKに出たのは、そうした話し合いが何度も行われた末に、「これは仕方ない、直接国民に語りかけよう」という話になったことがきっかけです。そうすると危険性を測る数値が必要になってきます。具体的に「新型コロナがどれだけ危なくて、どれだけの命を奪い得る感染症で、これから医療がどうなるのか」という問題がありました。エビデンスを提供しながら政策の成り行きを見る時点で難しかったのは、国民の理解を得ることだけでなく、政策決定者たちが新型コロナと社会への影響のバランスに直面する初動の中で、新型コロナのリスクを低く見積もってしまうことでした。本音として、普段の生活が止まるのは、やはりなかなか受け容れがたい。でも、感染症なので私たちの常識的感覚に忖度してくれません。いろいろなことが起こるわけですが、社会経済活動を維持しないといけないというミッションを持った政治家が様々なプレッシャーに日常的にさらされている中で、「正しく恐れる」という感覚を持ってもらうことが難しかったです。
結果的に、科学者が科学的事実を持ってくるというプロセスよりも、普段の暮らしの中で世間からどう見られているかとか、国がどういう評価を受けているかということのプライオリティが高い環境になってしまっていたというのが、一つの問題だと思います。まあ、そもそも人気が政府の生命を容易に左右してしまう時代ですので、その状況に生じた社会問題でもありましたから。
―― その結果、先生たちは科学者自らが語ることを選択されました。為政者を説得するのではなく、科学者が社会に直接問うという手段を選択せざるを得なかったということでしょうか?
西浦教授:現実に期待される被害規模や死亡リスクは非常に露骨な数字であって、ある意味でエグイものがあります。他方、それと比べて、被害の見通しについて骨を抜かれた後に国民に提示される内容との間には相当のギャップが生じますよね。そうなるしか選択肢がない条件下を想像いただくとわかりやすいと思います。例えば、加藤厚労大臣に依頼された「一定の対策が行われた仮定で、どれくらいの人数が入院しそうか」のシミュレーションを、厚労省の幹部の方が横に座りながら、メディアに向けてレクチャーしました。それは事務連絡や通知の添付資料として発表されるんです。ただ、そういった事務連絡や通知としてリリースされるものは「何も対策をしなかったら」の純粋な被害想定からはかなりかけ離れたものになっていました。シミュレーションをもとにした事務連絡通知は、医療提供体制を計画するためのもので、地方自治体が通知を受けて死に物狂いで頑張ればなんとか準備できるベッド数も念頭に置いたものになっています。なので、そこには、感染者が溢れたときどうするかとか、あるいは新型コロナを過小評価をして何もしないまま進んでしまったときにどうなるかとか、そういった危機管理上の想定は反映されていなかった。純粋な被害想定をリリースしてしまうと、国民の行動制限につながるシナリオがみえてしまうこともあり、「被害想定を発表しませんか?出す方法はないですか?」と何度か相談しましたが、ポジティブな回答は得られませんでした。ベッド数が足りないくらい感染者数が増えたときを想定して、どうやって死亡者数を最少に留めるオペレーションをするのか。そういったことに真正面から向き合ってオープンに議論できないことは、現状の政治主導下の官僚組織で対応できそうにない危機管理上の限界点の1つだと思います。
―― いわば“不都合な真実”になるわけですが、それを知らせることで、いろいろな予防や備えができる。世の中に知らせないことが先生たちには耐え難かったのですね。
西浦教授:日本では8割の接触削減やステイホームという対策は少しずつハイリスクの側に収れんされたものになっていきましたが、それでも第1波のときの暮らしを思い出していただくと、きつかったですよね。このきついことを国民のみなさんに強いる政策が行われるにあたって、被害想定や新型コロナの怖さを知らずに果たしてそれに同意できるのか。この後、感染拡大の波が繰り返しやってきて、このパンデミックの収束には2〜3年かかることは、私たち感染症対策の専門家には最初から概ね見えていました。なので、人生の3年分ぐらいがこれで消えるのは自分たちは覚悟していたのですが、不都合な真実に対応できない状況下で「このままでは自分たちの身が/日本がもたないな」とも強く感じていました。
厚労大臣は徐々にこちらの本音も聞いてくれるようになり、「これは国民に伝えておかないと政府にも跳ね返ります」という話さえも少し言えるようにはなりましたが、それでもなお被害想定を公表するところまでには至れませんでした。
―― 先生は一貫して「正しく恐れる」と言われています。情報がないと恐れようもないわけですが、情報の扱いを間違えると、過度に国民を混乱させると受け止められかねない。為政者と先生たちの思考やロジックとがなかなか交わらない場面において、為政者は専門家にどのようなことを期待していたんでしょうか。
西浦教授:率直にいうと、“政治と科学の問題”が生じる原因に繋がったと考えています。政治家としては、不都合な問題の責任は専門家のせいにして対応するしかないわけですね。このことは、日本では「専門家の使い方」について従来の考え方を脱することができなかったと考えています。パンデミックが起こる前から、例えば厚生労働行政で特定のワクチン接種をスタートするときや、何かをやめるときには、必ず専門家が関わります。
官僚が勝手に政策を決めるわけではなくて、学術会を代表する専門家がそろって合意して、ある種のお墨付きを与えられた状態で、その意を受けた形で政策が形づくられていた。それはメディアでのコメントも同様です。テレビなどではテレビ局が見つけてきた専門家と称される方が自由に発言するのですが、番組制作側は最終的にその人に責任を取らせることができるように作っています。「この発言の科学的な妥当性はあなた任せですよ」ということが前提になっている構造です。国や厚労省でやっていたのも、専門家任せの形にして責任をなすりつける形式にほかなりません。
ただし、こうしたプロセスは、私が英国で見てきたものと順序がおおきく違っています。本来は、ある程度の科学的見解を専門家の関与の下で作って、会議で自由な議論があった上で、政策の選択肢としてテーブルに並べ、最後に審議をする、という流れにあるべきです。しかし、厚労省の政策に関しては、あらかじめ方向性が決まっていて、それに与するエビデンスを提供すると。
―― エビデンスベースドというより、結論ありきで、それをサポートする情報を集めるためのシステム(エビデンス・ギャザリング)として審議会や専門家が位置付けられている状態から脱することができなかったと。
西浦教授:そのとおりですね。それが続いていたがために、専門家は政策の意に逆らうということはないだろうという意識は政策立案者たちには生まれていたように思います。
そうしたなかで「でも責任は専門家にある」ということを受け入れるのはとても難しかったです。特に、新型コロナではリアルタイムで何万という規模の命の問題に直面するわけですから、一時的なれども御用学者制度は終わりにしてもらわないといけない。
―― やはり、省として責任の所在は専門家に委ねたくなるものなのでしょうか?
西浦教授:いいえ、必ずしもそういうことではないと思います。流行が終わってから、各省庁の管理職の方々とお話をしていると、「申し訳なかった。ご苦労なさいましたね」と時々謝られます。新型コロナがいわゆるスロー・ディザスター(単発の危機でなく、長期間ゆっくりと続くような災害のこと)になったときも含めて、やはり「為政者の判断がもっと明文化されていないといけなかった」とおっしゃいます。ただ、心苦しいことに、緩和後の今も明文化されてはいませんが。
選挙によって選ばれているわけではない官僚がこうした政治的な責任を取ることができないということと、官邸を中心に政策形成が政治主導で行われているという現在の日本の現状の二つの特徴が重なると、官僚が実質動かしていても、専門家が責任を取るということになってしまう。必ずしも政治家のリーダーシップにまで意思決定の責任が及んでいかないという問題が生じていました。なので、流行中には何かといえば専門家が説明をしていた。それはこれまでの政策形成のあり方のツケだと思わされました。平場の会議でオープンな議論がもう少しできたらと期待したのですが。
―― 感染症では災害対応ほど行動規範が定まっていなかったような気がします。
西浦教授:おっしゃるとおりです。2009年の新型インフルエンザの遺残物として、行動計画が作られ、特別措置法が設定されていました。特別措置法がないと今回の緊急事態宣言はできなかったので、その点はまだよかった。数理モデルを利用した分析体制がぎりぎり間に合ったという話と似ています。
しかし、特措法の取り扱い方が必ずしもきれいに明文化されていなかったとか、それぞれの場面での役割分担が基本的対処方針の中に明文化されていない構造が問題の1つだったのではないかとは思います。
(取材・文 黒河昭雄、小熊みどり、編集・森田由子)
2025年1月10日インタビュー