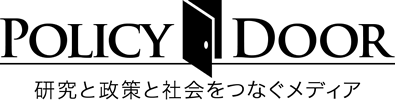感染症対策において、科学的助言者はどこまで踏み込むべきなのか。新型コロナウイルスの流行時に数理モデルを用いて政策の策定にデータ分析を通じて関与した西浦博教授は、科学的知見が政策決定に直結しない現実と向き合いながら、科学者としての良心に基づき発信を続けた。科学的助言者が直面したリスク、政策決定のあり方、そして危機における科学と政治の関係とは。本稿では、科学者としての責任と苦悩を通じて、今後の危機対応に求められる科学の役割を考える。
インタビュー前編はこちら
科学者の良心
―― 伝えたい情報を国民に伝えられないなど、もどかしさを感じる中で、埋められていないピースを科学者の良心から補完せざるを得なかったように見えたのですが、そうした強い思いがあったのですか?
西浦教授:「何もしなければ死亡者が42万人出ます」というメッセージを、当時クラスター対策班の定例会見で出しました。国でどのようなオペレーションをしているのかについて、きちんと答える必要がありました。為政者が考えている方針がどれだけ危険(リスクを過小評価してしまっている)であるかが科学として分かってしまって、そこに衝突が生じることが、2020年から2021年のオリンピックまで繰り返されます。どれだけ危ないかを知っているだけに、通常の手順を踏み越えてでも危険性を伝えないといけなくなってしまったというのが、尾身茂先生共々最も苦労したことです。尾身先生も「信念は曲げないでやった方がいい」と応援してくださった。国民のみなさんが科学的事実を知らずして大きな流行が起こるのを捨て置いて見ているよりも、自分が傷を負ってでも伝えることが得策であろうと、熟考の上で結論することになりました。「見過ごしてもこのまま研究者を続けることはできるけれど、今これを言わなかったら自分は研究者を辞めるな…」と何度も考えた結果、公表せざるを得ないという判断に至りました。
―― まさに先生が矢面に立たれて、傷だらけになっていかれる様子を外から見ていましたが、そこまでの使命感があったということですね。
西浦教授:感染症の流行のリスクは起こってから理解するのでは、あまりにも被害が甚大になります。感染者数は指数関数的に増加しますし、気付いたときには病院のベッドがなくなって、政府は国民の信頼を失うような状態になってしまいます。実際に第4波の大阪府やその周辺府県で、為政者による対策が遅れてしまって収容するベッドが足りない事態が起こりました。都道府県別での死亡率が第一位になる背後において、医療従事者さえ目の前で苦しむ人の命を助けられない状況に直面し、心に傷を負ってしまう方が続出する事態になったわけです。一方で、政府の中枢の人たちはそこまでになることを必ずしもちゃんと理解できていないと思われる状況が続きました。なので私の立場としては、これから何が起こるかが見えているだけに、それでもこれは危ないという声を上げるということをやらざるを得ない状況が続きました。
―― 強い職業倫理と使命感の中で、政治家の方々を諌め、科学的知見に照らして言うべきことを言わなければいけないという強い思いがあったのですね。
西浦教授:そうですね。だから今回の流行で家に帰れなくなる頃に、妻に先に謝りました。「申し訳ないけど、僕は研究者を辞めないといけなくなるかもしれない(これまで研究環境をかなり優先して家族生活の方向性を決定させてもらってきましたから)。そしたら一兵卒のお医者さんとして頑張って働くから許してね」と言いながら、仕事をやり続けました。場合によっては「これは命を落とすかもしれない」と思うようなことに直面したことも何度かあるのですが、人口のレベルで国民の命を背負ってしまう状態になっていたので、文字通り自分の命を懸けてでもやらないといけないという思いでした。ただ、オリンピックぐらいまでには政府の方々の必死さも伝わってきて、同じ船に乗っていると感じるようになってきました。ただ、それでもどこまで危ないかという感覚は必ずしもきちんと政治家に伝わらないので、どうしても自分の倫理感に従って行動するしかないと割り切らざるを得なかい場面が複数ありました。2021年頃には、何度もそうした苦しい思いをしました。同じ経験は2度としたくないですね。

科学的助言者が脅威にさらされる
―― 新型コロナ政策を主導したアンソニー・ファウチ氏(元アメリカ政府首席医療顧問)の警備に、アメリカ大統領府が多額の予算を投じていたという報道がありました。科学的助言者や政府の科学部門のトップの人たちが、政府に求められて様々な分析を行い、科学的な良心に従って知見を提供しているにもかかわらず、私的な生活に脅威を抱える状況に置かれてしまった。西浦先生もご自分の人生を賭して臨まれたわけですが、普通は発表を控えてしまって当然で、政策決定に活用されるべき知見があっても社会で活かすことができなくなってしまう。結果として社会はよくない方向に突き進んでしまうこともありえるわけです。そうしたときに、政府はどのように科学的助言者をサポートするべきでしょうか。
西浦教授:まず、科学的助言の位置付けを明文化しておくことが必要だと思います。実をいうと、積極的な流行対策が行われなくなった今、私たちは法的に何の責任もなく生きているわけではなくて、法律上も難しいイベントに直面しています。例えば議事録をオープンにする話が流行初期にありましたが、それは望ましくないとある専門家会議の年配の先生がおっしゃいました。「『あの時あの人がこういう話をしたからこっちに政策が動いた』と言われたらたまらない」という主旨でした。それは若手の私たちを気遣ってのことだったのだと今になって思います。少なくとも科学的助言や発言の内容そのものについては、ある程度免責をしておく制度を作っておかないと大変になるだろうなと。例えば、(民事上・刑事上)裁判が起こった場合、省庁が助けてくれるかというと、そんなことは一切ないわけです。私生活における物理的な安全性も脅かされ、社会的立場も危ぶまれる状態になりますし、訴えられたら自前の費用で弁護士に依頼をすることになります。そのため、こうした制度作りをしないといけないと感じています。
―― 科学者の良心がきちんと発露するためには、発言について法的な責任を取らない、そもそも意思決定は政治が行うのであって科学者はあくまで情報提供したに過ぎない、ということがきちんと制度化される必要があるということですね。そうしないと、個人の使命感に依存した科学的助言はきわめて脆い。
西浦教授:はい。アメリカなどでは健康的な話し合いが行われています。科学顧問であったファウチ先生が「トランプ大統領が対策を遅らせたから、これだけ死亡者が出ている」と言ったら、トランプ大統領が「ファウチのせいだ」と発言して、お互いオープンにやり合うことができる。それはある種、科学と政治の間の健全なやりとりであると思います。為政者の責任が問われますし、感染症の専門家として正しいことを述べることができるのが制度化され、最後は大統領を尊重して決定が下る、という形が作れているのでしょう。ファウチ先生は胃が痛い思いをした思いますが、米国で専門家が目指すべき位置と責任は若手の目には明らかだと思いました。
どこまで科学者がやるべきか
―― 科学者の役割として、分科会の報告書に「前のめりになり過ぎていた」ことも書かれていましたが、前のめりにならざるを得なかった側面も多分にあったと思います。一方で、専門家が政策を決めているように見えたところも確かにあった。危機における科学者の役割や行動のあり方を、今改めてどのようにお考えですか。どこまで科学者がやるべきなのか、やってよいのか。
西浦教授:科学者の政策関与の仕方にはいくつかあると思います。科学的な正解を提示して後は手を離す場合もありますし、「こっちに行った方が正解だ」と誘導する場合もある。今回の流行でいうと、責任の所在が不透明だったこともあり、個々の細かいケースから分類するならば、誘導する役割を果たした機会が幾度かあったのではないかと思います。現に、感染症は流行規模が大きくなってしまってからでは対応が大変なので、大きくなる前に先出しで対策を打たないといけなかったわけです。ただ、最終的な決定は官邸の中で行われていたのが実体で、そこでどういう話し合いが行われているのか専門家は知る由もありませんでした。
どの関わり方が最適かは、科学的助言に関連する政策決定や会議のあり方などの環境に依存して変わると思います。日本のように専門家が無理してでも火中の栗を拾わないといけない体制はガバナンス上の問題が多分にあるわけですが、英国のようにビューロクラクティックな(官僚制度上の)システムが緻密なところは責任の役割分担がしやすいですね。
むしろ、今回の経験を通じて質さないといけないと思われるのはこの点だと思います。政策の科学性の問題や日本独自の傾向があると思うので、政策決定側が科学的助言を受ける体制・システムとして日本独自のものがあっていいと思います。その最適なあり方を見つけていかなければいけません。
―― 今回、先生は科学的助言者としてどのようなスタンスで臨まれてきたのでしょうか。政策の選択肢を示すところまでなのか、それとも問題提起までを狙っていらっしゃったのか。
西浦教授:時とともに状況が変化していったため、また専門家が少なかったため、自らの関わり方も時とともに多様に変化しました。流行初期には大臣のブレーンとして機能し、例えばダイアモンドプリンセスの下船時には「選択肢にはこれらがあり、こうした理由から選択肢1がいいです」というところまで解説しました。一方で、パンデミック中盤以降に開催された会議では自分からの発言はできるだけ客観的な分析が主になるようにして、政策には後で求められたときにコメントする。本当は、その二つの役割を政策に関与する有識者と分担したり、会議の前に本音で意見交換をしたりできるのが理想ですが、難しいなと思いながら各自が一人何役もやらざるを得なかったのが実情ではないでしょうか。
―― ご自身が置かれている状況によって役割は変わってきたということですね。
西浦教授:科学的助言の最適な方法は、パンデミックの場面によっても大きく変わると思います。パンデミック前は旧式のやり方に近く、科学的助言が採用されるときもあるし、されないときもあるというような、状況をよい方向に持っていく辛抱強い努力が必要でした。しかし、今回の流行中には、岩盤を突き崩すウルトラCの決断が必要でした。実際に「この流行状況はどうしようもないから、専門家の言うとおりにやります」ということが、2021年の緊急事態宣言時などでみられました。そのような体制を自然なものとする方法は、今後検討する必要があると考えます。例えば英国などは、流行対策の大枠の方向性を決めるときには、3つぐらいの信頼できる数理モデルの研究者のグループから意見を求めています。同時にその3つのグループに分析を依頼し、論文をScienceやNatureに出る頃までに技術的議論を完了させた上で「どの政策選択肢が正しいか、どの不確実性が最も問題なのか」をある程度特定する、というやり方をしています。
合議制を中心とする日本では、エビデンスを参照する時間さえ確保されていないのが正直な感覚です。「政策に最適なエビデンスは何か」が事前に議論された上で、本当の意味での“研究者のお墨付き”に移行できる体制は作っておかないといけないと思います。

カウンターベイリングリスク
―― 様々な数理モデルに基づいて分析結果を提供され、実際に被害想定なども提示されていく中で、そうした判断に基づく対策のカウンターベイリングリスク(対象となるリスクを低減することを表向きの目的とした活動の結果、生じる有害な結果の可能性)については、実際どのくらい検討されていたのでしょうか。
西浦教授:感染症に関しては、定量的に異なるシナリオで進んだ場合どうなるのかは第5波まではほぼ全て捉えることができていました。また、いわゆる人口動態に係るところまでは自分たちで何とかしないといけない範疇でしたので、分析することができました。
一方で、たとえば自死には複数の要因が存在します。失業者や生活困窮者、うつ病の人が増えて、ミクロにはドメスティックバイオレンスが増えて、などいくつものメカニズムがあります。そういうデータを分析すると、自死の予測もある程度は成り立つので、その過程を簡易的に記述したモデルで試行錯誤しながら最終的な死亡者数を加味しながら分析するということはパンデミックとともに走りながら(緩和までの過程の途中で)できました。しかし、そのモデルで捕捉したメカニズムがパンデミック中のメカニズムは捕捉できたとしても、どこまでユニバーサルに次のパンデミックの機会を含めて適用可能かというと、相当に心もとないのが正直なところです。
例えば、尾身先生が途中でつらいなと繰り返しおっしゃっていたのは、中高生の子たちが学校のイベントや部活動に関して、自分たちは青春の機会を我々に奪われたと感じているだろうと。そういった奪われた機会や価値判断に至るような問題、経済学ではミクロ経済上の問題や消費構造などは、常に中枢で誰かがケアできている状態は作れていなかったと思います。価値判断は実はモデル化可能ですし、ミクロ上の社会活動もパンデミック中の流行波を繰り返す構造の中では定量化可能になっていました。
―― まずは感染症の流行の制御を目的に定めたときに、あらゆるリスクを考慮しないと動けず何も進まないということになるので、やはり初期に優先順位をつけて対応する必要がある。ただ、考慮しなければいけない要素が徐々に分かってくる中で、どうやってカウンターベイリングリスクまで考慮しながら対策を進めることができるでしょうか?
西浦教授:本当はそこに学際研究の可能性があります。しかし今回の流行では、英国でもそうでしたが、残念ながら経済学の先生と医学側の研究者とは価値観をぶつけ合うだけになって、なかなか上手く協調的な見解を見出すことができなかった。
英国では公衆衛生とマクロ経済学の間に起こったことについてbitter disagreementという表現を使って表現されていますが、自分もあまり積極的にコミュニケーションをとることができませんでした。しかし、それはやり方が間違っていたからかもしれません。正しい方向(機能的になるだろう方向性)としては、政策の意思決定モデルについて、様々な分野の専門家がそれぞれの知見を駆使して一緒に分析をしていく機会を作る。少なくとも、心理学や法学に関してはそれができたのではないかと思います。これまでに運営を開始した京都大学のヘルスセキュリティセンターではそうした実践を目指しています。
―― 各論的な話になりますが、例えば「2類から5類への移行が他国より遅かった」という指摘については、先生はどのようにお考えになりますか。また、何をもって移行を判断すべきだったのでしょうか。
西浦教授:この話もそろそろもうオープンにしていいと思いますが、日本がOECD加盟国の高所得国の中で死亡率が最低なのは、きちんと最低限の項目について緩和の随分前の時点にはインテリジェンスが入っているからです。緩和の話になったときにも、もちろん専門家の間だけではなく、政府からも見解の提示が求められました。特に、英国のような緩和の仕方をすると今後どれくらいの被害規模や入院の問題が生じ得るのかというような疑問に何度も答えていくわけです。あるいは、仮に3回目の予防接種終了時に最もひどい流行が起こったら、どれくらいの人が死亡し得るのかというのは常に計算をして、関係者にフィードバックは実施しました。
「日本は緩和が遅かった」と言われますが、英国のようにオミクロン株の侵入直後でいきなり緩和をしたら、オミクロン株流行の被害規模はやはり甚大なものになり得たと考えられますよね。それと比べて日本は、テーパリングというのですが、対策のレベルを少しずつ緩めながら緩和を迎えました。緩和の決断直前の第8波が遠隔地域で大きかったのですが、その後は流行規模が大きく変わっていないと思います。集団の中で免疫を保持している人や、死亡し得る人がこれくらい出るというのを科学的に見ながら、何とか対策のレベルが緩和されたという背景状況を反映しているものと考えられます。
死亡率を見れば、テーパリングで思い描かれる話に近い状態にはなったものと思います。高齢者が極めて多いこの国で、死亡率をここまで抑えられたというのを誇りに思うべきとさえ言える状況で推移したのです。一方で、それがよかったのかは価値判断に関わる問題であり、社会科学の領域からの専門家を交えた総合知としての評価も求められます。経済活動のマクロ指標だけで判断できるわけではないことも私たちは理解してきたわけです。経済の最適化ではお金を軸にし、医学であれば命を軸にするわけですが、お金や命だけではすべての価値を包含して評価できない。なので、どういう道が最適だったのかは当時から存在していた技術だけでは判定が困難だったと思います。このあたりは、まさにこれからの課題になるのではないかと思います。
―― 本日は貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。
(取材・文 黒河昭雄、小熊みどり、編集・森田由子)
2025年1月10日インタビュー