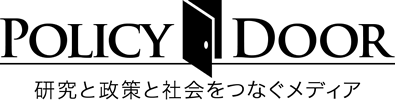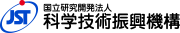早稲田大学の牧兼充准教授は「サイエンスとビジネスの好循環」にデータ分析で迫っている。
高被引用論文を多数発表し、特許の出願も多い卓越した研究者「スター・サイエンティスト」は、産学連携、特にスタートアップのビジネスに携わることで産業の面でもインパクトを与えていることがわかった。
*RISTEX採択のプロジェクトの内容については、こちらの記事を参照のこと。
特に、科学研究から科学的知識が生産され、それが産業界に移転されやすい創薬の分野では、スター・サイエンティストの寄与が顕著である。牧准教授は、内閣官房「創薬力向上により国民に医薬品を迅速に届けるための構想会議」の構成員になるなど、多くの政策形成の場に参加している。2024年7月の創薬エコシステムサミットでは、岸田元総理が「スター・サイエンティスト」という言葉を用いて未来のビジョンを語るなど、その研究成果が政策の実装に届き始めている。今回は、政策関与における牧准教授の意識や工夫について伺った。

一般書が行政官の目に留まった
――政策への実装という観点では、RISTEXのプロジェクト期間内には、政策サイドにスター・サイエンティストの概念を理解してもらい、直接政策につなげるのは難しかったかと思います。しかし、プロジェクトが2021年3月に終了してから現在(2024年12月)まで4年弱の間に、経済産業省の産業構造審議会や内閣官房の「創薬力の向上により国民に最新の医療を迅速に届けるための構想会議」(以下 創薬力構想会議)などに委員として参画されて、「スター・サイエンティスト」という言葉が政府の文書や首相の記者会見の文言に載るところまでたどり着かれています。この間どのような研究とアウトリーチをなさってきたのでしょうか。
牧先生:まず、プロジェクト終了後に科研費を2回取得することができたので、研究はRISTEXのプロジェクトを受ける形でそのまま続けました。社会実装の観点では、大きかったのは早稲田大学での授業をもとに「イノベーターのためのサイエンスとテクノロジーの経営学」という本を書いたことです。この本が行政官に届いたんですよね。本をきっかけに、産業構造審議会、内閣官房、文科省の戦略的調査分析機能に関する有識者懇談会にも声を掛けていただきました。あとは経団連のScience to Startupという政策提言の取りまとめにも関与しました。
――なぜ論文ではなく一般向けの書籍という媒体を選択されたのでしょうか。
牧先生:学者として、論文を書くのと本を書くのは両方やった方がいいなと思っています。ただ、あの本を一般向けと呼ぶのかは自分でも悩んでいるところがあって。一般向けというには結構マニアックですよね。一般の人も読める専門書を書いたという感覚です。
――ハイリテラシーだけれど専門家ではない人を読者として取り込むことに成功していると。
牧先生:そうだと思います。思ったより早く第2版までいったので、一応売れたかなと。いろいろな大学のゼミの輪読書などに使ってもらったみたいで、その反響は大きかったですね。ゼミの輪読で使っているということは一般書というよりは専門書なのかなと思います。
――皆で共有しておきたい知見が1冊に集約されていて、多くの人が手に取ってその分野の基礎について学べるようなものであったということでしょうね。
牧先生:一方で、大学の人事評価が実態と合わなくなっているところもあります。つまり、研究論文だけを評価するという考え方の人たちと、一般書まで含めた書籍の執筆も評価するという人たちがいる。なので、中堅の研究者が時間をどう配分するかは大切な課題です。狭い意味での研究業績だけを考えると書籍は書かない方がいいのですが、そこは社会的なインパクトを求めたという思いがあります。今の大学は「社会的インパクトが大事だ」と言いながら、それを評価する仕組みがなかなか作れていない。
――アウトリーチの仕方として、書籍という媒体の選択には意義がありますが、人事評価と噛み合わないのが難しいですね。でも、論文だけを書いていたら、行政官たちの目に留まることはなかったと思う。
牧先生:はい、政府の仕事はこんなにしていなかったでしょうね。おそらく行政官は本は読むけれど、論文まではなかなか手が出せないのではないかと思います。大切なポイントは、本はエビデンスとナラティブ(物語性)の融合だということ。読者たる行政官の目に留まるためには、まずナラティブがないと駄目。次に、行政官が主張を通そうと思うときには、ナラティブの中で部分的にエビデンスを使いたい。一方で、論文だとエビデンスに偏り過ぎてしまう。 それだとやはり行政官には届かないのだろうなと感じます。
――「エビデンスに偏り過ぎてしまう」というのは?
牧先生:論文というのは、基本的に質の高いエビデンスがなければ査読に通らない。でもそれだけでは行政官は拾いようがない。行政官は、まず「どんな政策をパッケージとして作りたいか」という物語があり、そのヒントを欲していると思うんですよね。
一方で、具体的な物語があるときに、いろいろな人を説得するためには、エビデンスが求められる。
例えば政策の企画立案から評価までのプロセスでいえば、前半の方がナラティブで、後半の細かいところを詰めていくときにエビデンスが必要なのだと思います。
人材育成がチームづくりにつながる
――政策へのインパクトが大きくなったのには、他にどのような要因がありましたか。
牧先生:振り返って思うと、ゼミの卒業生のコミュニティです。内閣官房の創薬力構想会議のメンバーに入ってすぐに政策チームを作らないといけなかった。その時に、ゼミの卒業生で製薬会社の人が多かったし、スタートアップやVCの人もいた。さらには、内閣官房に出向中のゼミの卒業生もいた。
――卒業生のネットワークの中でビジネスが生まれるような偶発的なつながりは、その組織が資源として提供し得るものですよね。牧先生は特に教育にエフォートを割かれている印象ですが、そのことが結果的にバックアップ体制の構築につながっていると。
牧先生:はい。教育にエフォートを割くと、コミュニティが強くなり、そのコミュニティはいろいろな分野で価値をうむものになっていきます。それが結果的に政策立案にも役に立っている。もともと、政策チームを作ろうと画策してゼミを立ち上げたわけではありません。内閣官房に出向する人がいるなんて偶然だし、スタートアップに転職する人がいたのも偶然だし、それは結果論ですよね。ただ、ゼミを取り巻くコミュニティを作ろうという意識はもともとありました。
――牧先生の知見だけで対処できないことはチームで補いながら、審議会に様々なメッセージを出したり資料を提供したりすることができたと。
牧先生:そうですね。創薬力構想会議のときは、あまりにも多くのことを急いで学びながらやらないといけなかった。自分自身が全体像を分かってないのに、いきなり首相官邸の会議室で話さないといけないという状況でした。なので、資料を作るときにかなりゼミの卒業生に手伝ってもらっていました。手伝ってもらっているうちにチームになった、というのが正確なところです。

提案だけでなく社会実装まで関わる
――研究者が政策過程に関与して知見を提供することを広義に「科学的助言」と呼びますが、牧先生はどのようなスタンスで政策に関与されていますか。
牧先生:研究をきちんと社会実装してデリバーするところまで研究者が関わらない限り、その知見は伝わらないと思っているので、能動的に関わることが多いです。例えば、創薬力構想会議ではKPIまで全部見ています。政策は細部に宿るので、KPIまで自分で見ないと結局歪んだものしかできないだろうと思っていました。今そのKPIをモニタリングする仕組みを作ろうとしていて、そこにも研究者が入らないと駄目だろうなと思っています。
――こういうところを見ていると提案が使われていないと感じるなど、そう考えるきっかけはありましたか?
牧先生:使われていない以上に、使われているものであったとしても、研究者が提案した政策は現場に落ちるまでに、最初の理念は必ず劣化していく。劣化する前提で、研究者が中に入り込んで実装していく仕組みを作らないと駄目なんだろうなと。そういう事例をたくさん見てきました。
――「劣化していく」というのは、都合よく解釈されたり、アイデアの一部だけが都合よく使われてしまうことなどでしょうか?
牧先生:更にいえばもともとの理念を理解しないまま表面的な実行プランになってしまう。エコシステムやスタートアップの分野では特にそういうのが目立ちます。それから、福澤諭吉が「学者は国の奴雁(どがん)なり」と言っています。奴雁とは雁の群れでの警戒役のことで、政局や流れに惑わされずに道しるべになるようなことを言い続けないといけない、ということだと思います。実務家の不都合な真実を暴くような研究が一番大切なのだろうなと思い、最近はそういう研究をやろうと心掛けています。
――スター・サイエンティストの知見を政策へのインプットでどのように活かせたか、もう少し教えていただけますか。
牧先生:創薬力構想会議の時に、大企業かスタートアップかという議論の中で、「日本でも優れたスター・サイエンティストほどスタートアップと組んでいる傾向がある」ということを官邸の会議で説明しました。これは結果的に「スタートアップをサポートすることが重要なんだ」というエビデンスを提供したと思います。
また、サイエンティストがスタートアップに関わると研究のパフォーマンスが下がると思われていたところが、スタートアップに関わると研究業績も上がるというモデルを示すことによって、少なくとも産学連携のサポートの仕方もガラッと変わる。この辺がより多くの人に理解されたのは大きかったと思います。
――それがきちんとメッセージとして提示され、かつナラティブとして理解され、その背景となるエビデンスをもって提示できているのは、重要ですね。
牧先生:「アメリカで言われているサイエンスとビジネスの好循環が、日本でも起きている」と伝えられたことはやはり大きいですよね。このプロジェクトをスタートする前は、みんな「アメリカだけの話でしょ」と思っていたので。
――お話を伺っていて、やはりサイエンスとビジネスの好循環が実証的に示されたことがとても重要な意味を持っていたのだと感じます。科学者が政策に関与することで結果的に科学者の側にも利点がある、つまり研究のパフォーマンスが上がったり、研究開発を取り巻く環境がよくなったりするような好循環がないと、政策形成のような多くのエフォートを割かなければいけない活動に関与することは割に合わず、成り立たないような気がします。牧先生はなぜこれを実行されているのでしょうか。
牧先生:政策実装に深く関わると、よりよいリサーチ・クエスチョン(研究のテーマや切り口)に出会うことは多いですよね。(理系分野の)スターの研究者を見ていると、その好循環をうまく回してる人が多い。例えば、副学長になってもパフォーマンス下がらない研究者がいて、それはチームで研究している人たちなんですよね。
私自身は研究対象としてのスター・サイエンティストたちをロールモデルとしています。なので、私の研究スタイルもチームを作っていろんな人が分析をするようになってきているので、私が政策に時間を割いても研究のパフォーマンスが下がりづらくなってきています。そして私が政策で社会にインパクトを出していけるようになると、よりよいリサーチクエスチョンをいろんな人から持ち込まれるようになるし、そのチームにいる人がその研究をより面白いと思うようになるから、周りの研究者のコミット量が上がる、というような好循環がある気がします。
――リーダーが果たすべき役割は、研究の詳細な部分を自分で動かすというよりも、チームにきちんと場やデータ、クエスチョンを提供すること。牧先生が現実の政策形成やビジネスに関与することで、それができているから、好循環が成り立っているということでしょうか。
牧先生:はい。授業が多いときはここまでできなかったのですが、サバティカルに入ってやれるようになりました。しかし、今の日本にはチームを率いることを評価する指標がないので、好循環のサイクルをいくら回しても大学で業績として評価されづらいという問題もあります。
――研究の評価については、論文数に固執し過ぎているのは問題意識としてはあるものの、なかなかその呪縛から逃れられていないのだろうなと思います。社会へのインパクトは測定と評価がしにくいという問題もありますね。
牧先生:はい、今まで以上に、社会への「インパクト」という言葉が重要になっています。でも、どんなインパクトを出しているかを本人がナラティブで語らないと全然伝わらない。インパクトを評価するのは難しいので、全てが評価されることは難しいですが、問題は評価する側がインパクトのエビデンスを集めようとしていないことではないでしょうか。まずはエビデンスを集めてみて、そこで経験を重ねないと駄目なんだろうなと思います。

若手行政官とのコミュニケーションを大事にする
――実際に政策当局とはどのようなコミュニケーションをされていますか。どのように信頼関係を構築し、継続的な関係性に持っていかれているのでしょうか。
牧先生:自分の主張をちゃんとするという前提で、それぞれの会議で「落としどころは何か」を事前に事務局に聞くようにしています。加えて、政策に関わる若手のキャリアの発展を手伝うことが大事だと思ったので、彼ら彼女らがやりたいことを聞いて、そのディスカッションをするようにしていました。これもある種の人材育成の取り組みでもあるのだろうなと考えています。
――教育や人材育成が、うまく政策サイドへのアウトリーチに効いていますね。これが関係性構築のプリンシプルのようにも思いましたし、その人を良くしてあげたいという思いがあり、実際に機会を提供されているので、結果としてより良い関係性に持ち込めているということになるんでしょうね。
牧先生:もう1つ思い出したのは、創薬力構想会議が終わった後に、運営を引っ張られた方が「今回の会議のMVPだった」とおっしゃってくださって。「民主主義という枠組みの中で『何をいうと何が通るのか』を考えながら発言していたのが、他の人と決定的に違った」と言われて。これはEBPMやRISTEXもそうですが、民主主義社会の中でどうやったら物事を通せるのかという前提がある中でのエビデンスなのだと思うのですよ。
――これは高度な会議運営の戦略で、これができる人って意外と少ないですよね。初代プログラム総括の森田朗先生が書かれた『会議の政治学』の世界につながります。
牧先生:このような、私の政策への関与は、若い頃の指導教員からの影響が大きいです。村井純先生からはチームやコミュニティの作り方、鈴木寛先生からは人材育成の仕方、國領二郎先生からは政策の提案資料のまとめ方など。慶應で多くの人から影響を受ける機会をもらえたのは本当に恵まれていたと思います。
――牧先生は先達から教わったことを実践されているのですね。
牧先生:はい。それから、これはサイエンス・コミュニケーションの話に近いのですが、「科学・技術イノベーション政策のドキュメントは読んだ人をワクワクさせないと駄目だ」と、必ず言うようにしています。霞ケ関の資料って大体は日本の問題点から始まるんですよね。そうしないと財務省から予算を取れないのは分かるのですが、1ページ目は今の日本の駄目なところではなく、日本の潜在的に持つ強みを語った方が良い。その後に現状の課題と解決方法、としていかないと読む側が全然ワクワクしない。創薬力構想会議でも、「この文章を読んでほしい最大のステークホルダーは誰か」という問題提起をしました。それは今健康で将来病気になる人たち。そういう人たちがワクワクする文章にして、投票行動にも反映されるような文言をたくさん入れないと駄目ですよね。そこまでは会議では言いませんでしたが、どんなメッセージを発信するかにはこだわりました。
――政治家とのコミュニケーションはいかがでしょうか。内閣官房、内閣府クラスの意思決定になってくると、その後ろにいる政治家とのコミュニケーション、あるいは政治家が抱える団体がどのようなステークを持った人たちなのかによって、議論の仕方が変わってくる。この辺はどのようにケアされたのか、探りながら進められたのかを教えていただけますか。
牧先生:結局、構想会議の間はそこまではできなかったんですよね。構想会議と同時に進められていた自民党の「創薬力の強化育成に関するPT(プロジェクトチーム)」にもキーパーソンがいらっしゃったのですが、実際には中間取りまとめ後にはじめてお話をさせていただき、その背景についてようやく理解できたという経緯がありました。政治家、特に若手・中堅議員さんたちのなかには、強い問題意識を持ち、政局によってぶれない中期的な視点を持っている人たちもおられるので、そうした方々が目指しているものについてもきちんと理解しておかなければいけないなと感じました。
――本日はたくさんのお話を聞かせていただきました。行政側のスタンスを決めるときに、ナラティブが背景として提供されていないと、どれだけエビデンスを提示してもコミュニケーションが成り立たない。なので、いかにナラティブを同時に作っていくことができるか、そしてそれをどう提供できるか。もちろんナラティブだけでも駄目なのですが、きちんと研究成果を作った上で、ナラティブがいかに重要かというのを改めて確認させていただきました。それから、実際にその政策の当局とコミュニケーションしていくときのコミュニケーションの取り方や配慮すべきポイント、あるいは人材育成の観点からチームを作っていくアプローチも教えていただきました。これはプログラムの知見としてもしっかりまとめさせていただきます。ありがとうございました。
(取材・文 黒河昭雄、小熊みどり、編集・森田由子)
2024年12月3日インタビュー