第21回「次世代AI開発 脳・情報科学を融合」
深層学習の限界
人工知能(AI)は私たちの日常に浸透してきた。スマホアプリや自動運転車、企業の業務AI化、さらには遠くない将来、AIの発展が人間の知性を超えた時点で社会に大きな変化が起こること、いわゆる「シンギュラリティ」への危機感が世間をにぎわせるなど、話題は尽きない。
プライバシー保護や公平性などAI開発がもたらす倫理的課題とともに、技術的に超えるべき高いハードルもある。人間の知的活動の大部分をAIで置き換えようとしても、現在のAIの原動力であるディープラーニング(深層学習)だけでは力不足で、新しいアルゴリズムが必要とされる。幼児が一目で人の顔や物体の特徴をつかめるにもかかわらず、深層学習は特徴を処理するためにいまだ膨大なデータを要する。
深層学習の源流は、1970年代に情報科学者の福島邦彦博士が脳の視覚情報処理に着想を得た「ネオコグニトロン」にさかのぼる。深層学習の限界が明らかになった現在、脳の他の機能を手本にすることが一つの方向性だろう。
脳科学には大きく分けて、生物学的に脳を理解しようとする実験的研究と、神経回路モデルや脳の動作アルゴリズムを考える理論的研究がある。AI研究に直結するのは理論の側で、実験側との接点は長い間ほとんどなかった。
しかし10年代に入り、技術の飛躍的な進歩で神経回路あるいは脳全体を対象にした実験が可能になり、理論と連携する道が生まれた。例えば、計測データに基づいた精密な脳モデルの構築から、脳機能の全体像の理解へ、などと期待されている。こうした挑戦が次世代AI開発への突破口となり得る。
若い頭脳を育成
欧米では理論と実験の両方に通じた脳研究者が増えている。その背景には、理論神経科学を含む脳科学を専門に学ぶ学部・研究科が多く設置されていることがある。わが国はこれまで理論・実験とも多くの成果を挙げてきたが、理論と実験の両方にまたがる脳科学のカリキュラムを組む大学・大学院はほとんどなく、次世代脳研究者の育成では欧米の後塵を拝している。
次世代AIは現行AIの持続的改良ではなく、ごく少数の研究者の独創的発想から創出される可能性がある。わが国が脳科学と情報科学を修めた若い頭脳を積極的に育成してゆけば、次世代AI開発のイニシアティブを取れる余地は十分にある。
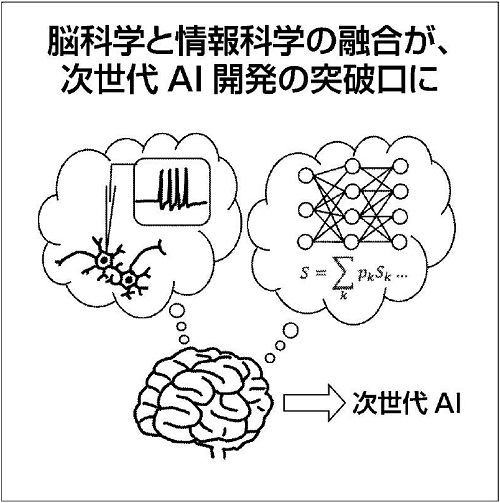
※本記事は 日刊工業新聞2019年9月6日号に掲載されたものです。
<執筆者>
井上 貴文 CRDSフェロー(ライフサイエンス・臨床医学ユニット)
大阪大学大学院医学研究科博士課程修了。東京大学助手・助教授を経て現在、早稲田大学教授。神経科学分野の研究を行う傍ら、調査・政策提言活動にも携わる。博士(医学)。
<日刊工業新聞 電子版>
科学技術の潮流(21)次世代AI開発 脳・情報科学を融合(外部リンク)
