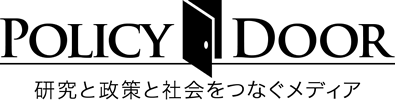政策形成を進める上で、科学的なエビデンス(根拠、裏付け)が重要である一方、頑健な専門知のエビデンスがあれば済むというわけではない。ステークホルダー同士が衝突する場合もあり、専門知だけでは判断できない場合も多い。エビデンスをもとに、一筋縄ではいかないステークホルダー間の「合意形成」をどのように進めていくのか。研究者は合意形成にどのように貢献しえるのか。お二人に合意形成と研究者の役割についての考えを伺った。
合意形成における研究者の関与
――「政策のための科学」において、合意形成における研究者の役割や、重要なことは何だと思われますか?
馬場:2つありまして、ひとつは科学的なエビデンスの創出と政策過程への実装です。EBPM(科学的知見をベースとした政策形成)が実現しないのには、相互に理解が不足しているなど、研究者側にも政策担当者側にも様々な理由があり、科学的な知見をいかに有効な形で政策過程に乗せていくのか。解はないのかもしれませんが、ずっと追求していかなければならない課題であると思います。
もうひとつは、ステークホルダー間のコンフリクト(衝突)の解消です。社会での意思決定にあたり、当事者間で合意が取れない場合に、第三者が入って合意を図ることはしばしばありますが、それを研究者やコンサルタントなどが担うケースは多いと思います。それでひとつの政策決定や意思決定が成立できればいいと思いますし、意義はあると思います。ただし、第三者が入ってうまく合意が形成できるのかというのもケースバイケースの永遠の課題で、こちらもなかなか答えは出ないと思います。
乃田:少し突飛な答えかもしれませんが、いわゆる「御用学者」という存在を考えると、従来はステークホルダーの後ろでコンサル的に動いていた人たちでした。それに対して、私たち研究者に今求められている役割は、ある意味で御用学者的ではありますが、コミュニケーションの最前線で仕事ができることかなと感じています。
異なる分野間でも研究者同士だと話ができるわけです。そのときに、科学的なエビデンスにもうひとつエッセンスを加えるならば、インタープリテーション(解釈)が大事だと思います。ひとつの事実に対して、その解釈は様々にできるように、インタープリターの役割も研究者に求められているのだろうと思います。研究者は、そのままでは理解し合うことが困難なステークホルダー間のコミュニケーションの潤滑油になり得る。利害の対立しがちなセクター間のステークホルダーを対象としたワークショップをやっている中でそのように感じています。
馬場:インタープリターはとても大事な役割ですね。ただ、我々が介入していったときに、何らかのシナジー(相乗効果)やトレードオフ(両立しないこと)を示せるようなインタープリターとなり得ているか。自戒を込めて考えると、十分には至れていないかもしれません。
よいインタープリターになるために、研究者としては「コ・デザイン」(ステークホルダーと共に、科学的知見や現場の知見を組み合わせて、まとまった知見を創り上げていくこと)を本当にやるとはどういうことかを考える必要があると思っています。例えば、気候モデルをつくるとき、モデルの変数やシステムの組み方を考えますが、多くの場合は研究者の頭の中だけで考えています。そのときに、現場の知見が本当に必要ないのか、あるいはステークホルダーがもつ知見はどういう意味を持つのかと考えてみると、仮説の立て方が変わってくる可能性があると思います。それでコ・デザインが重要となる。そうなると、乃田先生がおっしゃるような単なる御用学者ではなくなってくるという気がします。

馬場 健司 東京都市大学環境学部 教授
合意形成における課題
――科学的な手法により客観的で合理的な意思決定を行うことや、その地域の将来を皆で考えていくことは「言うは易し、するは難し」で、実際に合意形成の現場に立ち会われている先生方もいろいろな困難に直面されているのではないでしょうか。合意形成の難しさはどのような点にありますか?
馬場:合意形成には案件の数だけ答えがあり、こういう原則を守ってさえいれば、こういうガイドラインやマニュアルに沿ってやりさえすればうまくいく、ということではないですよね。その案件が存在する文脈の中で、追求していくものがその都度違います。
また、ひとつのファクト(事実)に対して、各々が違うフレーミング(考え方の枠組み)を持ち出してきます。そこがそもそも違うと合意形成は非常に難しい。難しさの大部分はそれに尽きるのではないかという気がします。
だからこそ、他人から供給されたものを眺めているのではなくて、皆でファクトを築いていこうというところが一番大事だと思います。
――ファクトを一緒に築いていけば、後から事実を確認し合うのではなく、初めから同じ事実を共有することができる、ということですね。乃田先生はいかがですか?
乃田:私が一番難しいと感じるのは、「合意しようとするかどうか」という点です。問題が明確であれば、「この件に関しては合意しない」というのも合意ですよね。解決すべき問題が共有できているのか、関与者に問題を解決したいと思わせるまでのプロセスがとても重要になります。しかしコンフリクトがある状態では、一堂に会して思いの丈を述べたところで、絶対に解決には向かわないわけです。だから、ワークショップの設計や、それまでの背景となる経緯をきちんと理解しておくことなど、開催にこぎつけるまでの準備がとても重要だと思います。
――今のお話を聞いて、あらためて難しさを感じたのは、関与者に問題を解決したい気になってもらうという点です。どのような試みをされたのでしょうか。
馬場:それも本当に難しくて、我々の今回の課題設定は「将来的な気候変動の影響を見て、今のうちにしなければならないことは何か」だったので、現在なにか具体的な利益の対立があるかというと、さほどそうでもない。そのため、ワークショップに参加してくれる人たちは、普段から自然保護や環境保全に関心があり、すでに活動されている方々に限定されます。一部の人たちが見出したエビデンスを、皆で共有できるかというと、そこにはまた壁があり、他の多くの人たちにとっては全くの他人事だというのが現状です。その壁をどのように壊すかは課題ですね。
乃田:馬場先生の気候変動の話は将来起こりうる問題についてなので、私が取り組む過去から現在に直面している問題とは、やや性質が異なるのかもしれません。現在の問題の場合、問題として認識されないのは、前もって各人に仕事が割り当てられているからなのかと思います。割り当てられた仕事をこなしている限り、困ってもいないし、今よりも良くしようとは思わない。
そこで、まずは異なる分野の御用学者同士で「それぞれの持っている問題意識を出し合ってみると意外と共通している。では一緒にやっていこう」という体制ができれば、これは社会のダウンサイジングの小規模モデルになるのではないかと思います。研究者同士での問題意識の共有に端を発し、それが社会にも広がっていくことが合意形成のヒントになる気がしました。
馬場:特に気候変動問題は、研究者側がアラートを出すパターンが多く、諸外国と比べて日本では一般市民の意識が非常に低いところがあります。したがって政治的な議題にもなりにくい。むしろ懐疑論が出てくるような状況があります。そこで、乃田先生がおっしゃったように、まずは研究者同士が膨大な縦横のつながりの中で科学のアウトプットを出しています。気候という題材で横串を通すことによって、異分野の専門家同士のコラボレーションが進んでいるというのは間違いないと思います。
一方で、行政の環境部局と他の部局の間にうまく横串を通せているかというと、形はできているけれども、中身はそうではないことがあります。行政を含めたステークホルダーの中でそうした横串が通っていない状況は、まだ課題として残っているのかなと思います。

乃田 啓吾 東京大学農学生命科学研究科 准教授
合意形成の実際
――実際の合意形成のプロセスや落とし所については、どのようにお考えでしょうか?
乃田:何ができたところを合意形成と言うか、ということですよね。難しいですよね。ある程度幅のある合意を先につくっておいて、それを現実に落としていく過程で調整していく、というのが一つやり方かなと思います。
馬場:私が思うのは、フェイクがあふれる時代だからこそ、真のファクトが何かを追求するプロセスが大事だということです。市民の6〜7割はいわゆる「サイレントマジョリティ」で、彼らは文字通りマジョリティで平時はものをいわない、その問題についてほぼ関心がないわけですが、ディープフェイクなどを使って彼らをマニピュレート(操作)しようとする人たちがいます。マニュピレートされると、市民が合理的な判断を維持できなくなってしまいます。だから、マニュピレートされないためにはどうするかというところが一番大事ですよね。
――お二人が取り組む科学的知見の可視化によって、マニュピレートされないように共有するべき基盤、つまり事実をゆがめて都合良くリードする人たちに対抗するための情報を提供するということですね。
馬場:先ほど研究者間の連携が大事だと言いましたが、一方で同じものを扱っている研究者同士でも、理学と工学では目線が違い、仮説の立て方も全く異なるわけです。研究者同士で議論するだけではなく、学際的なプロジェクトにおいて、現場で聞いてみると「ここでそういう現象があるなら、こういうことも考慮したほうがモデルとしてより良くなるのではないか」と、仮説の立て方が変わりはじめる。そうすると、仮説が皆でつくった強固(ロバスト)なものになっていく、そのようにして皆で事実を確認する。そこにはフェイクが入り込む余地がなくなっていく、ということになれば理想だと思います。
――馬場先生がプロジェクトで取り組む「自分事化」は、他人から適当に言われたことや利益などに左右されず、マニピュレーターに踊らされないための重要な要素で、ブレークスルーになるような気がします。乃田先生からご覧になっていかがですか?
乃田:「自分事化」はステークホルダーの参加を促すときに重要なキーワードという点で賛成です。その一方で、研究者の一番の強みは「他人事化・客観化」です。研究者は目の前の事象や自分に関わることでも、できるだけ客観的に捉えようとします。両方向の視点が必要なので、自分事化のプロセスの中で、他人事化・客観化が得意な研究者が果たす役割は大きいと思います。

次に目指すもの
――最後に、合意形成という困難で重要な取り組みに対して、お二人は今後何を目指していかれますか?
馬場:合意形成というのは、利害関係がある限り、常にあらゆるところで発生します。ガイドラインが1つできたからといって、それを遵守していればうまくいくわけではない。あくまでも一つの目安、あるいは参考にするということだと思います。ですから、今後もいくらでも題材は出てくるし、いくらでも焦点の当て方というのはあると思います。
この政策のための科学のプロジェクトで、「政策決定プロセスにどのようなエビデンスや合意形成が必要なのか」という課題に取り組んだ成果の蓄積は非常に重要であり、我々もその一翼を担うことができているのはとてもうれしいことです。
しかし、新たな課題に直面しつつあるとも感じています。先にも述べましたが、ファクトが揺らいでいるのが非常に不安です。ディープフェイクのように技術のほうがどんどん進展していってしまって、社会の側でそれをどうやって受け入れるのか、対応するのかというところが追いついていません。そういったところも含めた合意形成が大事かなと考えています。
乃田:私は社会のダウンサイジングが進む日本での事例の国際的な位置づけをきちんと明確にしていくのが、日本の強みにもなるのではないかと思います。日本型モデル、もしくは日本がフラッグシップとなったアジア型モデルを打ち出していけると、合意形成の個々の事例をケーススタディとしてとらえるだけではなく、学術的に意義ある知見としてアピールすることができるのではないでしょうか。
また、普段は意識しませんが、日本では社会の密度がものすごく濃いですよね。住民同士の距離が近く、利害の衝突がある、もしくは1人が複数の役割を担っているというのは欧米にはない特徴です。それをうまく世界に発信していけると、「個別の問題に対して頑張って取り組んでいます」というだけではない課題の位置付けもできるようになるのではないかと思います。
馬場:今日、2つのプロジェクトの違いと共通点が導き出されました。特に印象的だったのは、過去からの積み重ねで現在に至るという乃田先生に対して、私は将来から現在を見てバックキャスト的な思考をしているという違いです。合意形成にグラデーションがあるのだとしたら、過去からのしがらみがある現在の利益に対して合意形成をしなければならない乃田先生のプロジェクトと、皆でエビデンスを築いていきましょう、といった緩さのある私のプロジェクトの違いがよく理解できました。乃田先生のお考えはこれからもぜひ聞きたいので、また議論できたらと思います。
乃田:おそらく、今のように相対して話していると合意形成はできないですよね。少し離れたところで同じ方向を向けると議論が始まるのだなと思いました。議論の仕方のひとつとして、馬場先生が取り組んでいらっしゃるように将来から考えるというのは、ぜひ参考にさせていただきたいです。
――ありがとうございました。
(取材・文 黒河昭雄、小熊みどり、編集・森田由子)
2023年10月2日インタビュー