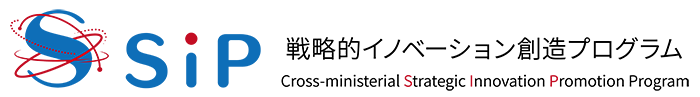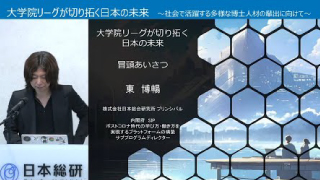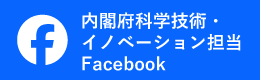研究開発成果
サブ課題Bオンラインセミナー「大学院リーグが切り拓く日本の未来
~社会で活躍する多様な博士人材の輩出に向けて~」
サブ課題B「「新たな『学び』」と働き方との接続」において、オンラインセミナー「大学院リーグが切り拓く日本の未来 ~社会で活躍する多様な博士人材の輩出に向けて~」 が2024年10月25日(金)に開催されました。本セミナーでは、我が国の大学院改革およびイノベーションを牽引する博士人材の輩出に向けた取り組みを紹介しつつ、今後の我が国の政策の方向性について議論しました。
開催概要
- 日時:2024年10月25日(金)13:00~15:00
- 開催形式:ZOOM
- 主催:株式会社日本総合研究所
- 共催:北陸先端科学技術大学院大学
- 後援:国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)
- 参加者数:オンライン100名
- 関連リンク:日本総合研究所ホームページ
当日の動画
プログラム
| 時間割 | プログラム |
|---|---|
| 13:00~13:05 | 1. 開会挨拶 サブプログラムディレクター/株式会社日本総合研究所 プリンシパル 東 博暢 氏 |
| 13:05~13:20 | 2. 「博士人材の活躍促進に向けて」 文部科学省 科学技術・学術政策局 人材政策課 人材政策推進室長 髙見 暁子 氏 |
| 13:20~13:35 | 3. 「これからの社会人博士 -大学院リーグが社会を変える」 北陸先端科学技術大学院大学 理事・副学長 永井 由佳里 氏 |
| 13:35~13:45 | 4. 「博士人材の民間キャリアパス拡充の課題と可能性」 株式会社 LabBase 代表取締役 CEO 加茂 倫明 氏 |
| 13:45~13:55 | 5. 「博士人材のアントレプレナーシップをどう育成する?」 アカデミスト株式会社 代表取締役 CEO 柴藤 亮介 氏 |
| 13:55~14:55 | 6. パネルディスカッション 「大学院の役割と社会で活躍する多様な博士人材とは」 ファシリテーター: サブプログラムディレクター/株式会社日本総合研究所 プリンシパル 東 博暢 氏 パネリスト: 文部科学省 科学技術・学術政策局 人材政策課 人材政策推進室長 髙見 暁子 氏 北陸先端科学技術大学院大学 理事・副学長 永井 由佳里 氏 株式会社 LabBase 代表取締役 CEO 加茂 倫明 氏 アカデミスト株式会社 代表取締役 CEO 柴藤 亮介 氏 |
| 14:55~15:00 | 閉会挨拶 サブプログラムディレクター/株式会社日本総合研究所 プリンシパル 東 博暢 氏 |
当日の様子
1. 東博暢サブプログラムディレクターより開会挨拶

冒頭、東サブプログラムディレクターは開会挨拶として、今回のセミナーの背景について、6月に発表された骨太方針2024iで大学院改革、博士号取得者の幅広い活躍がフィーチャーされており、地球レベルの課題をどう解決するかとい った社会システムの変革ができる人材が世界中で求められていると語りました。
また、内閣府の事業であるSIPは省庁横断で取り組むプログラムであり、第3期SIP「ポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築」のサブ課題B「新たな『学び』と働き方との接続」では、人材不足が顕在化する現代社会において産業界とアカデミアの接続に取り組んでいくと説明しました。
さらに、サブ課題Bのテーマの一つである、北陸先端科学技術大学院大学永井由佳里理事・副学長が取り組む大学院リーグをとりあげながら、総合知の活用を目指した博士人材の活躍の場や大学院改革について講演者の取組を紹介し、パネルディスカッションで議論を深めていきたいと述べました。
2. 文部科学省 科学技術・学術政策局 人材政策課 人材政策推進室長 髙見暁子 氏の講演
「博士人材の活躍促進に向けて」

髙見氏は、博士人材の活躍促進に関するR6年度の国の政策について、文部科学省が博士人材活躍プランを策定し、博士を研究者としてだけでなく多様なフィールドで活躍できる人たちと捉えて具体的な取り組みを進めていると語りました。解決すべき課題として、人口100万人あたりの博士号取得者数の国際比較では、英国、ドイツなどと比べて3倍程度の開きがあると指摘し、国民の中に博士人材をもっと輩出していくべきだと強調しました。
具体的な取組としては、一番目に社会人における博士人材の多様なキャリアパスの構築として、経済産業省と連携して進めている産業界での活躍促進、マッチング支援事業および公的機関や社会の様々な分野での活躍促進について、二番目に世界ト ップ水準の大学院教育拠点の形成等の大学院改革と学生等への支援について、そして三番目には、次世代を担う人材への動機付けについて紹介しました。これらの取組には産業界を積極的に巻き込む必要があるので、各経済団体などにも呼びかけ、連携を深めているとのことでした。この取組の拡充により、2040年における人口100万人当たりの博士号取得者数を世界でトップレベルに引き上げていくと語りました。
3. 北陸先端科学技術大学院大学 理事・副学長 永井由佳里 氏の講演
「これからの社会人博士 -大学院リーグが社会を変える」

永井氏は、大学院リーグについて、複数の大学院が連携して学生、教員がつながり、自治体や行政との関係も構築して新しい博士像を追求していこうという取り組みであると紹介し、特に社会人に学位を取ってもらいたいと述べました。社会人の学位取得者がアカデミアで修得したスキルを実社会で活かすというトランスファラブルスキルについても言及し、これは単に職業選択の幅の拡大という意味ではなく、理論と実践をつないで社会と交流し、議論、対話を深めていくためのスキルであると定義しました。そしてこのスキルの評価、検証を、大学院リーグに参加する各大学で行なっている具体例を紹介しました。
このような大学院リーグの狙いは、思考力、行動力、実践力など社会課題に真摯に立ち向かう能力を身につけていくことであり、社会で活躍する人たちが大学院に入ることで様々な能力が強化、高度化されて、また社会に戻ることで企業、社会の側も強化、高度化されるという相互の関係が期待できると述べました。さらに、どのような人材育成が必要かを含め、博士課程を取るための可処分時間について等の博士課程に関する意識調査をして大学院の課題を明確化していきたいと語りました。
4. 株式会社 LabBase 代表取締役 CEO 加茂倫明 氏の講演
「博士人材の民間キャリアパス拡充の課題と可能性」
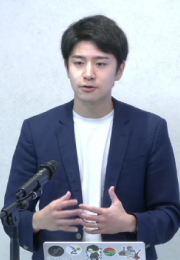
加茂氏は、まず自ら立ち上げた LabBase(ラボベース)iiについて、「研究の力を、人類の力に。」をパーパスとして掲げて、大学の研究者、企業でR&Dをする人など、研究に関わっている人々の可能性を開いていき、社会の発展に貢献していくことが理念であると語りました。特に課題視しているテーマとして、今の研究領域には研究ステークホルダー同士の様々なサイロ、壁があると指摘しました。そうした壁を打破するために、研究会のステークホルダーを可視化し、研究者、企業の出会いをジョブマ ッチングの形で提供する事業を運営していると述べました。
さらに、日本の企業が博士をあまり評価しない、あまり採用していない といった状況に鑑み、特に博士人材の民間キャリアパス拡充に力を注いで取り組んでいると語りました。まずはキャリアの可能性の認識を広げる必要もあると考えて、各大学、特にSPRINGiii対象の大学と連携しながら、その大学の博士課程生や修士生向けに、キャリアのセミナーやone on oneを通して支援していると紹介しました。ここでも、企業も巻き込んだキャリア支援や博士と企業の接点づくりが重要であり取り組む予定だと示し、産官学、手を取り合いながら博士の可能性が最大限発揮される社会を共につくっていきたいとメッセージを送りました。
5. アカデミスト株式会社 代表取締役 CEO 柴藤亮介 氏の講演
「博士人材のアントレプレナーシップをどう育成する?」
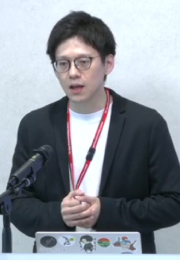
柴藤氏は、海外の大学を見て、異分野の場では専門的な話は通じなくても、研究のビジョンや解決したい社会課題の話には共感を覚えアイデアも生まれるという経験をしてきたので、研究者のビジョンを届けるような場が必要と考えた結果がアカデミストという会社であると語りました。そのために、クラウドファンディングという形でステークホルダーと一緒にアカデミアを作っていくという考え方が必要だとし、研究内容を発信すると意外な企業からの支援が集まりスタートアップを起業した例を挙げ、さらには、若手研究者向けの賞金付きのクラウドファンディング事業がTOKYO SUTEAMivのプログラムで採択されたことを紹介しました。最後に、クラウドファンデ ィングという仕組みは資金集めではあるが、本質は研究者のビジョンを可視化してよりたくさんの人たちに届け、その結果様々な連携を作るシステムであり、博士人材のアントレプレナーシップはそうした支援を通じたつながりから芽生える確率が高いと語りました。
6. パネルディスカッション
「大学院の役割と社会で活躍する多様な博士人材とは」
東サブプログラムディレクターのファシリテーションの下に、4人のパネリストが議論を行ないました。

■スタートアップで起業した当時の状況
加茂氏、柴藤氏とも起業に関する情報が無い中で、自分ならどうやるかを考えて起業に向け行動したことを明らかにしました。これを受けて永井氏は、彼らのコミュニティこそが重要で、彼らが本当の社会人だと思ったとの感想を述べました。さらに、彼らのようなコミュニティを文部科学省がどうやって底上げするかという東サブプログラムディレクターの質問に対して、髙見氏は、特に博士と企業のマッチングをしていく場合、既存の枠組みもうまく巻き込みつつ、皆さんのようなコミュニティをうまくつなげていくことはとても大事で、分野を越えたネットワーク作りを行っていきたいと語りました。
柴藤氏、加茂氏は、時の流れの中での出会いが大きく、大学院でのつながりやクラウドファンディングによる若手時代のつながりが、社会でまた新たなつながりに発展するところが面白いと語りました。
■博士とは何か?
加茂氏は、実際、企業の人事部の博士採用は形式的であり、どうしても博士が必要な状況にはなっていないと述べました。これを踏まえ髙見氏は、日本経済団体連合会 が R6 年度 2 月に行った調査によると標準的な企業の報酬体系は学部卒、修士、博士は同じであり、年数が異なるだけという採用の実態について説明しました。加茂氏は、この状況は企業側だけに課題があるのではなく、解決のためには大学側、学生自身にも博士を採用したいと思ってもらえる姿勢が必要と述べました。
永井氏は、アカデミアとしての差別のない世界に触れることができるのは大学院であり、その経験が社会にトランスファできていないために報酬体系に反映されていないと語り、社会人博士を多く生み出すことでアカデミアと社会の両方に活かされると付け加えました。
柴藤氏は、企業で働く社会人が自分の専門分野を体系的に整理して博士号を取るためにクラウドフ ァンディングを利用するケースが増えていると紹介し、過去に出会った人とあらためてつながっていく可能性があるというのは、大学院リーグに通じるものがあると述べました。これに対して永井氏は、クラウドファンディングは多数の人から支援され認められる場合に学位認定と近似しているところがあり、これを検証する立場は必要だが自然発生的に研究に人が集まる形になるだろうと応え、クラウドファンディングの可能性に共感を示しました。
■グローバル化について
柴藤氏は、クラウドファンディングのサポーター募集は海外に対しても行なっており、その逆方向もあると語りました。加茂氏は留学生の日本での活躍、グローバルなマネジメントができる人材のニーズについて紹介しました。このようなグローバル化の流れにいる子ども、学生をどう支援するかという東サブプログラムディレクターの質問に対して、髙見氏は、産業界とアカデミアの行き来をしやすくすること、更には国内外の企業、アカデミアにおける国際頭脳循環も進めたいと語りました。永井氏は自身の経験から、海外経験を積むための支援の必要性を説きました。
■時間の捻出について
東サブプログラムディレクターから、リカレント、リスキリングを行なうためや学位を取るための時間の捻出をどうすればよいかという問題提起がありました。これに対して、永井氏は作業の効率化を図った上で時間配分を工夫することが決め手だと語りました。髙見氏は、生活費を得る不安が払拭された前提で、博士課程学生のキャリアパスをどう作るか情報発信することを通して支援したいと述べました。これには東サブプログラムディレクターがアウトリーチの重要性を付け加えました。加茂氏は、分野をまたいだノンラベルな場に行くには時間の余裕がないとできないので、時間の問題はとても重要だと述べました。さらに東サブプログラムディレクターは、マネジメント側の工夫で研究者の付加価値時間を高めることが必要と述べ、髙見氏はマネジメント人材の重要性を説きました。
■最後に
髙見氏は企業との連携で博士の活躍フィールドを広げていきたいとし、永井氏は大学院リーグの成長を誓い、加茂氏は産官学のコラボレーションによって学生が面白いと思うチャレンジができる場を作りたいと述べ、柴藤氏はさらにコミュニティ化を進めいろいろな人を巻き込んでやりたいと語りました。
7. 閉会挨拶
東サブプログラムディレクターが、研究者に選択肢を増やし、経済的にも安心してチャレンジできる環境を作るための議論を引き続き行いたいと語りました。そして次は産業側を呼んで思いを聞きたいとの希望を述べて締めくくりました。
- 骨太方針 2024:経済財政運営と改革の基本方針 2024
- LabBase: https://labbase.co.jp/about/
- SPRING:次世代研究者挑戦的研究プログラム
- TOKYO SUTEAM:https://tokyosuteam.metro.tokyo.lg.jp/