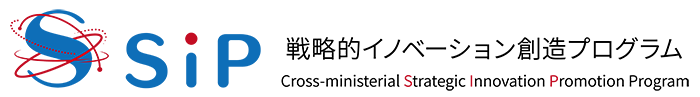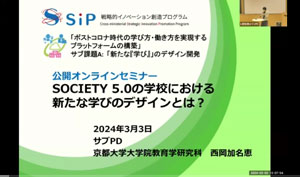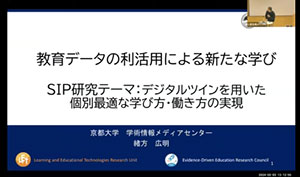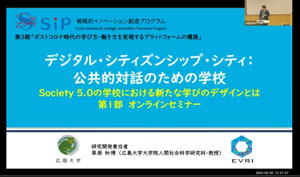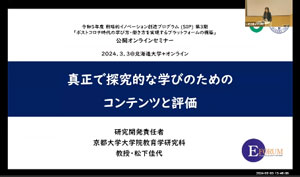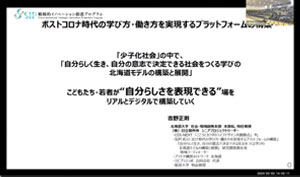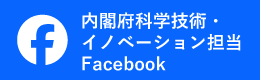研究開発成果
【2024.3.3】サブ課題Aに参画するメンバーが合同でオンラインセミナー「SOCIETY5.0の学校における、新たな学びのデザインとは?」を開催しました。
2024年3月3日(日)、サブ課題A「「新たな『学び』」のデザイン開発」に参画するメンバー合同によるオンラインセミナーが開催されました。本セミナーでは、「Society5.0において、⼀⼈ひとりが多様な幸せ(well-being)を実現できるようにするために、今後の⽇本においては、どのような「学び⽅」が求められているか」をテーマに、サブ課題Aに参画するメンバーが、現在、取り組んでいる研究開発の内容を紹介しました。
開催概要
- 日時:2024年3月3日(日)13:00~14:20(Zoomによるオンライン配信)
- 主催:SIP「ポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築」
サブ課題A「新たな『学び』」のデザイン開発 - 共催:SIP「ポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築」
サブ課題D「新たな『学び』」×働き方×バーチャル空間の有効性確認
(ショーケースの提示) - 後援:国立研究開発法人 科学技術振興機構
チラシはこちら
当日の動画
プログラム
| 時間割 | プログラム |
|---|---|
| 13:00~13:15 | オープニング ■開会挨拶 西村 訓弘(プログラムディレクター/三重大学大学院地域イノベーション学研究科 教授・特命副学長) ■サブ課題Aのご紹介 西岡 加名恵(サブプログラムディレクター(サブ課題A)/京都大学大学院 教育学研究科 教授) |
| 13:15~14:15 | 講演 ■教育データの活用による新たな学び 緒方 広明 (京都大学学術情報メディアセンター 教授)チーム ■デジタル・シティズンシップ・シティ:公共的対話のための学校 草原 和博 (広島大学人間社会科学研究科(教) 教授)チーム ■真正で探究的な学びのためのコンテンツと評価 松下 佳代 (京都大学大学院教育学研究科 教授)チーム ■次世代に向けた創造性の学びあい 吉野 正則 (北海道大学産学・地域協働推進機構 特任教授)チーム |
| 14:15~14:20 | クロージング |
当日の様子
-
西村訓弘プログラムディレクターは開会挨拶として、ポスコロSIPが目指す社会像について、人口減少によってこれまでの社会の仕組みが成り立たなくなるため、新しい社会をつくりあげていく必要があること、その上で、新しい社会を実現するには人が大事であり、特に子どもたちが自分の人生を自分で設計し、社会での役割を意識し、個性を持って生きることが求められること、それに向けてサブ課題Aで「新たな『学び』」による教育を進めることが重要であると述べました。

-
続いて、サブ課題A担当の西岡加名恵サブプログラムディレクターは、サブ課題A「新たな『学び』」のデザイン開発の全体像について、小学校から社会人まで幅広い年齢層を視野に入れ、且つ、教科学習、総合的な学習、デジタルスキル、アートの側面など多様な探究力・主体性・創造性・協働性を高める教育コンテンツの開発や、そのベースとなるコンテンツ・プラットフォームの構築、学習データの取得・連結・活用に取り組んでいることを紹介しました。それを受けて、サブ課題Aに参画する研究開発責任者が研究開発内容を発表しました。

-
緒方広明・京都大学教授は、教育データの活用による新たな学びの実現に向けて、SIPでは、開発したLEAFシステムを使って、学習の多面的な評価を行い、その結果を基に個別最適な学習環境を構築することや、学習ログを用いてデジタルツインを構築し、教室や学校を超えた学びの場をつくると説明しました。

-
草原和博・広島大学教授は、これまでの教室内に閉ざされた学びを外に解き放ち、他の学校・地域とつながり、多様な市民の参画を得ながらデジタル・シティズンシップ・シティを形成していく公教育構想を説明するとともに、東広島市で実施してきた広域交流型オンライン学習の取組と,これらを全国展開するために必要な社会基盤やAI学習支援システムの開発について説明しました。

-
松下佳代・京都大学教授は、フィジカル空間とサイバー空間を往還しながら、well-beingを追求していける社会を実現するためには、学校において「真正で探究的な学び」を保障することが重要であると語り、そのための取組として、パフォーマンス課題を含む教育コンテンツ、学びのストーリーを紡ぐデジタル・ポートフォリオ評価システム、探究指導力育成研修の開発について紹介しました。

-
吉野正則・北海道大学特任教授は、自分らしく生き、自分の意志で決定できる社会をつくる学びの北海道モデルの構築を目指して、世代を超えた学びの場を、をリアルとデジタルで構築する3rd Placeの取組や、サブ課題A~Dの検証・社会実装をつないでいくための連携体制について説明しました。

-
最後に、クロージングとして、当日参加していたサブ課題B担当の東博暢サブプログラムディレクターと、サブ課題C担当の大山潤爾サブプログラムディレクターが、サブ課題Aの研究開発の重要性や、サブ課題B・Cとの関係性等について延べ、西岡加名恵サブプログラムディレクターは、「新たな『学び』」の実現に向けて連携を図りながら、研究開発を進めていくとしてセミナーを締めくくりました。