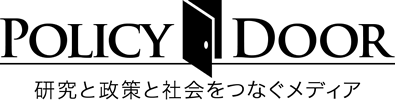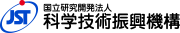続いて、「エビデンスに基づく意思決定がどこまでできて、どこまでできなかったのか」をテーマにパネルディスカッションが行われた。
行政学と公共政策を専門とする森田朗氏※1がモデレーターを務め、パネリストには仲田氏に加え、科学技術社会論が専門で科学的助言に詳しい横山広美氏※2、医療経済学と国際経済学を専門とする伊藤由希子氏※3、疫学・公衆衛生が専門の山縣然太朗氏※4の4名が登壇した。
※1一般社団法人 次世代基盤政策研究所(NFI)代表理事/東京大学 名誉教授、RISTEX前センター長、科学技術イノベーション政策のための科学 研究開発プログラム前総括
※2東京大学 国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)副機構長
※3津田塾大学 総合政策学部 教授
※4RISTEX科学技術イノベーション政策のための科学 研究開発プログラム総括 /山梨大学大学院 総合研究部医学領域社会医学講座 教授
限られた情報と時間での政策決定
パネルでは、まず山縣氏が
「直接的に感染症で亡くなるだけでなく、ステイホームによる高齢者のフレイルや、自殺者数の増加のような対策の副作用や間接的な影響は後からわかるもので、その時点での分析は難しい。これから起こるであろうリスクに対して、今どのように政策を決定していくのか」と仲田氏に問いかけた。

山縣 然太朗 RISTEX科学技術イノベーション政策のための科学 研究開発プログラム総括/山梨大学大学院 総合研究部医学領域社会医学講座 教授
仲田氏は、影響は1〜2年後に見えてくるため、意思決定時には分析しようがない面があると指摘しつつ、
「しかし、そういった分析不可能を考慮することが”非科学的”とは言えない。我々ができるのは、次のパンデミックに向けて、今回の事例から学べることを整理することだ。
また、こういった不確実性があるときに、効果の程度はわからないが最悪の事態を考えて強く行動政策を打つという予防原則は、不確実性に対するアプローチの一つだと思う。ただし、様々なアウトカムがあり、行動制限政策を強く打つことが中・長期的に社会経済に大きな影響を及ぼすかもしれないとき、予防原則を当てはめると全く別の最適解となる。そこがまさに価値観の話になる。これは、どんなにデータがあっても、科学的な知見が積み上げられても解決する問題ではない。そういった価値観に関する話が冷静にできるようになるとよい」と答えた。

仲田 泰祐 東京大学大学院 経済学研究科 准教授
それを受けて、横山氏は科学的助言のあり方として、学会等で意見を一つにまとめ上げる「ワン・ボイス」ではなく、さまざまな研究者集団により発せられる「グループ・ボイス」を提案する。
「専門家が価値判断にどの程度踏み込んでいいのか、あるいはいけないのか。この議論は古くからあり、簡単に白黒はっきりできる問題ではない。我々専門家は、ここまでは言うべきであろうというラインを常に見定めておき、価値判断自体は政治家が行う、という自制が必要。そのときに、1人あるいは少人数で動いていると、政治家ではなくその(一部の)研究者集団の価値観ばかりが前に出てしまうということが懸念される。
タイムリミットについては、状況が動いていて、今分かっていることが全てではない中では、状況が変わることを前提に国民への発表を組んでいくのが良いと思う。例えば宇宙科学の分野では、過去のロケット打ち上げ失敗時などの経験を踏まえて、『現在、状況を確認中です。何時間後に記者会見をします』というような形で、経過報告も含めて情報を随時発信している。そうしたスタイルがこの分野でも必要になる」と述べた。

横山 広美 東京大学 国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)副機構長
有事における生命に関するデータの価値
続いて「人権の問題をどう考えるか。感染症対策は、行動制限や情報開示など、私権をある程度侵害せざるを得ない状況がある。それが公衆衛生の感染諸対策の基本で致し方ないと考えられているが、問題はどの時点で制限を解除するかだ」と山縣氏が問題提起した。
これに対して、データに基づいてバランスを考えていくべきだという議論が展開された。
医療データの提供を受け分析を進める立場であり、実際にその課題に直面する伊藤氏が
「医療データは個人情報の塊であり、患者の人権を守るために、平時は時間をかけて医療機関の同意を得てようやくデータを利用できる。しかし、災害やパンデミックなどの有時には、絶対に同意がないと駄目だという原則を思い切って解除してほしい。有事には個人の情報を集めなければ、きめ細やかな対応はできない。原則を守ることによって失うものの方が大きく、『情報は守れたが、その人は亡くなった』という事態になってしまう。感染症法の改正で、医療機関・市町村・都道府県の間での感染者の情報共有は、同意があれば必要に応じてできるようになったが、データについて人間が作る障壁は取り払う必要がある」と答えた。

伊藤 由希子 津田塾大学 総合政策学部 教授
日本では数理モデル分析を有事の政策決定に用いること自体が初めての試みだったといえる。そのため、優先順位やバランスを考えることがうまくできなかったところがある。仲田氏は金融政策の観点を交えつつ、
「金融政策では常にアウトカム間にトレードオフがあり、バランスを考えるので、結論は白か黒かではなく灰色となる。かつ、バランスを考えての意思決定には人の価値観が関わる。今回の新型コロナ危機では、日本に限らず、研究者による客観的な分析の発信だけでなく、主観的な価値観に基づいた発信も多かった」と述べた。
人々を怖がらせるのか、安心させるのか
山縣氏は続いて、
「2022年の夏には、新型コロナの65歳未満の致死率はインフルエンザと同程度かそれ以下で、65歳以上が高いという状況だった。欧米は既にその時期に政策を変えていたが、日本では2023年5月まで2類相当を維持した。それは政策方針というより、国民が怖がっていて、あまり早く5類相当にしてほしくないと思っていたのではないか。それが価値観の問題なのか、科学リテラシーの問題なのか、この点は政策決定の際の重要な課題だ」と指摘した。
これについて、仲田氏は市民のリスク認識に対する情報介入実験を行なった結果をもとに、
「国民が新型コロナをどれくらい怖がるか、政府や専門家はある程度影響を与えることができる。国民が怖がっていたと言うこともできるが、政府や専門家が国民を怖がらせていたという側面もあるかもしれない」と述べた。
横山氏は東日本大震災との違いに触れることで、あらためてコロナ禍が市民に与えたインパクトについても指摘した。
「震災時は、専門家は国民に安心を促していたが、今回は反対で国民に危機感を持たせた。ひとつの要因としては、震災時は主に東北地域が非常に大変だったが、新型コロナは亡くなった方とその家族が全国にいるという違いがある。死亡者の数を考えがちだが、亡くなった方を取り囲む家族が一体何人いたのかということに思いを寄せる必要がある。緊急事態宣言など、全国民を巻き込んだインパクトの強さというのが、震災の原子力の話とは全く異なる」と述べた。
議論が尽くされた納得感、失敗も認める
続いて、モデレーターの森田氏が「初期には新型コロナがどのような病気かわからず、政府や専門家は国民の不安を煽ったが、徐々に状況が分かってくるにしたがって政策を変えていけたのではなかったか。方針転換を国民にどのように伝えて、理解してもらうのか」と議論を投げかけた。

森田 朗 一般社団法人 次世代基盤政策研究所(NFI)代表理事/東京大学 名誉教授、RISTEX前センター長、科学技術イノベーション政策のための科学 研究開発プログラム前総括
仲田氏は
「金融政策でも、常に全会一致で政策が決まるわけではなく、反対意見が出る場合も多い。しかし最終的に重要なのは、きちんと議論が尽くされて納得感があることだ。納得感を生み出すためにFRBの研究員は様々な分析をしているが、そこからパンデミック政策は学べるところは多いと考えている。金融政策では長年の経験があるが、金融危機など今後どうなるのか、どうすべきか全く分からない事態もあり、そういった局面ではパンデミック政策と同じ難しさがある」と述べた。
伊藤氏は、英国議会が作成した報告書を例に、政府や自治体による総括のあり方についての問題提起を行った。英国議会の報告書では『成果と失敗の両方から学び、そして今後の感染症に向けて最善を尽くせるようにするためにこのレポートがある』とされている。例えば、新型コロナ最初期の英国の方針(英国は接触回避ではなく集団免疫獲得を目指し、ロックダウンが遅れた)には大きな間違いがあったが、ワクチンの開発成功という大きな成果もあったと報告されている。
「このように成功と失敗の両方を正直に書き、特に失敗から学ぶというのがとても大事だ。一方、東京都の報告書には、例えば病床の確保について『感染状況に応じて先手先手で病床を確保し、着実に対応した』と書かれている(全体として見ると確保できたと言えるが、個々の事例を見ると、搬送先が見つからず自宅で亡くなった方もいたことには触れていない)。日本ではどうしても失敗を認めにくく、行政文書に失敗は書きづらいため、執筆担当者は苦渋の決断でこう書いたのだろう。しかし、このように書いてしまったがゆえに、この報告書を読みたいという気持ちをそがれる人たちがいる。
いろいろな意見を受容するためには『これは成功した。これは失敗した』と両方書かないと、その政策を支持したい人も、批判したい人も読んでくれないのではないか。失敗したことを否定しない、前例の失敗こそが学びなのだという考え方を、ぜひ次の感染症に生かしてほしい」と述べた。
専門家の信頼
横山氏は、陰謀論も含めて、ポピュリズムとの闘いをどう乗り越えていくのかが世界的に深刻な問題になっていることに触れた。
「日本の分断はアメリカと比べて緩やかかもしれないが、科学を信じる人とそうでない人が分かれる。国民は一様ではなく、スペクトラム(考え方の幅、広がり)がある。世界的に見て、年齢の高い人や女性が科学を信じて行動する傾向にある。彼ら/彼女らは社会的に弱い立場に置かれている人たちともいえる。科学を伝える際には、ターゲットを分けて、一番伝えやすい彼ら/彼女らから伝え、広めていくと言う方法もある」
横山氏は続いて、
「私はこのように考え行動している、と専門家は発信すべきではないか。震災当時、私が勤める東大柏キャンパスのある千葉県柏市は、局地的に空間放射線量の高いホットスポットになったが、『東大の先生たちがまだ柏に住んでいるのだから、大丈夫に違いない』と多くの人が思ったという話を聞いている。私たち専門家自身が、どのように生活して、どのように考えているかを言い続けることで、浸透しやすい人たちから広まっていく。スペクトラムのある国民の中の、どの層に何を言っていくのか、どうやって信頼を高めていくのかというのは、継続して大事である」と述べた。
メディアとの関係については、ワクチンの副反応検討部会の委員を務める山縣氏が「ワクチン接種後の死亡1例目をどのように報道したらよいか」とメディアから相談があった事例を紹介し、
「2021年4月の高齢者のワクチン接種開始にあたり、副反応ではない有害事象の報告も出てくることは想定していた。わが国では、毎日3000人近くの高齢者が亡くなるので、ワクチンを打った人が副反応とは無関係に亡くなることは当然起こる。『そうした現実をよく理解することと、それがどのような状態で起きたのかという情報を隠さずに公開するのがいいのではないか』と答えた。
その結果、メディアは『情報がきちんと出てきたので、我々が追加で情報を収集する必要がなく、各社が正確な情報を発信することができました』と言っていた。きちんと全部の情報を出すことによって、間違った情報をメディアが流すことがなくなる。
どうしても亡くなってしまう人がいるので、ワクチン政策は機微を伴うが、科学的助言のあり方や専門家への信頼を踏まえ、科学コミュニケーション・政策コミュニケーションをしっかりとっていくことが重要だ」と述べた。
モデレーターの森田氏が
「専門家は『ここは自分の責任で言うけれど、ここは政治家に任せる』という自覚をもつことが必要だ。裏返して言えば、政治家がなぜそのように決定したかという説明責任を問うていくことになる。『専門家の様々な見解がある中で、私はこのように納得してこれを選んだ』と、結果についてはやはり政治家が責任を負わなければならない。
また、後から分かった事実に基づいて、あれは間違っていたと批判するのはフェアではなく、それに騙されないようにするのは非常に重要だ。これこそ専門家としての倫理の基本である」とパネルディスカッションを締め括った。
最後に、小林傳司氏(JST社会技術研究開発センターRISTEXセンター長)が
「実際の科学は常に知見が更新され続ける。分からないから研究しているので、科学に不確実性があるのは当たり前なのだが、政策決定への繋ぎ方が難しい。仲田氏の研究紹介にあったように、日本では数理モデルが過大に評価され過ぎた。アメリカの金融政策の場合のように、数理モデルをコミュニケーションツールとする使い方ができるようになるとよい。
日本全体にとっても、東日本大震災や今回のパンデミックから何を学ぶか、日本の制度の中で科学的助言の仕組みをどのように設計するかをもっと考える必要がある。今日のような議論を、もう少し時間をかけて、様々な人と行っていくような場を考えなければならない」とセミナー全体を講評し、閉会となった。

小林 傳司 JST社会技術研究開発センターRISTEXセンター長
(取材・文 黒河昭雄、小熊みどり、編集・森田由子)
「科学技術イノベーション政策のための科学 研究開発プログラム」オープンセミナー
~感染症対策と経済活動に関する統合的分析~
プログラムとアーカイブ動画