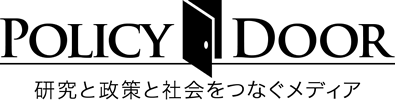森田:新型コロナウイルス感染症のパンデミックが始まってから3年になります。この間、西浦先生が実際に政策決定に関わられる局面がたくさんあったと思いますが、そこから見えてきた景色について、三つのポイントに絞ってお話を伺いたい。
まず一つ目は、科学技術でどこまでわかるのか、わかっているのか。二つ目は、科学者の見解が政策に反映されるためには政治的なリーダーがきちんと決める必要がありますが、当初かなり問題がありました。ここから、科学者による科学技術的な助言と政治的リーダーの関係はどうかということ。三つ目は、科学的な見解を伝えるサイエンスコミュニケーションはどのように行われていたかです。この回は最初の二つについてお話を伺います。
ぎりぎり間に合った
西浦:今までの過去のデータしかない状態では、未来のリスクアセスメントはなかなかできなかったのですが、数理モデルを用いることで、科学的に一定の認められた手法で未来を理解できるようになりました。ですから、今回のコロナ危機に日本でもぎりぎり間に合ったというのがおそらく表現として一番適切だと思います。
流行が起こり始めた頃からシナリオとしてシミュレーションのインプットを定期的に続けてきました。一般に知られているのは自分たちがやってきたほんの一部ですが、目の前に迫っているリスクがどれくらいのものか、ある程度、定量的に知ることができるようになったのは大きな変化だと思います。
一方で、それがどのように政策決定のプロセスに取り込まれるかというのは、走りながら進化しているのが実情なのではないかと思います。第1波が終わったあと、私はすごく批判されました。計算したような未来が必ずしも起こらなかったではないか、計算した死亡リスクは過大だったのではないか、やり過ぎたのではないか、そういう意見が多かったです。
森田:それでも、3年間の経験を積んで、未来のことについてどう対応したらいいか、だんだんわかってきたのだと思います。社会科学の意思決定の考え方では、まず最悪の場合を想定して備えていきます。そして、ここまでは大丈夫だとわかると、徐々に緩和していくのが賢明だろうと言われています。最初が厳し過ぎると、先生のケースもそうかもしれませんが、あれは何だったんだ、ちゃんと予測できていなかったのではないかという批判を浴びることになる。ただ、多くの場合、そうした批判は「後出しじゃんけん」みたいな話ですね。そういう意味で、この3年間で少しずつリスクというものがどうなるかがわかってきたと理解してよろしいですね。
西浦:はい。いい意味でも悪い意味でも、皆さんが肌感覚でリスクを理解してきたと思います。たとえば流行の最初の頃に僕が死亡の被害想定を研究者の立場で仕方なく説明したことがあったんですけども、今、その想定がだいたい現実に即しているのを皆さんが肌で感じられるように変わってきました。流行曲線でも第1波のときと比べて第2波のほうが大きくて、第2波より第3波が大きくて、これまで何度もそうやってホップステップジャンプを繰り返してきた。それは、どこまでならやってもいいんだろうかということを、科学的な面でも政策的な面でも皆が肌で感じながら受容してきた経緯があるからそうなっているのだと思います。幸運だったのは、リスクの判断を大きく誤って大量の死亡者を出すことにはならなかったことです。その点、日本はとても運がよかったなと思っています。

西浦 博 京都大学 大学院医学研究科 教授
「マスク着用の選択権」
森田:第1波を経験して、何をすればどうなるか、ある程度皆さんが予測できるようなったのはかなり違いますね。たとえばいま問題になっていますけれど、マスク着用は最初は絶対的な話で、国が配るということまでやりました。それが、ある条件ではそれほど無理してマスクしなくてもいいよと変わってきています。細かいマスクの必要条件やリスクはだんだんわかってきたと理解してよいのでしょうか。
西浦:はい。マスクの着用について選択権があるというのがこの社会が様変わりしたことの一つの表れだと思います。いま日本の着用率は85%ぐらいで、先進国の中でもマスクを義務化している状態に相当するぐらいたくさんの方が着用されています。科学的には、人口全体の実効再生産数はマスク着用で2割程度減っていて、屋外に関してはもうすでに国内外を問わず不要です。じゃあ、屋内ではどうかというと、本音を言うとまだかなりの場所で着用しないとなりません。ですが今は、科学的判断と皆さんの願望との間で価値判断しながら平衡点を探っていくという難しい過程にあります。コミュニケーションの上で、マスクの着用に関する集団行動動態が知られているのですけど、科学に基づかずに「要らない」と言ってしまうと、皆がいっせいにマスクを外してしまう帰結に至ることがわかっているので、本当は時間をかけながら丁寧に丁寧にやらないといけない。それがマスク着用に係る心理学的課題です。専門家としてこの件に関わる上で、焦らずに基本的なことをまずはしっかりと科学的に整理をしたいと強く思います。それが今の状況です。
森田:2022年の夏ぐらいから、感染者がこれまでになく増えても、飲食店の休業などの対策はほとんど出なかったですよね。第7波でものすごい山が来てもまだそのままだったのは、やはりそれで大丈夫だという判断が出たということなのでしょうか。
西浦:いいえ。第7波以降は、科学的予測というよりは一種の価値判断が行われて行動制限をしなかったというのが実態です。そうしたことを国民の皆さんが知らないという点に私は問題意識を持っています。第6波のころ、オミクロン株の流行が起こってから制御がなかなか難しくなりました。予防接種後で軽症の人も多くて、社会の流行対策が保健所でやっているような古典的なものでは追いつかなくなった。ただ、一定の度合いで制御は必要であろうという専門家の見解自体はずっと議論されています。一方で、制御した場合の社会活動への影響や、制御しなかった場合の想定被害規模などを両睨みにして価値判断が行われているのですが、その過程や詳細は明示的に皆さんに伝わっていない。今の国の政策でここが一定の度合いで見直すべきところなんだろうと思います。

森田 朗 一般社団法人 次世代基盤政策研究所 代表理事/東京大学 名誉教授
意思決定のプロセスが泥縄
森田:私の専門は政治学ですが、日本の制度上、政策については最終的に政治家自身が責任を負わなければなりません。他の国では科学技術顧問を置いて、科学的見解は見解として示し、政治家はその見解をどう考慮してどう決断したかをはっきり国民に示しなさいという風潮にあります。政治家は感染症の専門家ではない、しかし、リスクが高いことはわかっているときに、研究者からの助言を政治家はどう取り込んで自分の責任において決定すべきなのか。政治家の場合は、非常に単純に言うと支持率はどうなるかとか次の選挙に関心がある。いろいろ経験がおありだと思いますが、その辺についてどうでしょうか。
西浦:経験上で大変だなと思ったのは、最終的な意思決定プロセスが今の日本は率直に言うと泥縄だと思います。専門家が担当大臣や厚労大臣を通じていろいろ対策を頼むわけですが、その後の意思決定は官邸の中でブラックボックスの状態にあります。もちろんリーダーの周りを取り巻く人たちが必死に考えて決めているのですが、その時の最も重要な目的関数は、森田先生がおっしゃるように選挙のことだったり、あるいは「下手を打ちたくない」というのが率直なところでしょうか。
失敗をしたくないけれど、じゃあどうすればいいか、流行の制御の成功以外に経済活動を横睨みで見ていろんな意見を集約して決める。そういう泥縄的システムの中でやる政権担当者は気の毒とさえ思いました。それを改善するには危機管理庁をつくるとか、科学顧問を置くとかいうことがあります。
危機管理では前例がない考え方をしないといけません。これまでこんなことはなかったという判断も必要になる、リスクの迅速評価が求められるので、やっぱり一定のトレーニングを受けた専門家がそこに介在する必要があります。また、政治家と専門家の間にはそういう危機管理のときのアドバイスをする仲介役が必ず必要です。さらに「科学的な見解ではこういうことなんです」ということを毅然と言える立場が保障されている科学顧問を置く。この3点がしっかりと改善されると、パンデミックのような危機時の意思決定はもう少しよくなるのかなと率直に感じました。
森田:北欧やバルト三国などではそういう危機を考えています。これらの国では、実際に危機が起こった場合、何を捨てるかということが議論されて、国民の間にある程度共有されている。これはとても大切だと思うんですね。日本は何が起こっても全員助けるという前提で動くものですから、ロジカルに辻褄が合うような策が出なくなってくる。そうすると口先だけで議論することになり、それが政治家の決断をある意味で曖昧なものに歪めてしまうのだと思います。だから、こういうやり方をしたときにはこれだけの犠牲が出ますというような話を許容する決断ができない。もしうまくいかなかったときにはすぐに誰のせいだという話になる。
西浦:そうですね。
森田:専門家の意見にしても、地震の専門家、軍事の専門家、感染症の専門家とそれぞれの知見はよくても、同時に二つ以上のことが起こると今と同じように選べない状況が起こるのではないでしょうか。
西浦:実はそういう価値判断も科学的にやれると思います。優先順位付けとか、被害想定に応じた国のプライオリティとか、本当はモデル化できる話です。私自身は、このRISTEXでそういう機会に出会えたことは幸せでしたが、政策の科学として社会に実装されるにはまだまだ時間がかかりそうだなと思っています。
森田:たとえば今回のコロナよりももっと感染力が強くて致死率が高い場合、しかもワクチンが限られているときにどの順番でワクチンを接種していくのかという問題は、ある意味で意思決定のシミュレーションみたいな議論になるのです。日本の場合は、国民に対してとにかくワクチンをたくさん輸入しますというような話をするわけですけれども、それができないときの想定をどう考えていくのか。今回のパンデミックで、そういうことを本当にきちんとやってこれたのかどうか。
西浦:今回の流行でも公になっていない部分でのコンサルテーションはたくさんやりました。実は変異株で伝播性が上がった2021年のオリンピックのときは、本当に危ないと思っていました。あのとき、予防接種による間接効果などが追いついていなかったら、日本では見ないような流行規模になっていたところでした。本当に背筋を冷やしながらやっていたのです。専門家なら絶対にしなければならない想定を役所なり政治家に届けていくというプロセスを早く作らなければいけない。それが日本に今課せられている課題ではないかなと思いますね。

科学者として独立した見解
森田:そこのところはすごく私も重要だと思っています。科学技術者の専門的な発言としてアメリカの科学技術顧問のファウチ博士が説明したあと、トランプ前大統領が「大丈夫だ」って発言しました。そうしたら、横からファウチ博士が「私はそうは思わない」っておっしゃってましたね。あれを見た国民は、どちらの意見を信じるかどうかは別にして、少なくとも科学者の考えは理解できたかなと思いました。
日本の場合は意見をすり合わせて出すみたいなところがあって、尾身先生は必ず首相の脇で一緒に記者会見されましたけれども、そこで「私は総理の考えとは違う」とはまず言いません。本当は科学者が科学的な観点から出た結論ではないことを言わされて、信用を失うようなことになりかねないのではないかと私は心配していましたけど。
西浦:私が今回の流行で次の世代に引きずってしまったなと一番辛く感じているのがその点です。
英国では2020年4月のロックダウンが終わったときに、私のインペリアルカレッジのときの先輩が、ネイチャー誌に「首相があと1週間早くロックダウンをすれば2万人助かっている。首相の決断は遅かったのではないか」という論文を掲載しました。そして大衆紙のインタビューにも応じて、科学的な見解から言うと早ければ早いほどよかったのになぜあんなに遅かったのかと毅然と述べられていました。日本ではこういったことをサイエンスとしてオープンにできていないという負の遺産を、この流行を通じて次世代に残してしまっていると辛く感じているところです。この体制でよかったのかどうかはこれから相当厳しく見直す必要のあるところだと思います。
森田:そうですね。本来ならばそういうときに科学者としてのきちんとした組織がもうちょっと権威を持って活かせるといいのですが。そうでないと、科学者の「有志」になってしまいます。そこをもう少ししっかりと考えていかないと、せっかくの科学的な知見を反映していい政策を作っていくのは難しい。とくに、国の安全保障上の危機が起こったときにどう対応するかは本当に真面目に考えなければなりません。
(第2部に続く)
(取材・構成 黒河昭雄、前濱暁子、編集・藤田正美)
2023年2月6日インタビュー