- JST トップ
- /
- 戦略的創造研究推進事業
- /
 さきがけ
さきがけ- /
- 研究領域の紹介/
- 細胞の動的高次構造体/
- [高次構造体] 2022年度採択課題
[高次構造体] 2022年度採択課題
猪股 直生
細胞内熱ダイナミクスの解明
グラント番号:JPMJPR22E1
研究者
猪股 直生

東北大学
大学院工学研究科
准教授
研究概要
高感度微小温度センサアレイから得る細胞内の動的な温度・時間情報を基に,高次構造体の熱特性,細胞内熱プロセスへの寄与・役割および相互作用を解明します.高い温度・時間分解能,そしてマクロかつミクロの計測範囲を達成する新しい細胞内分析技術を確立します.本研究を通して,生命科学における新しい熱プロセスおよび熱制御概念を活かした,現在の技術を凌駕する熱工学における新技術の創出に寄与します.
大出 真央
実験と計算の協奏による生体分子動態解析法の開発
グラント番号:JPMJPR22E2
研究者
大出 真央

大阪大学
蛋白質研究所
助教
研究概要
生命現象の素過程は、細胞内生体分子や複合体の複雑かつ動的な相互作用によって営まれますが、それらの解析は容易ではありません。本研究提案ではクライオ電子顕微鏡での構造解析に計算科学アプローチを組み合わせることで構造分類・動態解析の新たな手法を開発します。さらに、開発手法を実際の蛋白質クライオ電子顕微鏡観察像へと適用し、ターゲット蛋白質の機能発現に伴う生体内でのマルチスケールな動態の解明を目指します。
加藤 一希
CRISPR-Cas酵素 Cas7-11を用いた細胞操作技術の開発
グラント番号:JPMJPR22E3
研究者
加藤 一希
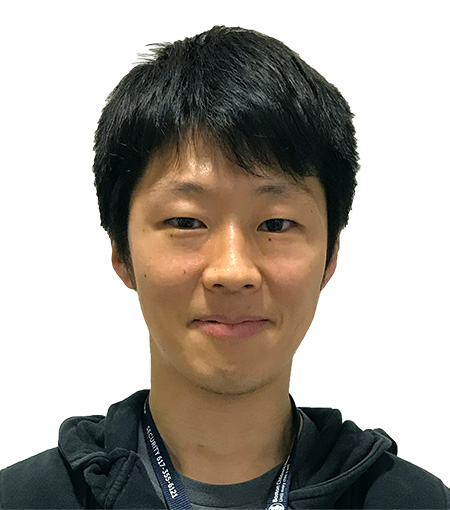
東京科学大学
総合研究院
テニュアトラック准教授
研究概要
新規CRISPR-Cas酵素、Cas7-11はRNA依存性のRNA分解酵素であり、タンパク質分解酵素です。本研究提案では、Cas7-11を用いて動植物細胞の操作技術の開発を目指します。
草木迫 司
汎用性の高いクライオCLEM戦略の確立と有毛細胞の高次構造体の解明
グラント番号:JPMJPR22E4
研究者
草木迫 司

東京大学
大学院理学系研究科
助教
研究概要
内耳の有毛細胞は音によって引き起こされる機械刺激を電気信号へと変換します。本研究では,効率的な細胞観察を行うために,蛍光観察と電子顕微鏡観察における画像を相関させるクライオCLEMを取り入れた汎用性の高い観察ストラテジーを確立します。この戦略を用いて,有毛細胞の動的なシグナル変換機能を担う高次構造体をクライオ電子線トモグラフィーにより可視化し,機能発現メカニズムの解明を目指します。
菅井 祥加
タンパク質の集合・離散を制御するペプチドタグの開発
グラント番号:JPMJPR22E5
研究者
菅井 祥加
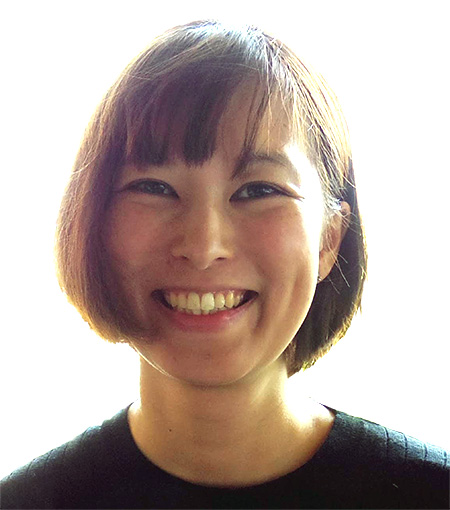
東京科学大学
総合研究院
特任助教
研究概要
タンパク質の集合・離散が関与する生命現象の役割や機構を理解するためには、細胞が自然に形成する集合体を観察する手法だけでなく、集合体を人為的に制御する技術が有用となります。本研究では、pH変化を外部刺激としてタンパク質の集合・離散を制御可能な短いペプチドタグを開発します。さらに、開発したペプチドタグを活用し、神経変性疾患に関与するタンパク質のアミロイド形成機構の理解を目指します。
高塚 大知
オルガネラ間の動的相互作用が駆動する細胞分化
グラント番号:JPMJPR22E6
研究者
高塚 大知

奈良女子大学
研究院自然科学系
准教授
研究概要
植物の根の表面から突出する「根毛」は、水分・養分の吸収に重要な働きを持つ細胞です。根毛の分化過程で発現する遺伝子が多数同定されていますが、それらを適切なタイミングで発現させる仕組みは不明です。本研究では、植物細胞の大半を占める「液胞」と、遺伝子発現の司令塔である「核」が互いの動態を制御し合う『動的相互作用』の存在を証明し、更には、その遺伝子発現と根毛分化誘導における役割を実証します。
武井 洋大
核内構造体への摂動による細胞状態遷移の制御
グラント番号:JPMJPR22E7
研究者
武井 洋大

カリフォルニア工科大学
バイオロジー、バイオエンジニアリング研究科
Research Scientist
研究概要
本研究では、合理的に選択された数百種類の摂動条件と、空間ゲノミクス法による高い空間解像度での一細胞マルチオミクス計測を組み合わせることで、核内構造体と細胞状態遷移の直接的な関係性の解明と、核内構造体への摂動を介した細胞状態遷移の制御を目指す。これを実現するため、胚性ゲノムの活性化のマウス及びヒト培養細胞モデルを用いて、研究を行う。
戸田 浩史
生体防御と睡眠:液-液相分離がつなぐ2つの高次機能
グラント番号:JPMJPR22E8
研究者
戸田 浩史

筑波大学
国際統合睡眠医科学研究機構
特任助教
研究概要
Nemuriという分子の挙動の理解を通じ、「液-液相分離」という細胞内で起こるミクロの現象によって、「生体防御」や「睡眠」というマクロの高次生命現象をどのように制御しているかを明らかにすることを達成目標とする。
那須 雄介
生体透明化技術の開発による脳深部神経代謝の解明
グラント番号:JPMJPR22E9
研究者
那須 雄介

中央研究院
生物化学研究所
助研究員
研究概要
生きている試料の組織深部の細胞内高次構造体を高時空間分解能で蛍光観察するため、生体透明化技術を開発する。開発にあたり、申請者が開発した超高感度乳酸バイオセンサーR-iLACCO1.1及びタンパク質工学手法を利用する。
堀 直人
長鎖RNA粗視化分子シミュレーションモデルの開発
グラント番号:JPMJPR22EA
研究者
堀 直人
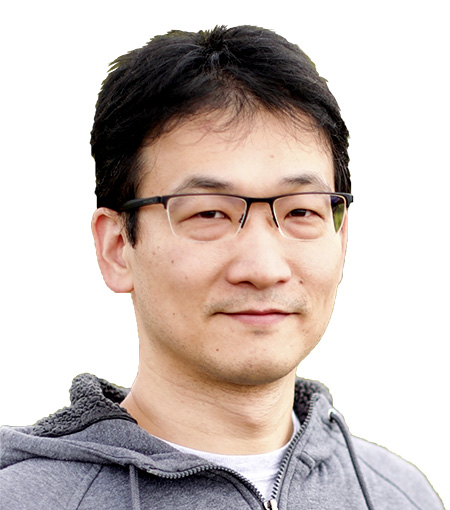
ノッティンガム大学
薬学部
助教
研究概要
長鎖RNAは、細胞内の遺伝情報伝達や機能制御を担っており、コロナウイルスやそのワクチンの構成物質としても重要です。ところが、特性や機能を理解する上で鍵となる分子レベルでの構造は、実験による直接観察が難しくほとんど分かっていません。本研究では、数千塩基にわたる長いRNAの構造アンサンブルを明らかにする分子シミュレーション技術を開発し、機能メカニズムの解明やRNA医薬への応用を目指します。
増渕 岳也
DNA分子配置技術を用いた免疫受容体高次構造体分子機能の解明
グラント番号:JPMJPR22EB
研究者
増渕 岳也
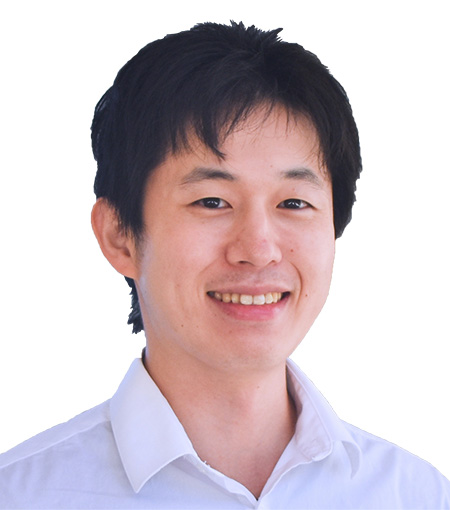
カリフォルニア大学サンディエゴ校
生物科学部
博士研究員
研究概要
本研究は、DNAナノ分子配置技術を、従来の免疫シナプス再構成系、無細胞再構成と組合せ、空間分解能を向上した新規再構成系を樹立する。確立した新規再構成系を用いて、PD-1高次構造体形成に必要な因子を同定し、申請者が見出した新規分子モデルを検証する。さらに、PD-1の未知の分子機能を新規分子モデルの文脈で検証する。
蓑島 維文
持続可能な標識法による時間無制限オルガネラ動態イメージング
グラント番号:JPMJPR22EC
研究者
蓑島 維文

大阪大学
大学院工学研究科
准教授
研究概要
本研究では、独自に開発した持続可能なタンパク質標識法を応用し、細胞内オルガネラを時間無制限に観察し、その動態解析を行う。蛍光プローブが入れ替わり続けるタンパク質標識法の開発と応用を進め、オルガネラの長時間・超解像イメージング、マルチカラーイメージング、コンタクトサイトのイメージングを行うことで、オルガネラの微細構造とオルガネラ間相互作用を解析し理解する。
持田 啓佑
小胞体タンパク質分解過程の場の観測と分子基盤の解明
グラント番号:JPMJPR22ED
研究者
持田 啓佑

東京科学大学
総合研究院
助教
研究概要
小胞体は、タンパク質の品質と量を適切に保つため、それらを分解する独自の仕組みを備えています。しかしながら、タンパク質分解に関わる各過程が小胞体上のどこで、どのようなキネティクスで行われるのかという時空間情報については意外にも殆ど明らかにされていません。本研究では、分解過程を観測する蛍光イメージング技術の開発などを通じて、小胞体におけるタンパク質分解を新たな次元・観点から理解することを目指します。
山本 詠士
非膜性構造体内部における分子挙動の階層統合的理解
グラント番号:JPMJPR22EE
研究者
山本 詠士

慶應義塾大学
理工学部
准教授
研究概要
細胞内では、特定のタンパク質やRNAが液-液相分離現象によって集まることで、非膜性構造体が形成されます。本研究では、ミクロ階層(原子・分子挙動)・メゾ階層(相分離)を繋ぐマルチスケールシミュレーション手法の開発を行い、非膜性構造体内部の動的不均一性が分子の拡散・局在・相互作用に与える影響の解明を目指します。









