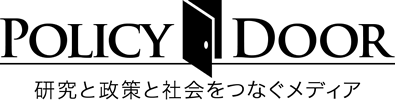――この1年、新型コロナウイルス感染症対策の過程で政治と科学の在り方が問われてきました。政策を決める過程でやはり科学的な根拠が必要であるということが一般的にも認知されています。この状況についてはどのように考えられますか。
山縣 科学的根拠とは何かという概念が少しずつ変わってきています。医学であれば結核には予防接種と薬が効くというエビデンスで来たけれど、高血圧などの慢性疾患は因子がたくさんあります。どのくらいの人が治り、コントロールでき、あるいはうまくいかないのは確率の話です。同じように科学的根拠についても、これをやれば必ずこうなるというものから、確率論になってきたときに、一般の人々と研究者ではエビデンスというもののとらえかたが違っているかもしれません。
政策決定ではさらに、いま何かをしなければならないというときには限られた情報で分析しなければなりません。考えなければならないことは時によって違いますし、手に入る情報は刻々と変わっていきます。半年前は科学的根拠であったものが、新しい情報でアップデートされて変わっていくのです。その時々に最適な政策を立て、国民に受け入れてもらう仕組みが必要なのですが、さまざまな温度差があってなかなかうまくいきません。そのようなことが表面化していると思います。

予測がなければどうすればいいかわからない
――たとえば京都大学の西浦博教授のシミュレーションについては今回、政策に生かしきれなかったように思います。2020年の緊急事態宣言のときは、感染が下火になったあと、予測が当たらなかったとずいぶん批判されました。
山縣 予測はそのときに必要だから使うものであり、当たるかどうかは結果論でしかありません。しかし、予測がなければ何をすればいいかすらわかりません。予測があるかないかで、できることに大きな違いが出てくるのです。西浦先生のモデルは極めてシンプルでありながら高いレベルの推定ができるもので、日本の感染症対策に画期的な予防方法を提示したと言えます。現在では経済学を含めた推計も出されていますが、モデルの中の要素が違うので結果も違ってきます。目的が違うのでそれは当たり前です。
2020年春の段階では世界に先駆けて「三密」ということを政府が言いました。これは、クラスター分析があったからこそです。それをもとにどうすれば感染を抑制できるのかという形で、科学的根拠を政策に結び付けた好例となりました。
――第1波の押さえ込みがある意味でうまくできたが故に、時に政治は科学の影に隠れ、科学は政治を忖度するといった、科学と政治との関係についての課題がそのままになってしまった面があったのではないでしょうか。
山縣 それは科学者と政治家との役割の違いだと思います。本来、感染症対策と経済を回すというのは対立するものではありません。感染症対策は直接に命を扱いますが、経済もまた命の問題です。トータルとして考えなければなりません。ただ、目に見えない要因は測定できず、数字が出せません。感染者数や実効再生産数など、測定できるものしか分析できないというのが、科学の限界です。しかし、科学の進歩はとても速いので、科学として見ることができるものはこれからもっと増えて行くでしょう。それを正しく解釈し、政策に移すことが必要です。そういった点で、課題がはっきりと見えた1年だったと言えます。
政策に結びつくきっかけを目指した第2期
――これまで経験と勘に頼っていたものを、エビデンスに基づいて政策を決定していくのが Evidence-based Policy Making、略してEBPMですね。そして平成23年度から開始された「政策のための科学」研究プログラムは、EBPMを実現するための研究を推進するものです。第1期、第2期を経て令和3年度は第3期の募集が開始されますが。
山縣 第1期は比較的大型の予算をつけて進めてきましたが、第2期では政策まで結び付くきっかけとなるようなところを目指して、一つ一つの研究費は小さくなっています。第1期では、たとえば東京大学の古田プロジェクトの災害時のレジリエンス(回復力)の研究のように、極めて重要でありながら、なかなか政策に結びつきにくいところがありました。もっと行政に向けて発信する必要があるのではないかということで、このPolicy Doorのような媒体を含めて情報を整理して理解してもらおうとしています。西浦プロジェクトが受け入れてもらえたのは、研究者側が行政側のニーズに寄り添うアプローチをとる努力をしたことと、研究内容と行政をつなぐ医系技官の存在が大きかったと思います。
医学・医療のエビデンスには、いくつかのレベルがあります。無作為割り付け研究(Randomized Controlled Trial: RCT)と呼ばれる、人を対象にした介入研究を集めたレビュー論文、これがトップクラスのエビデンスです。次に介入研究そのものの論文。それに続くのがコホート研究という追跡観察研究、症例対照と呼ばれる対照群を用いた比較研究、そして症例報告、ここまでの論文がエビデンスとなります。この新型コロナの状況下で、エビデンスの使い方は一般にも理解されてきたように思います。しかし、社会実装に至るまでには科学だけでは対応できない、倫理的・法的・社会的課題(Ethical, Legal and Social Issues: ELSI)という側面があり、エビデンスがあるというだけでは、科学技術イノベーションを政策に反映することはできません。科学と政策を結ぶ、いわゆる中間人材が今までにも増して重要になってきています。
第2期ではたとえば、先端科学についてのコミュニケーションのあり方についての研究がありました。今までの科学技術コミュニケーションでは、講演会をしたり、理解してもらうためのコンテンツを作ったりということがなされてきましたが、その中にアートという要素を入れて、「難しい、怖い」という感情を和らげ、関心を持てるような新しい仕組みを作ってくれたのが三成プロジェクトです。第2期の梶川プロジェクトは研究者と政策担当者のエビデンスの違いを明らかにして、それを認識したコミュニケーションの必要性を提言しました。今走っている加藤プロジェクトにしても、難病の研究をするときに、研究者と患者の関係が研究をする側とされる側ではなく、患者自身に研究に参加してもらう患者参画型の方法を具現化する仕組みを作り、成果を出していこうとしています。そういったことが第2期ではできていると思います。
また、情報の利活用も非常に重要で、研究者自らが情報をとってくるだけではなく、行政が持っているさまざまな情報をいかにオープンにしてもらって、それを活用してエビデンスをどう作っていくのかが阿部プロジェクトで進められています。自治体が持っているデータをどのようにすれば共有できるのか、道筋が見えてくるような気がしています。
第3期のテーマは行政との「共進化」
――そのような流れの中で、第3期にはどのような応募を期待しますか。
山縣 さまざまなテーマで募集をしていますが、政策に結び付くという意味では、専門的な研究の視点の中にもう一つ、政策という視点を入れて、政策を理解した上で、または理解ができる研究と政策をつなぐ中間人材を研究チームの中に入れて、応募していただきたいと思います。つまり研究の視点のみのエビデンスではなく、政策に結び付くエビデンスを求めています。
これまではシーズありきの研究テーマが多く見られましたが、第3期では、「共進化」の視点を入れて欲しい。政策側がこういったものを求めているというテーマを設定しますので、そこに自分たちのこれまでの研究成果をうまく乗せることで、政策に結び付いていく早道となります。ぜひ、政策に結び付けていくという熱意をもって応募していただきたく思います。
政策科学というものはまだ狭いコミュニティですが、小さく固まらず、いろいろな分野の研究者が入ってきているのもこのプログラムのいいところです。テーマがさまざまありすぎるという批判を受けやすい点でもありますが、逆にこのプログラムによって、今まで政策科学をまったくやっていなかった人が、これは非常に重要な分野なのだと応募してくれるという傾向が見えます。今年度で終了した横山プロジェクトはまさにそういうものでした。横山先生は決して教育政策の専門家ではありませんでしたが、各種の専門家をうまく束ねて、女性の数学・物理学研究者をどう育成していくのか、これをきちんとやっていかないと日本は先がないぞという思いで、非常に高い評価につながる成果を上げていただいたと考えています。
――どうもありがとうございました。
(文・前濱暁子)
English: Scientific Evidence is Needed to Determine Policy (PDF)