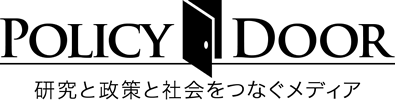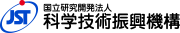新型コロナウイルス感染症のパンデミックで、感染拡大の波が襲うたびに、病床がひっ迫しているというニュースが流れる。そのような中、「病床が多すぎることが問題だ」と述べてきた伊藤教授。病床はむしろ足りないのではないのか。今、なぜあえて病床削減が必要なのだろうか。

ダウンサイジングは待ったなし、の理由
「人口半減社会」。この衝撃的な言葉は遠からず現実になる。人口全体の縮少とともに、特に、総人口に占める生産年齢人口の割合は、2000年の68%から2050年には約54%に縮小する(内閣府「少子化社会対策白書」2021年)。公的保険と公費で維持する医療は、人口規模に合わせて柔軟に規模を調整することが難しい。一方で、公的保険の支え手の負担は増すばかりである。保険が破綻するか、病院が破綻するか、ではなく、ソフトに着地するための戦略的ダウンサイジングが必要である。
病院の再編には、少なくとも4~5年かかるのが通常、と伊藤教授は言う。「なので、2025年頃のダウンサイジングを目指して、厚労省に提出されている入院の診療記録を1年ごとに頂いて検討が進む予定でした」(伊藤教授)。しかし、この新型コロナのパンデミックで、乗船者の5分の1あまりもの感染者が出たダイヤモンドプリンセス号を皮切りに、続々と入院患者が増加した。このような緊急時に、どこの病院に空きがあるのか、どこが対応可能なのかがわからなければ危機対応はできない。限りなくリアルタイムに近い病床データが必要になったのだ。「どれだけリソースがあったとしても、あるという情報が伝わらなければ人々は入院できません。いわゆる有事対応の重要性がこれまでになく増したことが医療機関の中でコロナ禍での一番の変化だと思います」(伊藤教授)。
必要な役割と経営を両立する難しさ
現在、病院の内訳は民間8割、公立2割である(厚生労働省2022年)。いざと言う時の生死に関わる重要なリソースであるにもかかわらず、民間の経営的ガバナンスと公的な政策的ガバナンスが入り組んでいて制御がきかない状況である。それを調整して、うまく再編の方向へ持っていくということが必要だ。しかし、それは一筋縄ではいかない。
病院の担う診察機能の実態と課題を捉える際には、DPCデータ(※)が手がかりとなる。このデータを使うと、どういう診療機能を持っていて、治療の内容ごとに収支がプラスになるのか、マイナスになるのかがわかる。病院の役割と収支が明確になるのだ。その収支差を見たときに、たとえば、「この地域になくてはならない救急だけれども赤字だ」など、必要性の軽重と収支の赤字、黒字といった二軸で各病院をマッピングできる。また、類似する診療機能がどれだけ近くにあるか、地域の診療実績でどれだけのシェアを占めているかなどもわかる(伊藤2019年)。「大多数の市民は、自分の住む地域の病院ごとの医療の質を知りません。データを地域の中で使えるツールにして、誰かが第三者目線でコメントをすることがとても大事なのではないかと思います」(伊藤教授)。
地域の人々は、同じような問題意識を持っていたとしても、しがらみがあって言えない場合や根拠となるデータにアクセスできない場合も多々ある。伊藤教授がそのような意見を代弁することもあるという(伊藤他2022年)。第三者だから利害関係がなく言えることもあるし、研究手法をふまえて分析したデータから結果を出すこともできる。「そういう意味では、単なるおせっかいかもしれないけれども、研究者だからこそ立ち位置があるのではないかと、そこを見つけようと研究を始めました」。地域が持続していくことは大切だ。持続させていくためには将来像が描けなければ人はそこに残らない。数値に基づいて、持続可能な未来を描くこと、そのための手助けをしたいと語る。
※ DPC (Diagnosis Procedure Combination) データ:匿名化された患者の個票で、治療内容と支払いがわかる全国統一形式の電子データセット。
コロナ禍は逆風でもあり、追い風でもあった
医療は地域の必須リソースだということは、誰もが賛同する。ならば、やはり病床は多ければ多いほうがいいと考えている人は少なくない。「いや、それは全然安心ではないと気付かせたのが、ある意味COVID-19だった」という。病床の数はあっても、どの病院も人材には限りがある。重症度に応じた対応はできるのか、医師や看護師の手が回るのかといった情報共有がされていなかった(伊藤2021年)。機能分化ができていないために重症者用の病棟に軽症者が入ったり、入院の必要性が高い方の受け入れが整わず放置されたりする問題もあった。これは多かれ少なかれコロナ以前からあった問題だ。「私が言わなくても、これまでの医療の構造的な問題を声高に叫んでくださる方が増えたという意味では、追い風だったと思います」(伊藤教授)。
政府の検討会では、医療法の見直し、都道府県の権限強化、保健所の指示系統の整理など、たくさんの論点があぶり出された。病床が多いので人材が手薄で、何より病院の情報がよくわからないという課題も示された。病院の再編や病院の機能分化など、単純に地元の問題という点を越えて、国はどこまで踏み込んで何をすべきかということが「国民的な議論になったということは、ほんとうにある意味ありがたかった」と言う。一方、オミクロン株の第6波の中、病院が目下の対応に追われるタイミングで病床数を考えなければいけないのかという現実もある。課題は分かったが解決は先送り、となるならば当然逆風となる。それについて伊藤教授は次のように説明する。
たとえば急性期治療に対応できる病床が30床あるとする。一方で、急性期病院という看板は掲げているけども、いざ対応できるかどうかはその日によるし、来てみないとわからないという病床が100床あるとする。現状は後者なのだという。「確実に治療してもらえる、ここに行けば安心という30床」と、「数はあってもたとえば10分の7の割合で治療が受けられない100床」のどちらかを選ぶ話になるのだ。やはり30であっても確実に、いざという時に治療を受けられる体制を選び、整備すべきなのだ。「普段から公的保険で支え、さらにコロナ対策の補助金としての包括支援金も出して、なんとか維持しようとしている医療で、いざ藁をもすがる思いで待っているのに治療を受けられないというのは最悪ですよね」(伊藤教授)。「とりあえず入院して様子をみましょう、と言われるのが普段の病院。その状況が感染症で大きく変わったのは衝撃的だったと思います。しかし、この“とりあえず入院”というのが実は問題でした。寝たままの刺激のない生活で体力や気力が低下してしまいますし、医療従事者もさまざまな容態の方を多数看なければなりません」(伊藤教授)。
結局のところ、急性期医療を確実に対応できる数に絞り、専門の医師や看護師を適正に配置する。その一方で、医療だけでは完結しないケアについては新しいヘルスケアサービスと結び付けて健康維持の拠点をつくりたい。伊藤教授の目標はそこにある。
病床を減らすのはより良い医療のため、という意識に変えるために
それには地域に必要な機能を定量化して、そこに資源を投入しなければいけない。「私は医療費削減派ではない。受けなくてもよい医療サービスがある一方で、受けるべきサービスが整っていないケースもある」と伊藤教授。医療費を使うこと自体は必要だが、内容を吟味して最大限役に立つ形にしなければならないということだ。「保険が適用される医療行為であれば、その要・不要にかかわらず、国全体で費用を負担しています。内訳が分からないまま請求書通りに払っていてよいのでしょうか」(伊藤教授)。結局は私たち、あるいは将来世代の子供たちが身銭を切る話なので、やはりそれをある程度自分ごとにしていかなければならない。自治体や国がやってくれればいいという感覚を、今すぐにでも変えなければ手遅れになる。
「病床を減らすのは何のためかというと、病床を減らしてより健康になるためなんですよね」。伊藤教授は、健康イノベーションという言葉を研究テーマに掲げている。減らすことは一つの大きな変化を伴うが、痛みだけではないという示し方は必ずできる。「まさにダウンサイジングすることで、現場の人の働き方に余裕ができて、離職が減って、人材を確保できる見込みが立てば、次の将来計画を立てることができるのです」(伊藤教授)。データがもたらす警鐘だけではなく、活路も伝えていきたいという。
今後は引き続き、つながる地域や協力病院を増やし、仲間を集めてスケールアップしていきたいと語る伊藤教授。効率化の視点をもつことは、決して医療サービスの縮少を意味するのではなく、新しい社会の姿に適合した医療体制を創造することでもある。政策提言にも関わりながら、さまざまなハードルを越えてそのビジョンが地域で生かされる未来を見据えている。
(まとめ・前濱暁子、編集・北川潤之介)
2022年1月25日インタビュー