- JST トップ
- /
- 戦略的創造研究推進事業
- /
 さきがけ
さきがけ- /
- 研究領域の紹介/
- 時空間マルチスケール計測に基づく生物の復元あるいは多様化を実現する機構の解明/
- [生命力の二面性] 2024年度採択課題
[生命力の二面性] 2024年度採択課題
岩上 哲史
農業活動が駆動する雑草の高速進化メカニズムの解明
グラント番号:JPMJPR24N2
研究者
岩上 哲史

東京農工大学
大学院農学研究院
准教授
研究概要
雑草は農耕地において人間による排除の対象となってきましたが、雑草は遺伝的に変化することで様々な排除圧に適応してきました。本研究では、雑草における典型的な農耕地適応現象である除草剤抵抗性の進化機構の解明を目指します。また並行的な進化の背景にあるゲノム特性を解析することで、急速な進化を可能にする「進化的転用」機構を明らかにします。これにより、除草剤抵抗性雑草の防除と進化抑制技術の確立を目指します。
大瀧 夏子
慢性疾患における細胞間相互作用カタログ・多様化経路マップの作成
グラント番号:JPMJPR24N3
研究者
大瀧 夏子

千葉大学
大学院医学研究院
特任助教
研究概要
慢性疾患は、健常状態で安定している細胞に、細胞間相互作用などの外力が非連続的に積み重なって進む、疾患安定状態への多様化と捉えられます。しかし、個々の細胞間相互作用の情報を大量に取得するのに適した実験・解析手法がないため、多様化過程を理解することは困難でした。そこで本研究では、網羅的な1細胞間相互作用データを取得する技術基盤を開発し、世界初の細胞間相互作用カタログ・多様化経路マップ作成を目指します。
樫尾 宗志朗
代謝レジリエンスと破綻から識る生命力
グラント番号:JPMJPR24N4
研究者
樫尾 宗志朗

東北大学
加齢医学研究所
助教
研究概要
オミクス解析は生命科学に大きな進展をもたらした一方、見かけ上変化の無い要素が見落とされる傾向にあります。栄養欠乏や産生阻害においても安定して保たれる重要な代謝経路として、S-アデノシルメチオニン(SAM)代謝を見出しました。本研究では、SAM代謝の時空間的制御を包括的に解析し、細胞内の局所から個体全体に至るまで生命現象を横断的に探求することで、変化に隠れた生命力の解明を目指します。
加藤 遼
微生物本来の生命力を可視化する
グラント番号:JPMJPR24N5
研究者
加藤 遼

大阪大学
大学院基礎工学研究科
助教
研究概要
生物が本来示すはずの代謝の多様性を可視化するには、代謝物及び代謝を支える細胞内の酵素や核酸などの分子を破壊せずに、時空間的マルチスケールに観察することが必要です。本研究では、微生物内の分子を限りなく損なわずに複数の代謝物を可視化する超解像中赤外分光イメージング法を確立します。油脂酵母の生命力解明を1例とし、従来の代謝物計測では得ることができなかった生物本来の生命力の知見獲得を目指します。
北沢 太郎
履歴探索ゲノミクスによる脳の復元力の解明
グラント番号:JPMJPR24N6
研究者
北沢 太郎

オーフス大学
DANDRITE北欧EMBL
グループリーダー・准教授
研究概要
本プロジェクトでは生命力を脳のストレスからの復元力として捉えます。ストレス応答に関する研究は数多く行われてきましたが、個体間・細胞間の応答の多様性もたらす分子レベルの因果要因を長期的な時間スケールの中で解析することは困難でした。本プロジェクトでは1細胞履歴探索ゲノミクスを樹立することでこの問題を克服し、脳のストレスからの復元をもたらす要因を分子・細胞・個体・集団レベルの解析で明らかにします。
京極 大助
花寿命をめぐる花粉とめしべの敵対的な相互作用とその進化
グラント番号:JPMJPR24N7
研究者
京極 大助

奈良女子大学
研究院自然科学系
准教授
研究概要
進化生態学の理論予測にもとづき「花粉は花を枯死させる性質を進化させ、めしべはこれに抵抗する性質を進化させる」という仮説を多角的なアプローチで検証します。主にシロイヌナズナを用いて、花粉とめしべの性質を決定している遺伝子を特定します。また、近縁種間での遺伝子の系統進化パターン等を明らかにします。これらにより、ミクロスケールからマクロスケールを統合しつつ、花粉とめしべの「生命力」を明らかにします。
久保田 茜
温度変動を起点とした季節性花成応答の復元と多様化の分子基盤
グラント番号:JPMJPR24N8
研究者
久保田 茜

奈良先端科学技術大学院大学
先端科学技術研究科
助教
研究概要
本研究では植物が発揮する生命力である開花制御の仕組みに迫ります。植物が温度変動に対して季節情報を「復元」する一方で、日々の温度の移ろいに対して開花応答を「多様化」させる仕組みに着目することで、植物の温度応答の二面性を支える分子基盤を明らかにします。また温度応答を操作することで、環境変動に強い農作目の創出の知的基盤の提供を目指します。
清家 泰介
酵母のフェロモン認識の二面性と環境適応メカニズムの解明
グラント番号:JPMJPR24N9
研究者
清家 泰介

九州工業大学
大学院情報工学研究院
准教授
研究概要
本研究は、分裂酵母のフェロモン認識機構における「厳密さ」と「柔軟さ」の二面性を理解し、環境適応のメカニズムを解明することを目指します。具体的には、フェロモンとその受容体の認識特異性の変化が生殖隔離や種分化にどのように寄与するかを、時空間スケールで詳細に計測し解析します。また自然界から実際に単離した野生酵母株の調査と組み合わせることで、酵母の生命力を把握し、自然界での進化の理解を深めます。
高野 哲也
時空間プロテオーム技術開発で解明する生命力強化の分子メカニズム
グラント番号:JPMJPR24NA
研究者
高野 哲也

九州大学
高等研究院
独立准教授
研究概要
恐怖記憶は、一見不快な体験でありながら、将来の危険を回避するための生存本能を強化する重要な役割を果たします。しかし、過剰な恐怖記憶はうつ病や不安障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの精神疾患の原因となり、現代社会でも深刻な問題です。本研究では、時空間プロテオーム技術を用いて、脳の生命維持に関わる機能変化を制御する分子メカニズムを網羅的に解明し、新しい治療アプローチの開発を目指します。
高橋 徹
暑熱から生命を守る柔軟かつ強靭な最上位体温調節中枢
グラント番号:JPMJPR24NB
研究者
高橋 徹

筑波大学
医学医療系
助教
研究概要
日本を含む「暑い」環境に生息する生物は「暑熱応答」なる生命力を宿します。恒温動物である哺乳類には高体温症・熱中症のリスクが常に伴うため、この力は特に不可欠です。本研究では、体温調節中枢である視索前野POAを軸に時空間スケールの大きい研究を展開します。生体内/外の温度情報の統合、暑熱レベルに適した柔靭な応答、暑熱順化を実現する神経機構の解明に挑み、暑熱から生命を守る「しなやかな力」の真髄に迫ります。
鳥井 孝太郎
ライブセルオミクスを用いた受精卵に潜む個性の診断と操作
グラント番号:JPMJPR24NC
研究者
鳥井 孝太郎

理化学研究所
最先端研究プラットフォーム連携(TRIP)事業本部
研究員
研究概要
本研究は遺伝にも環境にもよらずに生物を自発的に個性化させる生命力を明らかにします。生個体オミクス法は個体内の細胞を破壊せずにオミクスデータを取得可能にする手法です。この手法を用いて同一個体における発生過程の起源的個性と孵化後の行動個性を記録し、両個性データ間の一貫性を探索することで個性の起源である発現変動遺伝子を特定します。加えて、特定した遺伝子のmRNA注入による個性の出生前操作にも挑戦します。
藤原 圭吾
「不都合な配列」解析で切り拓く翻訳制御と生命力の理解
グラント番号:JPMJPR24ND
研究者
藤原 圭吾

科学技術振興機構
さきがけ研究者
研究概要
翻訳の一時停止は時に細胞毒性を引き起こします。一方で、翻訳を一時停止するアミノ酸配列が様々な生理機能に利用されていることがわかりつつあります。本研究では大規模ゲノム情報の生物情報学的解析と実験的検証により、「避けられている」アミノ酸配列パターンをむしろ有効活用する生命システムを発見し、翻訳制御と生理的役割、進化的背景について理解することを目指します。
牧野 浩史
集団適応力を支える多様性出現の神経基盤解明
グラント番号:JPMJPR24NE
研究者
牧野 浩史
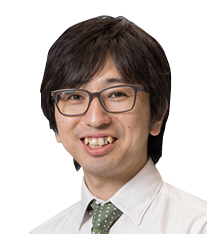
慶應義塾大学
医学部・医学研究科
教授
研究概要
本研究では、神経細胞から個体、集団といった多層的なレベルで実現される多様化のプロセスを、脳とAIの分野を横断した研究によって理解することを目指します。異なる報酬環境で訓練されたマウスやAIエージェントがどのような個性を獲得し、集団における競争社会でどのようにふるまうのか、その神経基盤を検証します。本研究により、今後、多様な個体で構成される集団が持つ「生命力」の本質に迫ることができると期待されます。
森下 英晃
細胞内破壊が創出する個体機能:その分子基盤、制御、進化
グラント番号:JPMJPR24NF
研究者
森下 英晃

九州大学
大学院医学研究院
教授
研究概要
生体内のいくつかの組織では、オルガネラ等の細胞内成分を大規模に「壊す」(本研究では「細胞内破壊現象」と呼ぶ)ことで、新たな個体機能を創出しています。ところが、その分子基盤はほとんど不明です。本研究では、ゼブラフィッシュやヒトプライマリー細胞3次元培養系等を用いた独自の高深度時空間解析手法を確立することで、細胞内破壊現象の責任因子を同定し、その分子機能、個体機能、進化を解明します。









