- JST トップ
- /
- 戦略的創造研究推進事業
- /
 さきがけ
さきがけ- /
- 研究領域の紹介/
- 海洋バイオスフィア・気候の相互作用解明と炭素循環操舵/
- [海洋バイオスフィア] 2024年度採択課題
[海洋バイオスフィア] 2024年度採択課題
伊左治 雄太
ヘム鉄:人為起源鉄を追跡する次世代方法論
グラント番号:JPMJPR24G1
研究者
伊左治 雄太

海洋研究開発機構
海洋機能利用部門
副主任研究員
研究概要
人間活動により排出される人為起源鉄は、海洋一次生産を支える重要な鉄の供給源です。本研究では、一次生産を支える鉄の供給源を解析する新たな手法として、含鉄生体分子ヘムBの鉄安定同位体比分析法を開発します。この手法を海水や海底堆積物に応用し、現在および過去の一次生産者による人為起源鉄の利用を可視化することで、人為起源鉄が炭素循環に与える影響を明らかにします。
大野 良和
サンゴ骨格の結晶成長界面における観察手法の高度化
グラント番号:JPMJPR24G2
研究者
大野 良和

科学技術振興機構
さきがけ研究者
研究概要
造礁サンゴは長い年月をかけて地形を形成し、サンゴ礁域の豊かな生物多様性を支えています。しかしながら、サンゴを含む海洋生物の骨格形成過程や、その生育阻害との関係については、細胞生理学的な研究が進んでおらず、不明な点が多く残されています。本研究では、非破壊的な生体イメージング技術を応用し、サンゴ骨格表面の固相―液相界面の可視化技術の構築を目指します。
高橋 迪子
海洋未培養ウイルスのサルベージとそのライブラリ化
グラント番号:JPMJPR24G3
研究者
高橋 迪子

産業技術総合研究所
バイオものづくり研究センター
主任研究員
研究概要
大規模ゲノム解析技術により海洋炭素循環システムにおけるウイルスの役割が解き明かされつつありますが、それらの多くは未培養であるため生物学的性状を正確に評価できていません。本研究では海洋の未培養ウイルスを粒子として再生する基盤技術を開発し、再生ウイルスをライブラリ化することによって、海洋炭素循環システムの理解の深化に貢献します。
仲村 康秀
海洋炭素循環における単細胞動物プランクトンの役割解明
グラント番号:JPMJPR24G4
研究者
仲村 康秀
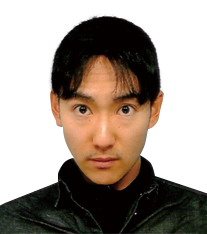
島根大学
エスチュアリー研究センター
助教
研究概要
プランクトンは大気中のCO2を深海へと運ぶため、海洋炭素循環において非常に重要な役割を担っていますが、特に微生物ループの詳細については未解明な部分が多いです。そのため、本研究では単細胞動物プランクトンに着目し、彼らを通じた微生物ループの新たな経路を明らかにする事を目指します。
二井手 哲平
海洋微生物への非光合成炭酸固定経路設計
グラント番号:JPMJPR24G5
研究者
二井手 哲平

大阪大学
大学院情報科学研究科
助教
研究概要
本研究は、沿岸工業地域でのカーボンネガティブ技術の開発を目指し、海洋微生物へ人工の炭酸固定経路を実装することでCO2からの有用物質生産に挑戦します。そのために、データベース上の全酵素反応を統合した代謝モデルで代謝シミュレーションを実施することで、高いエネルギー効率を示す人工の炭酸固定経路を設計します。
平井 惇也
カイアシ類を用いたゲノム時代の気候変動リスク評価
グラント番号:JPMJPR24G6
研究者
平井 惇也

東京大学
大気海洋研究所
講師
研究概要
地球規模の気候変動に伴い海洋の昇温化や酸性化は急速に進行し、海洋生態系における’目に見えない種内の遺伝的多様性の消失’が予想されています。本研究は環境変化に迅速に応答し、魚類餌料としても重要な動物プランクトンであるカイアシ類に着目し、将来的な変化に脆弱な集団・海域をゲノムレベルで特定します。また、プランクトンの多様化プロセス等、ゲノム情報を活用した今後の生態学的研究の道筋を示すことも目的とします。
藤井 学
沿岸海域における溶存有機物の分子構造と環境機能
グラント番号:JPMJPR24G7
研究者
藤井 学

東京科学大学
環境・社会理工学院
准教授
研究概要
超高分解能質量分析(FT-ICR-MS)やケモインフォマティクス技術、ネットワーク解析等を活用して、DOM分子構造の探索かつ網羅的スクリーニングが可能なネットワークトラバーサル法を開発します。タンデム質量分析やLC分析による構造候補の検証、さらには分子変換過程の解明、分子構造情報からの環境機能推定等を通して、炭素循環を含む様々な角度から沿岸海域DOMの環境機能や生物地球化学的プロセスを評価します。
堀 真子
珪藻シリカのホウ素同位体組成から導くpH指標
グラント番号:JPMJPR24G8
研究者
堀 真子

大阪教育大学
理数情報教育系
准教授
研究概要
大気中に増加した二酸化炭素の多くは海洋に吸収されます。生物源シリカは、過去の海洋環境を記録する地質試料として有望です。本研究では、様々な水環境に生息する現世の珪藻殻を分析し、珪藻殻に含まれるホウ素同位体比を用いてpHを求める換算式を構築します。また、堆積後の続成作用を調べ、指標の長期安定性を検証します。pH記録を長時間スケールに拡張することで、二酸化炭素吸収における海洋の機能解明に貢献します。
水野 勝紀
革新的な海底生態系3次元構造観測ツールの開発
グラント番号:JPMJPR24G9
研究者
水野 勝紀

東京大学
大学院新領域創成科学研究科
准教授
研究概要
海底近傍における物質循環やブルーカーボン生態系拡大施策の評価を進める上で、最も重要な情報基盤のひとつとなる生物の3次元的な生態情報を、従来よりも高精度・高効率に取得するため、本研究では、様々な時空間スケールの海底画像データに超解像技術を応用し、海底ハビタットマップ作成の高精度化、高効率化を実現します。また、堆積物中における物質循環の定量化に資する、生態系3次元構造観測技術を開発します。
渡辺 謙太
ブルーカーボン貯留と大気CO2除去の統合的理解
グラント番号:JPMJPR24GA
研究者
渡辺 謙太

海上・港湾・航空技術研究所
港湾空港技術研究所
主任研究官
研究概要
藻場などの海面下に分布するブルーカーボン生態系は海洋中に有機炭素を貯留する機能を有しますが、それはどの程度の時間・空間スケールで大気CO2の除去に寄与しているのでしょうか。本研究では、藻場による炭素貯留量の実測と、CO2除去効果の時間・空間的な広がりを浅海域から沖合域にかけて実測・推計することで、藻場による炭素貯留機能と大気CO2除去効果の統合的理解を目指します。









