- JST トップ
- /
- 戦略的創造研究推進事業
- /
 さきがけ
さきがけ- /
- 研究領域の紹介/
- 地球環境と調和しうる物質変換の基盤科学の創成/
- [調和物質変換] 2024年度採択課題
[調和物質変換] 2024年度採択課題
井口 翔之
窒素と炭素の資源循環を指向した硝酸態窒素からの尿素の電解合成
グラント番号:JPMJPR2471
研究者
井口 翔之

京都大学
大学院工学研究科
准教授
研究概要
ものづくりの電化を指向し、排水中の硝酸態窒素と大気中の濃度増大が問題視されている二酸化炭素から、肥料・接着剤・樹脂等の原料として欠かせない尿素を再生可能エネルギー由来の電力を用いて、常温・常圧の条件下で合成します。そのために活性な窒素種や炭素種の生成、および窒素-炭素結合の形成に有効な革新的な電極触媒と反応場の設計と開発に取り組みます。
大須賀 遼太
赤外分光法を駆使した液相固体酸塩基触媒反応ダイナミクスの解明
グラント番号:JPMJPR2472
研究者
大須賀 遼太

北海道大学
触媒科学研究所
助教
研究概要
液相中での固体触媒の酸塩基性質は、これまでブラックボックスとされてきました。本研究では、赤外分光を用いた液相での固体触媒の酸塩基性質評価手法を確立します。本手法をカーボンニュートラルの実現に資する「バイオマス変換反応」のoperando計測へと展開し、触媒反応ダイナミクスの解明を目指します。これらの解析を通じて得られた情報を触媒設計へとフィードバックすることで、触媒反応系の高効率化を実現します。
清川 謙介
アンモニアを窒素源とする高効率アミン合成
グラント番号:JPMJPR2473
研究者
清川 謙介

大阪大学
大学院工学研究科
助教
研究概要
窒素循環の中心を担うアンモニアを窒素源として付加価値の高いアミンを直接合成できれば、資源循環やエネルギー効率の観点から理想的です。本研究では、アンモニアを窒素源とし、省エネルギーかつ廃棄物を極力減らした環境調和型のアミン合成の基盤技術を開発します。
小林 裕一郎
廃棄硫黄を原料とした機能性硫黄ポリマー材料の創製
グラント番号:JPMJPR2474
研究者
小林 裕一郎

大阪大学
大学院理学研究科
助教
研究概要
エポキシ、イソシアネート、カルボニルクロリド等を用いて、様々な逐次重合硫黄ポリマーを合成し物性評価を行うことで、その構造と物性を系統的に評価し相関させ、プラットフォームを構築します。この際、社会実装を目指し、低環境負荷な硫黄ポリマー合成法(室温・無溶媒合成)も実現します。その得られた硫黄ポリマーを用いてリチウム硫黄電池や自己修復材料などの機能性材料を創製します。
中村 貴志
大環状錯体によるバイオマス炭素資源の精密自在変換
グラント番号:JPMJPR2475
研究者
中村 貴志
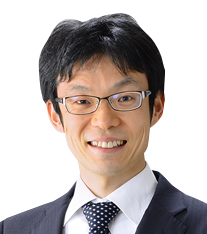
筑波大学
数理物質系
助教
研究概要
バイオマスは石油に代わる炭素資源として注目されていますが、ファインケミカル合成の原料として石油化成品を置き換えるには至っておらず、主に燃焼エネルギーとして利用されています。本研究では、バイオマス炭素資源を直接変換し、その化学修飾を精密に制御する新たな手段として、配位結合で基質を認識する大環状錯体を開発します。そして、その金属間距離に応じた高選択的触媒反応を実現することを目指します。
前野 禅
低濃度CO2吸蔵・水素化を革新する多元機能触媒の設計開発
グラント番号:JPMJPR2476
研究者
前野 禅

工学院大学
先進工学部
准教授
研究概要
本研究では、O2と5%以下の低濃度CO2を含む混合ガスからCO2を吸蔵し、水素化により回収したCO2を直接COやCH4へ変換しながら、同時に再生できるCO2回収・資源化プロセスの構築を目指します。従来のCO2吸蔵・水素化が抱える、O2による失活、多量の白金族元素の利用、高温での運転(300~400℃台)、低いCO2処理速度の全てを解決する革新的な触媒反応場の開発に取り組みます。
村田 慧
C1資源を活用する新規遷移金属光触媒の創製
グラント番号:JPMJPR2477
研究者
村田 慧

理化学研究所
環境資源科学研究センター
理研ECL研究ユニットリーダー
研究概要
本研究では、光化学的に発生させた活性な金属錯体による化学結合形成/切断を基盤として、C1化合物を多様な炭化水素へと変換する光触媒反応の開発に取り組みます。一連の反応開発を通して、地球上に豊富に存在するC1資源および太陽光エネルギーを活用する炭素循環の実現に貢献することを目指します。
山本 達
マルチモーダルX線オペランド計測による触媒構造活性相関の解明
グラント番号:JPMJPR2478
研究者
山本 達

東北大学
国際放射光イノベーション・スマート研究センター
教授
研究概要
反応中の触媒表面は構造ゆらぎがある動的な反応場ですが、構造ゆらぎと触媒活性の関係は明らかではありません。本研究では、3GeV高輝度放射光施設NanoTerasuの高輝度X線を利用した触媒表面の化学・電子状態と構造を同時計測可能なマルチモーダルX線オペランド計測システムを立上げ、触媒構造ゆらぎと触媒活性の相関を解明します。動的な触媒反応場という新学理に基づき、新規触媒開発設計指針の確立を目指します。
山本 貴之
電解液の完全利用を指向した省資源型デバイスの開発
グラント番号:JPMJPR2479
研究者
山本 貴之

京都大学
エネルギー理工学研究所
講師
研究概要
今後予測される蓄電池の需要増加に対応するため、希少金属が不要な省資源型デバイスの開発が必要と考えられます。本研究では、炭素材料のみを活物質として用いたデュアルカーボン電池に注目しています。中性溶媒が含まれないイオン液体を電解液に用い、複数のイオン種を適切に組み合わせることで、室温付近で使用可能な新規高濃度電解液の開発および電池の高性能化を目指します。
百合野 大雅
炭素・窒素循環を実現するシアニドの非古典的資源化法の開拓
グラント番号:JPMJPR247A
研究者
百合野 大雅

北海道大学
大学院工学研究院
助教
研究概要
炭素・窒素循環は近年の環境問題を解決する目標の一つとして注目を集めています。シアニドは炭素と窒素からなる最小の分子状アニオンです。我々の生活に欠かすことのできない工業用化学製品でありますが、その毒性は高く、また、無毒化のために資源循環サイクルから外れていました。本研究では、シアニドを炭素・窒素資源とみなし、その効率的な回収、固定化と非古典的な高付加価値化を目指した研究を行います。









