- JST トップ
- /
- 戦略的創造研究推進事業
- /
 さきがけ
さきがけ- /
- 研究領域の紹介/
- 地球環境と調和しうる物質変換の基盤科学の創成/
- [調和物質変換] 2023年度採択課題
[調和物質変換] 2023年度採択課題
岩瀬 和至
触媒から電極構造の一貫制御による高効率電気化学的二酸化炭素変換
グラント番号:JPMJPR2371
研究者
岩瀬 和至

東北大学
多元物質科学研究所
准教授
研究概要
本研究では、反応に関与する触媒と、二酸化炭素の物質輸送に関与する電極構造を一貫制御することを通じて、従来研究では達成できなかった高い生成物選択性およびエネルギー効率での二酸化炭素電解の達成を目指します。特に、触媒の金属活性中心の配位環境と、触媒電極の触媒層の多孔質構造の制御に着目します。研究を通じて、高効率な二酸化炭素電解を実現する触媒電極の設計指針の解明を目指します。
荻原 陽平
ポリエステル資源のケミカルアップサイクル活用
グラント番号:JPMJPR2372
研究者
荻原 陽平

岐阜大学
工学部
准教授
研究概要
ペットボトルや繊維などに由来する廃棄ポリエステルを、再生可能な非在来型炭素資源と捉え、これを様々な高価値化成品へと直接アップサイクルする触媒的物質変換プロセスを開発します。依然として熱的・物理的処理が支配的なポリエステルの既存リサイクルスキームから脱却し、有機合成化学のアプローチから地球環境と調和し経済的にも合理的な炭素循環システム構築を目指します。
信田 尚毅
AEM型リアクターを利用した廃棄物の電気化学的資源化
グラント番号:JPMJPR2373
研究者
信田 尚毅

横浜国立大学
大学院工学研究院
准教授
研究概要
産業的な廃棄物の多くは、高酸化状態の化学的に安定な構造を有しています。このような安定廃棄物は、高温・高圧・高エネルギー試薬の利用といった過剰なエネルギー投入により還元可能ですが、持続可能な産業の確立に向けては、温和でクリーンな資源化法が必須となります。本研究では、アニオン交換膜(AEM)型電解装置の利用を鍵とし、安定廃棄物を電気化学的に還元し有用な化学物質へと変換する新手法を開発します。
多々良 涼一
アルカリ金属イオンを俯瞰する未踏電極反応開拓と蓄電応用
グラント番号:JPMJPR2374
研究者
多々良 涼一

横浜国立大学
大学院工学研究院
准教授
研究概要
アルカリ金属イオンを用いた蓄電デバイスのうち、リチウムイオン電池は既に商用化され、ナトリウムイオン電池も実用化を目指した研究開発が進んでいます。一方で、本研究では敢えて重アルカリ金属であるルビジウム・セシウムに着目し、大きなイオンサイズにより得られる特異な反応挙動を利用した新たな電池材料の創製と、アルカリ金属イオン全体を俯瞰した学理の構築を目指します。
土井 良平
フッ素化合物の水素還元反応の開発
グラント番号:JPMJPR2375
研究者
土井 良平

東京都立大学
理学部化学科
准教授
研究概要
広範な有機フッ素化合物を水素と塩基により温和な条件(常温~150度程度)にて分解し、対応する炭化水素とフッ化物に変換する触媒を開発します。触媒としては炭素フッ素結合を切断する均一系Ni錯体と水素化触媒の組み合わせを検討します。実用化に向けて、有機フッ素化合物の混合物の脱フッ素水素化、官能基許容性の検証、フッ素資源回収およびスケールアップ検討を行います。
中川 由佳
木材を機能性マテリアルに変換する分子性錯体触媒の開発
グラント番号:JPMJPR2376
研究者
中川 由佳

京都大学
化学研究所
特定助教
研究概要
本研究では、分子性錯体触媒を用いて「強固な木質細胞壁の破砕」および「木材由来の高分子に機能性をもたらす官能基変換」を穏和な条件下で、単段階で実現できることを実証します。さらに、技術の社会実装やLCAに鑑み、触媒とその反応効率にとどまらず、原料調達やスケールなど生産システム全体の最適化を検討します。これにより木材の化成品利用の拡大展開を目指します。
松本 剛
未利用資源利活用を鍵とする糖質バイオマス化学変換
グラント番号:JPMJPR2377
研究者
松本 剛

北海道立総合研究機構
産業技術環境研究本部 エネルギー・環境・地質研究所
主査
研究概要
本研究では、人口減少と需要低下に伴い余剰在庫が増加している甜菜糖関連品に注目し、その製糖工程中途の抽出液を原料とし、5-ヒドロキシメチルフルフラールを経由して液体燃料(パラフィン類)を合成する化学変換プロセス開発に取り組みます。この調和物質変換プロセスの確立は、甜菜農業および製糖産業に新たな付加価値を提供し得るとともに、北海道における環境調和型社会の実現にも貢献できると期待されます。
村岡 恒輝
原子シミュレーションによるゼオライト触媒のデータ駆動的設計
グラント番号:JPMJPR2378
研究者
村岡 恒輝
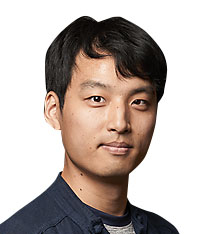
東京大学
大学院工学系研究科
助教
研究概要
ゼオライトの骨格トポロジー、組成、原子位置、活性種、モルフォロジーの無数の組み合わせを網羅するゼオライト触媒データベースを構築します。大スケールの触媒スクリーニング手法を採用することで、C1 化学の各経路に最適なゼオライトを予測します。さらに、それを実現するために必要な合成条件を予測します。
本林 健太
イオン液体を基盤とするCO2回収・電解一括プロセスの開発
グラント番号:JPMJPR2379
研究者
本林 健太

名古屋工業大学
大学院工学研究科
准教授
研究概要
CO2の電解還元プロセスでは、まずCO2を吸収液に選択的に取り込み、さらに一度分離して電解液に溶かし直してから電解還元を始めるのが一般的です。本研究では、エネルギー消費の多くを占めるCO2の分離過程を省略できるように、CO2の選択吸収液と還元用電解液の機能を併せ持つイオン液体を開発します。これにより、エネルギー効率が劇的に向上したCO2回収・電解一括プロセスの実現を目指します。
芳田 嘉志
高密度CO2の化学変換を指向した新規触媒反応場設計
グラント番号:JPMJPR237A
研究者
芳田 嘉志

金沢大学
理工研究域
准教授
研究概要
CO2が高密度環境において発現する分子間相互作用や基質溶解機能、溶媒極性制御などの物理化学特性を化学反応に応用し、CO2膨張液体を基軸とする液ー液二相のエマルション反応場における低温CO2化学変換を目指します。CO2活性化におけるPdの構造敏感性を解明して触媒回転のさらなる高速化を試みるとともに、相間物質移動を利用した目的生成物の連続抽出と組み合わせることで高速CO2化学変換を実現します。









