RInCAクロストーク2024 #03「自動運転が切り開く未来と ELSI/RRI」(12月19日(木)開催)
イベント | 2024年12月19日
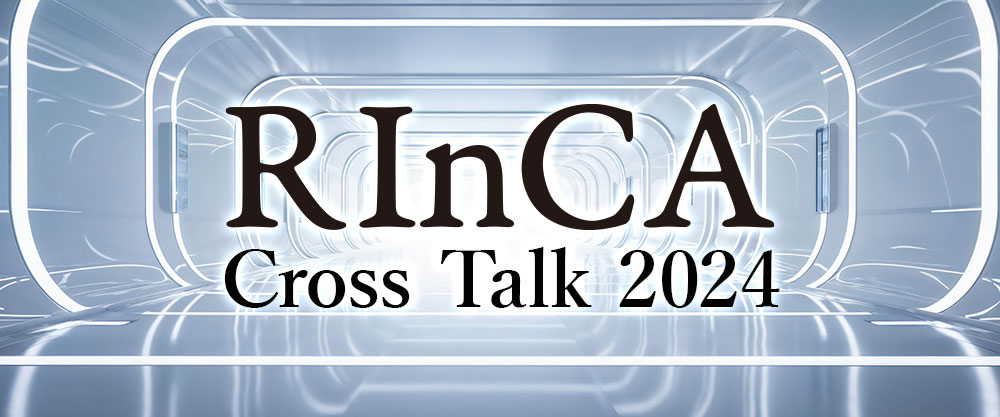
RInCAクロストーク2024とは
ELSI (Ethical, Legal and Social Implications/Issues: 科学技術がもたらす倫理的・法制度的・社会的課題) への先駆的な取り組みを行っている研究者を始め、様々な分野の研究開発に係るアクセラレーター、ビジネスセクター、文化人、省庁関係者など多様な立場のスピーカーが集まり、最新動向や今後の可能性、目指すべき未来像等を議論します。
※RInCAクロストークは、プログラムの取り組み紹介を通じて、多様な分野の専門家、実践家、イノベーター、学生などさまざまな方が出会い、社会課題の解決やこれからの科学技術イノベーションをともに語る場の創出を目的として開催しています。
主催:JST-RISTEX 科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)への包括的実践研究開発プログラム (RInCA)
開催日時

JST-RISTEX RInCAクロストーク2024 #03
「自動運転が切り開く未来とELSI/RRI」
- 日 時:2024年12月19日(木) 18:00-19:00
- 開催形態:現地とオンラインのハイブリッド開催
- 現地会場:CIC Tokyo(東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー)
- 参加:参加費無料(要事前登録) ※現地でのご参加を歓迎しております。
- 登録用URL:https://venturecafetokyo.org/sessions/jst-ristex-rinca-crosstalk2024-3/
参加ご希望の方はリンク先ページ上部にある「事前登録」ボタンから参加方法の選択および事前登録をお願いします。
[ご参加にあたっての留意事項]
*本セッションは、Venture Café Tokyoが行うThursday Gathering #318の1コマとして開催します。従って、本フォームへの参加申込とあわせてVenture Café Tokyoへのイベント参加登録が必要です。当日会場にてサインアップするか、あるいは事前にオンライン登録をお願いします。イベント参加登録における個人情報等の取り扱いは、Venture Caféのイベントプライバシーポリシーに基づきます。
*会場参加の方は、虎ノ門ヒルズ ビジネスタワーにお越しください(森タワーとお間違いないようお気を付けください)。1階のセキュリティゲートにて受付をお願いします。
概要
近年、急速に進化する自動運転技術は、私たちの生活や社会に多大な影響を与える可能性を秘めています。また、実証実験が各地で行われるなか、ビジネス市場としても熱い視線が注がれています。
今回は、自動運転の最新動向や倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)、責任あるイノベーション(RRI)の観点から、社会実装に向けた取り組みをテーマに、ELSIを踏まえた自動運転の社会実装を研究する東京大学教授 中野 公彦氏、「完全自動運転」実現を目指すTuring株式会社共同創業者/CHROの青木俊介氏、共助型交通サービスを提供し地方の交通課題に取り組むオムロン ソーシアルソリューションズ株式会社の横田美希 氏をお招きしてトークを展開します。
それぞれのゲストから見えている課題、将来展望を皮切りに、ELSI/RRIの視点から、自動運転がもたらす新たな価値や未来の可能性を探索します。
登壇者・モデレーター紹介
登壇者:
- 中野 公彦氏 東京大学 生産技術研究所 教授(2020年採択プロジェクト代表者)
「ELSIを踏まえた自動運転技術の現場に即した社会実装手法の構築」
東京大学生産技術研究所 教授。2000年に東京大学大学院工学系研究科産業機械工学専攻博士課程を修了し、博士(工学)を取得。山口大学助手、講師、助教授を経て、2006年より東京大学生産技術研究所助教授(後に准教授に改称)に着任。その後、大学院情報学環准教授を経て、2018年より現職。機械力学と制御を専門とし、運転支援、自動運転の研究に従事。経済産業省・国土交通省自動運転レベル4等先進モビリティサービス研究開発・社会実装プロジェクトテーマ4のリーダを務める。その他、自動車技術会理事、日本機械学会フェロー、日本工学アカデミー会員、国道交通省、警察庁等の各種有識者委員会委員など。 - 青木 俊介氏 Turing 株式会社 共同創業者 / 取締役 CHRO
米・カーネギーメロン大学 計算機工学科で博士号取得。米国では自動運転システムの開発・研究に従事し、サイバー信号機の開発や大手自動車メーカーの自動運転機能の開発に携わる。2021年に完全自動運転を目指すチューリング株式会社を創業し、CTO・CHRO を務める。名古屋大学 客員准教授・JST さきがけ研究員を兼任。MITテクノロジーレビュージャパンより35歳未満のイノベーターIU35に選出。 - 横田 美希氏 オムロンソーシアルソリューションズ株式会社
2018年にオムロンソーシアルソリューションズ株式会社に転職。新規事業部門にて2019年に地域創生事業とライドシェアサービス「meemo」を立ち上げ、現在事業責任者。2020年には運行管理者資格を取得し舞鶴市にて3年間実務経験を積む。今後2種免許も取得予定。全国自治体ライドシェア連絡協議会、交通空白解消本部官民連携プラットフォームにも参画し、2次交通の確保に向けて実装経験を積む
モデレーター:
- 本田 隆行氏 合同会社SOU サイエンスコミュニケーター
神戸大学にて地球惑星科学を専攻(理学修士)。地方公務員(枚方市役所)事務職、科学館(日本科学未来館)勤務を経て、国内でも稀有なプロの科学コミュニケーターとして活動中。「科学とあなたを繋ぐ人」として、科学に関する展示企画、実演の実施・監修、大学講師やファシリテーター、行政委員、執筆業、各メディアでの科学解説など、なんでもこなす。著書・監修に『宇宙・天文で働く』(ぺりかん社)、『もしも恐竜とくらしたら』(WAVE出版)、『知れば知るほど好きになる 科学のひみつ』(高橋書店)、『科学のなぞとき マジカル・メイズ』シリーズ(ほるぷ出版)など多数。<www.sc-honda.com>
<開催終了>

JST-RISTEX RInCAクロストーク2024 #01
「共に生きるロボットの未来:技術・倫理・文化の交差点」
- 日 時:2024年8月22日(木) 18:00-19:00
- 開催形態:現地とオンラインのハイブリッド開催
- 現地会場:CIC Tokyo(東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー)
- 参加:参加費無料(要事前登録)
概要
配膳ロボットや、ペット、身近な家族としてのロボットなど。ロボット達はSFの世界から飛び出し、その存在は私たちにとってますます身近になってきています。人と共に生きるロボットが私たちの生活にどのような影響をもたらし得るのか。ロボットという人ならざるものとは。法学者・ロボット工学者・認知心理学者・文化人類学者、まさに総合知を結集した研究チームによる、最新の研究進捗報告とともに、企業が実際に開発・提供している共棲ロボット・弱いロボットの事例を紹介し、技術革新がもたらす社会的影響や倫理的課題に対する具体的な解決策、法制度の整備、そしてベンチャー企業が直面する実務的な課題や市場展開の可能性について深く議論しました。
登壇者・モデレーター紹介
登壇者:
- 稲谷 龍彦氏 京都大学 大学院法学研究科 教授 (2023年採択プロジェクト代表者)
「『共棲ロボット』との親密な関係形成におけるELSIに関する越境型文理融合研究」
RInCA2023 年採択プロジェクト代表者。京都大学大学院法学研究科附属法政策共同研究センター「人工知能と法」研究ユニット PI から AI 研究者・ロボット研究者・認知科学者・文化人類学者などの多分野研究者、企業・公共団体などと共に学際的な研究プロジェクトを推進。デジタル庁デジタル関係制度改革検討会、同国際データガバナンスアドバイザリー委員会などで、日本社会・日本政府のデジタル化政策に携わる。 - 青木 俊介氏 ユカイ工学株式会社 CEO
東京大学在学中にチームラボを設立、CTOに就任。その後、ピクシブのCTOを務めたのち、ロボティクスベンチャー「ユカイ工学」を設立。「ロボティクスで、世界をユカイに。」というビジョンのもと、家庭向けロボット製品を数多く手がける。2015-2021年グッドデザイン賞審査委員。2021年より東京藝術大学非常勤講師、武蔵野美術大学教授(特任)。 - 伊藤 亜紗氏 東京工業大学 科学技術創成研究院 未来の人類研究センター長 / リベラルアーツ研究教育院 教授
美学者。MIT客員研究員(2019)。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程を単位取得のうえ退学。博士号(文学)。主な著作に『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社)、『どもる体』(医学書院)、『記憶する体』(春秋社)、『手の倫理』(講談社)。第13回(池田晶子記念)わたくし、つまりNobody賞、第42回サントリー学芸賞、第19回日本学術振興会賞、日本学士院学術奨励賞受賞。 - 原山 優子氏 東北大学 名誉教授(RInCA プログラムアドバイザー)
1998年からジュネーブ大学経済学部助教授、2001年から経済産業研究所研究員を経て、2002年より東北大学大学院工学研究科教授に就任、科学技術イノベーション政策の教育・研究に従事。2006年~2008年に総合科学技術会議非常勤議員、2010年から経済協力開発機構(OECD)の科学技術産業局次長を務め、2013年~2018年総合科学技術・イノベーション会議常勤議員。2020年~2022年理化学研究所理事。2022年~2023年日本科学振興協会代表理事。
モデレーター:
- 宇野 常寛氏 批評誌『PLANETS』編集長 株式会社PLANETS代表取締役
立命館大学文学部を卒業後、批評誌「PLANETS」創刊編集長に就任。ニュース番組や討論番組を中心に様々なメディアに出演。立教大学社会学部兼任講師も務める。『ゼロ年代の想像力』(早川書房)、『リトル・ピープルの時代』(幻冬舎)、大学入試頻出の『日本文化の論点』(筑摩書房)、『母性のディストピア』(集英社)、石破茂との対談『こんな日本をつくりたい』(太田出版)など。

JST-RISTEX RInCAクロストーク2024 #02
「未来のイノベーションと社会の調和:ELSI/RRIを取り入れるヒント」
- 日 時:2024年10月24日(木) 18:00-19:00
- 開催形態:現地とオンラインのハイブリッド開催
- 現地会場:CIC Tokyo(東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー)
概要
科学技術を社会に実装させていくために、戦略的なルール形成や社会受容の構築が求められています。ELSI/RRIの議論が、このような基盤づくりの鍵となるかもしれません。本セッションでは、新興科学技術がもたらす倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)と責任ある研究・イノベーション(RRI)の基本概念を説明し、それらをビジネスにどう取り入れるかについて道筋を探ります。国立研究開発法人科学技術振興機構 社会技術研究開発センター(JST-RISTEX)センター長の小林 傳司先生とELSIプログラム(RInCA)のプログラム総括である唐沢 かおり先生が、JST-RISTEX内での取り組み、本プログラムの目的と取り組みを紹介し、CIC Japan会長の梅澤高明様とメルカリR4DManagerの多湖真琴様をお呼びし、実際のビジネスシーンでの取り組みとその可能性についてディスカッションしました。
登壇者・モデレーター紹介
登壇者(50音順):
- 梅澤 高明氏 CIC Japan 会長
東京大学法学部卒、MIT経営学修士。A.T.カーニーのコンサルタントとして、日米で20年以上にわたり、戦略・イノベーション・マーケティング・組織関連のテーマで企業を支援。日本代表、本社取締役、消費財・小売プラクティスのグローバルリーダーを歴任。現在は日本法人会長。CIC Japanの会長として、国内最大の都心型スタートアップ拠点“CIC Tokyo”の設立準備中。CIC (Cambridge Innovation Center)は米ケンブリッジ(マサチューセッツ州)に本社を持つ世界最大級のイノベーションキャンパス運営企業。インバウンド観光、クールジャパン、知財、デザイン、イノベーションなどのテーマで政府委員会の委員を務める。クールジャパン機構社外取締役。『NEXTOKYO Project』を主宰し、東京の将来ビジョン・特区構想を産業界・政府に提言し、都内の複数の再開発プロジェクトを支援。著書に『NEXTOKYO』(共著、日経BP社)、『最強のシナリオプランニング』(東洋経済新報社)など。 テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」コメンテーター。 - 唐沢 かおり氏(RInCAプログラム総括)
1984年京都大学文学部卒業。1992年カリフォルニア大学ロサンジェルス校大学院博士課程修了。博士(心理学)。名古屋大学情報文化学部助教授などを経て、東京大学大学院人文社会系研究科教授。専門は社会心理学。主として、自己や他者、社会的出来事などに関する情報処理のメカニズムを研究。社会心理学の知見や研究手法を、社会的課題に役立てる研究にも取り組んでいる。編著書に『なぜ心を読みすぎるのか: みきわめと対人関係の心理学』東京大学出版会(2017)、『社会的認知ー現状と展望』ナカニシヤ出版(2020)などがある。 - 小林 傳司氏(JST-RISTEX センター長)
国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 社会技術研究開発センター(RISTEX) センター長 大阪大学名誉教授、同COデザインセンター特任教授
1978年京都大学理学部卒業、1983年東京大学大学院理学系研究科博士課程単位取得退学。2005年大阪大学コミュニケーションデザイン・センター(CSCD)教授、2015年から19年大阪大学理事・副学長。2020年大阪大学名誉教授、2021年からJST RISTEXセンター長。
専門は、科学哲学・科学技術社会論。著書に、『誰が科学技術について考えるのか コンセンサス会議という実験』名古屋大学出版会(2004)、『トランス・サイエンスの時代 科学技術と社会をつなぐ』NTT出版ライブラリーレゾナント(2007)など。 - 多湖 真琴氏 株式会社メルカリ mercari R4D Director
弁理士。京都大学卒業後、開発職として富士通株式会社に勤務。
2013年に弁理士資格を取得し、TMI総合法律事務所にて権利化から係争案件まで幅広い知財業務を担当。
2018年、メルカリに入社後、知財チームの初期メンバーとして知財活動の立ち上げに従事。
2019年よりR4Dを兼務し、R4Dのガバナンス構築に尽力。2022年より現職。
モデレーター:
- 西川 信太郎氏 株式会社グローカリンク 取締役/日本たばこ産業株式会社 D-LAB ディレクター
食や農業、バイオ分野などのゲームチェンジャーに対して投資を行うインキュベーターであるグローカリンクの取締役。特に食の分野に精通。また、グローバルで活動するFuture Foodの日本支部であるFuture Food Hub in Japanや、一般社団法人Tokyo Food Instituteの設立メンバーとして活動中。