エッセイ #21「臨床研究における患者・市民参画(PPI)推進の潜在的暴力性について」
言説化の取り組み | 2025年5月16日
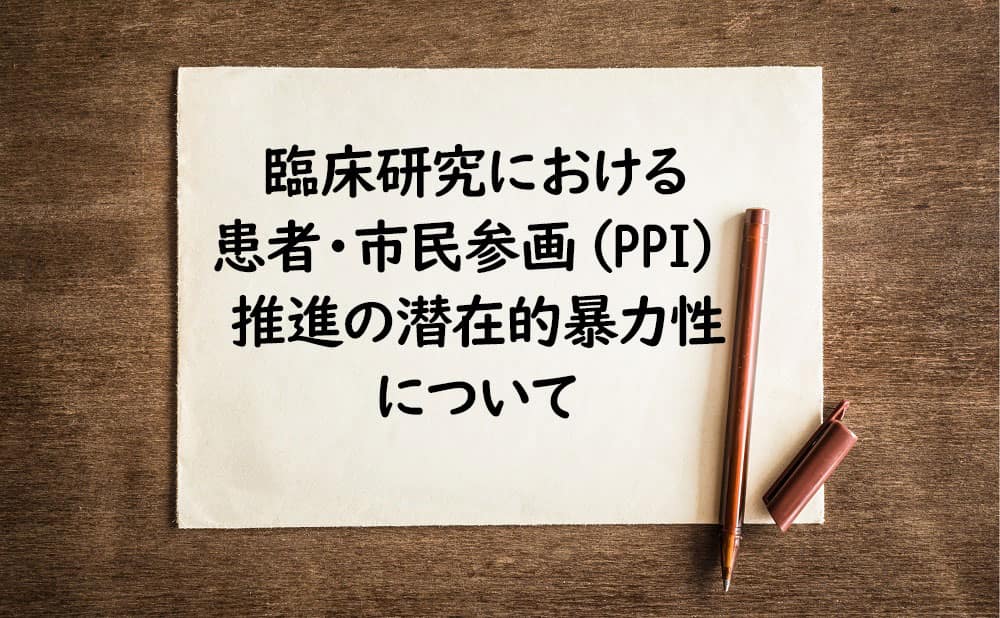
- 松井 健志 国立がん研究センター がん対策研究所 生命倫理・医事法研究部 部長
2022年採択松井プロジェクト:「胎児-妊婦コンプレックス」への治療介入技術臨床研究開発に係るELSI
キーワード Ver.2.0:ものごとを決めるにはどんな要因や問題点があるの? 「市民関与と社会的合意形成」
キーワード Ver.2.0:便利さや快適さは公平に与えられている? 「アクセスしない自由」
英国での保健制度改革の中で登場した「患者・市民参画(Patient and Public Involvement: PPI)」は、当初の病院運営に係る方針決定や診療ガイドライン作成あるいは薬価決定等の診療に関わる場面に留まらず、その後2006年頃には研究の場面にまで広がった。現在では、臨床研究に係る政策・制度の中にも広く浸透し、研究政策の立案・評価や公的研究費の助成申請・評価など様々な場面で取り入れられている。臨床研究におけるPPIに関して政策の中で強調されるのは、患者・市民「とともに(with)」、あるいは患者・市民「によって(by)」臨床研究が実施されるという研究の在り方・体制の実現とその推進である。
この英国に端を発した臨床研究におけるPPI推進への注力という世界的潮流は日本にも押し寄せ、近年は定着の兆しをみせている。例えば、日本医療研究開発機構(Japan Agency for Medical Research and Development:AMED)の各種事業の公募要領には、その冒頭に「医療研究開発の意義やそれが社会にもたらす恩恵等を積極的に社会と共有すること、研究開発の立案段階から患者・市民参画(PPI: Patient and Public Involvement)によって社会のニーズに応えるような研究開発成果を創出すること、対等なパートナーシップに基づく研究者と患者・市民の協働が広がることが重要です。〔中略〕AMED事業においては、医療研究開発プロセスにおいて、研究者が患者・市民の知見を取り入れるPPIの取組を推進します」とあり、研究開発計画の応募の際にはPPIについて述べる項目が設定されている。また、本RInCAプログラムでも、「本プログラムへの提案においては〔中略〕研究開発現場やステークホルダー、コミュニティとの具体的な連携や協働の下に取り組むことを原則としている」ことが明示されている。実際、われわれが実施する「『胎児-妊婦コンプレックス』への治療介入技術臨床研究開発に係るELSI」プロジェクトでも、サイトビジットの際にあるアドバイザーから、「胎児治療研究のガイドラインや提言のようなものを策定するというが、その策定にあたっては、社会的受容が政治的にも必要になるはずであるが、反発もあるはず。どういう形で一般の人に浸透させていくのか?」というコメントを受け取っている。
確かに一般論としては、例えば自動運転ドローンタクシーなどの新たな科学技術の研究・イノベーションの多くは、それが社会実装されると、広く「一般市民」の生活や生命に影響を及ぼし得るものであることから、利害当事者たる一般市民を巻き込んだ社会的受容や合意の形成に向けた議論や対話が必要なのであろう。しかし、医学領域の臨床研究、中でも取り分け、研究にアクセスしない妊婦の自由と中絶選択の自由を巡る問題までもが互いに複雑に交錯し得る胎児治療研究のように、極めてセンシティブな内容を伴い、そこで得られた技術が社会実装された場合にも、その直接の影響を受ける当事者が限定された患者とその親密圏内の者に限られるような一般には殆ど知られていない臨床研究では、こうした「一般市民」や「社会」といった第三者からの声や一般的見解は、単なる無責任を通り越して、当事者に対して時に極めて暴力的なものとなり得るだろう。即ち、市民社会から大上段の「懸念」や「異論」が多く提出され、それへの対応によってただでさえも限られている研究リソースが消費され、また、倫理審査委員会への無言の圧力として作用して、研究がますます遅れていきかねない。
また、臨床研究では、患者参画として「患者」を一括りにして論じることの暴力性にも目を向ける必要のある場合もあるだろう。しばしば患者は弱い立場にある者(弱者)と言われるが、一口に「患者」と言っても、患者団体を形成して政策や研究立案に参画し大きな声をあげることのできる(一種の「弱者の中の強者」)患者もいれば、そうした声も出せず望んでも参画のスタートラインにさえ立てない「弱者の中の弱者」に当たる患者もいる。さらには疾患胎児のように、当事者でありながら、当事者以前に社会の成員としても見なされない「弱者の中の弱者の中のさらなる弱者」に当たる存在もいる。こうした幾重にも弱い立場の者たちは、PPIを礼賛してその推進を強力に図る社会的潮流の中で、その存在と利害が無視され、時に暴力的なまでにさらに周縁化されていきかねない。
このように、PPIは諸手を挙げてただ推進されればよいといった性質のものではない。しかし、PPIに潜在する暴力性、非倫理性についてはこれまで生命倫理やELSIの領域での十分な検討がないように思われる。また、そのことと、近年のELSIの議論の多くで、「E」の視点、即ち倫理的観点からの深い洞察が欠落しているように思われることとの間に、何か関連があるような気がするのは、果たして自分だけだろうか。
エッセイ一覧に戻る 言説化の取り組みへ戻る