エッセイ #20「渾沌マトリックス:分子ロボットを創成した異分野融合のためのパラダイム」
言説化の取り組み | 2025年3月10日
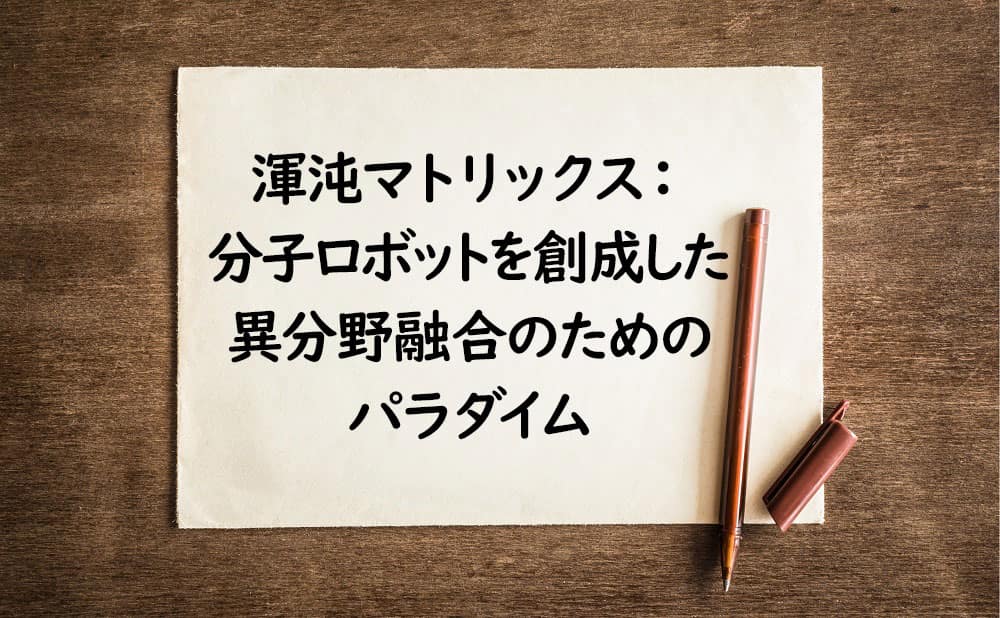
- 小長谷 明彦 恵泉女学園大学 人文学部 客員教授
2021年度採択小宮プロジェクト:研究者の自治に基づく分子ロボット技術のRRI実践モデルの構築
キーワード Ver.2.0:「専門家」や「市民」とは誰のこと?それぞれの役割はなに?
DNAやタンパク質などの生体分子を組み合わせて、「感覚」と「知能」と「運動」という機能を持つ人工物を創生する研究は「分子ロボット」と呼ばれている。分子ロボットは日本発の研究領域であり、2010年に生物、化学、物理、情報、工学などの様々な分野の専門家が集まり、「分子ロボティクス研究会」を発足させたことから始まった。これまでに、分子アメーバ型ロボット、分子人工筋肉、分子スワーム型ロボットなどが創成され、基礎研究においては日本の技術が世界をリードしている。また、分子ロボットは生物との親和性が高く、自己複製や遺伝子操作が原理的には可能なため、基礎研究の段階から倫理研究者の耳目を集めていた。1
責任ある研究・イノベーション(Responsible Research and Innovation: RRI)の観点からは、分子ロボット研究の一番の特徴は前人未踏の技術創出のために多種多様な背景を持つ研究者が自発的に集まり、ディシプリン(秩序)の壁を乗り越えて境界領域研究を推進してきた点にある。だが、異分野の研究者が集まれば自動的に革新的な研究が生まれるわけではない。境界領域研究の難しさは背景知識の違い、価値観の相違、目指すべき方向性の違いなど様々な理由が挙げられる。
では、最終的に境界領域研究を推進し、分子ロボットの創成を可能とした要因は何であったのだろうか。このような要因の一つとして、異分野を結びつける「場(マトリックス)」の重要性を提唱したい。分子ロボットには様々な分野の研究者が集まっているが、出自となる分野間で主導権争いをしている状況では境界領域研究は進展しない。異なる分野の研究者が出自である分野への拘りを捨て、境界領域に注力し、互いに相手の分野を尊重し、相互理解を深め、同一の目標に向かって共創することが不可欠となる。このような場を本エッセイでは、「渾沌マトリックス」と呼ぼう。
「渾沌マトリックス」の出自は、目鼻を付けたら死んでしまったという中国故事「渾沌」にある。この故事のように、境界領域であるコミュニティを無理やり線引きし、出自である分野に持ち帰ろうとすると、もはやコミュニティは境界領域ではなくなり、境界領域を推進する力が失われるということを意味する。異なる分野を結びつけるには分野間を結びつけるための場(マトリックス)が不可欠である。マトリックスにおいて各分野の経験や暗黙知がデータ、情報、知識として形式化され、形式知と形式知が融合してあらたなる形式知を生み、さらに各分野において暗黙知として共有される。つまり、渾沌マトリックス上のコミュニティに属する研究者が異分野融合のためのトリックスターの役割を果たす。
トリックスターの役割は既存のディシプリンの破壊と新しいディシプリンに基づく研究コミュニティ(社会)の創成である。それは、芋虫が蛹を経て蝶になる過程になぞらえることができる。芋虫が直接蛹になるわけではなく、蛹の中で芋虫の構成物である胴体や足が溶け、アミノ酸のスープの状態を経て、蝶の翅や手足に再構成される。渾沌マトリックスという場において、自然科学のディシプリンだけでなく、社会科学や人文科学を含む様々な分野の知識や技術が融合し、時を経て新たなる体系が整ったとき、真の分子ロボット技術という名の研究領域が生まれると信じている。
1 2017年採択JST-RISTEX「人と情報のエコシステム (HITE:Human Information Technology Ecosystem)」領域において「分子ロボットELSI研究とリアルタイム技術アセスメント研究の共創(研究代表者:小長谷明彦)」「情報技術・分子ロボティクスを対象とした議題共創のためのリアルタイム・テクノロジーアセスメントの構築(研究代表者:標葉隆馬)」と共に、新学術領域研究「分子ロボティクス」と並走する形で分子ロボット倫理の研究が推進された。
エッセイ一覧に戻る 言説化の取り組みへ戻る