エッセイ #18「研究者の多様性と、研究者の自治」
言説化の取り組み | 2025年1月23日
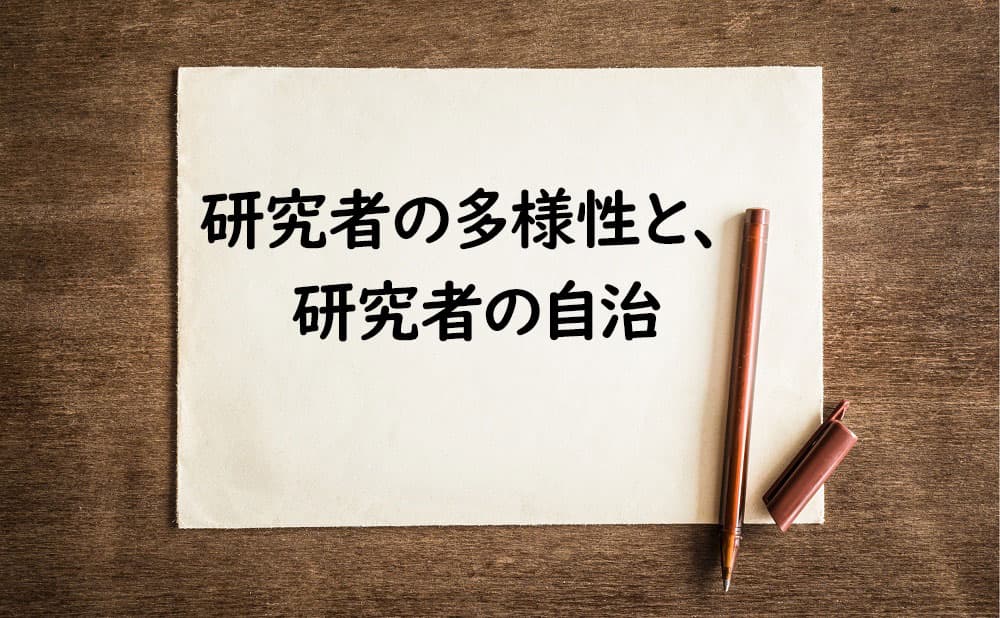
- 西 千尋 同志社大学 学習支援・教育開発センター 助教/慶應義塾大学 理工学部 研究員
2021年度採択小宮プロジェクト:研究者の自治に基づく分子ロボット技術のRRI実践モデルの構築
キーワード Ver.2.0:「専門家」や「市民」とは誰のこと?それぞれの役割はなに?
2010年頃からヨーロッパを中心に議論が始まった「責任ある研究・イノベーション(Responsible Research and Innovation:RRI)」は、研究やイノベーションとそれらに関わる社会的課題について、未来に対してケアを行うという観点から様々なステークホルダーが議論し、新たな研究・イノベーションの展開を実現することを理想とする。このような考え方は、私たちが実施する「研究者の自治に基づく分子ロボット技術のRRI実践モデルの構築」研究開発プロジェクト(以下、本プロジェクト)でも重視してきた。本プロジェクトの特徴は、分子ロボティクスと呼ばれる分子レベルの大きさの技術の構築を目指す研究者たちが、主体的にその社会的な側面についても検討し、社会との対話の機会を持とうとしていることにある。本プロジェクトには人文・社会科学や学際科学の研究者も参画しており、分子ロボティクス分野の研究者はそのような他分野の研究者との連携の下で、プロジェクトの名前にもある「研究者の自治」の実現を目指して様々な取り組みを行ってきた。
そもそもRRIの実践では、多様なステークホルダーがその議論に参加することが想定される。科学技術のステークホルダーには様々な職種や業界の人がおり、議論を通じてその人たちの価値観がまじりあうことになる。その中には、専門家だけでなく、社会を構成する市民も含まれなくてはならない。専門家が各々の職務やそれに関する経験を通じて得た専門的知見をもとに議論することを求められるのに対し、市民は各々の生活や社会での経験を通じて獲得した知見や感覚をもとに議論することになる。科学技術はそれを作り出した専門家のみが使用するのではなく、社会の中で予期されない形態も含めて様々な形で活用されることを考えれば、そのような市民の声が重要であることは自明だろう。分子ロボティクスでもそのような市民との議論を促進すべく取り組みを行ってきた1,2。ただし、これまでに指摘されてきたように、非専門家である市民が議論に参加できるようにするためのコミュニケーションは簡単ではない。その背景には市民の多様性がある。地域や世代など様々な文化背景の影響によって、各人が持つ知見や感覚は異なるはずであり、恣意的に選び出すことなく包括的な形でそれを議論の土台に乗せていくことが必要である。
一方で研究も多様であり、多様な分野の研究者が存在することを忘れてはならない。分子ロボティクス分野では、研究開発を行う自然科学分野の研究者も工学系から、生物学系、情報学系の研究者まで様々である。更には分子ロボティクス分野の営みを俯瞰しつつ、そのような研究者とともにRRIを実現しようとする人文・社会科学系の研究者や学際科学の研究者も存在する。このように複数の異なる分野の研究者が集まり、共に議論するのであれば、専門家の一つの属性として一括りにされがちな「研究者」も、その過程で他分野の文化に触れたり、他分野に特有の用語や表現を見聞きしたりすることになる。したがって、それぞれの文化や言葉を尊重しながら、異分野の研究者による建設的な議論がどのように実現できるのかという課題がやはりひそんでいるのである。建設的な議論を通じて、分子ロボティクス分野の研究者の間で共通認識が構築できたならば、市民を含めた多様なステークホルダーを交えた議論へと展開する際にも研究者間の見解のずれによって混乱が生じることが回避できる。
そのような共通認識の構築も、市民とのコミュニケーションと同様に、やはり科学技術コミュニケーションの課題である。本プロジェクトでは、特に「研究者の自治」を目指す自然科学の研究者と人文・社会科学や学際科学の研究者の間の科学技術コミュニケーションを念頭に、特に人文・社会科学や学際科学の文化や言葉に対する理解を促進させるための支援ツールの開発を行ってきた。そして作成されたのが『「研究者の自治」のためのレファレンスブック』3である。2024年秋に完成した最終版は、分子ロボティクス分野の研究者や学生はもちろん、幅広い自然科学分野の研究者や将来研究者を目指す学生たちが、これまで科学技術の社会的側面について検討をしてきた人文・社会科学の研究者と共通認識を持つことができるよう、科学者としてのあり方に関する考え方や、これまでの科学研究と社会に関わる議論などが幅広く、そして簡潔にまとめられている。『「研究者の自治」のためのレファレンスブック』を活用してもらうことで、自然科学の研究者と人文・社会科学の研究者の距離がより近くなってくれれば、RRIの実現も全くの夢ではないはずである。
文献
- 分子ロボット倫理研究会(2022)『分子ロボットをめぐる対話要点集 2020年度版』、CBI学会出版
- 分子ロボット倫理研究会(2022)『対話のための遺伝子リテラシー』、CBI学会出版
- 西 千尋、桜木真理子、見上公一(2024)『「研究者の自治」のためのレファレンスブック』