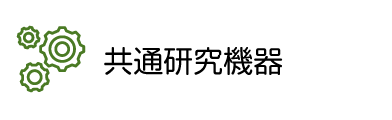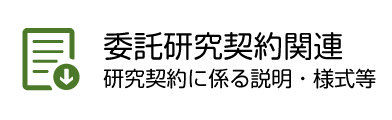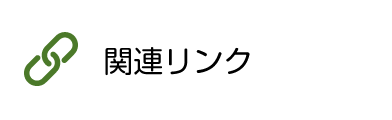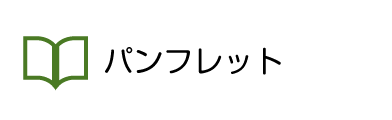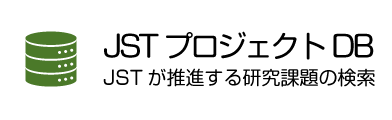バイオものづくり領域 研究開発課題紹介
- JSTトップ
- 革新的GX技術創出事業
- 領域
- バイオものづくり
- 研究開発課題 多様な微生物機能の開拓のためのバイオものづくりDBTL技術の開発


トピックス
- 2025年11月26日
- 大阪公立大学 山田亮祐 准教授らが研究成果を発表しました
「ゲノム編集で酵母のストレス耐性を強化!有用化合物の生産効率が向上」
大阪公立大学プレスリリース
- 2025年10月29日
- 名古屋大学 加藤晃代 准教授、産業技術総合研究所 本野千恵 主任研究員らが研究成果を発表しました
「微生物によるタンパク質生産効率向上の新技術を開発 ~医薬品や酵素、抗体などバイオものづくりへの応用に期待~」
名古屋大学プレスリリース 産業技術総合研究所プレスリリース
- 2025年 5月20日
- 東京大学 姫岡優介 助教らが研究成果を発表しました
「代謝ダイナミクスの応答性とネットワーク構造の関係に新たな知見」
東京大学プレスリリース
- 2025年 4月30日
- 神戸大学 西田敬二 教授らが研究成果を発表しました
「乳酸菌のゲノムを精密に編集する手法を確立」
神戸大学プレスリリース
- 2025年 2月 5日
- 大阪大学 清家泰介 助教らが研究成果を発表しました
「沖縄のショウジョウバエから新種酵母の発見~Hanseniaspora属酵母の進化学と産業応用に新たな可能性~」
JSTプレスリリース
- 2025年 1月24日
- 大阪大学 青木航 教授らが研究成果を発表しました
「リボソース生合成の試験管内再構成に成功」
大阪大学プレスリリース
- 2024年12月19日
- 神戸大学 石井純 准教授らが研究成果を発表しました
「酵母のタンパク質合成を自在に制御する手法を確立 -バイオものづくりを担う「デザイナー酵母」の開発へ-」
神戸大学プレスリリース
- 2024年11月15日
- 物質・材料研究機構 岡本章玄 グループリーダーらが研究成果を発表しました
「増殖しない「冬眠状態」のバクテリアを調べる新しい技術 ~低エネルギー状態の病原細菌を理解し、難治性感染症の新しい治療法の開発へ~」
物質・材料研究機構プレスリリース
- 2024年11月12日
- 神戸大学 蓮沼誠久 教授らが研究成果を発表しました
「プロポリス主成分の微生物生産における世界最高値を10倍以上更新」
神戸大学プレスリリース
- 2024年 9月 3日
- 「社会課題解決に貢献する微生物研究」バイオものづくり領域微生物中核チーム 公開シンポジウム(ハイブリッド)(10/31)
プロジェクトサイトイベントページ
- 2024年 5月10日
- 京都大学 宋和慶盛 助教ら共同研究グループが研究成果を発表しました
「導電性を持つ酵素の触媒メカニズムを解明
―テーラーメイドな第三世代型バイオセンサの開発に向けて―」
京都大学プレスリリース
チームリーダー

グループリーダー
| 氏名 | 所属・役職 |
|---|---|
| 蓮沼 誠久 | |
| 松田 史生 |
目的
温室効果ガスの排出量削減やエネルギーの安定供給に貢献すべく、CO2等を原料に燃料・樹脂・繊維等を生産できる人工微生物の開発と、バイオものづくり産業の基盤技術の確立に取り組む。
研究概要
日本のバイオものづくりは中規模・多品種型生産で世界をけん引してきた。しかし、一連のプロセス開発研究が個社に委ねられてきたため、プロセス開発期間の長期化と高コスト化、スケールメリットの小ささがボトルネックとなっている。この課題を解決するためには、産業形態の垂直統合型から水平分業型への変革、実プロセスからバックキャストした設計思想に基づく新たな育種技術の開発が必要である。
これらを実現するために本研究では以下の課題に取り組む。
1) プロセス開発の共通言語となる標準的な細胞(ベーシックセル)の作出
2) 汎用微生物にはないユニークな機能を備えた微生物の探索と宿主化
3) Design-Build-Test-Learn (DBTL)サイクルの次世代化
これらの取り組みによりプロセス開発期間の短縮、新規事業者の参入拡大、プロダクトの多様化を加速し、持続的なバイオエコノミー拡大に貢献する。

共同研究機関
大阪大学、大阪公立大学、大阪産業技術研究所、海洋研究開発機構、神奈川県立産業技術総合研究所、北里大学、京都大学、京都工芸繊維大学、九州大学、九州工業大学、神戸大学、埼玉大学、産業技術総合研究所、東京大学、東京科学大学、名古屋大学、広島大学、物質・材料研究機構(五十音順)
関連サイト
プロジェクトサイト|https://www.gtex-microbe.jp/
PDFダウンロード
成果報告書はこちら|評価・報告書>成果報告
所属・職名は、研究者がresearchmapに登録した情報をそのまま表示しています。(詳細はこちら)
researchmapの登録状況により、情報が最新ではない、あるいは空白に見える場合があります。
また、インターネット接続がない状態では表示されません。