成果概要
多様なこころを脳と身体性機能に基づいてつなぐ「自在ホンヤク機」の開発[6]「自在ホンヤク機」にかかわるELSIの検討
2024年度までの進捗状況
1. 概要
研究開発項目6では、「自在ホンヤク機」の開発と社会実装に伴う倫理的・法的・社会的な課題(ELSI)を明らかにします。これにより、「自在ホンヤク機」が広く社会的に利用される環境づくりが期待されます。
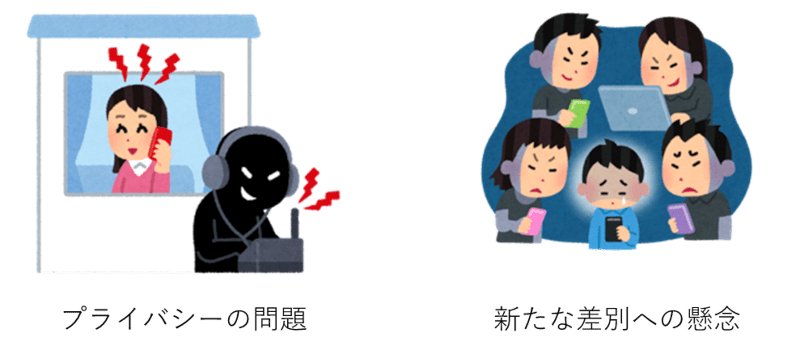
「自在ホンヤク機」は、こころの状態を読み取り、それを私たちのコミュニケーション支援に使います。この点について、プライバシー保護や、新しいコミュニケーションの形について、不安を抱く人がいるでしょう。
また、「自在ホンヤク機」の研究と開発には、発達障害がある人々(当事者)が参加します。当事者がおかれた状況への配慮、特に、「自在ホンヤク機」が発達障害当事者への新たな差別を生まないようにすることも必要です。
研究開発項目6は、「自在ホンヤク機」の研究・開発・社会実装のあらゆる場面で生じうるELSIを明らかにするとともに、その解決に取り組んでいます。
2. これまでの主な成果
- 外部有識者との第二回ELSI検討会の実施
- 研究開発担当者との意見交換と懸念点の聴取・分析
- 自在ホンヤク機の利用ガイドライン作成に向けたELSIの明確化
成果1では、2024年6月にオンラインにて第二回ELSI検討会を実施しました。橋田浩一博士(RIKEN)を講師と招き、パーソナルデータの分散管理の手法とその長所について議論しました。また、研究開発チーム(北城PIと中村PI)から「自在ホンヤク機」の研究開発におけるデータ管理の現状を紹介し、第一回から引き続き参加いただいた明谷早映子先生(東京大学)と中澤栄輔先生(東京大学)から専門的なご指摘をいただきました。本検討会により、自在ホンヤク機を実装する上でのデータ管理の重要性が明確になりました。
成果2では、前年度に引き続き2024年7月・12月と2025年3月に開催されたプロジェクト全体会議にて、研究開発者との意見交換を行いました。全体会議での研究発表を受けてELSI上の懸念点・課題点を分析し、研究開発者と共有しました。特に、「自在ホンヤク機」が社会実装されるまでの道のりについて、将来的には市民への啓発と、一般書出版までも視野に入れた検討が必要であることを示しました。

成果3では、「自在ホンヤク機」の利用ガイドライン作成にあたり、プライバシーに関するリスク評価の必要性が明らかになりました。「自在ホンヤク機」において、パーソナルデータの管理は最も重要なELSI対策上の課題の一つになると想定されます。そこで、パーソナルデータの倫理的な管理方法について検討し、研究開発チームと共有しました。
このように、研究開発の初期から科学者・工学者と協働してELSIを検討するというアジャイルな進め方により、「自在ホンヤク機」が社会的に受け入れられる環境づくりを推進しています。
3. 今後の展開
継続して、「自在ホンヤク機」に伴うELSIの理論的分析および科学者・工学者との合意形成を進めていきます。
また、社会実装を目指す「自在ホンヤク機」およびコミュニケーション支援技術全般について、ELSIの観点からガイドブックを作成し公表することを計画しています。
(東北大学・大隅典子、原塑)