成果概要
主体的な行動変容を促すAwareness AIロボットシステム開発[2] Awareness AIの応用
2024年度までの進捗状況
1. 概要
研究開発項目「Awareness AIの開発」では、このような人の動作観察に基づく無意識的な気づきをAIに実装することを目指し、歩行や姿勢などの身体的な動きから、個人の抱える問題や将来的に起こりうる疾患リスクを予測するAIシステムの構築に成功しました。
しかし、人の五感で感知できる情報には限界があります。身体の内部で起こっているごく微細な異変や、外見には現れない不調など、従来の観察ベースでは見落とされてしまうリスクもあります。そこで、本プロジェクトの応用研究フェーズでは、Awareness AIをより深く、より正確に活用するために、「見えない生体信号を可視化」する技術開発に着手しました。筋電図、皮膚電気反応などのセンシング技術を統合することで、人の内部状態を外部から読み取ることが可能となり、それをAwareness AIに組み込むことで、従来では検出できなかった問題点の把握や、病の予兆の解明が可能となります。
こうして明らかになった課題に対しては、Robotic Nimbusを用いた動作介入や、医学的な処置を組み合わせることで、これまで「治療が難しい」とされていた疾患へのアプローチや、フレイルのように知らず知らず進行してしまう身体的な衰えを未然に防ぐことを目指しています。
私たちの最終的な目標は、「治らなかった疾患が治る」「気づけなかった問題に気づける」といった、次世代の予防・治療の実現です。さらに、それがなぜ可能になるのかを科学的に明らかにするため、脳神経科学に基づいた理論的な検討も進めています。
また、こうした研究成果を社会とつなげる取り組みにも力を入れています。科学技術が私たちの生活をどう変えていくのかを広く伝えるために、市民公開講座を継続的に開催し、分かりやすい言葉で研究内容と未来像を共有しています。
これら一連の研究と社会活動を通じて、私たちが目指すのは、「日常生活を送るだけで、Awareness AIが自然に不調を検知し、介入と回復をサポートしてくれる」社会の実現です。人とAI、そしてロボティクスが調和する未来の医療・生活支援環境が、いま着実に形になりつつあります。
2. これまでの主な成果
図1に示すのは、私たちが開発した新しい筋活動計測センサーによって、身体内部の筋肉の活動を直接可視化した結果です。これは、自然な日常動作を対象にしながら、筋活動計測を基に深層を含む筋活動を可視化するという、世界で初めての成果です。
この技術は、従来の治療では効果が限定的であったジストニアに対して、顕著な治療効果をもたらすことが明らかになっています。図2に示すのは、その応用例のひとつとして、書痙の患者に対する治療事例です。書痙は、通常の動作には支障がないものの、いざ文字を書こうとすると特定の筋肉が異常に緊張し、手がうまく動かなくなる病気です。
私たちは、患者が「書こうとした瞬間」に起こる筋肉の異常な活動パターンを、開発したセンサーとAwareness AIを用いて詳細に解析しました。その結果、問題を引き起こしている特定の筋群を特定することができ、神経ブロック注射による標的治療によって、症状が即座に改善することが確認されました。
この方法は、書痙を含む同様の運動障害を持つ10名以上の患者に対して適用し、いずれも有効な治療成果を得ています。これにより、症状が曖昧で診断や治療が困難だった患者に対しても、より正確な介入が可能となりました。
さらにRobotic Nimbusを活用した運動支援にも取り組んでいます。図3は、パーキンソン病患者に対する立ち上がり動作の支援実験の結果です。パーキンソン病では、初動が極めて困難になる「すくみ足」症状が典型的に見られますが、Awareness AIによって適切なタイミングでロボットから刺激を与えることで、患者が自然な流れで立ち上がることが可能になりました。
これらの成果は、従来のリハビリテーションや薬物治療では十分に対応できなかった運動障害に対して、個別化された新しい治療アプローチの可能性を提示するものであり、社会実装に向けた実証と臨床応用を進めていきます。

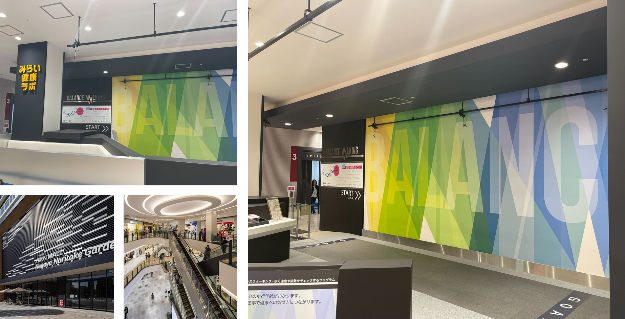

3. 今後の展開
Awareness AIの応用のため、ジストニアやパーキンソン病患者さんの治療を行ってきましたが、今後はこのような技術を日常の中に埋め込むことで、このような患者さんが普段から不便を感じることなく生活ができるようなシステムを構築していきます。