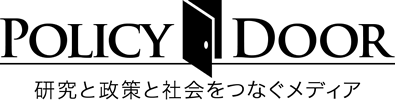「発達障害 という言葉は多くの人が知るようになりました。しかし、その一人一人の発達特性に応じた配慮や、エビデンスに基づく支援については、まだまだ浸透していないのが我が国の現状です 」
熊仁美さんが共同代表を務める特定非営利活動法人ADDSのウェブサイトに、そう問題提起されている。学校での合理的配慮なども行われるようになったが、発達障害の支援は科学的なエビデンスではなく、個人の経験や勘に頼っている場合が多い。
政策のための科学プログラムで発達障害児の支援者を現場で支援する熊先生と、SOLVE for SDGsプログラムで発達障害の当事者支援を研究する筑波大学の佐々木銀河准教授にお話を伺った。

熊 仁美 特定非営利活動法人ADDS 共同代表
――熊先生は、意思決定のプロセスを共有して行動化につなげる、発達障害児の保護者らを支援するアプリケーションを開発されています。 佐々木先生は、青年期・成人期の発達障害当事者の方々が自ら意思決定をする際の支援を、チャットボット(AIによる自動応答システム)の開発などを通じて行っています。 対象者は異なりますが、ともにデジタル技術を駆使して取り組んでいる互いのプロジェクトについて、どのように思われますか?
熊:青年期を対象にした佐々木先生の取り組みを拝見し、子どもから成人に至るまでは連続した話なのだと感じました。これまでのプロジェクトを通じて、対象のお子さんの発達段階が低年齢の場合、支援者の意思決定にはある程度の共通性がみられますが、年齢が上がるにつれて人によってばらついていくことがわかりました。未就学期は、発達段階に沿って、ご本人の発達基盤そのものを底上げしていく支援が中心ですが、小学生くらいになってくると、例えば「持ち物の管理が苦手で毎日忘れ物をしてしまう」ですとか、「苦手な授業中に立ち歩いてしまう」といった日常の具体的な困りごとを起点に支援を行う課題解決型支援 が重要になってきます。日常の課題には、お子さんを取り巻く環境や、ご本人の希望など様々な要因がより複雑に影響していますので、支援者の意思決定がばらついていくのはある種当然ともいえます。その多様な部分を体系化していくのはやはり大変です。
佐々木先生は大学生や成人を対象に意思決定の支援をされていますが、もっと低年齢から、アプリなどを使って自分の困りごとに合った支援を選ぶなど、自己決定の支援をしていく視点はとても大切だと感じました。これまでは保護者や支援者がやっていたことをすこしずつお子さん自身ができるように、より低年齢からそういった支援ができたら、とてもいいなと感じました。
――制度上、未就学のときには福祉(厚生労働省の管轄)、就学すると教育(文部科学省の管轄)となり、当事者の特性やこれまでの支援の履歴などの情報が途切れてしまう状況がありますね。
熊:はい。福祉から教育に移行し、就労するとまた福祉へ、という制度下で発生する情報の断絶は大きな課題だと思っています。現在はどうしても保護者頼みの制度になっているので、一生を通じたパーソナルデータのような仕組みがつくれるといいと思います。
佐々木:私もそれは問題だと思っています。間断なく支援するために、デジタルを活用した仕組みや、繋いでくれる専門員が必要だと思います。
また、熊先生のプロジェクトから改めて感じたのは、属人化(個々の支援者にノウハウを留めていて共有できていないこと)するのは悪いことではありませんが、属人化だけでは十分ではないという共通点があることです。非常に共鳴するのは、最終的には対人ですが人だけでは成り立たない現状が突きつけられているという課題意識です。
支援に関心をもってくれる方がいても、支援に必要な知識や、支援を仕事と考えた場合にその職能がまだ不明確であることがハードルになっています。個人の知をどうしたら共有できるかが課題です。
――個の情報の断絶や支援者の属人性を乗り越えるために、デジタル技術を活用しているわけですね。
佐々木:はい。それにはまず、紙からデータへの移行が地道に行われなければいけません。データへの移行をいかに効率的に、効果的に進めていくかという点では、熊先生のプロジェクトのようなシステムを使って、いかにプラクティス(実践例) をエビデンスに近づけていくかが重要になります。かつ、システムだけではなく、政策面や投資も非常に重要だと思っています。
――政策が重要だという話が出ましたが、政策については熊先生はどのようにお考えでしょうか?
熊:専門職の質を上げていくという点で、「エビデンスのあるものを取り入れましょう」という意思決定のルールやスローガンはあるべきだと思います。 それは、大前提として、行政がトップダウンでやるべきことだと思います。同時に、現場の方々がエビデンスに基づいた支援きちんと学んで提供していくというのはとても大変なことなので、それに取り組む動機づけとなるような報酬のあり方も不十分だと感じています。
また、一人一人に合わせていくことの価値がまだ重視されていないことも課題だと思います。「ニューロダイバーシティ (脳や神経、それに由来する個人レベルでの様々な特性の違いを多様性と捉え、相互に尊重し、それらの違いを社会の中で活かしていこうという考え方)」はとても大事ですが、徹底的に個別化された支援がセットに行われないと、人は皆違うのだから分け隔てしなくてよい、つまり単に「発達障害がある子ども、そうでない子どもも、同じ空間でみんなで過ごそう」という方向にすすみかねない、取り扱い注意な概念だと思います。真に「ニューロダイバーシティ」が実現するためには、個の違いや特性に合わせた支援を充実させていくことが重要です。その支援は、経験と勘ではなくエビデンスをベースにし、かつ本人の自己決定を尊重したものでなければいけません。概念が独り歩きをするのではなく、社会として「ニューロダイバーシティ」を実現するために必要なことを議論し、発信をしていく必要性を感じています。

佐々木 銀河 筑波大学 人間系 准教授
――デジタル技術の活用が解決策になりえる一方で、デジタル化に伴うリスクはありますか?
佐々木:私のプロジェクトでは、大学生向けの「Learning Support Book」や「ダボット」などのツールを提供していますが、情報提供が主なので、ツール自体が問題解決につながるかはその方の行動次第になっています。その解決策として、情報を選択する際 の判断基準もあわせて提供しています。つまり、Aという解だけでなくて、BやCという解もあって、どの選択肢を選んでもいいのですが、 選ぶための情報を提供する。知的障害のあるお子さんでも、“選ぶこと”は非常に重要で、 選べるようにするのが私の仕事だと思っています。それは支援を一人一人に合わせてカスタマイズすることとも関連します。
しかしそうした場面でも、その情報に対する留意事項を付けなければならないと思います。例えばチャットボットで人類の課題が全て解決するわけではないので、「生成AIに全幅の信頼を置いてはならない、参考程度にしなさい」と注意書きを付けるなどです。
熊:私がリスクだと思うのは、私たちが開発しているアプリ「AI-PAC LAB.」のレコメンデーション機能で出てきた課題(例えば、「靴を履く」課題や「ちょうだい、と要求する」課題など)を、現場の先生が実際にお子さんに対して取り組んでみたとき時に、子どもが嫌がったり、うまくいっていないのに続けたりしてしまうことです。それを防ぐために、子どもの反応や行動の様子をデータとして記録していくプロセスを組み込んでおり、記録を活用して、「選んだ課題をやってみた結果、うまくいっていたら続ける。うまくいかなかったら変える」というところまでを意思決定のフローに組み込んでおくことが重要だと思っています。

――属人性を乗り越え、統合された知見にしていくために、お二人は支援の様々なケースをデータベース化して、フィードバックしていく仕組みづくりをしています。その仕組みが社会にもっと普及するためには、さらにどのような取り組みが必要でしょうか?
佐々木:日々の仕事の中で、実践に基づくデータがたまっていき、その集合知がエビデンスとして解釈できるものもあると考えています。これまでは「エビデンス・ベースド・プラクティス(根拠に基づく実践)※1」が主流でしたが、その逆の「プラクティス・ベースド・エビデンス(実践に基づいた証拠) ※2」という形で、実践から得られたデータを利活用できるものにしていく。既存の取り組みの知見を集約するようなシステムづくりを後押しして広めていくというのがとても重要だと思います。熊先生のプロジェクトの成果は非常に参考になります。
ただし対人支援なので、データだけでは仕事ができないところもあります。熊先生と私のバックグラウンドには応用行動分析学という共通項がありますが、どのような理念や価値観に基づいて支援をするかも大事だと思います。単に「これができました・できません」というデータがあるだけではなく、データを使って行動や現象をどのように解釈し、学問の枠組みを使って実践プランをつくっていくかというフィロソフィーも併せて重要だと感じます。
※1 医療分野で対象者の特徴・文化・優先傾向に照らして、最良の利用可能な研究成果(すなわちエビデンス)を臨床技能に統合すること。Evidence based Medicineが、診療支援領域等に広まることでPractice(実践)となった。「個々の患者のケアについて決定を下す際に、現時点で最良の根拠を良心的、明示的、かつ思慮深く用いること」と定義され、エビデンスに専門的知識・経験、患者の選択を統合する取り組みが求められる。
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2349778/pdf/bmj00524-0009.pdf
※2 Practice based Evidenceでは、実践の対象となる人たちの状態を厳密に揃えるのではなく、様々な因子を包括的かつ統計的に扱うことで、特定のタイプの対象者に何が最も効果的かを見いだす。Evidence based Medicineを補完する、あるいは代替すると期待されている。
https://journals.lww.com/lww-medicalcare/fulltext/2010/06001/practice_based_evidence__incorporating_clinical.5.aspx
熊:私も実践からエビデンスを見出す「プラクティス・ベースド・エビデンス」がとても有効なアプローチ だと思っています。現場では、 日々の実践でデータが集まって いるので、そのデータが価値あるものとして使ってもらえる土壌さえあれば、エビデンスができていくと見込んでいます。
また、当時のこども政策担当大臣と直接お話をして要望書をお渡ししたのですが、 トップの政策をつくる方々も「一人一人にいいことをしたいけれど、それがあまりにも難しい」と思っていらっしゃる。そこで、それができそうと思ってもらえる事例やデータを持っていけば、政策にも取り入れていきやすいのかと思いました。実践からエビデンスをつくっていくことの価値が上がっていくと、それが政策にもつながっていくと思いました。
佐々木:エビデンスに関していうと、昨今「エビデンス」という言葉自体が、非常に平均値化されたものだと捉えられるケースがとても多くなっています。しかし、私たちは9割のマジョリティではなくて、マイノリティーと呼ばれる1割の方を相手に仕事をしています。だからこそ、この領域ではパーソナルなエビデンスをとても大事にしています。
まず自分自身における自分のデータの価値を見いだしてもらう。そして自分のデータは、自分だけではなく他の人にとっても価値があるという考え方を広げたいと思っています。
熊:プラクティス・ベースド・エビデンスでは、まさに個人のデータが共通の価値になりますよね。
未就学期の発達支援は、まだ診断等がつかない状況で、子どもたちの特性や困り事をきっかけにスタートしていくのが一般的です。早期からの診断前支援はとても重要ですが、ある種診断というラベリングがない状況下で、エビデンスを蓄積していくための手法が確立していないと感じています。
一般的に、エビデンスレベルが高いとされる研究を行う際には、自閉症群と統制群などとラベルを付けて類型化していきますよね。しかし、現場ではその手前から困りごとも支援もスタートしているわけです。そのような、診断よりもうちょっと手前の、特性や困りごとといった細かい概念で類型化していかないといけないような現場で、どうやってエビデンスをつくり、活用するサイクルをつくっていくのかというのは非常に難しいなと思っていて。 自閉症のお子さん100人のグループに対して行った研究と、現場で個別に支援した事例を100件集めて分析した研究にはそれぞれ価値があるのではないでしょうか。個別の100事例から帰納的にエビデンスをつくりあげていく研究の手法は、存在するけれども、軽視されている気がしています。
きっと介護や医療など他の対人支援領域でも、同様の課題があり、似たような研究に取り組んでいる方がいらっしゃると思うので、そうした方々とつながり、知見を共有する機会を増やしたいです。 このように事例を積み上げていく研究の手法が価値を発揮する領域は他にもあるはずなので、もっといろいろな事例を勉強したいし、他の領域とも 手を組んでプラクティス・ベースド・エビデンスの価値を広めていきたいです。
――現場の知見や経験が、発達障害の方の意思決定の新しいありかたを可能にしていく。このプラクティス・ベースド・エビデンスというアプローチ はもっと注目されてよく、様々な期待がもてる、ということをお示しいただきました。ありがとうございました。
対談は終始和やかな雰囲気で行われた。「フィロソフィーが共通しているからだ」と二人は言う。熊先生・佐々木先生の今後の協働にも期待したい。
(取材・文 黒河昭雄、小熊みどり、編集・森田由子)
2023年12月5日インタビュー