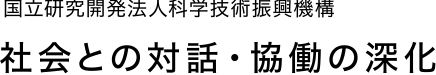科学コミュニケーションについて知りたい
吉川弘之対談シリーズ
「科学コミュニケーションを考える」
Vol.08
言葉を超える理解の形 -博物館は科学の何を問い、伝えることができるのか
ゲスト 西野 嘉章さん[美術史学者]
東京大学総合博物館 館長・教授
![Vol.08 言葉を超える理解の形 博物館は科学の何を問い、伝えることができるのかゲスト 西野 嘉章さん[美術史学者]東京大学総合博物館 館長・教授](items/wide_08.jpg)
シリーズ最後の対談は、東京大学総合研究博物館館長の西野嘉章さんをゲストにお迎えし、博物館が挑む言語を超えたコミュニケーションについて語っていただきました。
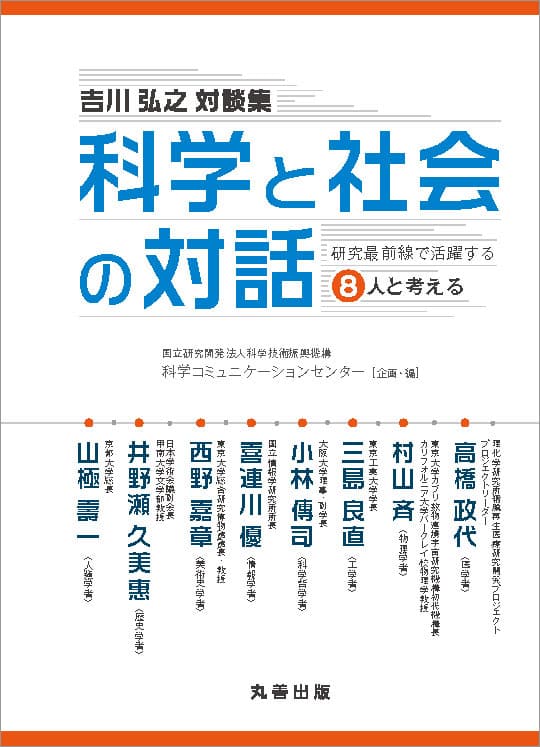
吉川弘之対談シリーズ 書籍化のご案内
本対談シリーズは、2017年3月に書籍にまとまりました。 このページでは、当センター長がご案内するダイジェスト版のみを掲載しています。
これまでの科学コミュニケーションは、読み書きによる書記言語と会話による口頭言語が中心でした。しかし、今見直されるべきは石器等のモノ自体を見ることで読み解く造形言語で、これは材料やつくり方から使い方に至るまで包括的な知識を伝える言語であり、さらに世界共通言語でもあると西野さんは語ります。科学が専門用語によって狭い領域のみでしか理解し合えない現代社会の欠陥を、造形言語で問題解決しようという考え方です。
造形言語においては、科学の成果を社会化するためにも、国や地域ごとに異なる言語の障壁を破るためにも、見た人が分かるための「デザイン」が重要となります。もちろん、解釈は人それぞれ異なりますが、普遍的な概念を伝えるという点では造形言語は優っています。
また、西野さんは、人が見て、知り、学ぶためには、その人が必要とする水準の知識を得ることが重要ですが、人間にはもともと自分の生存のために必要なものを自ら求めて狩りをするという本能があるため、その「狩猟本能」をもっと刺激し、コミュニケーションの受け手が好奇心に駆られて自分に必要な知識や知恵を自ら狩りとる方法を用意することで、受け手の主体性を重視することができると言います。西野さんの博物館では、まず受け手が求める情報だけを提供し、次に詳しく知りたい人には詳しい情報を、さらにより深い知識を求める人にはより詳細なデータの世界を提供するという「段階説」をとっているそうです。科学は知識を得たい人が自ずと理解できる知識体系なのであって、科学者が科学に興味がない人にやさしく説明するのは、自らの学問の水準を下落させてしまうことになると警告します。
終盤、お二人の話は科学のあり方にも及びました。科学はこれまで、システムを分解して理解するという壊す方向で進んできましたが、分解した部品からシステムをつくり上げる「戻す科学」は進めてこなかった、アマチュアも含めて不可逆的に戻すことで多様かつ自由な創造性につながる可能性があるとお二人は語ります。また、生物の進化において突然変異が進化の重要な要素になるように、間違いを尊重することも大事、間違いや偶発性を排除してきたことが科学の弱点と捉えます。科学は客観性を過度に重視し、主観を削ぎ落として抽象的なことだけを取り扱い、これが科学をつまらないものにした、総合の科学は主観的であり、デカルトやニュートンが築き上げた科学も実は主観的なものと語り合います。
人間が発展させてきた科学は局所的なものであり、科学にはまだまだやるべきことがたくさんある。そんな示唆を与えてくれる対談です。
[渡辺 美代子]
INDEX
- 00 イントロダクション
- 01 知のコミュニケーション -深い知を伝え合うことの意味
- 02 大学改革で実践する新しい対話 -学生目線で見出すこれからの教育
- 03 人類の進化が投げかける -科学コミュニケーションの行く先
- 04 基礎研究から臨床まで -見えない科学を社会に開く
- 05 情報化時代のコミュニケーション -生のデータで対話するダイナミズムを考える
- 06 専門語を自然言語に訳す -研究を始めた頃の素朴な疑問に立ち返る
- 07 意見の違いを認めて共に生きる -科学と社会はメタ合意の時代へ
- 08 言葉を超える理解の形 -博物館は科学の何を問い、伝えることができるのか