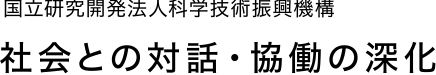科学コミュニケーションについて知りたい
吉川弘之対談シリーズ
「科学コミュニケーションを考える」
Vol.02
大学改革で実践する新しい対話 -学生目線で見出すこれからの教育
ゲスト 三島 良直さん [工学者]
東京工業大学 学長
![Vol.02 大学改革で実践する新しい対話 -学生目線で見出すこれからの教育 ゲスト 三島 良直さん [工学者] 東京工業大学 学長](items/wide_02.jpg)
第2回となる今回の対談は、東京工業大学 学長の三島良直さんをゲストにお招きし、「大学改革で実践する新しいコミュニケーション」をテーマに、吉川弘之さんと議論いただきました。コミュニケーションは言葉だけの問題ではなく、特に聞き手の動機が大きく影響するという一致した見解をもとに、各々の教育者としての経験を交えた熱意あるお話がなされました。
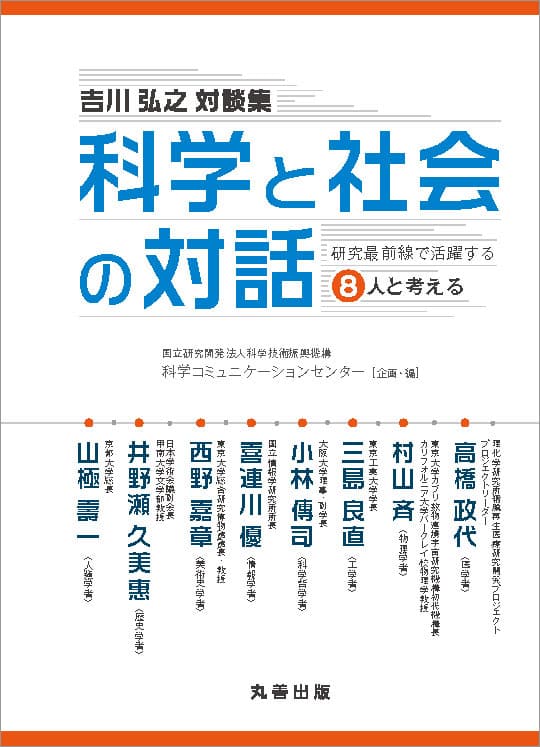
吉川弘之対談シリーズ 書籍化のご案内
本対談シリーズは、2017年3月に書籍にまとまりました。 このページでは、当センター長がご案内するダイジェスト版のみを掲載しています。
時代とともに変わる学生の気質や社会状況を踏まえて、大学の教育と研究も変わるべきですが、東京工業大学はこの春から抜本的な教育改革を開始しました。三島さんは、大学改革で最も重要なことの1つは学生と教員の間のコミュニケーションであるとして、教員は学生が自ら考え自ら意見を持つことを求め、学生の内面的動機づけのための科学技術教育を進めることが必要と強調しました。そのための事例として、自らの意見を持って相手の話を聞き、自分の意見を修正することを積み重ねるリベラルアーツ教育を初年次の必修科目に据えた、カリキュラム改訂の実践例を紹介しました。
学ぶ意欲の源となる社会的動機づけを得るのが難しく、個人の動機づけが中心となってしまっている現代においては、教員でさえ研究費獲得や論文競争、研究評価で疲弊し、学生たちにとって気概に満ちた環境は作りにくい状況にあります。だからこそ、大学は社会の中の一群であり、研究室はその1つであり、大きな社会システムの一部であることを認識して役割意識を生み出す必要性があると、お二人は指摘します。他の人たちと組むことで強くなるという意識を教員が持ち、留学経験によって多様な文化を体験することで、学生にも社会的動機が生まれることが期待されます。さらにお二人は、これまでの産学連携は研究を中心になされてきましたが、教育にも産業界の知を入れることで学生の好奇心を刺激し、両者の挑戦と努力、対話の積み重ねによって社会の中の役割意識が生み出されるだろうと語ります。
人間を変えることができるのは教育です。学生が自ら学ぶ動機を見出し、他者とコミュニケーションする教育こそが、日本の教育全体に波紋をもたらし、大学改革と社会にとっての大きな力になる、そのことを期待させる対談です。
[渡辺 美代子]
INDEX
- 00 イントロダクション
- 01 知のコミュニケーション -深い知を伝え合うことの意味
- 02 大学改革で実践する新しい対話 -学生目線で見出すこれからの教育
- 03 人類の進化が投げかける -科学コミュニケーションの行く先
- 04 基礎研究から臨床まで -見えない科学を社会に開く
- 05 情報化時代のコミュニケーション -生のデータで対話するダイナミズムを考える
- 06 専門語を自然言語に訳す -研究を始めた頃の素朴な疑問に立ち返る
- 07 意見の違いを認めて共に生きる -科学と社会はメタ合意の時代へ
- 08 言葉を超える理解の形 -博物館は科学の何を問い、伝えることができるのか