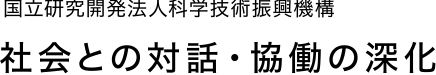科学コミュニケーションについて知りたい
吉川弘之対談シリーズ
「科学コミュニケーションを考える」
Vol.03
人類の進化が投げかける -科学コミュニケーションの行く先
ゲスト 山極 壽一さん [人類学者]
京都大学 総長
![Vol.03 人類の進化が投げかける -科学コミュニケーションの行く先 ゲスト 山極 壽一さん [人類学者] 京都大学 総長](items/wide_03.jpg)
今回の対談は、「人間とは何か」を求めて人類を生物学的に追及する「自然人類学」の第一人者で、京都大学の総長でもある山極壽一さんをゲストに迎え、吉川弘之さんと、人類学から見た人間のコミュニケーションと科学コミュニケーションについて語っていただきました。
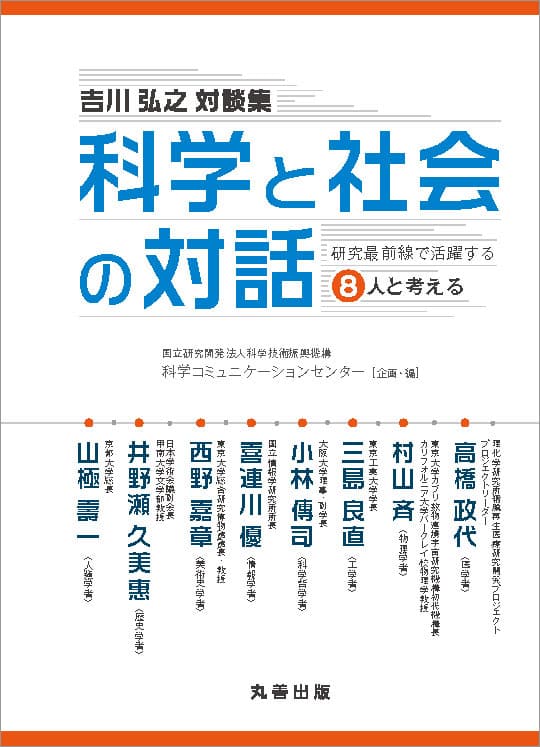
吉川弘之対談シリーズ 書籍化のご案内
本対談シリーズは、2017年3月に書籍にまとまりました。 このページでは、当センター長がご案内するダイジェスト版のみを掲載しています。
人間の祖先であるサルは、熱帯雨林で誕生し、植物や昆虫などの多様な自然とコミュニケーションをとっていました。そのとき獲得した五感は、今の人間にも受け継がれていますが、人間らしいコミュニケーション能力は、地球規模の気候変動によって人間が安全で豊かな森林から草原に進出したことに起因していると、山極さんは捉えています。
進化の過程で人間は、まず、目を見て相手の考えを察するという対面コミュニケーションを発達させました。これは今の私たちにも生まれつき備わる能力です。その後、人間は言語を獲得しますが、その駆動力は、「食」と「子育て」にあったといいます。人間は、食物を分配・運搬するようになりその分布を変え、同時に人間関係を築いていきました。次に栄養価の高い肉を食べることによって脳を大きくしつつ、コミュニケーションによって社会脳を発達させていきました。一方で人間は、多産を実現するために母親から乳児を早く引き離す子育ての仕方を選び、母親は離れた乳児に対して声の抑揚や音調でコミュニケーションをとるようになりました。これらが、言語の獲得につながっていきます。
言語が生まれ、視覚優位の世界から概念の世界をつくることができるようになると、人間の想像力は大きく広がり、神の存在が生まれました。人間の社会とは、言葉によってつくられる「神話社会」であり、科学も基本は神話による世界と捉えることができると、山極さんはいいます。そして科学は、社会の外に出て神話を疑う手段になり得ると同時に、社会を存続させるための神話づくりにも寄与できるものであり、新たな改革をするときには、従来の神話を基にして新たな神話を築く姿勢が重要と語ります。
現代はインターネットの時代ですが、対面による対話には、ネット上の情報にはない大事なことがあり、それは「信頼」と「考え」であると、お二人は指摘します。人間が時間をかけて獲得してきた考える力は人間の本性であり、辛抱強く考え、人を信頼してやり遂げる力こそが重要です。
人間はコミュニケーションによって現実にはない世界を見ることができ、より高みに飛躍しようとする願望が生まれた結果、科学や技術が生まれました。科学技術によって人間の考え方が変えられていくのは、進化とは逆の危険な方向であり、科学優先の社会ではなく、社会優先の科学を考えるべきと、お二人は語り合います。社会と文化のあり方を動物学に求めるのは、欧米にはできない日本が得意とするところであり、日本の進めるべき科学について、示唆の多い対談です。
[渡辺 美代子]
INDEX
- 00 イントロダクション
- 01 知のコミュニケーション -深い知を伝え合うことの意味
- 02 大学改革で実践する新しい対話 -学生目線で見出すこれからの教育
- 03 人類の進化が投げかける -科学コミュニケーションの行く先
- 04 基礎研究から臨床まで -見えない科学を社会に開く
- 05 情報化時代のコミュニケーション -生のデータで対話するダイナミズムを考える
- 06 専門語を自然言語に訳す -研究を始めた頃の素朴な疑問に立ち返る
- 07 意見の違いを認めて共に生きる -科学と社会はメタ合意の時代へ
- 08 言葉を超える理解の形 -博物館は科学の何を問い、伝えることができるのか