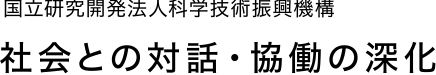科学コミュニケーションについて知りたい
吉川弘之対談シリーズ
「科学コミュニケーションを考える」
Vol.01
知のコミュニケーション -深い知を伝え合うことの意味
ゲスト 井野瀬 久美惠さん [歴史学者]
日本学術会議副会長/甲南大学文学部教授
![Vol.01 知のコミュニケーション -深い知を伝え合うことの意味 ゲスト 井野瀬 久美惠さん [歴史学者]日本学術会議副会長/甲南大学文学部教授](items/wide_01.jpg)
シリーズ最初の対談では、歴史学者である井野瀬久美恵さんをゲストに迎え、吉川弘之さんと「知のコミュニケーション」について語っていただきました。コミュニケーションとは何か、何について誰がどのように話すことがコミュニケーションなのか、深い議論がなされました。
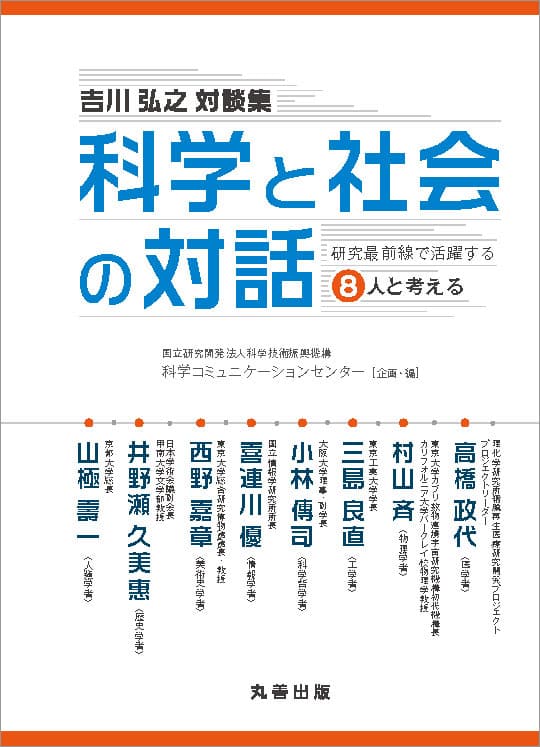
吉川弘之対談シリーズ 書籍化のご案内
本対談シリーズは、2017年3月に書籍にまとまりました。 このページでは、当センター長がご案内するダイジェスト版のみを掲載しています。
人間は他者との関係性の中でしか生きることはできませんが、その関係性にとって必要なのがコミュニケーションであり、コミュニケーションは各自が自分と対話する相手の立場を理解することから始まります。この理解がないまま対話しても、お互いの話す内容を分かり合うことはできず、コミュニケーションは成立しません。井野瀬さんは、全ての人が自らの中に複数の立場を持っていることに注目し、自分のアイデンティティの複数性を意識しながら、その複数性を局面ごとに使い分けて伝えていくことと、相手に対して興味を持つことが、円滑なコミュニケーションの第一歩となると語りました。
一方で、知識を伝え合うコミュニケーションは、社会全体において絶えず双方向であるべきで、また、多様な関係者間の複数の対話が、社会の中で循環するための「ループ」が形成されなければならないと、吉川さんは指摘します。ループの形成には、誰と誰が対話すべきなのかを明確にして、対話を啓発する場を人工的につくることが必要です。しかし、わが国の現状では、専門分野が異なる科学者間のコミュニケーションと、市民から科学者への伝達が欠落している傾向にあり、これらをつなぐ場が望まれます。
さらにお二人は、現代社会においてはインターネットの発展と普及により、表層的情報の氾濫が起こり、これが本質的コミュニケーションを阻害していると懸念します。現代に特徴的なコミュニケーションの課題を見つめ、現代にふさわしい知のコミュニケーションのあり方や構造を考えていくことが、今、求められているのです。
知のコミュニケーションとは、ことの本質がどこにあるのかを各自が考え、全ての人が責任ある意思を持ち、意思のある者同士が共に考えることである。お二人の対談は、私たちに、対話の意義とあり方を多方面から問いかけ、たくさんの示唆を投げかけてくれます。
[渡辺 美代子]
INDEX
- 00 イントロダクション
- 01 知のコミュニケーション -深い知を伝え合うことの意味
- 02 大学改革で実践する新しい対話 -学生目線で見出すこれからの教育
- 03 人類の進化が投げかける -科学コミュニケーションの行く先
- 04 基礎研究から臨床まで -見えない科学を社会に開く
- 05 情報化時代のコミュニケーション -生のデータで対話するダイナミズムを考える
- 06 専門語を自然言語に訳す -研究を始めた頃の素朴な疑問に立ち返る
- 07 意見の違いを認めて共に生きる -科学と社会はメタ合意の時代へ
- 08 言葉を超える理解の形 -博物館は科学の何を問い、伝えることができるのか