エッセイ #10「間接民主政と市民の声」
言説化の取り組み | 2023年9月26日
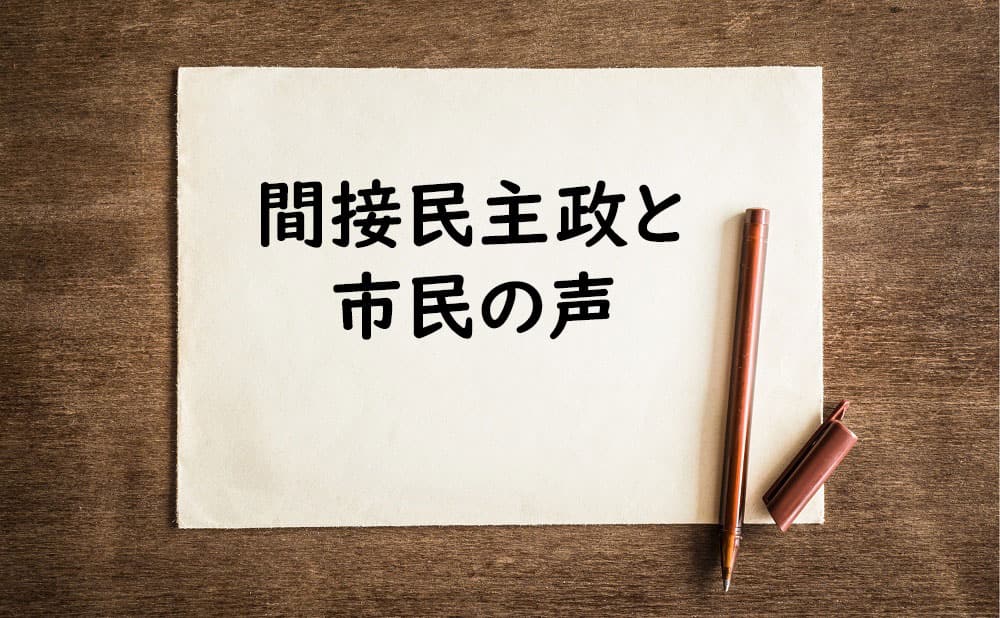
- 大屋 雄裕 慶應義塾大学法学部 教授(法哲学)
「市民の声を聴く」とは、どういうことなのだろうか。民主政が正しい政治体制であることの最大の根拠は、統治される対象である国民自身が主権者として統治を行なっていることに求められてきた。当事者自身の声に基づいて統治が行なわれる以上、その意図や利益に反する結果が生じる可能性はなく、不当な支配の問題も生じないはずだというのである。
だからこそ、選挙を通じて国政を担う政治家を選ぶという間接民主政は、国家規模の拡大によってやむを得ず採用された代替手段だと理解されてきた。本来、古代ギリシアに見られたようにすべての市民が民会に集い、議論に参加する直接民主政(その典型はアテナイだろう)を通じて当事者の声が直接に聴かれることが理想である。だが近代以降の国家においてそのような場を作り、維持することは現実に不可能であり、通常の政治はそれを専門に担当する政治家に委ねざるを得ない。国民が彼らに対する評価を声に出す限られた機会が選挙なのだというわけだ。「我ら人民」(We the People)が直接政治の場に登場して、体制の基本的なあり方自体を変貌させる革命の瞬間や「憲法政治」(アメリカの憲法学者ブルース・アッカーマンの表現)が特権的なものと理解されたり、特定の問題に対する市民の意思を直接に問う国民投票制度が一定の場合に支持されてきた背景にもこのような理解がある。
だが情報技術の発展により、現実の市民の意見を確認したり、選好や行為を集計することは容易になっている。計画経済の可能性をめぐって戦われた社会主義計算論争においては、たとえばトイレットペーパーの年間消費量を確認できなければ、生産計画の立てようがなく、その情報は全国に分散していて調査のしようがないと議論されたのであった。しかしいまやその数字はドラッグストアとコンビニエンスストアの大手チェーンから、かなり精度の高いものが入手できるのではないだろうか。人々が自動車でどのように移動しているかは、双方向通信に対応したカーナビゲーション・システムの普及によってかなりの程度可視化されている。市内の河川に新たな橋を架けるべきかどうかについては、そのデータをもとにシミュレートして結果を予測する方が、我々が選んだはずの政治家たちに任せるよりも正確で効率的に検討できるのではないだろうか。
このように、人々の現実の行動記録から将来の需要を予測し、それを実現するような政治のあり方をここでは、データベース政治と呼んでおこう(東浩紀が『一般意志2.0』(講談社、2011年)で検討したものが典型だろう)。アンケートのように各自の自覚的な選好を確認する手段には、現実の選択との乖離があることが常に指摘されてきた。たとえばファーストフード店が顧客の望む新商品をアンケートで尋ねると、ヘルシーな商品を求める声が常に上位にくる。だが現実にそのような商品が発売されると誰も購入しないというように、我々が現実に口に出す声はそれを聴く人の印象を考慮して歪み、あるいは自分の真の利益を捉えそこねることが多い。だからこそデータベース政治においては、各人が自覚してすらしていないかもしれないが、現実の行為や選択として現われている何かを社会的意思決定の基礎に据えることが提唱されているのだ。
だがそこで明らかに見落とされているのは、我々の選択はすでに存在している対象のあいだでしか行なうことができず、これまで存在しなかった何かに対する志向は存在しないということである(欲望はそれを満たすものが出現したときに発動するものだと、ハンニバル・レクターは言った)。そして我々の社会はそこで排除される未来への夢、将来人々が欲求するだろうものを作り出す人々がいることによって発展してきた。起業家(アントレプレナー)とはそのような人々のことであり、その多くが失敗に終わることも事実ではあるが、そこにないものへの夢を通じて新たな商品やサービスが生まれ、我々の選好自体を変容させてきたということを無視するべきではない。
そして政治においても来るべき社会を想像すること、将来に人々が受け入れるだろう制度を構想することが本来は必要なのだ。欧州各国が死刑を廃止したとき、国民の多くはそれに反対していたことを想起しよう。だがいまや彼ら自身が、そのような社会が自然なものだと確信している。政治家に対して次の選挙までの身分保障、言い換えればある種のフリーハンドを我々が与えているのも、そのように将来の我々の声という、いま・ここにはないものを先取りする規範起業家としての機能を期待しているからだと考えるべきではないだろうか。
未来にあるだろう市民の声を聴くためには、現在の市民の声から耳を塞ぐ必要さえあるかもしれない。社会調査や市民対話によってELSIの課題が解決されきらない理由は、ここにある。
エッセイ一覧に戻る 言説化の取り組みへ戻る