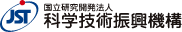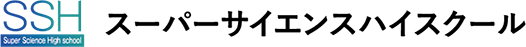【事例】現場視点の取組紹介
兵庫県立長田高等学校
「全校へ探究をひろげる」体制づくり~第Ⅰ期3年間での取組と工夫~
紹介者名:SSH推進委員 奥田 大志
1.学校の概要
本校は、令和7年度で創立105年目を迎えた全日制普通科高校で、自由な校風と積極的な自治活動を特徴としています。開校以来の教育理念(神撫(しんぶ)教育)にある「一芸一才、これを見出し、これを啓培し、以て職業的方向を自覚するに至らしめること」の具現化をめざし、令和4年度にスーパーサイエンスハイスクール(SSH)の指定を受けて、今年度で4年目を迎えています。第Ⅰ期では「人文・数理探究類型(平成25年度設置)」で取り組んできた文理融合の課題研究に加え、高大連携、行政・企業連携、国際交流、防災教育等のプログラムを整備し、探究活動を全校へ広げる校内体制の構築を進めています。昨年度(令和6年度)には科学の甲子園全国大会に初出場を果たすなど成果が見え始めてきました。
2.取組の概要
SSH指定を機に、人文・数理探究類型の3年間を通した探究活動プログラムのうち、グループ課題研究を一般クラス(7クラス)に波及させることに取り組みました。具体的には、1年次に理数探究基礎(1単位)を導入し探究スキルを身に付け、2年次総合的な探究の時間を2単位として課題研究を行い、3年次選択探究(希望者1単位)で論文を外部へ投稿するというカリキュラムとしました。特に2年次の課題研究では、指導方法に関して不安を口にする教員が多かったことから、SSH事業の中心を担う教育企画推進部が指導案と使用教材を準備し、指導ではなく伴走のイメージで生徒に接するよう伝え続け、無理なく探究を進められる体制づくりを目指しました。

生徒と共に取り組む課題研究

理数探究基礎のTTの様子
3.工夫のポイント
まず、教員が探究に慣れ親しむことをねらいとして、3年かけて2年次課題研究の担当教員を14名→18名→20名と増員させていきました。次に1年次理数探究基礎をティームティーチング形式にしました。この授業は7つの講座を各クラスが輪番で受講するリレー形式で実施していますが、1年次の学びを2年次課題研究の指導につなげにくいと課題研究担当者から指摘がありました。そこで、次年度に課題研究を担当するクラス担任も生徒と一緒に受講し、指導にも加わってティームティーチング形式とすることで2年次の指導に連携させるよう改善したのです。現在は計17名の教員が関わっています。また、実際に教員も探究してみようという趣旨で「大人の探究活動」を企画し、12名の有志教員が日頃気になる事柄などについて研究発表を行いました。

大人の探究活動研究発表会(発表者が寄稿者)

非認知能力について学ぶ職員研修
4.取組の成果
探究の指導に不安を感じる教員が多い中でのスタートでしたが、関わった教員の多くが前向きに改善案を提示するようになり、実施方法を毎年少しずつ改善しています。また、SSHに関する職員研修にはほとんどの教員が参加し、教員の探究学習指導力の自己評価も初年度から徐々に上昇しています。通常の授業にも「自分で問いを立てる」、「答えのない問いに取り組む」などの探究要素を自然と取り入れられるようになってきました。このように「伴走」のイメージで教員が無理なく取り組めるよう促してきた効果として、生徒にとって「探究」が身近なものになってきつつあると感じます。生徒も教員も夢中になる探究を目指し、今後も前向きな体制づくりをすすめていきたいと思います。