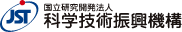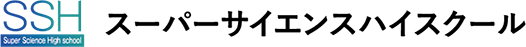【事例】現場視点の取組紹介
福岡県立城南高等学校
データサイエンスの手法を用いた課題研究の推進と校内の組織的な運営について
紹介者名:SSH部 部長 藤上 侑亮
1.学校の概要
本校は、令和6年度で創立61年目を迎える理数コースを擁する全日制普通科高校です。「進取・明朗・端正」の校訓のもと、平成7年にキャリア教育の先駆けとなった「城南ドリカムプラン」を開始し、常に時代を先駆ける人材の育成に取り組んでまいりました。その精神はSSHへと引き継がれ、平成22年度に指定を受けてから第Ⅲ期5年目となり、15年目を迎えています。第Ⅲ期では、第Ⅱ期で取り組んできた文理融合型の課題研究に加え、データサイエンスの手法を取り入れた課題研究を行っています。
2.取組の概要
理数コースでは、1年次から3年次まで「理数ゼミⅠ〜Ⅲ」(各学年2単位)の授業において課題研究に取り組みます。研究活動の質の向上を図るため、大学校や大学と連携して1年次に「海洋生物観察実習」、2年次に「先端技術体験講座」を実施しています。研究活動は、2年次から行い、12月に中間発表、3年次の6月に最終発表会を開催します。また、並行して論文の執筆と英語ポスターの作成を行なっています。論文は、全ての班が外部コンテストに応募するように指導しています。そして、3年次9月には英語ポスター発表会を実施しています。
理数コースを除く普通科では、1年次から3年次まで「ESD探究」(各学年1単位)の授業において課題研究に取り組みます。オリジナルテキスト「ドリカムBOOK」を用いて、指導をしていきます。

海洋生物観察実習の様子

発表会の様子
3.工夫のポイント
第Ⅲ期では機械学習やプログラミングの手法を学び、活用することに力を入れて取り組んでいます。理数コースは、「理数DS」の授業において、機械学習の分類問題を扱い、実習に重きを置いて授業を展開しています。これにより機械学習の手法を情報分野の研究に限らず、様々な分野の課題研究で用いることをねらいとしています。また、本校で行われている探究活動を中学生が体験する「中学生理数セミナー」において、昨年度は「手書き数字の分類」に関する基礎的な内容を扱い、理数コースの生徒をTAとして活動に参加させました。
このような理数コースに関する活動や課題研究についての検討を行うために「理数会議」を毎週実施しています。「理数会議」は、時間割に組み込み「理数ゼミⅠ〜Ⅲ」の担当者で行い、前年度の課題を踏まえた改善や各研究の進捗確認などは言うまでもなく、研究指導の行き詰まった際は、講師の紹介や過去の事例の共有など教員の集合知で解決を目指して取り組んでいます。
「ESD探究」についても活動内容の共有、検討を行うために「デザイン会議」を設定しています。このデザイン会議は、各学年の「ESD探究」の主担当者や学年主任だけでなく、管理職も交えて行い、学校全体で課題研究に取り組む体制と風土を築いています。

プログラミングを用いた課題研究
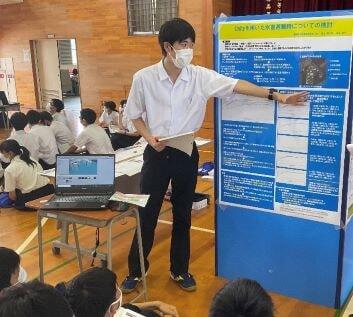
第46回全国高等学校総合文化祭自然科学部門発表
4.取組を通じた生徒の姿など取組の成果
第Ⅲ期の取組により、生徒が主体的に情報分野の研究に取り組むことができており、その生徒の数も増加傾向にあります。また、生物部において「理数DS」での学習内容を発展させ、重回帰分析を用いた研究が行われるなど、データサイエンスの手法を活用した研究が出てきています。他にもUnityを用いた災害シミュレーションの研究などプログラミングを用いた研究などが行われています。「中学生理数セミナー」では、理数コースの生徒がTAとして中学生に対してサポートすることで、理数コースの生徒においても内容理解に繋がる活動となっています。また、情報分野の理数セミナーに参加した中学生36名中6名が本校に入学(そのうち3名が理数コース)しています。このように情報分野や探究活動に関心のある生徒が本校を志望し、その生徒たちを中核として、データサイエンスの手法を用いた課題研究の開発を進めていく体制が整ってきています。