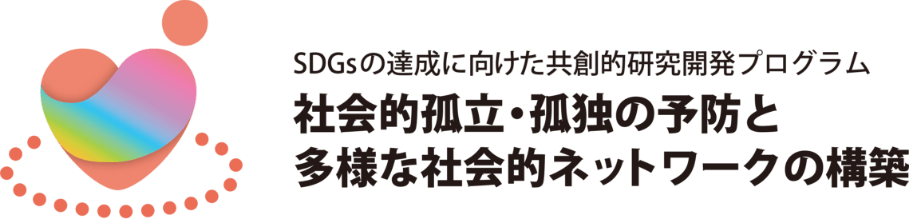プロジェクト

ケアの葛藤によりそい、ケアラーの社会的孤立・孤独を予防する包括的支援システムの構築

研究代表者:斎藤 真緒
立命館大学 産業社会学部 教授
ヤングケアラー、親ケアラー、家族まるごと支援、ケアリング・ソサイエティー(ケアに満ちた社会)
研究開発期間:2024年10月~2028年3月
researchmapプロジェクト概要
ケアの発生を契機とする、ケアを担う人(ケアラー)の社会生活およびライフチャンスの制約
日本を含む東アジア地域においては、家族によるケア(介護や看護など)が重視されているために、いったん家族にケアが発生すると、家族の世話を日常的に担うケアラーは、学業や仕事など自分のライフチャンスを犠牲にせざるを得ません。ケアラーの自己実現とケアニーズとの間の葛藤は深刻であり、社会的孤立・孤独のみならず、虐待や自殺、殺人などの社会問題にもつながっています。また、ケアが「負担」となるがゆえに、東アジア地域では、少子化の進行に歯止めがかかっていません。
ケアの葛藤に寄り添う包括的なケアラー支援システムの開発を通じた、ケアリング・ソサイエティーの実現
育児や介護、看病といったケアは、貧困や虐待とは異なり、解消されるべき事象ではなく、むしろ人間が生まれてから死ぬまでに必要な営みです。ケアラー自身のライフチャンスと、目の前のケアニーズとの間に生じる深刻な葛藤を支えるためには、ケアの負担軽減という<狭義のケアラー支援>だけではなく、ケアの社会的価値が尊重される<広義のケアラー支援>という視点を射程に入れる必要があります。
「ケアリング・ソサイエティー(ケアに満ちた社会)」の実現のために、本プロジェクトでは、ケアラーの葛藤に寄り添い、ケアとの距離を多様にデザインできる<スペクトラム型ケアラー支援システム>を開発します。その際、ケアラーが、自分の人生をあきらめることなく両立を探求することができるツールとして、ケアとライフチャンスとのバランスを可視化できる「ライフチャンス・チャートシート」を開発します。また、切れ目ないケアラー支援のために、支援団体のネットワーク化をすすめ、<ケア・エンパワメントプラットフォーム>を構築します。


Q&A
- 社会的孤立・孤独の一次予防のために、本プロジェクトが目指す社会像についてもう少し教えてください。
- 生まれてから死ぬまで、ひとの命と生活を支えるケアは、断続的に発生するものであり、誰しもがケアを受ける側にも担う側にもなりえます。だからこそケアは、単に<する/しない>という二項対立図式にはなじまず、ケアラーは、ケアニーズと自分自身のライフチャンスの間でジレンマを抱えます。2024年に、ヤングケアラー支援は法制化されましたが、負担軽減を中心とするケアラー支援では、ケアの社会的価値の尊重にはつながりません。本プロジェクトでは、親も含めた全世代のケアラーをささえる仕組みを創出することで、ケアの社会的価値の転換を図ること―ケアリング・ソサイエティーの実現―を最も重視しています。
- 上記の社会像を実現するための最大の課題(ボトルネック)は何ですか?
- 現在の福祉制度は、高齢者であれ、障害であれ、ケアを必要とする個人への支援を基本としています。その人をささえるケアラーへの支援は、現在は、ヤングケアラーのみが対象となっています。本プロジェクトでは、ユースショートステイ事業や、親子で参加できるプログラムの拡充など、民間団体主導で事業を実施し、その効果を検証することを目指しますが、事業の継続性、自治体での実装化が最大のボトルネックとなっています。
参画・協力機関
- 立命館大学、公益財団法人京都市ユースサービス協会、NPO法人芹川の河童、一般社団法人merry attic、一般社団法人インパクトラボ、YCARP(子ども・若者ケアラーの声を届けようプロジェクト)、茨木市 子育て支援課、尼崎市、こども家庭庁、滋賀県 子ども若者部 子どもの育ち学び支援課、東大阪市ヤングケアラー支援事業、一般社団法人日本ケアラー連盟、京都ケアラーネット、一般社団法人officeひと房の葡萄、ユーカリ訪問看護ステーション、伊藤産婦人科医院、天使心家族社会福利基金会、婦女救援基金會、蘇州大学、成均館大学、Sheffield Young Carers、性的健康センター(CSS:Centres de Santé Sexuelle)