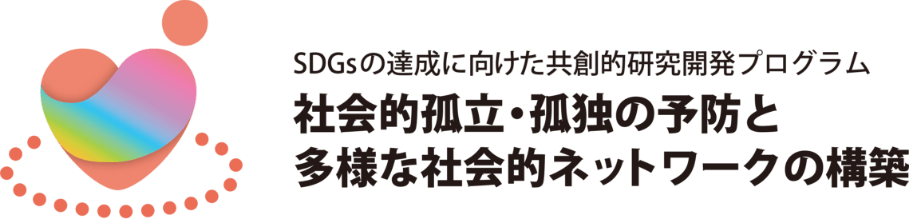プロジェクト

行政・NPOの孤立・孤独対策現場知を支援する総合知に基づく学術体制構築

研究代表者:岡 檀
情報・システム研究機構 統計数理研究所 医療健康データ科学研究センター 特任教授
現場知、学術知、総合知、質的/量的研究混合アプローチ、孤独予防因子
研究開発期間:2024年10月~2028年3月
researchmapプロジェクト概要
学術の知の統合と現場知へとつなぐ仕組みが不全であり、長期的視野に立った孤独予防因子研究が展開されていない
孤立・孤独問題に取り組む地方自治体やNPOはいわゆる経験値・暗黙知によって活動していて、連続性の維持が容易ではありません。学術知や専門知へのニーズは常に高いのですが、連携するための仕組みがありません。孤立の実態把握という点では、分布や地域間格差、その要因の解明が進んでいません。「孤立」を抽出する精度は十分といえず、「孤独」の顕在化はさらに困難です。また、現状への対処だけではなく、未然防止のための長期的視野に立った研究に注力しなければ、対策の内容は対症療法に終始する可能性があります。
枠を超えた多様な領域が呼応して集結し、孤立・孤独予防のためのプロセスを継続的かつ科学的に改善できる社会の実現を目指して
本プロジェクトでは、学術の知と現場の知をつないで、制度・政策の提言と実装を目指し、対策が持続的に改善される仕組み「孤立・孤独対策総合知支援ネットワーク」を社会に構築します。
現場のニーズを集めて、多様な学術領域の知の統合を図り、専門家、実務家と連携して政策の開発に取り組みます。具体的には、実装の実現可能性を行政学の専門家が評価して、現場の個別性と制度・政策の一般性を架橋します。また、連携する地方自治体やNPOが政策案のPoC実施の場として協力して、改善のPDCAサイクルを回していきます。こうした現場での質的調査を踏まえて、国が保有する大規模な個票データの解析によって指標の開発と要因分析を行い、PoC実施によって改良を重ねます。
上記と並行して、長期的視野に立った孤独予防因子の研究を行います。子どもコホートスタディによって孤独に傾きにくい思考や行動パターンを探索すると共に、周囲の偏見や価値判断など社会の包摂性に関わる規範がどのように形成されていくのか、そのプロセスについても検討します。また、孤立・孤独に傾きにくい住環境づくりを目指し、町の空間構造特性といったハード面からも検討を行います。


Q&A
- 社会的孤立・孤独の一次予防のために、本プロジェクトが目指す社会像についてもう少し教えてください。
- 本プロジェクトは孤立・孤独の再定義を起点としており、孤立や孤独を善悪の二項対立で扱うことに慎重であるべきと考えています。孤立していても孤独ではないケース、群れるよりはあえて独りを選択するケース、孤独を嗜好するケースなど、またその逆に、孤立していなくても強い孤独を感じているケースなど多面的であり、さらにそれらは平時と緊急時、ライフイベントなどによっても変容します。孤立・孤独に苦しむ人への対処はもとより、孤立・孤独を自ら嗜好し選択した人であったとしても、すべての人々が他者や地域社会とのゆるやかなつながりを実感できる、そうした社会の在り方を探求します。
- 上記の社会像を実現するための最大の課題(ボトルネック)は何ですか?
- この問題については数多の学術研究が進められているもののその統合が出来ておらず、現場知との連携の仕組みが構築されていません。地域社会に根差した活動が求められているにもかかわらず、これを担うNPOは常に資金や人手の不足に悩まされており、また、地方自治体の担当者には異動があるため、活動連続性が寸断されてしまうという障壁があります。
参画・協力機関
- 情報・システム研究機構 統計数理研究所、多摩大学、東京科学大学、一般社団法人いのち支える自殺対策推進センター、慶應義塾大学、北海道大学、日本福祉大学、東海大学、立正大学、日本自殺総合対策学会、認定NPO法人長野犯罪被害者支援センター、高知県自殺対策推進センター、座間市福祉部地域福祉課、一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト、NPO法人OVA、心といのちを考える会、一般社団法人Saa・Ya、NPO法人自死遺族支援ネットワークRe