インタビュー「科学と技術の関係性が変化、AI駆動で目指す新たな価値創出」
「科学技術」と一括りにされやすい科学と技術の結合は、資本主義社会のなかで様々な価値を生み出してきました。しかし理化学研究所の高橋恒一氏によれば、AIなどの情報技術が発展する第4次産業革命の最中にある現在、科学と技術の関係性が変化する可能性があるといいます。産業もアカデミアも旧来型の構造にとどまる日本社会において、次なる打開策はどこにあるかを伺いました。
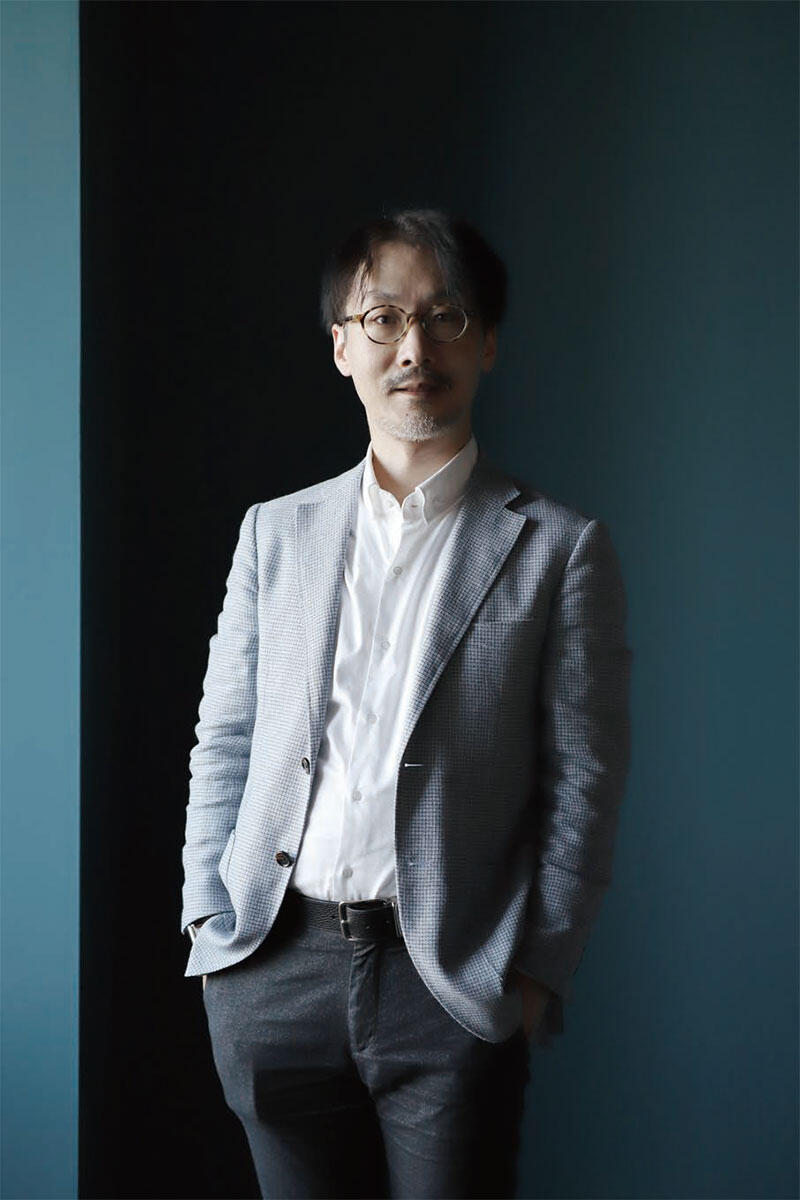
高橋恒一
理化学研究所 生命機能科学研究センターで研究室を主宰。慶應SFC特任教授、全脳アーキテクチャ・イニシアティブ理事・副代表などを兼務。専門はロボティック・バイオロジー、脳型人工知能、計算システム生物学など。AI社会論研究会共同発起人として人工知能技術の社会への影響にも関心を持つ。
HITE「法・経済・経営とAI・ロボット技術の対話による将来の社会制度の共創」
Writer:野口理恵/Photo:牧口英樹
アカデミアも産業も、没落の危機にある日本
─まずは高橋先生の研究と、現在のご関心について教えてください。
高橋恒一(以下、高橋):AIを科学の道具として研究活動にどう活かせるか、最終的にはAI自体が科学を推進していくことを目指す「AI駆動科学」に関する研究をしています。具体的には主に3つで、ひとつがロボットによる生命科学実験の自動化の研究で、「ロボティック・バイオロジー」と呼んでいます。ふたつめが脳型人工知能の一種である「全脳アーキテクチャ」というプロジェクト。三つめが細胞という生命を丸ごとシミュレーションする、ゲノムスケールシミュレーションの研究です。一見バラバラですが、いずれも生命科学を自動化してゆく上で私の中では一貫しています。
─最近「科学と技術の離婚」ということを仰っていますが、その背景は何でしょうか。
高橋:あるウェブメディアに「科学と技術の離婚」というコラムを発表し、思いのほか大きな反響を得ました。そこでは純粋に科学史と文明論で終始しており、足下の社会や日本のことには一言も触れていないのですが、実はこの文章を書いた私の意図は日本の現在に対する危機感です。
昨今はAIブームとともに情報技術と社会との関係に関する議論が増えてきました。私自身も慶應義塾大学のSFC研究所を母体とした「AI社会論研究会」の共同発起人であり、これまで数十回にわたって各界の有識者と議論を重ねてきましたし、政府関係の場でも発言してきました。この数年で議論は一定の積み重ねが進んだと思う一方、何かひとつ消えない違和感のようなものがありました。AI倫理問題、プライバシーの問題など喫緊の問題は様々ありますが、日本の議論は「何が正しいのか」を延々と議論しているように思える。でも2000年代以降、日本の一人当たりのGDPはほとんど伸びていない一方で、世界では先進国の入れ替え戦を勝ち抜くために各国各企業が死に物狂いで成長の努力をしているわけです。そのダイナミズムの中で結果残ったものが次の時代をつくる。何らかの正しい答えがこれまでの延長線上にあらかじめ用意されているような問題ではないんですよね。
─そうした日本の危機の背景には何があるのでしょうか。
高橋:近現代という大きな時代が終わり、工業化社会から情報化社会へと世界は変化しているにもかかわらず、新時代に合わせた産業構造をいまだに構築できていないことが最大の理由でしょう。よく言われているように、第1次~第2次産業革命の根幹は、労働力の組織化と機械化による効率的な大量生産です。日本は第2次産業革命の最後のバスにぎりぎり乗り込むために明治維新の前後で大きな背伸びをした、その結果として工業化社会に国全体で過剰適応したところがあります。そして、そのような変革は内発的に生まれたものではないため、本来は技術進展による産業構造の変化に合わせて常に再構築してゆくべきところ、自発的には変化が起こせないまま現代まで来てしまった。1990年代のインターネットの普及による第3次革命は日本にとって大きな好機でしたが、社会の仕組み自体を再考するような大きな動きとはならなかった。現在はAIなど知的労働の自動化が進む第4次産業革命の最中にあります。前提となる常識が変わりつつあるいま、日本は教育システムから根本的に変革する必要があると思います。毎日決められた時間に学校に行き、規則正しい生活を守るといった集団行動を基本とする教育自体すらも見直していくべきでしょう。

AI駆動型科学で、個人の力を最大限発揮する
─第4次産業革命に対しての処方箋はあるのでしょうか。
高橋:工業化社会では、定時に来て手順書を理解し作業して定時に帰ってゆくような質の高い生産従事者と生産管理者の頭数をいかに揃えられるかが国力に直結していました。しかし知識社会ではソフトウェア工学の生産性法則の影響下にあり、突出した技術者や経営者などの天才の頭数を何人揃えられるかの競争になります。これは、豪傑と貴族の時代であった中世から、中間層の時代である近代へ移り変わった時と同等の根本的な変化です。その意味で、現在起きつつあることは近現代という時代の終焉、そしてまだ名前の付いていない全く新しい時代への突入という数百年単位の変化です。今から100年前には既に近代的な社会構造は成立していましたから、今生きている人でこれに匹敵する変化を実体験として経験した人はいない。現在はその規模の変化が起きつつあるということです。
そこでは、組織から個人に力と資本を移す必要があります。少子高齢化が進行する現代の日本では人口動態が特異な過渡期にあるため、大きな単位で平均化し公平性を考慮するとどうしてもイノベーションの芽を摘む結果とならざるをえない。僕はミクロコスモスと言っていますが、多少人為的、意図的にでも少人数で新しい考え方、平均値から外れた革新的な考え方を持つ人材を集めてチームをつくり、そこで生まれた芽を社会全体に還元するという方法を取らざるを得ない。それは大学の研究室かもしれないし、ベンチャー企業かもしれない、地域コミュニティかもしれない。様々な形態があり得ると思いますが、ともかく国全体の統計学に打ち勝つために、小さな集団にお金と権力を付与する仕組みが必要です。
─そのとき、「AI駆動科学」はどのように突破口として貢献できると思いますか。
高橋:マクロ経済学の井上智洋さんによると、知的労働が自動化された後の経済構造では、GDP成長率は技術進歩率と密接に結びつきます(AK型生産経済)。過去の産業革命で原動機が肉体労働を自動化したように、AI技術の本質は知的労働の自動化にあります。そして知的労働の最たるものは研究開発です。従って、過去の産業革命の起点が工場にあったように、次の産業革命の発震源は科学技術の研究現場になる蓋然性が高い。
私は実験、理論、シミュレーション、データに次ぐ第五の科学は自動化だと考えていますが、技術進歩率自体に直接貢献する研究開発プロセスへの自動化技術の導入は費用対効果が非常に高くなるだけでなく、国際競争上も最重要になると思われます。複雑な対象に関する知識とモデルを自律的に構築・洗練させ、対象の効率的な予測と制御を行う装置を自動で構築する仕組み、つまり仮説生成と検証の自動化技術は、まず実験科学を始点に発展し、早晩製品開発、市場調査から行政、企業経営、都市運営まで社会のあらゆる分野に広がり、現代社会の電気や原動機のような社会に不可欠のテクノロジーになってゆくと考えられます。
次の時代では天才の数を揃えることが国力に直結するならば、少子高齢化が当面進行する日本は大きく不利です。しかし、高度な知的労働の分野にまで自動化の波を導入することができるならば、ゲームチェンジャーとなりえる可能性があります。
─「AI駆動科学」の導入先としてどのような科学分野を期待しますか。
高橋:私が注目しているのは高エネルギー物理と細胞生物学です。まず物質世界の理解という意味での現代科学のフロンティアは明らかにダークマターやダークエネルギーなど、この宇宙の成り立ちの理解が進んでいないことです。これまでは、たかだか数百GeV程度の領域までしかよく探索されてきませんでした。実験データ処理の確率モデル構築では深層学習が活躍しはじめていますし、時空間およびエネルギースケールが、人類の脳が進化的に扱ってきた日常的なスケールとはかけ離れた領域である以上、人間の脳が把握できる程度のコンパクトな記述で法則を記述できる保証はなく、法則探索にも機械化が求められます。
次が、私が専門とする生命科学です。宇宙の成り立ちに次ぐもうひとつの現代科学のフロンティアは大自由度非平衡系です。平衡系に関してはボルツマン以降の統計力学で、例えばカルノーサイクルに結実し内燃機関の発達を支えましたが、非平衡系に関しては20世紀を通じて、目立った発展はありませんでした。現代科学が扱う先端的な問題の多くは細胞をはじめとする生命、高分子、生態系、社会などの大自由度で非線形な非平衡系であり、これらを理解・制御する技術体系は社会に大きなインパクトを生みます。人間の認知能力はたかだか数個の変数しか同時には扱えませんが、その限界を超えた領域での予測や法則性探索が行える方法論が求められます。そこには機械的知性の導入が不可欠です。
─先生がご専門とする生命科学への実験ロボットの導入は、現状でどの程度進んでいるのでしょうか。
高橋:世界的な潮流としては進んでいますが、研究現場で当たり前に使われるような状況にはまだなっていません。この点はアカデミアよりもベンチャー企業の方が先行していますね。かつての20世紀型の研究システムはアポロ計画が特徴的なように、何らかのミッションに向けて大きな投資が動いていました。21世紀の研究開発はプラットフォーム型であるべきで、グーグルのように検索フォーマットを持ち、その精度を0.1%でも上げると何十億円と利潤が返ってくるような状況が理想です。その利潤をさらに次の技術に投資するフィードバックサイクルができている。そうしたシステムを日本はうまく整理できていないのは大きな課題だと思います。

科学と技術が離婚するとき、新たな価値創造が生まれる
─先生の見解では、本来別物であった科学と技術が「結婚」して資本主義のシステムと接続し利潤を生み出してきた時代から、今後は「離婚」が始まると仰っていますね。
高橋:本来、自然哲学はこの世界がどうしてこのようなかたちをしているかを純粋に考える形而上学で、特に役に立つものとはされていませんでした。ベーコンの経験論やデカルトの分析的方法論の整備などを契機に経験論的アプローチが肥大し、さらにニュートンの力学などに代表されるように数学の形式性なども取り込んで予測性を獲得しました。自然現象の形式的な理解が価値と力を生み出すということは人類史上の大発見であり、ここでいわゆる「科学技術」が成立しました。しかし、現在発展しつつある統計的機械学習は、対象の明証的かつ形式的な記述がなくても将来状態の予測が外形的な入出力関係として成立すれば、それ自体で経済的価値を生みます。自然現象の形式的な理解である科学がなくても、技術がそれ自体で価値を生むのであれば、もはや科学と技術の結婚関係は終わります。
これまでの社会では研究開発など何か新しいものを生み出すには膨大な労力とコストがかかっていたので、どのように成し遂げるか(how)に価値があり、それが教育から社会の価値観、組織のあり方までに影響してきました。しかし、研究開発にまで自動化の波が押し寄せた将来には、人々の意識の中からテクノロジーは薄れ、希薄化、透明化するでしょう。そのとき、どんな価値が生まれるかは「何を望むか(what)」で決まり、「どうやってそれをなすか(how)」の意味は相対的に薄くなる。つまり、中世以前そうであったように、技術(テクネー)とアート(アルス)が未分化な本来の状態へと一種回帰してゆく。その一方で、技術とは現在よりも距離を取った科学自体は、「そもそも理解とは何か」「理解そのものの理解」が大きな問題として浮上し、おそらく将来の自然科学では認知科学がその中心の一角を占めることになるでしょう。
※本記事は、「人と情報のエコシステム(HITE)」領域冊子vol.04に収録されています。
そのほかの記事、そのほかの号については以下をご確認ください。
HITE領域冊子